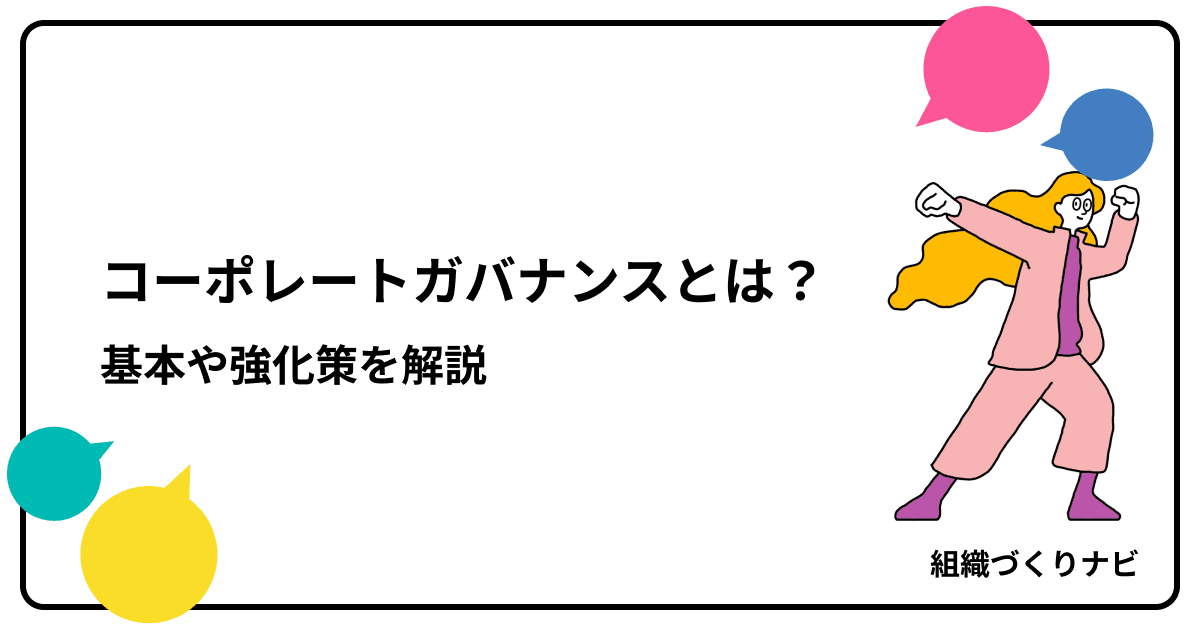
コーポレートガバナンスとは?基礎や強化策などを解説
コーポレートガバナンスは、企業の透明性と公正さを保ち、持続的な成長を実現するための仕組みです。近年、企業の不祥事防止、社会からの信頼獲得、そして株主・従業員・顧客といったステークホルダーの利益保護の観点から、その重要性が高まっています。 本記事では、この基本概念から、内部統制、社外取締役・監査役の活用、情報開示強化といった具体的な強化方法を解説。また、日本のコーポレートガバナンス・コードの原則や、G20/OECD原則改訂に見る国際的なサステナビリティ開示の動向までを詳述します。 従来の「守り」のガバナンスから、ESG要素を取り入れ企業価値向上を積極的に目指す「攻め」のガバナンスへと進化する潮流を理解し、人事・管理職の方々が自社の健全な経営体制強化に貢献するための一助となる情報を提供します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
コーポレートガバナンスとは?目的・効果から強化方法などを解説
企業を経営する上で、その透明性や公正さを保ち、持続的に成長していくことは非常に重要です。近年、企業の不祥事や社会情勢の変化を受け、「コーポレートガバナンス」という言葉を耳にする機会が増えました。これは、単に法令遵守に留まらず、企業が社会から信頼され、健全な形で持続的に発展するための仕組み全体を指します。
本記事では、コーポレートガバナンスの基本的な考え方から、今なぜ重要視されているのか、そしてどのように強化すべきかを、人事や管理職の皆様にも分かりやすく徹底的に解説いたします。本記事が、貴社の経営体制強化の一助となれば幸いです。
コーポレートガバナンスとは?基本概念と定義
企業統治としての役割、内部統制との違いと関係性
コーポレートガバナンスとは、簡単に言えば「企業を適切に統治するための仕組み」です。企業の所有者である株主をはじめ、従業員、顧客、取引先といった「ステークホルダー」(企業と関わる全ての人々)の利益を考慮し、透明で公正な方法で運営されるための枠組みを指します。これにより、経営陣が恣意的な判断を下したり、不正を行ったりすることを防ぎ、企業が健全に成長することを目指します。
これとよく似た言葉に「内部統制」がありますが、これは企業内での業務ルールや手続きを定め、不正やミスを未然に防ぎ、効率的に目標を達成するための具体的な仕組みを指します。例えば、資金管理のチェック体制や、情報管理のルールなどがこれにあたります。コーポレートガバナンスは、企業全体のあり方を定める「大きな方針」であり、内部統制はその方針を実現するための「具体的な手段」の一つと捉えると分かりやすいでしょう。両者は密接に関わり、互いを補完し合う関係にあります。
なぜ今、注目されているのか?(社会的背景)
コーポレートガバナンスが今、これほど注目されている背景には、いくつかの重要な理由があります。一つは、過去に発生した企業の不正会計や不祥事が社会に大きな影響を与え、企業経営における透明性が強く求められるようになったことが挙げられます。これにより、企業が社会に対して説明責任を果たすことの重要性が認識されました。
また、グローバル化が進む中で、海外の投資家が日本企業を見る目も厳しくなっており、国際的な基準に適合した経営体制が求められています。さらに、企業の長期的な成長には、環境問題や社会貢献といった持続可能性の視点が不可欠であるという考え方が広がり、これらの要素を経営戦略に組み込む「攻めのガバナンス」の重要性も高まっています。企業が社会から信頼を得て、長く存続していくためには、適切なガバナンス体制の構築が不可欠であると認識されているのです。
コーポレートガバナンスの目的と期待される効果
経営の透明性・公正性の確保
コーポレートガバナンスの最も大切な目的の一つは、経営の透明性と公正さを確保することです。これは、企業の経営判断や活動が、隠蔽されることなく、誰から見ても納得できる正しい方法で行われるようにすることです。具体的には、重要な意思決定のプロセスを明確にし、不正や特定の個人の利益に偏った経営を防ぎます。
もし経営が不透明であれば、社内外からの信頼を失い、株主は投資をためらい、従業員はモチベーションを維持できません。透明で公正な経営は、企業の健全性を保つ基盤となり、社会からの信用を築く上で不可欠です。これにより、企業は長期にわたって安定した事業活動を続けられるようになります。
株主・ステークホルダーの利益保護と尊重
もう一つの重要な目的は、企業の所有者である株主の利益を保護し、最大化すること、そして従業員、顧客、取引先、地域社会といった様々なステークホルダーの利益も尊重することです。経営陣は、これらの多様な関係者の期待に応え、バランスの取れた経営を行う責任があります。
例えば、短期的な利益追求だけでなく、従業員の働きがいを向上させたり、顧客に質の高い製品やサービスを提供したりすることも、長期的に見れば株主価値の向上につながります。コーポレートガバナンスの仕組みが機能することで、経営陣が特定の利害関係者だけに偏った判断を下すことを防ぎ、すべての関係者にとって公平で持続可能な企業活動が実現され、それが結果として企業の安定した成長を支えることになります。
企業価値の持続的向上と健全な経営
コーポレートガバナンスは、企業が短期的な視点に囚われず、長期的に企業価値を高め、健全に経営されることを目指しています。これは、単に売上や利益を増やすだけでなく、ブランドイメージの向上、優秀な人材の確保、リスク管理の徹底といった要素も含みます。適切なガバナンス体制が整っていれば、経営における意思決定の質が高まり、新しい事業機会を積極的に追求できるようになります。
また、不祥事のリスクが減り、安定した経営基盤を築くことができます。これにより、社会からの評価が高まり、投資家からの信頼も得やすくなるため、資金調達がスムーズになるといった効果も期待できます。結果として、企業は持続的に成長し、社会に貢献し続けることができる、強固な企業体質を構築できるのです。
実効的なコーポレートガバナンスを強化する方法
内部統制、社外取締役・監査役の活用
コーポレートガバナンスを効果的に機能させるためには、様々なアプローチが必要です。まず、「内部統制」をしっかり整えることが重要です。これは、組織内での業務のルールや手続きを明確にし、不正やミスを未然に防ぎ、効率的に目標を達成するための仕組みです。例えば、経費の承認フローを厳格にしたり、情報セキュリティのルールを徹底したりすることが含まれます。
さらに、外部の客観的な視点を取り入れるために「社外取締役」や「社外監査役」の存在が非常に重要です。社外取締役は、企業の経営に直接関わっていないため、中立的な立場で経営陣を監督し、助言を行います。一方、社外監査役は、会計監査や業務監査を通じて経営をチェックし、不正がないかを確認します。これらの外部の目が機能することで、経営の透明性と公正さが保たれ、経営陣の暴走を防ぐことができます。
執行役員制度、社内判断基準の明確化
経営の効率性と責任の所在を明確にするために、「執行役員制度」の導入も有効な手段です。これは、経営の意思決定を行う「取締役」と、その決定に基づいて実際に業務を執行する「執行役員」の役割を分ける制度です。これにより、取締役は企業全体の戦略や監督に集中でき、執行役員は現場での業務遂行に専念できるため、経営のスピードと専門性が向上します。
また、企業としてどのような基準で判断を下すのかを明確にすることも欠かせません。例えば、「投資に関するガイドライン」や「リスク管理のポリシー」などを明確に定め、従業員全員が共通の認識を持って業務に取り組めるようにします。これにより、個人の裁量に任されがちだった判断に一貫性が生まれ、恣意的な決定や不適切な行動を防ぐことができます。明確な基準は、従業員が自信を持って仕事を進めるための指針にもなります。
情報開示の強化とコンプライアンス徹底
コーポレートガバナンスを強化するためには、「情報開示の強化」が非常に重要です。これは、企業の財務状況、経営戦略、リスク情報などを、株主や投資家、そして一般社会に対して分かりやすく、適時に公開することを指します。透明性の高い情報開示は、外部からの信頼を得る上で不可欠であり、企業価値を高める要因となります。経営の意思決定プロセスや、取締役会の構成なども積極的に開示することで、より客観的な評価を受けられるようになります。
同時に、「コンプライアンスの徹底」も不可欠です。コンプライアンスとは、法律や会社のルール、社会の倫理規範などを遵守することです。企業がどんなに利益を上げていても、法令違反や不適切な行為があれば、社会からの信頼を瞬く間に失い、事業の継続が困難になる可能性があります。社内研修の実施、相談窓口の設置、罰則規定の明確化などを通じて、従業員一人ひとりが高いコンプライアンス意識を持ち、日々の業務に臨むことが求められます。
日本におけるコーポレートガバナンスの動向とコードの原則
コーポレートガバナンス・コードの概要と改訂
日本においてコーポレートガバナンスの強化を推進する上で、非常に重要な役割を果たしているのが「コーポレートガバナンス・コード」です。これは、企業が持続的に成長し、企業価値を高めるための具体的な指針として、金融庁と東京証券取引所が策定したものです。法的強制力はありませんが、上場企業に対して、このコードの原則を実施するか、実施しない場合はその理由を説明することを求めています。
このコードは、時代や社会情勢の変化に合わせて何度か改訂されており、直近では2021年に改訂されました。主な変更点としては、企業の持続的成長には、気候変動などの環境問題や多様性の確保といった要素が不可欠であるという考え方が強く打ち出されています。これは、企業が短期的な利益だけでなく、長期的な視点で社会や環境との共存を考えることの重要性を示しています。
「プリンシプルベース」と「コンプライ・オア・エクスプレイン」
コーポレートガバナンス・コードの特徴的な考え方に、「プリンシプルベース・アプローチ」と「コンプライ・オア・エクスプレイン」があります。
「プリンシプルベース」とは、企業に細かな規則を押し付けるのではなく、目指すべき原則(プリンシプル)を示し、それぞれの企業がその原則に沿って、自社の状況に合った最適なガバナンス体制を自律的に構築することを促す考え方です。これにより、画一的なルールでは対応しきれない多様な企業の事情に対応できる柔軟性が生まれます。
そして、「コンプライ・オア・エクスプレイン」とは、「(コードの原則に)従うか、さもなくば(従わない理由を)説明せよ」という意味です。企業がコードの各原則を実施しない場合、その理由を具体的に開示し、なぜそのやり方を選んだのかを社会に説明することが求められます。これは、単に形だけルールを守るのではなく、企業自身がガバナンスについて真剣に考え、説明責任を果たすことを促す強力な仕組みとなっています。
スチュワードシップ・コードとアクション・プログラム
コーポレートガバナンスを考える上で、企業の行動だけでなく、投資家の役割も非常に重要です。そこで導入されたのが「日本版スチュワードシップ・コード」です。これは、機関投資家(年金基金や投資信託会社など、巨額の資金を運用する専門の投資家)に対して、投資先企業の価値向上や持続的成長のために、建設的な対話を通じて関与していくことを求める行動規範です。
関連する参考サイト
スチュワードシップ・コードに関する有識者会議(金融庁サイト)
https://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/index.html
つまり、投資家は単に株の売買をするだけでなく、企業の経営に積極的に関わり、企業価値が上がるよう働きかける責任があるという考え方です。このコードもまた、時代とともに改訂が行われ、企業の持続可能性に関する課題(ESG要素など)への関与の重要性が強調されています。
また、政府は「コーポレートガバナンス・コードの実効性確保に向けたアクション・プログラム」などを通じて、コードの浸透と実効性を高めるための具体的な取り組みを進めています。これは、企業の持続的な成長を日本経済全体の活性化につなげようとする強い意図の表れです。
関連する参考サイト
コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025の公表について(金融庁サイト)
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250630-1.html
まとめ
本記事では、「コーポレートガバナンス」について、その基本的な定義から、なぜ今これほど注目されているのか、そしてどのように強化していくべきかまで、幅広く解説いたしました。コーポレートガバナンスは、単に法令遵守という「守りのガバナンス」に留まらず、企業の持続的成長と企業価値向上を目指す「攻めのガバナンス」へと進化しています。
人事や管理職の皆様にとって、会社のガバナンス体制を理解し、その強化に貢献することは、健全な組織文化を醸成し、従業員のモチベーションを高める上でも極めて重要です。透明で公正な経営を実践することで、社内外からの信頼を築き、企業の持続的な発展を確かなものにできるでしょう。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

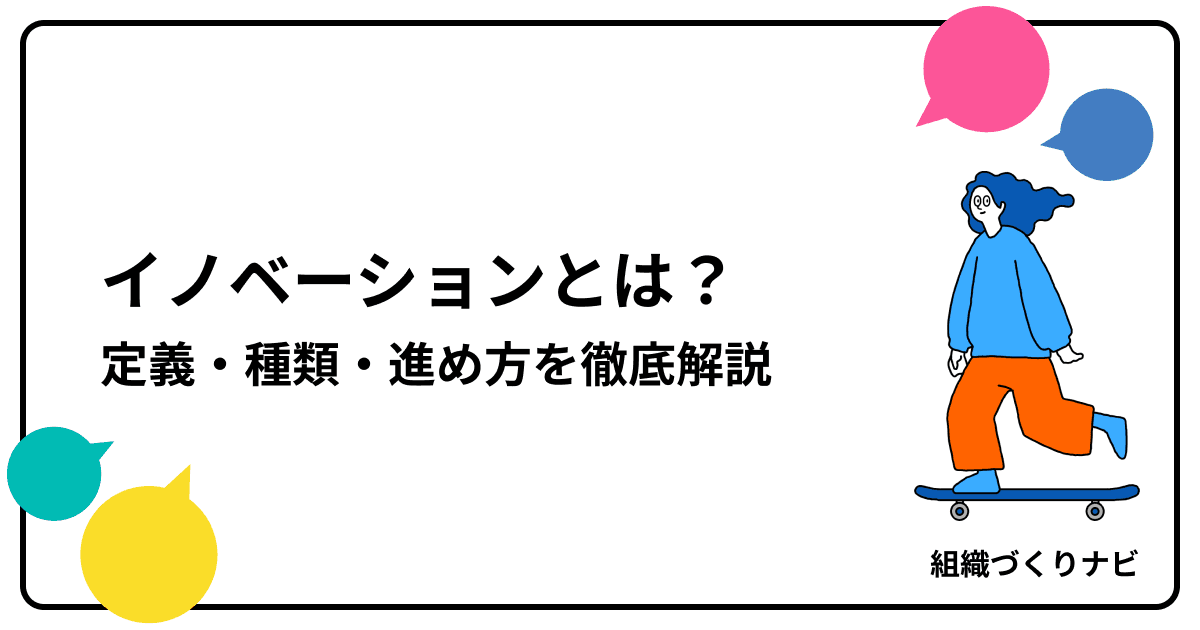
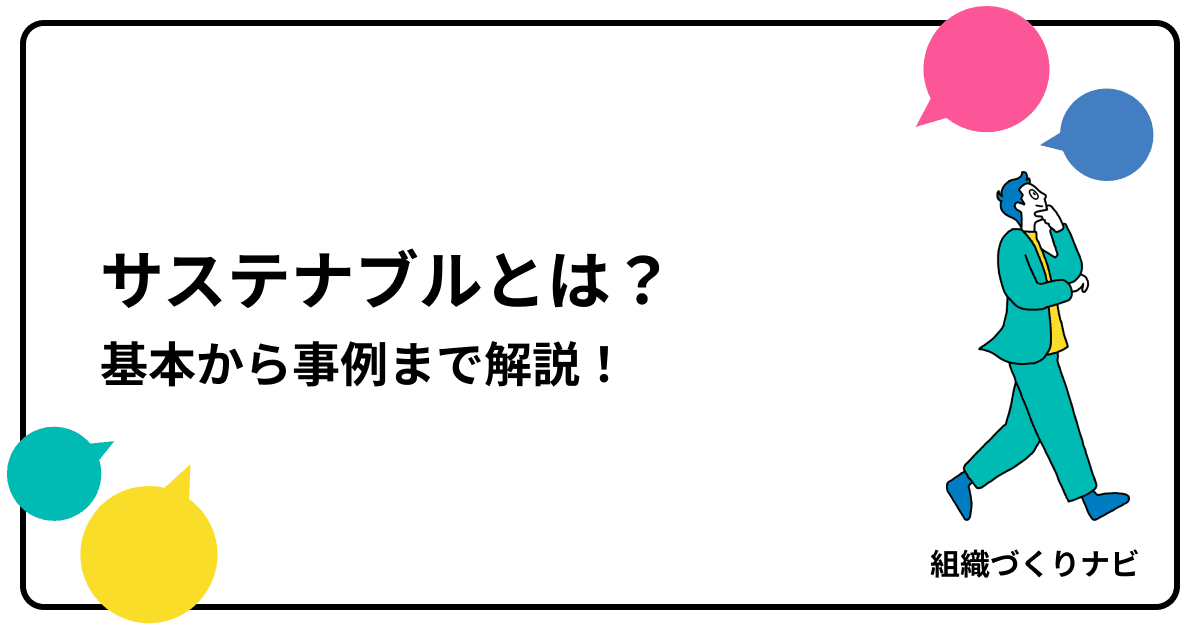
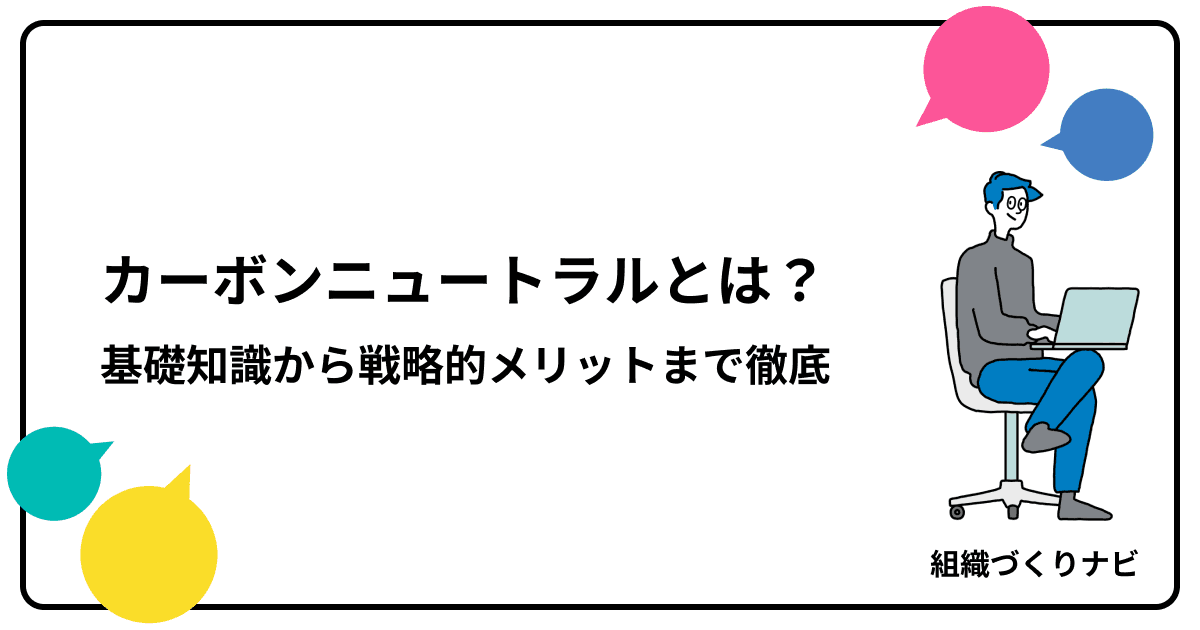
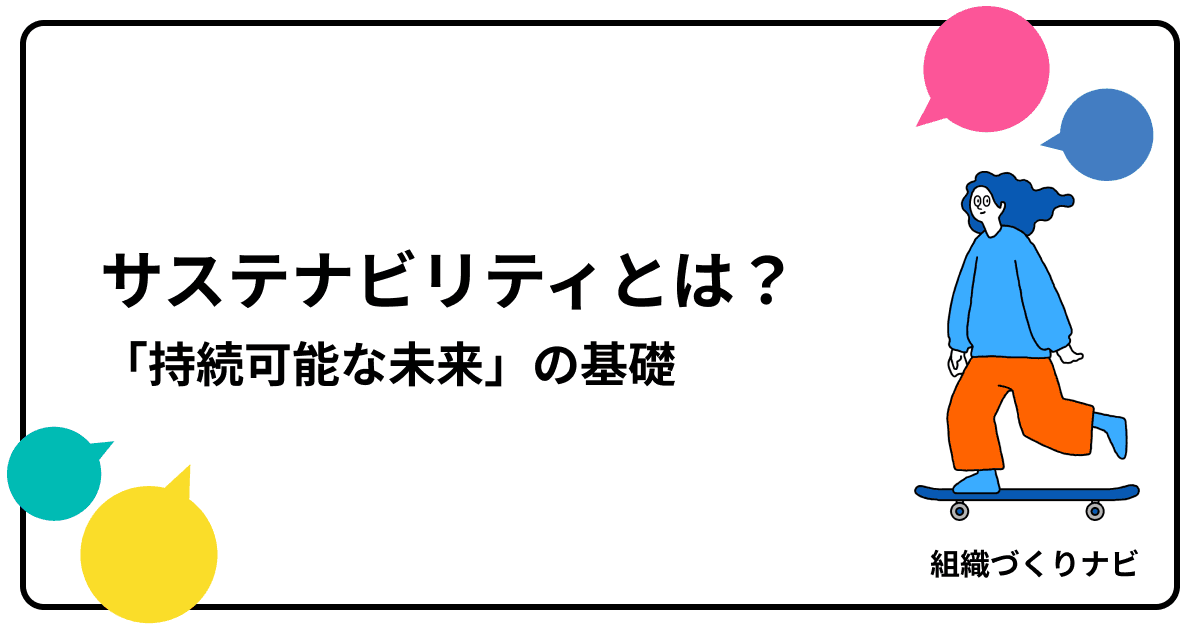
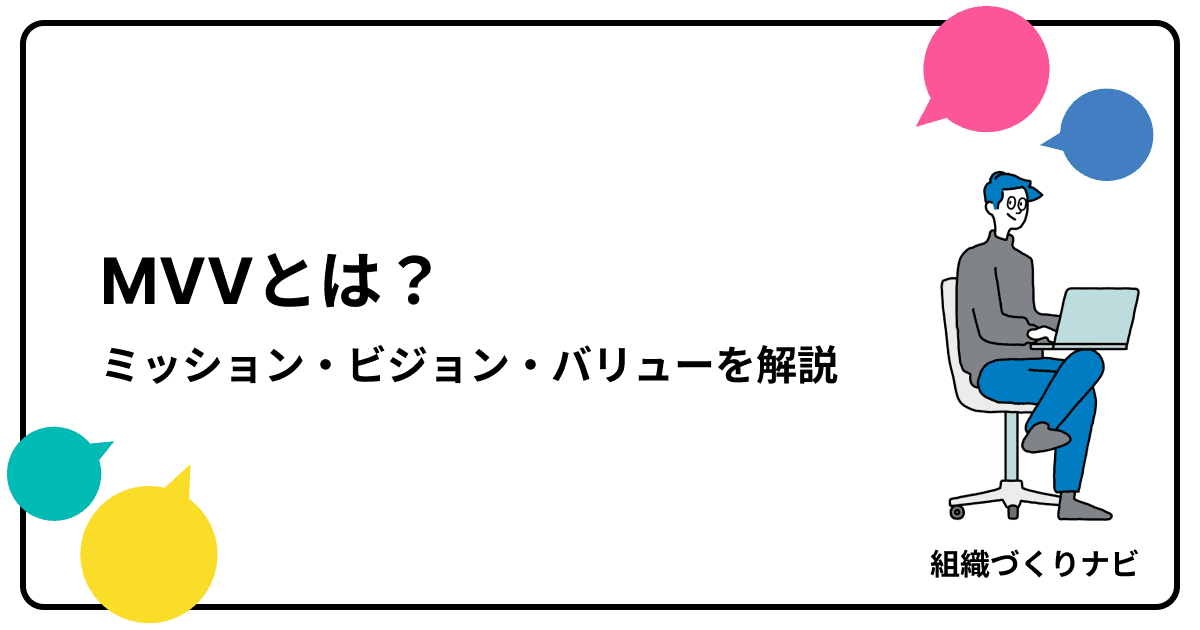




 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


