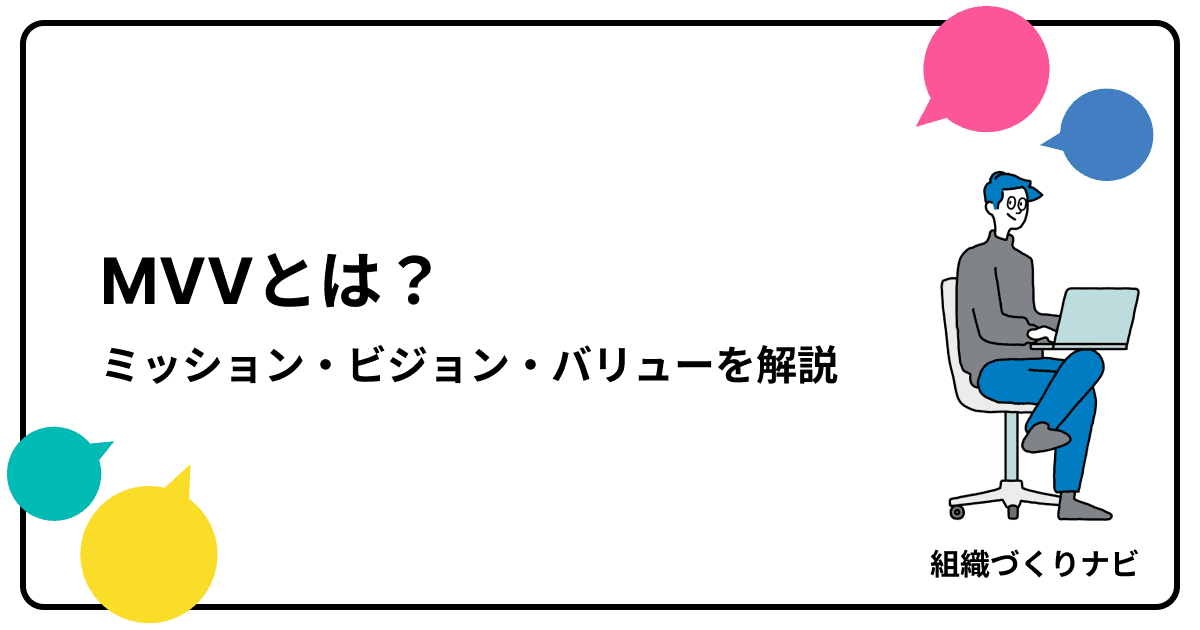
「MVV」って何?組織の羅針盤「ミッション・ビジョン・バリュー」を徹底解説
ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)は、組織が何のために存在し、どこへ向かい、どう行動するかを示す「羅針盤」です。ミッションは組織の存在意義、ビジョンは目指すべき未来の姿、バリューは日々の行動指針を明確にします。これらが明確になることで、社員は仕事の意義を理解し、組織は一体感を持って目標に向かえます。MVVは、人材採用・育成・評価の人事戦略、社員のエンゲージメント向上、そして変化に強い持続的な組織成長を実現する重要な土台です。ただ策定するだけでなく、共感を呼ぶプロセス、日常業務への具体的な落とし込み、定期的な見直しを通じて、MVVを「生きた羅針盤」として機能させることが、現代の企業経営に不可欠と言えるでしょう。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
組織の羅針盤「ミッション・ビジョン・バリュー」とは?
ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)は、組織が何のために存在し、どこへ向かい、そしてどう行動するかを示す、いわば企業の「羅針盤」です。これらが明確であることで、社員一人ひとりが自分の仕事の意味や意義を理解し、組織全体が一体感を持って目標に向かって進むことができます。人事や管理職の皆様にとっては、人材の採用、育成、評価、そして組織文化を醸成する上で重要な土台となる概念です。これらを深く理解し、組織内で共有することは、変化の激しい時代において組織の持続的な成長に不可欠と言えるでしょう。
ミッション:組織の存在意義と社会への約束
ミッションとは、「私たち(組織)は何のために存在しているのか?」「誰に、どんな価値を提供しているのか?」という、組織の最も根本的な問いに対する答えです。これは、企業活動の原点であり、時代や環境が変わっても簡単には揺らがない普遍的なものとされています。社員にとっては、日々の業務が社会や顧客にどう貢献しているのかを理解し、仕事に誇りを持つための拠り所となります。「私たちの会社は、こんな未来を実現するためにあるんだ」と胸を張って言える、活動の「なぜ?」にあたる部分です。
ビジョン:目指すべき未来の姿と成長の原動力
ビジョンとは、「私たちは将来、どんな姿になっていたいのか?」「どんな世界を実現したいのか?」という、具体的な未来の姿を示すものです。ミッションを実現した先に広がる、達成したい目標や理想の状態を指します。社員全員が「よし、あの山を目指して頑張ろう!」と思えるような、ワクワクするような到達点であり、具体的な行動を促すモチベーションの源となります。ミッションが「なぜ存在するか」という永遠の問いであるのに対し、ビジョンは「その存在意義を発揮してどこへ行き着きたいか」を明確にする役割を担っています。
バリュー:組織文化を育む行動指針
バリューとは、ビジョンを達成するために、社員が日々の活動で「何を大切にし」「どう行動すべきか」を示す具体的な指針です。「私たちはどのように働くべきか?」「どんな考え方で行動すべきか?」といった、組織内で共有される共通の価値観や行動のルールを指します。困った時にどう判断するか、新しいことを始める時に何を優先するかなど、迷った時の拠り所となり、組織文化を形作る上で非常に重要です。バリューを共有することで、社員一人ひとりが自律的に正しい意思決定を下せるようになり、組織全体の生産性向上にも繋がります。
ミッション・ビジョン・バリューが組織にもたらす計り知れない価値
ミッション・ビジョン・バリューが明確であることは、組織運営において計り知れない価値をもたらします。これらが共有されている組織では、社員は自分の仕事の目的意識を持ち、自主性を持って業務に取り組むことができます。また、組織全体が同じ方向を向き、一体感を持って目標達成に向けて進むため、組織の結束力が高まります。これらは強固な組織文化を形作り、持続的な成長を可能にする不可欠な土台と言えるでしょう。
人事戦略の明確化と採用力強化
明確なMVVは、採用活動における強力な武器となります。組織が求める人物像や価値観を言語化することで、採用担当者は候補者のスクリーニング基準を明確にできます。これにより、単なるスキルマッチだけでなく、組織文化にフィットする人材を見極め、採用ミスマッチを大幅に削減することが可能です。また、MVVは企業の強力なブランドイメージを構築し、多くの優秀な人材を引き寄せる磁石のような役割も果たします。
社員のエンゲージメント向上と自律的な成長促進
社員が自身の業務と組織のMVVが繋がっていると実感することで、仕事へのエンゲージメントは飛躍的に向上します。自分の仕事が社会や組織にどう貢献しているのかを理解することで、貢献意欲を高めます。また、バリューが日々の行動指針となることで、社員は自ら考え、判断し、行動する自律性を育みます。これにより、個人の成長が組織全体の生産性向上に直結し、主体性のある組織へと変革するのです。
変化に強い組織と持続的成長の実現
VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)と呼ばれる現代において、MVVは組織の確固たる軸となります。予期せぬ困難や環境変化に直面した際にも、組織の存在意義と目指すべき未来、そして行動規範が明確であれば、迅速かつ一貫性のある意思決定が可能になります。共通の価値観に基づく強固な組織文化は、困難を乗り越えるためのレジリエンス(回復力)を高め、組織を持続的に成長させる原動力となるでしょう。
関連する参考記事
別役:商品開発本部として、MVVIを作成したのは2020年でした。組織が目指す方向性をあらためて定義づけることで、社員一人ひとりが仕事の意義や価値を語れるようになったらいいなと。そしてその先で、個人がより働きやすくなったり、組織として成長したりすることを期待しています。
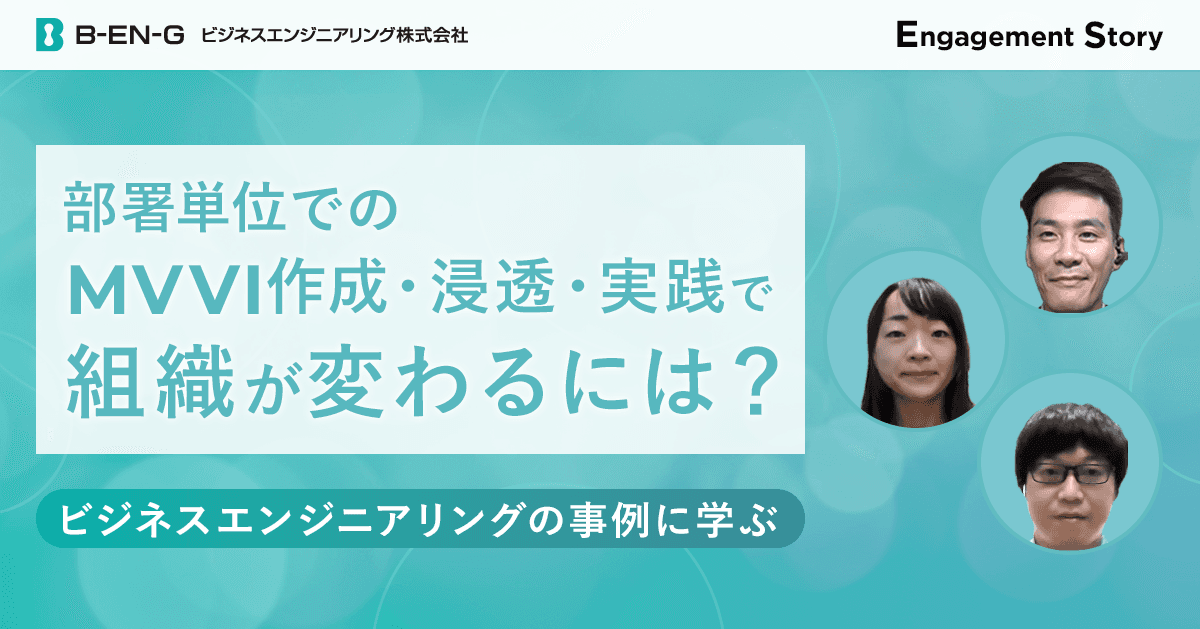
形骸化させない!ミッション・ビジョン・バリュー浸透の秘訣
ミッション・ビジョン・バリューは、ただ策定するだけでは意味がありません。真の価値を発揮するには、組織全体に深く浸透させ、日々の活動で実践される「生きた羅針盤」とすることが不可欠です。ここでは、MVVを形骸化させずに運用するための具体的な秘訣をご紹介します。
共感を呼ぶ策定プロセス
MVVの策定は、経営層だけが行うものではありません。社員が「自分たちのもの」と捉え、共感を持って行動に移せるようにするためには、策定プロセスに社員を巻き込むことが重要です。ワークショップや対話の場を設け、部署や役職を超えて意見を募ることで、多様な視点を取り入れ、MVVをより具体的で実効性のあるものにできます。このプロセス自体が、社員の当事者意識を高め、浸透への第一歩となるのです。
日常業務への落とし込みと実践
策定したMVVは、抽象的なスローガンで終わらせず、日々の業務に具体的な行動として落とし込むことが不可欠です。例えば、人事評価制度の項目にバリューに沿った行動を組み込んだり、社内研修でMVVと業務を結びつけるワークを行ったりするなど、具体的な接点を設けてください。また、MVVを体現している社員の事例を社内報や朝礼で共有し、ロールモデルを示すことも効果的です。これにより、MVVが「理想」ではなく「現実の行動」として根付いていきます。
定期的な見直しとアップデート
企業を取り巻く環境は常に変化しています。そのため、MVVも一度策定したら終わりではありません。定期的にMVVが現状にフィットしているか、組織の方向性や社員の意識と乖離していないかを見直す機会を設けることが重要です。事業戦略の変化や組織拡大に伴い、必要であればMVV自体をアップデートする柔軟な姿勢も求められます。MVVを「生きた羅針盤」として機能させ続けるためには、時代や環境に合わせた鮮度を保つ努力が不可欠です。
関連する参考記事
新美:まずは、エンゲージメント向上活動を行う目的や自部署の現状を自分が理解し、その上で色々な取り組みを行いました。いくつか例示すると、1つは、会社のビジョンをメンバーに伝える機会を増やしたことです。それまでは、期初キックオフでプレゼンするだけでしたが、自分たちの活動目的について一人ひとりが理解を深められるよう、部内会議を始め様々な会議でことあるごとに伝えるようにしました。

まとめ
ミッション・ビジョン・バリューは、単なる企業の標語ではなく、組織の存在意義、目指すべき未来、そして行動規範を明確にする企業の根幹を成すものです。これらを明確にし、組織全体に深く浸透させることは、人事戦略の成功、社員のエンゲージメント向上、そして変化に強い持続的な組織成長を実現するために不可欠な要素と言えるでしょう。策定にとどまらず、共感を呼ぶプロセス、日常業務への落とし込み、そして定期的な見直しを通じて、MVVを常に「生きた羅針盤」として機能させることが、現代の企業経営において最も重要な課題の一つです。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

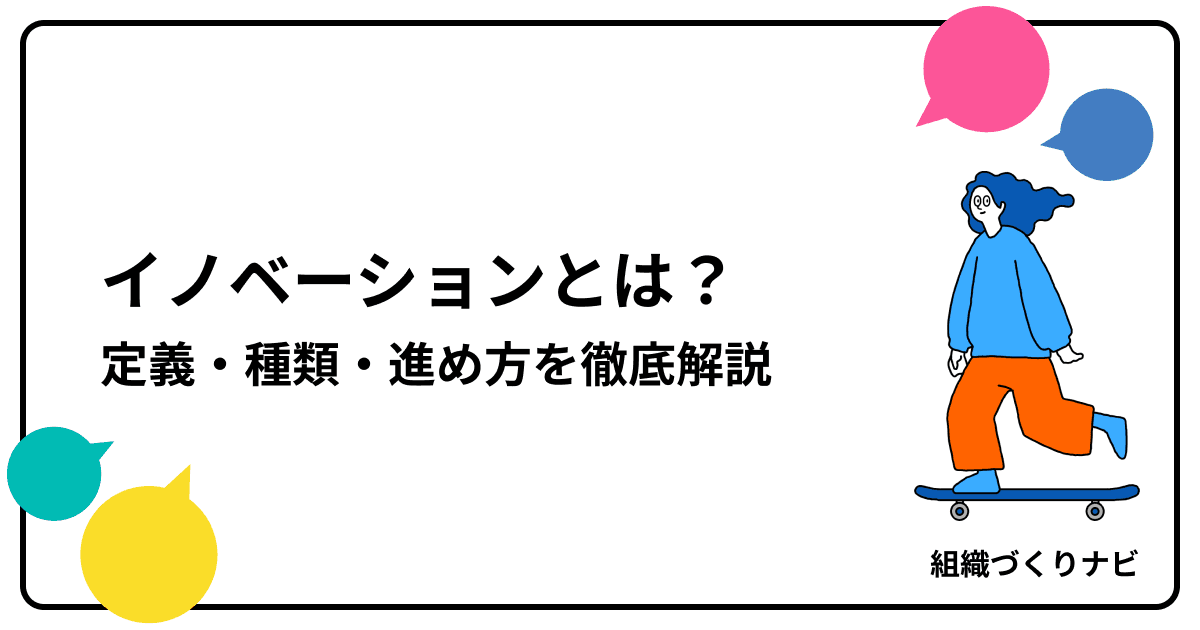
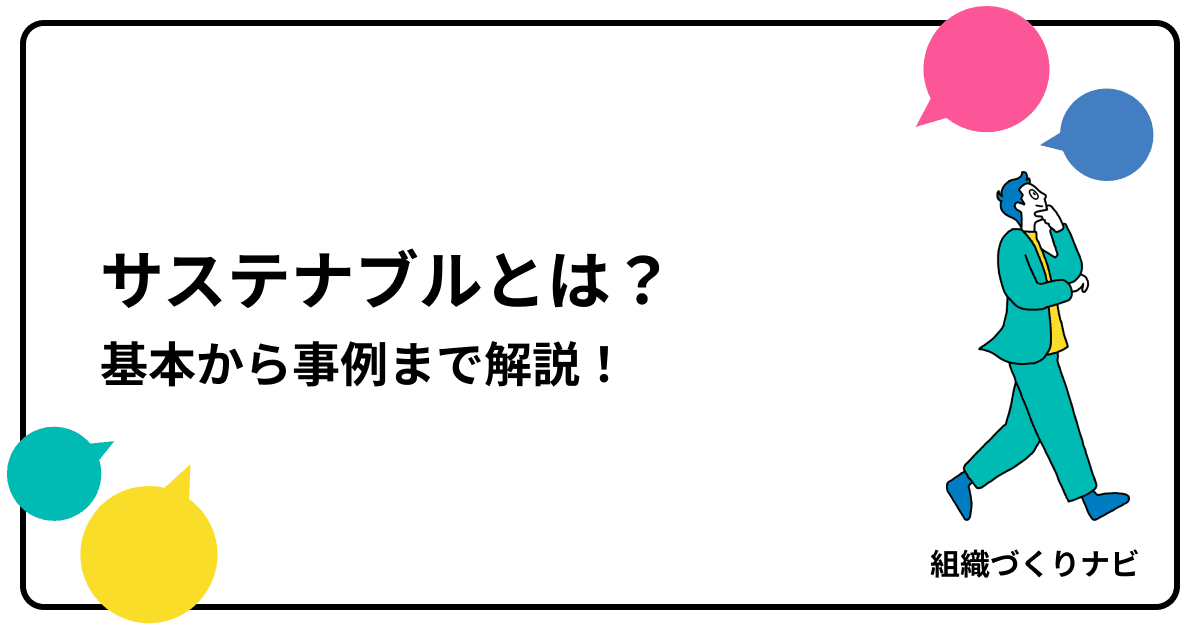
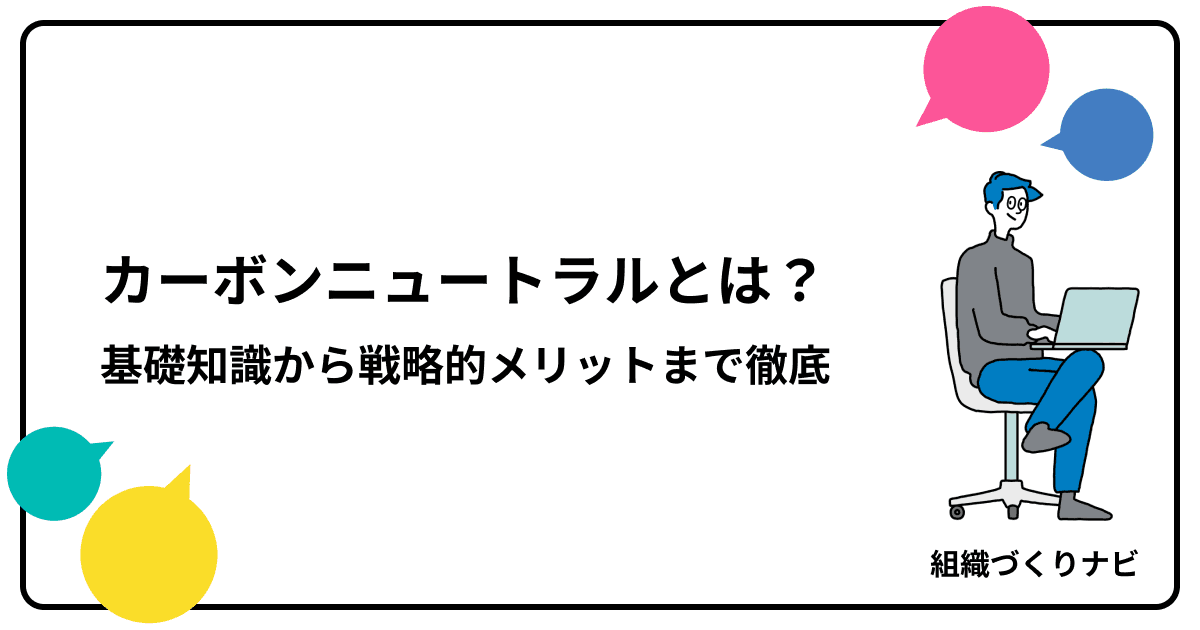
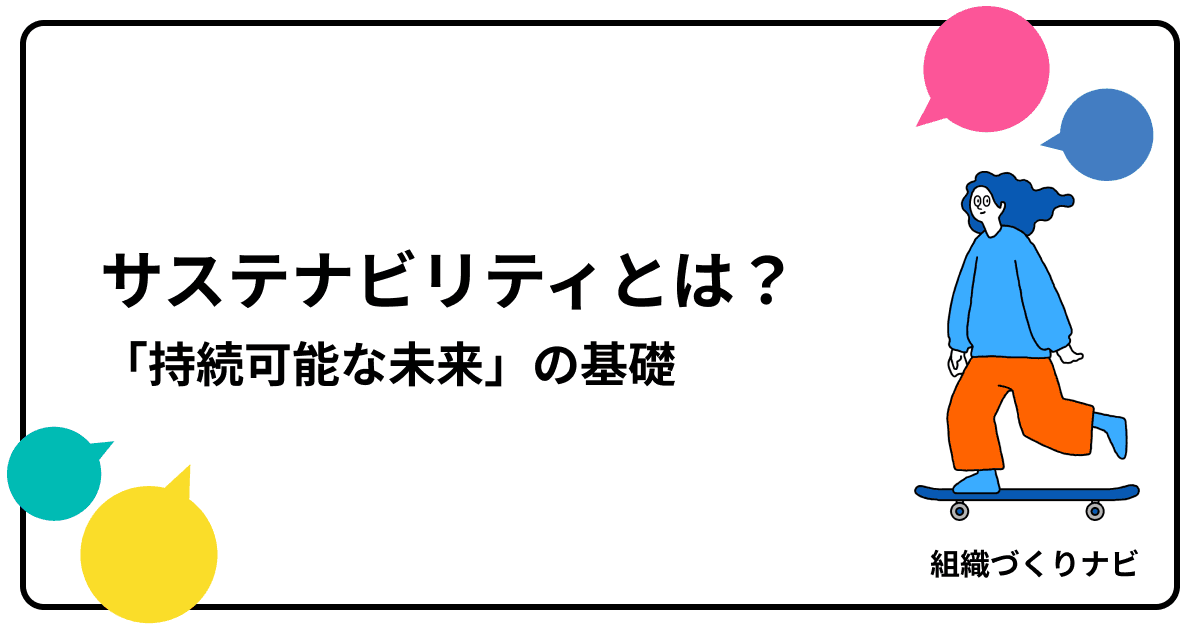
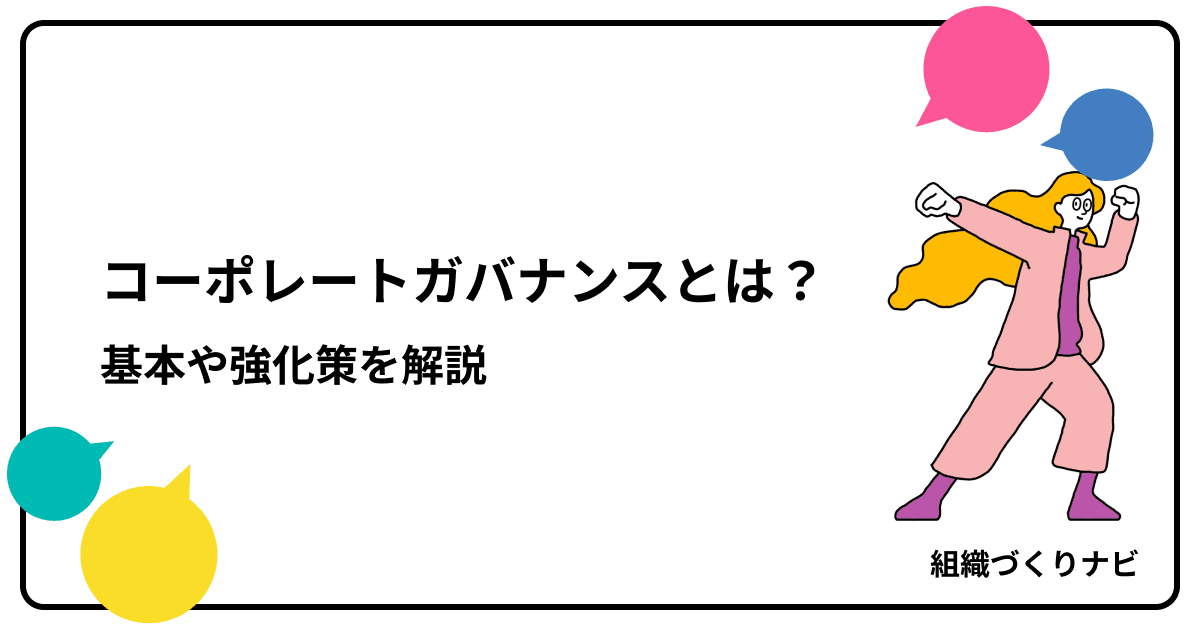




 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


