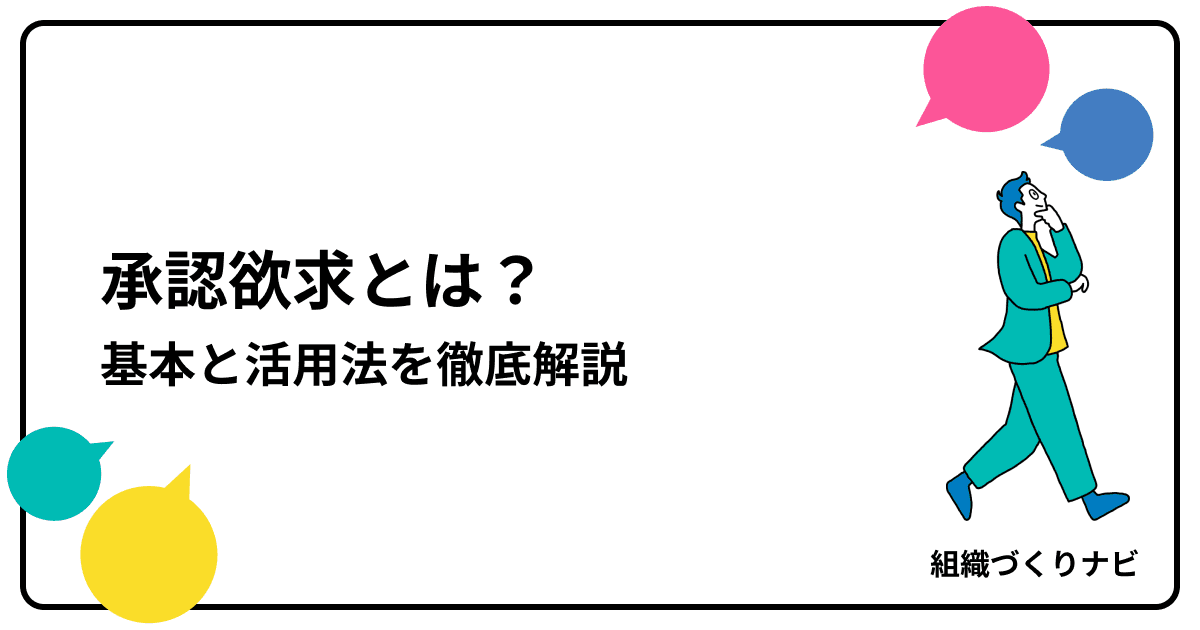
「承認欲求」とは?基本と活用法を徹底解説
承認欲求は、組織へのエンゲージメントに深く関わる心理です。人事・管理職がこの「認められたい」という心の動きを理解し活用することは、個人の成長と組織のパフォーマンス向上に不可欠。マズローの欲求段階説でも示されるように、他者からの評価を求める「他者承認」と、自分で自分を認める「自己承認」の二つの種類があり、どちらも健全に満たされることで、従業員の「もっと頑張ろう」という意欲や帰属意識が高まります。
具体的には、「見てるよ」というサインを送り、結果だけでなくプロセスも評価し、自己承認を促すサポートが重要。承認欲求が満たされないと、モチベーション低下や離職のリスクがありますが、適切に満たすことでエンゲージメントや定着率が向上し、組織全体の生産性や持続的な成長に繋がるでしょう。人事・管理職は、健全な承認文化を醸成し、従業員が安心して挑戦できる環境を築くことが求められます。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
承認欲求とは?人事・管理職が知るべき基本と活用法
「承認欲求」という言葉を耳にすることは多いですが、その本質を理解し、組織運営に活かすことは、人事や管理職の皆様にとって極めて重要です。エンゲージメントに深く関わるこの心理は、健全に満たされることで個人の成長を促し、ひいては組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。ここでは、承認欲求の基本的なメカニズムから、人事・管理職がどのように向き合い、日々のマネジメントに活用すべきかを分かりやすく解説します。
承認欲求とは何か?
承認欲求とは、「自分という存在や、自分の行い、努力が、他者や自分自身に認められたい」という、人間関係の基盤となる心理的欲求の一つです。これは、マズローの欲求段階説でも「社会的欲求」や「尊厳欲求」に位置づけられる、誰もが持つごく自然な感情と言えます。私たちは、自分の存在意義や価値を確認し、安心感を得るために、この欲求を満たそうとします。この承認欲求は、組織へのエンゲージメントに深く関わる、重要な要素です。
「認められたい」という心の動き
「認められたい」という心の動きは、私たちの行動や心理に大きな影響を与えます。例えば、仕事で良い成果を出した際に上司から具体的な褒め言葉をもらったり、困難なプロジェクトを成功させた時に同僚から感謝されたりすると、私たちは大きな喜びや達成感を感じます。これは、まさに他者からの承認欲求が満たされた状態です。また、自分自身で目標を達成し、「よくやった」と自己評価できることも、大切な自己承認です。この満たされた感覚こそが、自己肯定感を高め、「自分は組織に貢献している」「ここに居場所がある」という意識を育み、さらなる意欲へとつながるのです。
「承認欲求」にアプローチする施策事例↓
宮崎:また、前部署でなかなか成果を出せなくてどんよりした状態で異動してくるメンバーもいますし、中途入社のメンバーも増えているので、配属されてきたメンバーにあえて役割を与えることもしています。個々の得意なことに応じた役割、例えば、朝会での発表を任せるなどをすることで、「あなたのことを必要としているよ」ということが伝わるように意識しています。

承認欲求の種類
承認欲求は大きく分けて二つの種類があります。一つは「他者承認欲求」、もう一つは「自己承認欲求」です。他者承認欲求は、文字通り他者からの評価、賞賛、感謝、尊敬などによって満たされるものです。上司からの具体的なフィードバックや同僚からのねぎらいがこれにあたります。一方、自己承認欲求は、自分で自分を認め、肯定する気持ちです。目標達成による自信や、努力が実を結んだことによる満足感などがこれに該当します。組織で働く上では、他者からの承認だけでなく、従業員が自分で自分を認められる力を育むことも非常に重要であり、この両者のバランスが健全な承認欲求の実現には不可欠です。
なぜ人事・管理職にとって重要なのか?
人事・管理職にとって承認欲求への理解は、単なる心理学的な知識に留まらず、組織の健全な運営と従業員のパフォーマンス最大化に直結する極めて実践的な課題です。この欲求を深く理解し、適切に満たすことが、従業員のエンゲージメント向上、ひいては組織の定着率や生産性向上に直結するからです。承認欲求が満たされない状況は、従業員のモチベーション低下、離職率の上昇、さらには組織全体の生産性低下を招くリスクがあります。
従業員のモチベーション向上
承認欲求が満たされることは、従業員のモチベーションを飛躍的に向上させます。自分の仕事や努力が上司や同僚に認められ、「見てくれている」と感じることで、「もっと頑張ろう」「期待に応えたい」という内発的な意欲が湧き上がります。これは、一時的な外的報酬とは異なり、持続的な内発的動機付けとして、従業員のパフォーマンスを長期的に支える力となります。特に、結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスや努力を評価されることは、従業員が困難に直面した際の粘り強さや、新たな挑戦への勇気にもつながるでしょう。
エンゲージメントと定着率への影響
承認は、従業員の組織へのエンゲージメント(愛着と貢献意欲)を高め、結果として定着率の向上にも貢献します。自分の仕事が評価され、組織の一員として認められていると感じる従業員は、組織への帰属意識と貢献意欲を高め、より積極的に業務へ参画するようになります。逆に、承認が不足すると、「自分は認められていない」「組織にとって必要とされていない」といった不満や不信感につながり、エンゲージメントの著しい低下、ひいては離職へと発展する可能性が高まります。日々の小さな承認の積み重ねが、従業員と組織との強固な絆を築く土台となるのです。
承認欲求を健全に満たすために
人事や管理職の皆様は、従業員の承認欲求を理解し、それを健全な形で満たすための具体的な行動が求められます。単に褒めるだけでなく、一人ひとりの個性や努力に目を向けたアプローチが必要です。承認欲求は強すぎると、他者の評価ばかりを気にしてしまうといった不健全な状態に陥ることもあります。そうならないよう、他者からの承認と、自分で自分を認める自己承認の両方をバランスよく促すことが、健全な組織を築く上で極めて重要であることを認識してください。
「見てるよ」のサインを送る
従業員の承認欲求を満たす第一歩は、彼らの仕事ぶりや努力に「見てるよ」というサインを明確に送ることです。これは、大げさな称賛だけでなく、日々の何気ないコミュニケーションの中にこそ、その機会は潜んでいます。例えば、業務報告の際に単に進捗を確認するだけでなく、「あの資料、細部までよく作り込まれていて助かったよ」「新しいツール導入の件、スムーズに進めてくれてありがとう」といった具体的な言葉を添えることです。結果だけでなく、その過程でどのような工夫や努力があったか、どんな困難を乗り越えたかに関心を示し、ねぎらいの言葉をかけることで、従業員は自身の貢献が正しく評価されていると感じ、深い満足感を得られるでしょう。
結果だけでなくプロセスも評価する
管理職として、従業員の評価は結果だけでなく、そこに至るまでの「プロセス」も評価することが非常に大切です。特に若手社員や新しい業務に挑戦している従業員の場合、すぐに目に見える結果が出なくても、その過程での努力や工夫、成長の姿勢を認めることが、彼らの自己肯定感と挑戦意欲を育みます。
例えば、「今回のプロジェクトは目標達成には至らなかったが、未経験の分野に果敢に挑戦し、〇〇の新しい知見を得られたことは大きな収穫だ」「困難な状況でも最後まで粘り強く課題解決に取り組んだ姿勢を高く評価する」といったフィードバックは、従業員が失敗を恐れずに新たな挑戦を続ける勇気を与え、長期的なキャリア成長に不可欠な経験となるでしょう。
自己承認を促すサポート
他者からの承認も大切ですが、最終的には従業員が自分で自分を認められる「自己承認」の力を育むことが、持続可能なモチベーションと自律的な成長を促す上で不可欠です。管理職は、そのためのサポートを意識的に行うべきです。例えば、具体的な目標を、達成可能なスモールステップに分解して設定させ、一つひとつの達成を通じて「できた」という成功体験を積み重ねさせることです。
また、定期的な1on1ミーティングなどで振り返りの機会を設け、本人が自身の成長や貢献、克服した課題を言語化し、客観的に評価できるように促すことも効果的です。自己承認力を持つ従業員は、他者の評価に一喜一憂することなく、困難に直面しても自力で立ち直り、前向きに進むレジリエンス(回復力)を高めることができます。
まとめ
承認欲求は、エンゲージメント、そして定着率に深く関わる、組織運営において極めて重要な心理的欲求です。人事・管理職の皆様には、この欲求を深く理解し、単に褒めるだけでなく、日々の業務の中で「見てるよ」という具体的なサインを送ること、結果だけでなくプロセスも評価すること、そして従業員が自分で自分を認められる「自己承認」の力を育むサポートを行うことが求められます。
健全な承認の文化を組織全体で醸成することで、従業員一人ひとりが自分の価値を実感し、安心して挑戦できる環境が生まれます。これが、組織全体の生産性向上と持続的な成長に繋がり、競争が激化する現代において、競合他社との差別化を図る強固な基盤となるでしょう。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

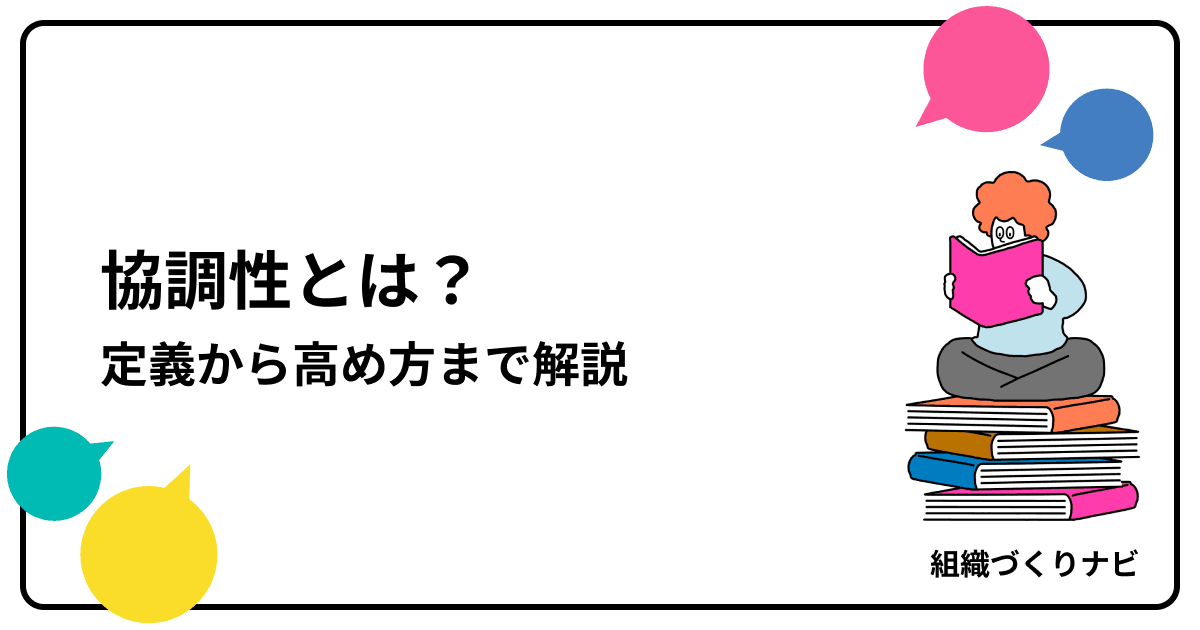








 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


