
目標達成指標の基本、KGIとは?
KGI(重要目標達成指標)とは、組織が最終的に達成したい最も重要な目標を、具体的な数値で示したものです。本記事では、KGIの基本的な意味から、中間目標であるKPI、成功要因であるKSFとの違い、設定するメリットまでを解説。売上や顧客満足度、定着率など、部門別KGI設定例やSMART原則に基づいた効果的な設定のポイントもご紹介します。目標の明確化、客観的な進捗評価、モチベーション向上に繋がり、組織全体のパフォーマンスを最大化するKGIの運用方法(PDCAサイクル)にも触れています。ビジネス目標達成に不可欠なKGIの基本から実践までを分かりやすく解説し、持続的な成長を支援します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
KGIとは?:ビジネス目標達成に不可欠な理由
KGIとは、「Key Goal Indicator」の略称で、日本語では「重要目標達成指標」と訳されます。これは、**「ビジネスやプロジェクトにおいて、最終的に達成したい最も重要な目標を、具体的な数値で示したもの」**です。例えば、「年間売上高を1億円にする」や「顧客満足度を90%にする」といった、組織が目指すべき最終的なゴールそのものを指します。
KGIを設定することで、組織全体の目指す方向性が明確になり、すべてのメンバーが同じ目標に向かって力を合わせることができます。漠然とした目標ではなく、具体的な数字で示すことがKGIの最大の特徴であり、目標達成の状況を客観的に評価し、次の戦略を立てる上で不可欠な指標となるのです。
KGIとKPIの決定的な違い:混同しやすい二つの指標を明確に
KGIと混同されやすい指標にKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)があります。人事や管理職の方々が最も悩むポイントの一つではないでしょうか。この二つの決定的な違いは、KGIが**「最終的なゴール」であるのに対し、KPIは「そのゴールを達成するための中間目標やプロセスを評価する指標」**である点です。
KGIが目指すべき「山頂」だとすれば、KPIはその山頂にたどり着くための「道のりにあるチェックポイント」と考えると分かりやすいでしょう。例えば、KGIが「年間売上1億円達成」であれば、KPIは「新規顧客獲得数月50件」「ウェブサイトのコンバージョン率5%」といった具合に設定されます。これらのKPIを達成することで、最終的なKGIの達成へと繋がっていくのです。KGIツリーやKPIツリーといった形で両者の関係性を可視化すると、より理解が深まり、目標設定の解像度が高まります。
関連する参考事例
2021年の夏頃、三井倉庫ホールディングスの人事の方から三井倉庫グループ全体でESGを推進していくというお話があり、ESGのSに含まれる社会の重要課題、安全・多様性、働きがいのある労働環境を実現するにあたって、KPIの一つを従業員エンゲージメントの向上に設定することが決定しました。
引用元:共通言語が組織を変える!経営×現場が挑むエンゲージメント推進〜三井倉庫エクスプレスの3年の変革〜【Teamwork Sessionレポート】
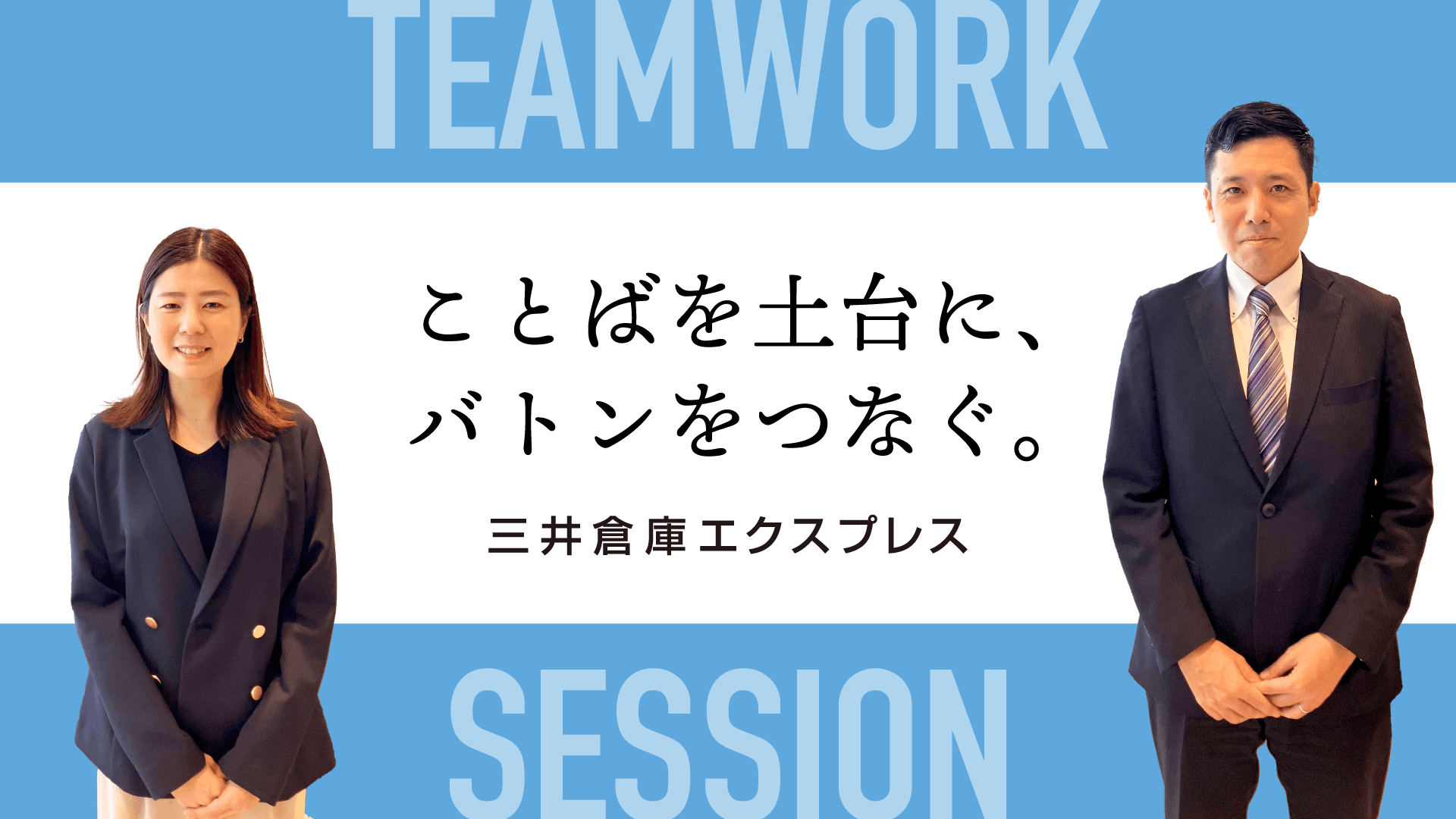
KGIとKSFの関係性:成功への戦略を可視化する
目標達成にはKGIとKPIだけでなく、KSF(Key Success Factor:重要成功要因)も欠かせません。KSFは**「KGIやKPIを達成するために、何が成功の鍵となるのかという要因」**を示すものです。KGIやKPIが「何を」「どれだけ」達成するかという「数値目標」であるのに対し、KSFは「どのように」「何が」達成を可能にするのかという「定性的な要素や具体的な戦略」を指します。
例えば、KGIが「顧客満足度90%達成」の場合、KSFは「迅速な顧客サポート体制の確立」や「従業員のサービススキル向上」「顧客からのフィードバックを製品開発に活かす仕組み」などが挙げられます。これらのKSFを実践することでKPIが改善し、結果としてKGIの達成に貢献するというように、三者は密接に連携しながら組織の目標達成を力強く後押しします。
KGIを設定するメリット:組織と個人のパフォーマンスを最大化する
KGIを設定することには、組織運営において多くのメリットがあります。
目標の明確化と方向性の統一
: 組織全体の目指す方向が明確になり、各部門や個人の業務が最終目標にどう貢献するかが分かりやすくなります。これにより、従業員一人ひとりが自身の役割を認識しやすくなり、主体性が向上します。
客観的な進捗評価
: 事業の進捗状況を客観的な数値で評価できるため、問題点を早期に発見し、迅速に改善策を講じることが可能です。これにより、感覚ではなくデータに基づいた意思決定が促進されます。
優先順位の明確化
: 限りある時間や人材、予算といった資源を最も効果的に配分するための指針となります。何が本当に重要なのかが明確になり、無駄な業務が削減されるでしょう。
モチベーションの向上と公平な評価
: 達成すべきゴールが具体的であるため、従業員のモチベーション向上に繋がりやすくなります。また、目標達成度合いを客観的に評価できるため、公平な人事評価制度の構築にも寄与します。
ステークホルダーへの説明責任
: 株主や顧客などのステークホルダーに対して、事業の成果や目標達成への取り組みを具体的に説明できるようになります。
エンゲージメント活動においても、ゴールを明確にすることは重要です。
関連する参考事例
前田: 各施策の目的や背景、最終的なゴールを部員にしっかり伝えること、あとはエンゲージメントアンバサダーのメンバーに、各施策を進める上での注意点などを助言してきました。例えば、「座談会が、ただの愚痴大会になると意味が無いので、次に繋がる建設的な意見を出し合う場にすること」とか、「出てきた各意見は、ただ聞くだけではなくて、きちんと改善・解決に向けて動かないと逆効果になる」とかですね。
引用元:エンゲージメントはなぜ必要? 三井住友銀行の職場発「誠実さと思いやり」で長く活躍する組織づくり
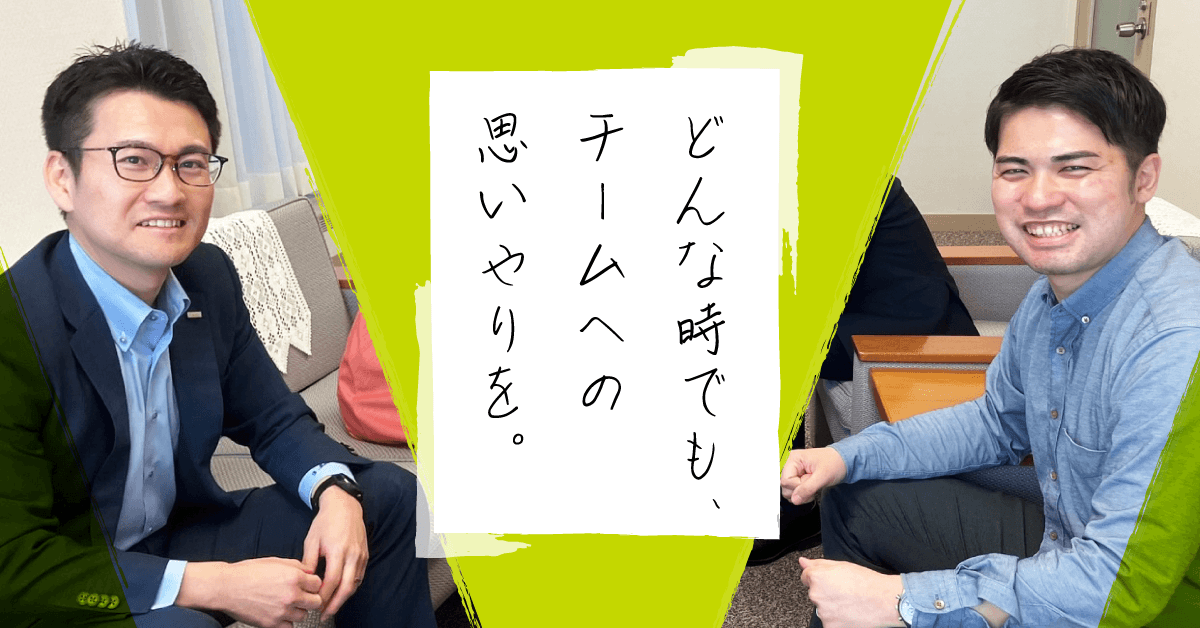
効果的なKGI設定の5つのポイント:SMART原則と具体的な実践法
効果的なKGIを設定するためには、以下の5つのポイントを意識することが重要です。これらは目標設定の基本である「SMART原則」にも通じる考え方です。
具体的かつ定量的に設定する(Specific & Measurable)
: 「売上を上げる」ではなく、「年間売上を1億円達成する」のように、誰が見ても同じ解釈ができる明確な数値目標にします。達成状況を測定できる形にすることが不可欠です。
期限を設定する(Time-bound)
: 「いつまでに」達成するのかを決めなければ、計画も進捗管理も曖昧になります。「〇年〇月までに」という明確な期限を設けることで、逆算して具体的な行動計画を立てられます。
実現可能性のある目標を設定する(Achievable)
: 高すぎる目標は従業員のモチベーション低下に繋がりかねません。しかし、低すぎる目標も成長を阻害します。過去の実績や現在のリソースを考慮し、ストレッチは効かせつつも達成可能な目標を設定することが大切です。
KGI達成に必要な要素を分解し、KPIと連動させる(Relevant)
: 最終目標であるKGIから逆算し、それを達成するための中間指標(KPI)を設計します。KGIとKPIが関連性を持つことで、全体として整合性の取れた目標体系が構築できます。
定期的に見直し、柔軟に調整する
: 市場環境や内部状況は常に変化します。一度設定したら終わりではなく、定期的に進捗を確認し、必要に応じてKGI自体やその達成戦略を見直す柔軟性を持つことが成功の鍵となります。
【人事・管理職向け】実践!部門別KGI設定例
KGIは企業全体の目標だけでなく、各部門の役割に応じて具体的に設定されます。人事・管理職の皆様が自部門のKGIを考える際の参考にしてください。
営業部門
: 企業全体のKGIが「売上〇〇円達成」の場合、営業部門のKGIは「年間契約件数〇〇件」「新規顧客からの売上〇〇円」「顧客単価〇〇円向上」など、直接的な収益に結びつくKGIを設定します。
マーケティング部門
: 「ECサイトの年間売上〇〇円」「ブランド認知度〇〇%向上」「リード獲得数〇〇件」「顧客ロイヤルティ(リピート率)〇〇%」のように、顧客獲得やブランド価値向上、顧客育成をKGIとします。
開発部門
: 「新製品リリース数〇〇件」「プロダクト利用継続率〇〇%」「不具合発生率〇〇%以下」「開発リードタイム〇〇日短縮」など、製品の質や顧客体験向上、効率化に関するKGIが考えられます。
人事部門
: 人事部門のKGIは、組織全体のパフォーマンス向上に直結する重要な指標です。「従業員定着率〇〇%」「採用コスト〇〇円削減」「従業員エンゲージメントスコア〇〇点」「〇〇人月あたりの研修時間〇〇時間」「評価制度浸透度〇〇%」といった、人材の定着・育成・活用に関するKGIを設定します。
各部門のKGIが最終的な企業全体のKGI達成にどう貢献するかを、KPIツリーのように俯瞰して考えることが大切です。これにより、部門間の連携もスムーズになり、組織全体としての目標達成力が向上します。
KGI設定後の運用と見直し:PDCAサイクルで成果を最大化
KGIは設定したら終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。KGIを組織の目標達成に真に役立てるためには、設定後の適切な運用と定期的な見直しが不可欠です。
定期的な進捗確認
: KGIとそれに紐づくKPIの進捗状況を、週次や月次で定期的に確認します。どのKPIが順調で、どのKPIが目標に届いていないのかを早期に把握することが重要です。
要因分析と改善策の検討
: 目標未達のKPIがあれば、その原因を深く掘り下げて分析します。外部環境の変化なのか、内部のプロセスに問題があるのか、それともKSFが十分に機能していないのか。原因が特定できたら、具体的な改善策をチームで検討します。
アクションプランの実行
: 検討した改善策を実行に移します。責任者を明確にし、期限を設けて取り組みます。
KGIとKPIの見直し
: 市場環境やビジネスモデルに大きな変化があった場合、あるいは設定したKGIが非現実的であったり、逆に容易すぎたりした場合は、KGIやKPIそのものを見直す勇気も必要です。柔軟性をもって対応することで、常に最適な目標設定を維持できます。
この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを回し続けることで、KGIは単なる数字の目標ではなく、組織の成長を加速させる強力な羅針盤となるのです。
まとめ
KGIは、組織が目指すべき最終的なゴールを数値で明確に示す**「重要目標達成指標」**です。人事や管理職の皆様にとって、KGIとKPIの違いを明確にし、効果的に設定・運用することは、組織のパフォーマンスを最大化し、持続的な成長を実現するために不可欠なプロセスとなります。
本記事では、KGIの基本的な意味から、KPI・KSFとの関係性、そして具体的な設定方法や部門別の事例、さらには設定後の運用と見直しの重要性までを解説しました。競合との差別化を図り、明確な目標設定を通じて組織の力を最大限に引き出すためには、単にKGIを設定するだけでなく、その背景にある「なぜ目標達成が重要なのか」を理解し、SMART原則に基づいた実現可能な目標を立て、PDCAサイクルで継続的に改善していくことが求められます。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

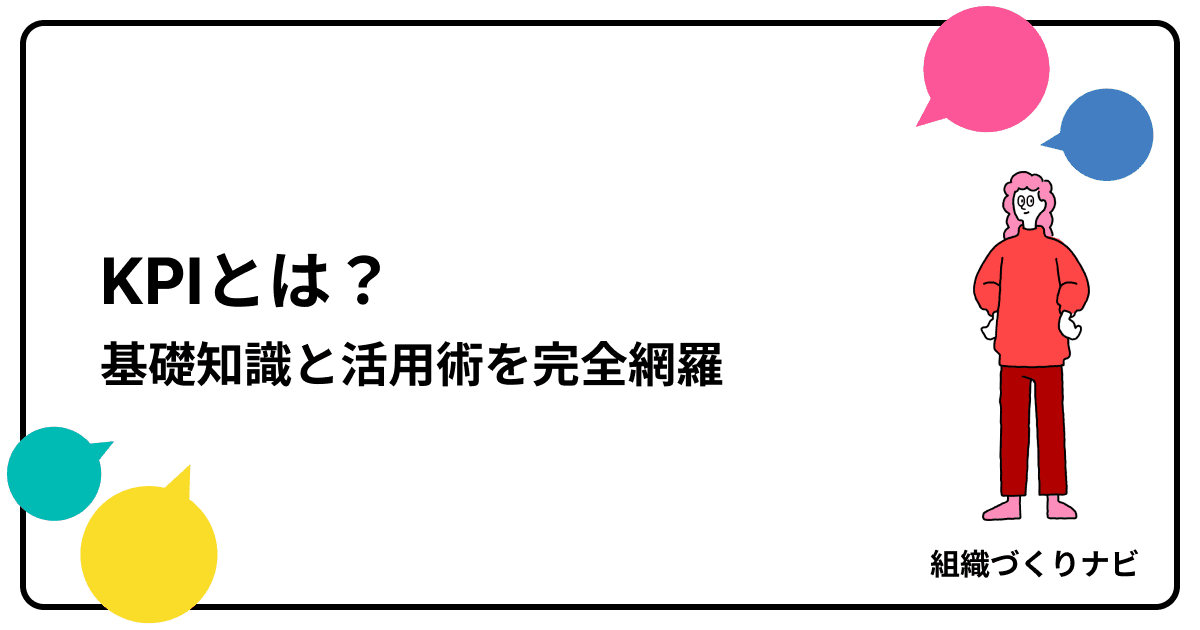

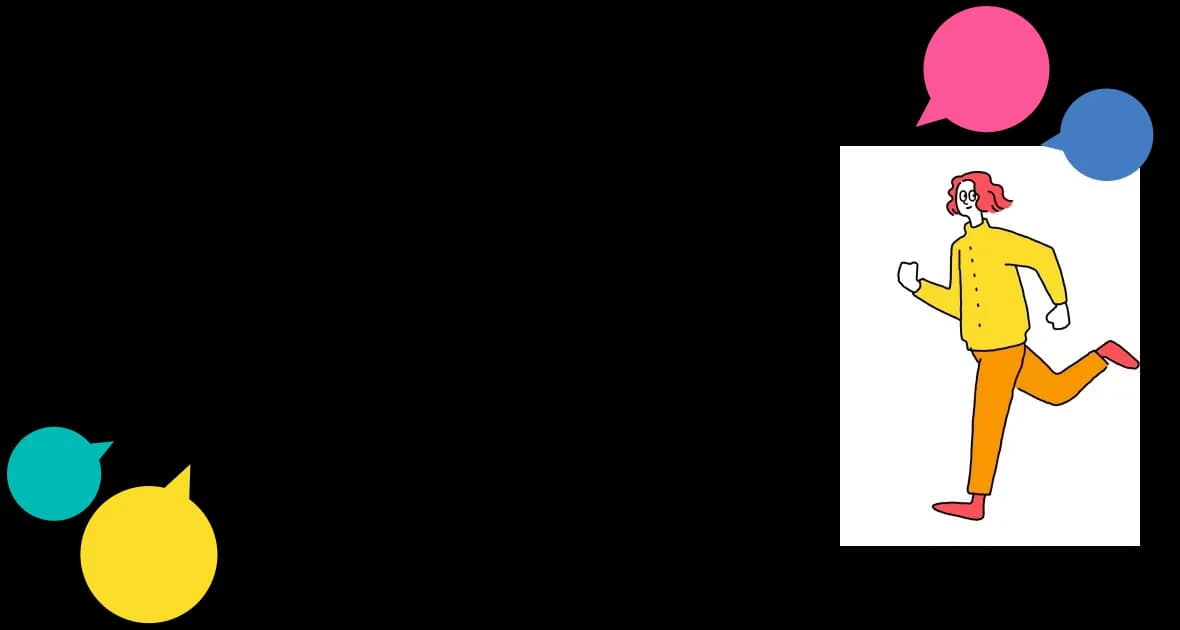






 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


