
「サーベイ」入門解説!組織の現状を可視化し成長に繋げるツールを知ろう
「サーベイ」とは、従業員のモチベーションや離職率、生産性など、組織の目に見えにくい課題をデータで可視化し、解決に導く強力な調査ツールです。本記事では、サーベイの基本的な定義から、働きがいを探る従業員満足度サーベイ、貢献意欲を高めるエンゲージメントサーベイ、多角的な成長を促す360度評価、タイムリーな現状把握に役立つパルスサーベイなど、主要な種類を解説。目的設定、匿名性確保、データ分析から具体的な改善行動、そして戦略的な活用まで、成功のためのステップとポイントを網羅しています。組織の健康状態を正確に把握し、持続的な成長と働きがいのある未来を切り拓くための羅針盤を、今こそ貴社に。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
人事・管理職必見!「サーベイ」とは?組織の課題を見つけ、成長を加速させる調査の力
人事・管理職のための「サーベイ」入門:組織の現状を可視化する重要性
日々、組織運営や人材マネジメントに携わる人事や管理職の皆様は、「従業員のモチベーションが上がらない」「離職率が高くて困る」「チームの生産性が伸び悩んでいる」といった様々な課題に直面されているかもしれません。これらの課題は目に見えにくく、原因が特定しにくいものも少なくありません。
そこで役立つのが「サーベイ」です。本記事では、この「サーベイ」という言葉の基本的な意味から、具体的な種類、そして組織の課題解決にどう活用できるのかを、人事・管理職の皆様が明日から実践できる形でわかりやすく解説いたします。組織の現状を正確に把握し、未来に向けた具体的な一歩を踏み出すための知識を、ぜひここから得てください。サーベイは、単なる調査に留まらず、組織の「健康診断」であり、未来を切り拓くための戦略的羅針盤となり得ます。
「サーベイ」の基本:組織変革の羅針盤
サーベイの定義と目的
「サーベイ(Survey)」とは、日本語で言うところの「調査」「概観」「測量」といった意味を持つ言葉です。ビジネスの文脈では、主にある特定の対象や集団に対して、質問や観察を通じて情報を集め、現状や傾向を把握する活動全般を指します。例えば、従業員に対してアンケートを実施して意見を集めたり、市場の動向を調べて顧客のニーズを探ったりするのもサーベイの一種です。
漠然と「何か問題がありそうだ」と感じている状況から一歩踏み出し、具体的なデータや事実に基づいて課題を浮き彫りにすることが、サーベイの最も重要な役割と言えます。これにより、感覚や経験則に頼りがちな意思決定から脱却し、客観的な根拠に基づいた組織運営を可能にします。
なぜ今、組織にサーベイが必要なのか?
組織にとってサーベイは、まるで健康診断のような役割を果たします。従業員のコンディション、組織全体の雰囲気、業務におけるボトルネックなど、普段は見えにくい内部の「声」や「状態」をデータとして可視化することで、人事や管理職は客観的な根拠に基づいて意思決定できるようになります。
例えば、従業員のエンゲージメント(会社への貢献意欲)が低いと感じた際、サーベイを通じて「コミュニケーション不足」が原因だと判明すれば、具体的な改善策として「定期的な1on1ミーティングの導入」などを検討できます。このように、サーベイは感覚に頼らない組織改善の第一歩となるだけでなく、組織文化の醸成や心理的安全性の向上といった、より高度な組織開発にも繋がる重要なツールなのです。VUCA時代において、変化の兆候をいち早く捉え、迅速に対応するためにサーベイは不可欠です。
主要なサーベイの種類
エンゲージメントサーベイ:組織への貢献意欲を高める
エンゲージメントサーベイは、従業員が自身の仕事や組織に対してどれほどの愛着や貢献意欲を持っているかを測定する調査です。単なる満足度だけでなく、「会社のために貢献したい」「自分の成長が会社の成長に繋がる」といった、より積極的な心理状態を測ります。エンゲージメントが高い組織は、離職率が低く、生産性も高い傾向にあるため、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。サーベイ結果からエンゲージメントを阻害する要因を特定し、例えば「成長機会の提供」や「企業理念の浸透」といった施策で、より一体感のある強い組織を目指すことが可能です。
360度評価サーベイ:多角的な視点で成長を促す
360度評価サーベイとは、対象となる従業員に対して、上司だけでなく、同僚、部下、そして本人自身が多角的に評価を行う調査方法です。これにより、自分では気づきにくい強みや課題を発見したり、周囲からどのように見られているかを客観的に知ることができます。特に管理職の方々にとっては、リーダーシップやコミュニケーション能力など、マネジメントスキルの具体的な改善点を見つける上で非常に有効です。評価の透明性を高め、個人の成長を支援し、チーム全体の協調性を高めることを目的として活用されます。
パルスサーベイ:タイムリーな現状把握で迅速な対応を
パルスサーベイは、短い期間で頻繁に実施される簡易的な調査です。大規模なアンケートとは異なり、数問程度の短い質問で構成され、週ごとや月ごとなど、短いスパンで従業員の意見や感情の変化を捉えます。これにより、組織の現状をリアルタイムに近い形で把握し、迅速に問題へ対応できるメリットがあります。例えば、新しい施策を導入した直後の従業員の反応や、特定のプロジェクト期間中のチームの士気など、変化の兆候を早期に察知し、手遅れになる前に改善策を講じるために活用されます。特に、リモートワークが普及した現代において、従業員のコンディションをタイムリーに把握し、必要なケアを行う上で非常に有効な手段と言えます。
サーベイを成功に導く実施ステップとポイント
目的設定と質問設計の極意
サーベイを成功させるためには、まず「何を知りたいのか」「何のために調査するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。漠然とアンケートを取るのではなく、「離職率が高い原因を特定したい」「従業員のエンゲージメントを向上させたい」など、具体的な課題意識を持つことが重要です。
その目的が明確になれば、それに沿った適切な質問を設計できます。質問は曖昧さを避け、具体的に、そして回答者が答えやすいように工夫しましょう。例えば、「満足していますか?」ではなく、「仕事の裁量権についてどの程度満足していますか?」と具体的に問うことで、より深い洞察が得られます。質問が的確であればあるほど、有益なデータを得られ、次のアクションに繋がりやすくなります。
従業員の協力と信頼を築く方法
サーベイは、従業員の正直な意見や心情を集めることが何よりも重要です。そのためには、回答の「匿名性」と「目的」を明確に伝え、従業員が安心して回答できる環境を整えることが大切です。例えば、結果が個人の評価に影響しないこと、得られた情報は組織改善のためにのみ使われることなどを事前に丁寧に説明しましょう。
「あなたの意見が組織を良くする」というメッセージを繰り返し伝えることで、従業員は安心して協力してくれるようになり、信頼に基づいた質の高い回答が集まります。透明性を持ち、従業員の声が真剣に受け止められる組織であるという姿勢を示すことが、協力体制を築く第一歩です。
関連する参考記事
礒端:会社がエンゲージメントサーベイを行う理由が分かりました。というのは、これまではスコアを何となく見ていただけでしたが、今回、サーベイ結果をもとにチームとして弱いところに気づき、そこをどのように改善していくかみんなで考え、考えた施策を実行する、と段階的に取り組んだことで、サーベイに回答して結果を分析し、施策に移すまでが繋がった感触を得ました。具体的な活動に移していける手応えも得られたこともあり、これからもそのサイクルを回していかないといけないと思うようになっています。

データ「分析」から具体的な「行動」への転換
サーベイは実施して終わりではありません。集まったデータは宝の山です。このデータを様々な角度から分析し、「何が課題なのか」「どの部署で問題が深刻なのか」「どの属性の従業員が不満を感じているのか」といった具体的な情報を引き出す必要があります。単なる平均値だけでなく、部署別、年代別、職種別などのセグメント分析を行うことで、より具体的な課題の根源が見えてきます。
そして、最も重要なのは、分析結果に基づいて「次の一手」を打つことです。例えば、「コミュニケーション不足」という結果が出たら、すぐに「部署ごとの定期的なランチ会を推奨する」や「社内SNSの活用を促進する」などの具体的な行動計画を立て、実行に移します。分析結果を行動に繋げ、その効果を測定することで、サーベイは真価を発揮します。
成果を最大化するためのサーベイ活用術と注意点
実施後のフィードバックと改善サイクルの確立
サーベイを実施する際に最も陥りやすい失敗は、結果を公表せず、あるいは具体的な改善行動を起こさずに終わってしまうことです。それでは従業員は「結局、何も変わらないのか」と感じ、次回以降の協力意欲を失ってしまいます。
重要なのは、サーベイの結果を従業員全体にフィードバックし、その結果を受けてどのような改善策を講じるのかを明確に伝えることです。たとえ小さな改善でも、「意見が反映された」という実感は、従業員の信頼とエンゲージメントを大きく高めます。PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回す意識を持つことが不可欠です。改善策の効果を再度のサーベイで検証するなど、継続的なサイクルを構築しましょう。
回答者のプライバシー保護と匿名性の徹底
従業員からの正直な意見を引き出すためには、回答者のプライバシー保護と匿名性の確保が絶対条件です。特に個人の特定に繋がるようなデータや、デリケートな質問への回答は厳重に管理し、漏洩がないように細心の注意を払う必要があります。
誰がどのような回答をしたのかが特定されないような仕組み(例えば、一定数以上の回答が集まらないと部署ごとの集計結果は出さないなど)を導入することも重要です。従業員が安心して本音を語れる環境を徹底して作り上げることが、サーベイの質を高める基盤となります。これは組織の心理的安全性を担保する上でも非常に重要な要素です。
サーベイ結果を「戦略」に昇華させる視点
多くの企業でサーベイは実施されていますが、その結果が単なる「現状報告」で終わってしまうケースも少なくありません。競合と差をつけるためには、サーベイ結果を経営戦略や人材戦略と紐付けて解釈し、未来に向けた具体的なアクションプランに落とし込む視点が不可欠です。
例えば、「エンゲージメントが低い」という結果が出た場合、それは単に施策を打つだけでなく、「企業のビジョン浸透が不十分なのではないか」「キャリアパスが不明確で従業員の成長意欲を阻害しているのではないか」といった、より本質的な経営課題と関連付けて考える必要があります。時には、サーベイ結果が予期せぬ「ネガティブな真実」を突きつけることもありますが、それらを真摯に受け止め、変革のチャンスと捉えることが重要です。
データから示唆を得るだけでなく、その背景にある組織文化、経営層のメッセージ、現場のリアルな感情なども加味して多角的に分析し、短期的な改善だけでなく、中長期的な組織能力の向上に繋がる戦略を立案する。この「戦略的視点」こそが、サーベイの真価を最大限に引き出し、組織の持続的な成長を支える鍵となります。
関連する参考記事
佐藤:当社では、Wevoxのカスタムサーベイを使って組織ごとのWevoxの活用度を把握するアンケートを定期的にとっています。その結果から、スコアの共有ができていない組織や、スコアの共有や話し合いはできていても、アクションを実施するところまではできていない組織などがあり、組織によって活用度が異なっていることがわかりました。
そこで、Wevoxのスコアを活用してアクションを実施している組織の事例をHuman Capital Report 2024で共有することで、「スコアの共有→話し合いの実施→アクションの実施」というサイクルを多くの社員がイメージできることを期待しています。

まとめ:サーベイで組織の未来を切り拓く
本記事では、「サーベイ」の基本的な意味から、人事・管理職の皆様が組織の課題解決に活用できる種類、導入から活用までのステップ、そして成功のための注意点、さらには競合との差別化を図るための戦略的活用術までを解説いたしました。サーベイは、漠然とした組織の課題を明確にし、データに基づいた具体的な改善策を導き出す強力なツールです。
従業員満足度、エンゲージメント、多角的な評価、そしてタイムリーな現状把握まで、様々な種類のサーベイを目的に合わせて賢く活用することで、組織の健康状態を常に把握し、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。
単に調査を実施するだけでなく、得られたデータを真摯に受け止め、改善行動に繋げ、そのプロセスを従業員にフィードバックすることが成功の鍵です。そして、その結果を経営戦略と連動させる視点を持つことで、サーベイは組織の持続的な成長を推進する強力なエンジンとなるでしょう。ぜひ、サーベイを積極的に活用し、従業員が生き生きと働き、組織が持続的に成長する未来を切り拓いてください。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

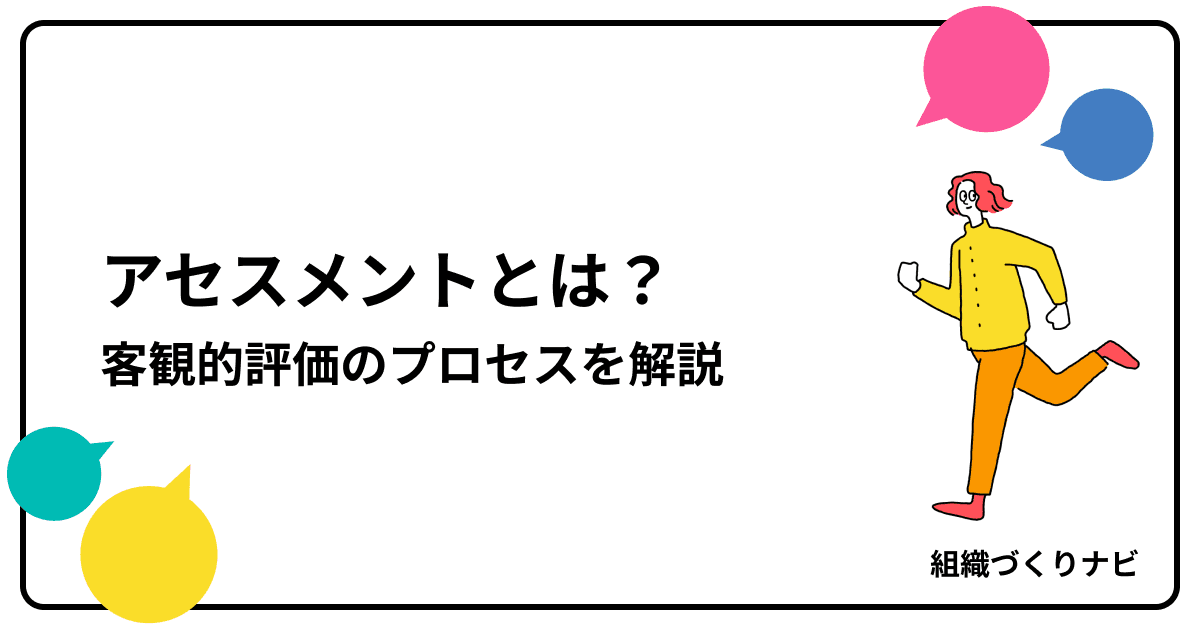








 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


