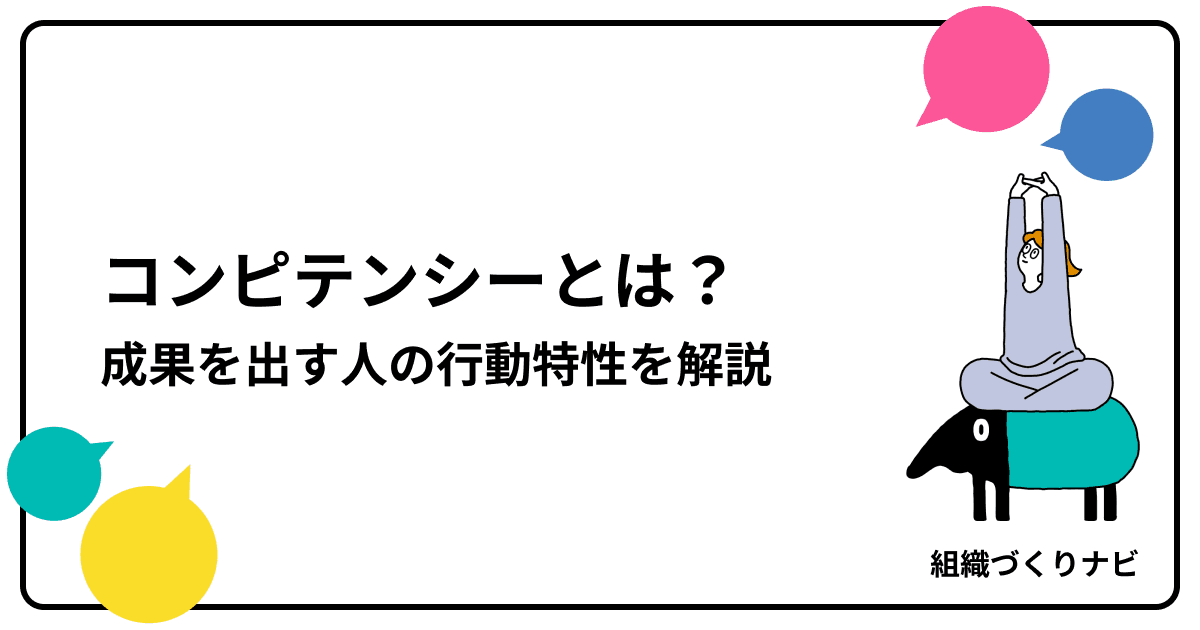
コンピテンシーとは?成果を出す人材の行動特性を基本から徹底解説
コンピテンシーとは、高い成果を出し続ける人に共通する「行動の習慣」や「考え方」のこと。単なる知識やスキルだけでなく、「どのように行動して成果を出しているか」に焦点を当てる考え方です。現代の予測困難な時代において、組織の成長には社員一人ひとりの自律的なパフォーマンスが不可欠であり、コンピテンシーはその実現に役立ちます。本記事では、コンピテンシーの基本から、人事評価や採用、人材育成への具体的な活用方法、導入のメリット・デメリット、成功の秘訣までを解説。社員の能力を最大限に引き出し、変化に強く生産性の高い組織を築くためのヒントを提供します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
コンピテンシーとは?成果を出す人材の共通行動特性を徹底解説
「優秀な社員とそうでない社員の違いは何だろう?」「人事評価が曖昧で、社員の納得感が低い」「社員の能力をどう伸ばせばいいか分からない」――。もし、あなたがこのような課題を抱えている人事担当者や管理職であれば、「コンピテンシー」という考え方が、その解決の糸口になるかもしれません。
コンピテンシーは、単なる知識やスキルでは測れない、実際に高い成果を出す人に共通する「行動の習慣」や「考え方」を指します。本記事では、コンピテンシーの基本的な意味から、なぜ今この概念が重要視されるのか、導入するメリット・デメリット、そして具体的な活用方法までを分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの組織が目指す「理想の人材像」を明確にし、社員一人ひとりの成長と組織全体の生産性向上に繋がるヒントが得られるでしょう。
コンピテンシーとは?成果を出す人材の行動特性
優れたパフォーマンスを生む「行動」に注目します
コンピテンシーとは、高い成果を継続的に出す人に共通して見られる「行動特性」や「思考パターン」を指します。例えば、「積極的に周囲と協力する」「困難な課題にも諦めずに取り組む」「顧客のニーズを深く理解しようと努める」といった具体的な行動の積み重ねが、コンピテンシーの核となります。これは、単に「能力がある」というだけでなく、その能力を「どのように発揮しているか」という、より実践的な側面に焦点を当てた概念です。企業が求める人材像を明確にし、その行動を評価・育成することで、組織全体のパフォーマンス向上を目指します。
スキルや知識とは違う?類語との違いを明確にします
コンピテンシーは、しばしば「スキル」や「知識」と混同されがちですが、これらには明確な違いがあります。「知識」は「知っていること」、「スキル」は「できること」を指します。例えば、「語学力がある(スキル)」や「経営学を学んだ(知識)」は、それぞれ知識やスキルにあたります。これに対し、コンピテンシーは「その知識やスキルを、どのような状況で、どのように活用し、実際に成果に繋げたか」という、より具体的な行動や態度に着目します。つまり、知っている、できるだけでなく、「実際に成果を出すためにどう行動するか」がコンピテンシーのポイントなのです。
なぜ今、コンピテンシーが求められるのか?
成果主義と変化の激しい時代への対応
コンピテンシーという概念は、1970年代にアメリカのハーバード大学で、「学歴や知能が高いだけでは、必ずしも仕事で高い成果が出るとは限らない」という研究結果から生まれました。これまでの、知識や経験を重視した評価制度では見えにくかった「成果を出すための行動」に焦点を当てることで、より本質的な人材評価や育成が可能になると考えられたのです。
現代は、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)と呼ばれる予測困難な時代であり、企業には常に変化に対応し、新たな価値を創造する力が求められています。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や人的資本経営の重要性が増す中で、社員一人ひとりが自律的に高いパフォーマンスを発揮できるような組織作りが不可欠です。このような背景から、単なる知識やスキルでは測れない「成果を再現する行動特性」を明確にし、評価・育成するコンピテンシーが、企業の持続的な成長を実現するための有効な手段として再び注目を集めているのです。
コンピテンシーを導入するメリットとデメリット
企業にも従業員にも嬉しい!導入のメリット
コンピテンシーを導入することは、企業と従業員の双方に大きなメリットをもたらします。企業側から見れば、まず人事評価の公平性・納得感が高まります。評価基準が「具体的な行動」で明確になるため、「なぜその評価なのか」が分かりやすくなり、社員は評価に納得しやすくなります。次に、採用活動におけるミスマッチを防止し、自社に合った人材を見極める精度が向上します。さらに、人材育成が効率化され、社員一人ひとりが「どのような行動をすれば成長できるのか」を具体的に理解し、計画的に能力を伸ばせるようになります。結果として、組織全体の生産性向上やエンゲージメント向上にも繋がり、企業の競争力強化に貢献するでしょう。
導入前に知っておきたい注意点やデメリット
コンピテンシー導入には多くのメリットがありますが、いくつかの注意点やデメリットも存在します。まず、コンピテンシーモデルの策定には、時間とコストがかかります。高い成果を出している社員へのヒアリングや分析、評価項目への落とし込みには専門的な知見と労力が必要です。また、策定したモデルが現実と乖離してしまうと、社員の不満や評価の形骸化に繋がりかねません。さらに、評価が主観的にならないよう、評価者のトレーニングが不可欠です。導入後も、定期的な見直しと改善を怠ると、時代や組織の変化に対応できず、機能しなくなるリスクもあります。これらの課題を認識し、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。
企業でのコンピテンシー活用シーン
公平で納得感のある「人事評価」の実現
コンピテンシーは、人事評価の場面で特にその真価を発揮します。従来の成果目標やスキル評価だけでは測れなかった「成果に至るまでのプロセスや行動」を具体的に評価できるようになるからです。例えば、「顧客との関係構築力」というコンピテンシーがあれば、単に「売上目標達成」だけでなく、「顧客の課題を深くヒアリングし、期待を超える提案を行った」といった行動を評価できます。これにより、評価基準が明確になり、評価される側も「どのような行動をすれば評価されるのか」が理解しやすくなるため、評価への納得感が高まり、社員のモチベーション向上に繋がります。
自社に合う人材を見極める「採用活動」
採用活動において、コンピテンシーは「自社で本当に活躍できる人材」を見極めるための強力なツールとなります。事前に自社で高い成果を出している社員のコンピテンシーモデルを明確にしておくことで、単に経験やスキルがあるだけでなく、「自社の文化や仕事の進め方に合致し、活躍を再現できる行動特性を持つ候補者」を効率的に探し出すことが可能になります。面接では「過去に困難な状況に直面した際、どのように行動しましたか?」「チームで協働する上で、どのような役割を果たしてきましたか?」といった具体的な行動を問う質問をすることで、候補者のコンピテンシーを効果的に見極めることができます。
計画的で効果的な「人材育成」
コンピテンシーは、人材育成においても非常に有効です。社員一人ひとりの現状のコンピテンシーレベルと、期待されるコンピテンシーレベルとの「ギャップ」を明確にすることで、個別最適な育成プランを立てることができます。例えば、「課題解決力」が不足している社員には、具体的なケーススタディを用いた研修や、OJT(On-the-Job Training)を通じて先輩社員の行動を学ぶ機会を提供するといった具体的な育成施策を講じられます。これにより、社員は自身の成長課題を明確に認識し、どのような行動を意識すれば良いか分かりやすくなるため、より計画的で効果的なスキルアップ・キャリアアップに繋がります。
関連する参考記事
また他の施策としては、エンゲージメントとは⼼なので、その⼼と⼈事評価にあるコンピテンシーの項⽬をどうやって紐づけて⾏こうかなと考えはじめました。本来、⼼と⼈事評価はくっつけてはいけないはずだと考えていました。たとえば、ものすごく能⼒がある⽅が職種や部署を超えて能⼒を提供するような価値観は、良い部分も悪い部分もあるというのが私の経営者としての考え方としてあったんです。でも実際は仲間を助けるような⼈と⼀緒に働きたいというコメントがアンケートにとても多く出てきたので、それを⼈事評価のコンピテンシーの項⽬に⼊れていくというキャッチボールはしました。

コンピテンシー評価の導入ステップと成功の秘訣
導入前に知るべき3つのステップ
コンピテンシー評価を導入する際は、以下の3つのステップで進めるのが一般的です。
コンピテンシーモデルの策定
: まず、自社で最も高い成果を出している「モデル社員」を選出し、その社員がどのような行動や思考パターンを持っているかを徹底的に分析します。ヒアリングや観察を通じて、
成果に繋がる共通の行動特性を抽出し、言語化
します。これが、自社独自のコンピテンシーモデルとなります。
評価項目の設定とレベル定義
: 策定したコンピテンシーモデルをもとに、具体的な評価項目へと落とし込みます。各項目について、
「期待される行動」を具体的な記述で表現し、さらにその達成度を測るためのレベル(例:5段階)を詳細に定義
します。これにより、評価者が客観的に評価できる基準を設けます。
運用と定期的な見直し
: 設定した評価項目とレベルに基づき、実際に人事評価や面談でコンピテンシー評価を運用します。評価者への十分なトレーニングも不可欠です。導入後も、
組織や事業環境の変化に合わせて、定期的にコンピテンシーモデルや評価項目を見直し、改善していく
ことが重要です。
導入を成功させるための注意点
コンピテンシー評価の導入を成功させるためには、いくつかの注意点を押さえる必要があります。
経営層と現場の理解・協力
: コンピテンシー導入の目的やメリットを全社で共有し、経営層から現場社員までがその重要性を理解し、協力体制を築くことが不可欠です。
現実的な評価項目の設定
: 理想を追求しすぎず、現場で実際に観察・評価できる具体的な行動を項目として設定しましょう。抽象的すぎると評価が難しくなります。
評価者への教育とトレーニング
: 評価基準の解釈や、公平な評価方法について、評価者となる管理職への徹底した研修が欠かせません。評価者の主観に頼りすぎないよう、繰り返しトレーニングを行うことが重要です。
過度な依存を避ける
: コンピテンシーはあくまで評価・育成の「ツール」の一つであり、全てをコンピテンシーだけで測ろうとすると、かえって柔軟性を失う可能性があります。他の評価軸と組み合わせるなど、バランスの取れた運用を心がけましょう。
まとめ:コンピテンシーで強い組織作りを
本記事では、コンピテンシーが「高い成果を継続的に出す人に共通する行動特性」であることを解説しました。単なる知識やスキルではなく、「どのように行動して成果を出しているか」に焦点を当てることで、人事評価の公平性を高め、採用ミスマッチを防ぎ、人材育成を効率化するなど、多くのメリットがあることをご理解いただけたかと思います。
VUCA時代と呼ばれる現代において、コンピテンシーの導入は、単なる人事制度改革に留まりません。社員一人ひとりが自律的に成長し、企業文化を醸成する力を育むことで、変化に強く、持続的に成長できる強い組織を作るための重要な戦略です。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

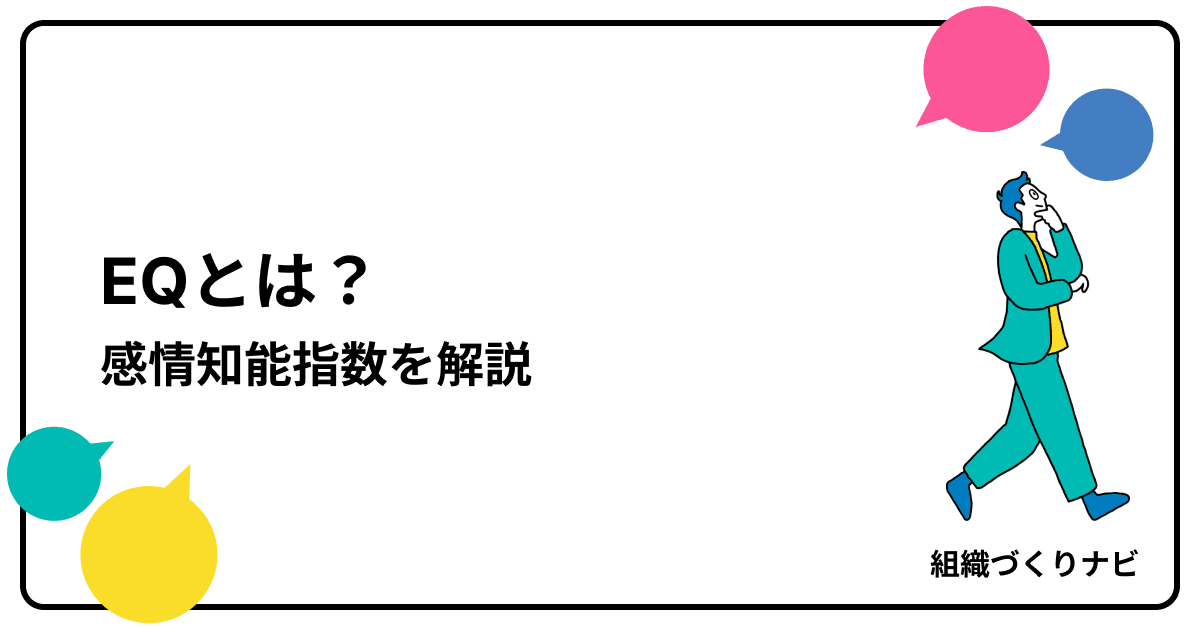
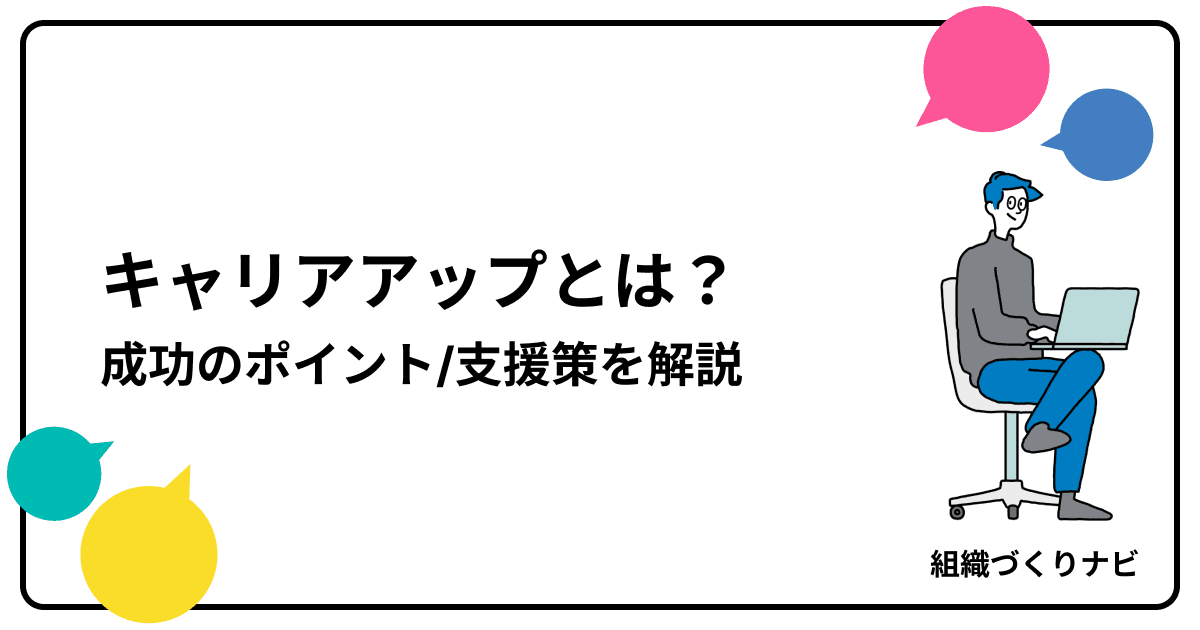
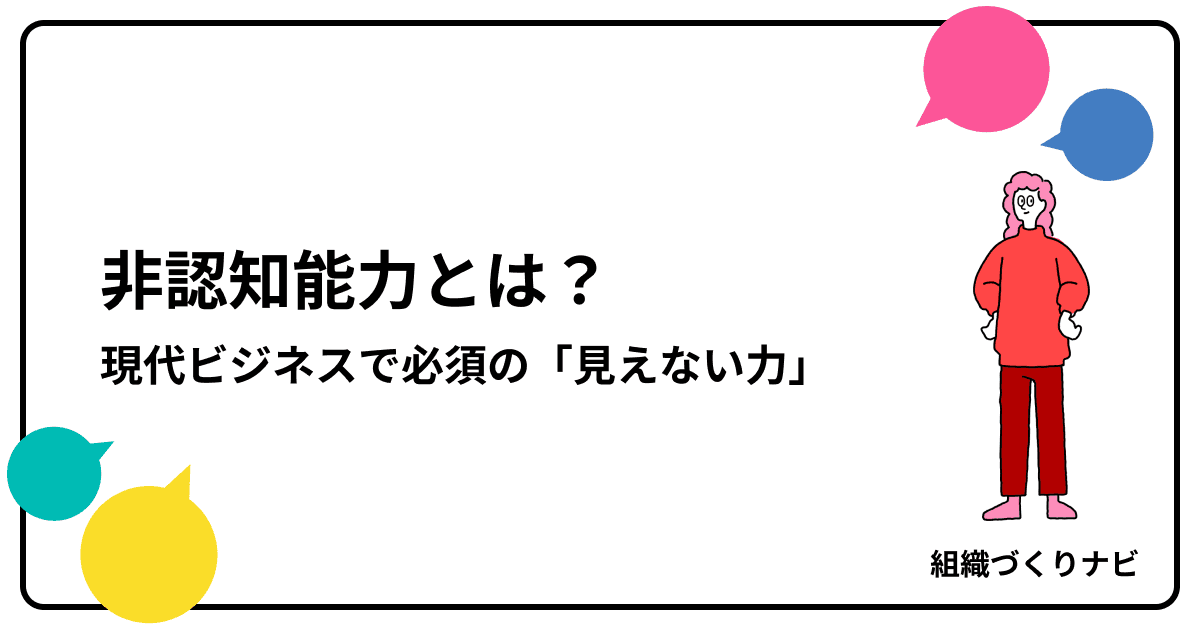
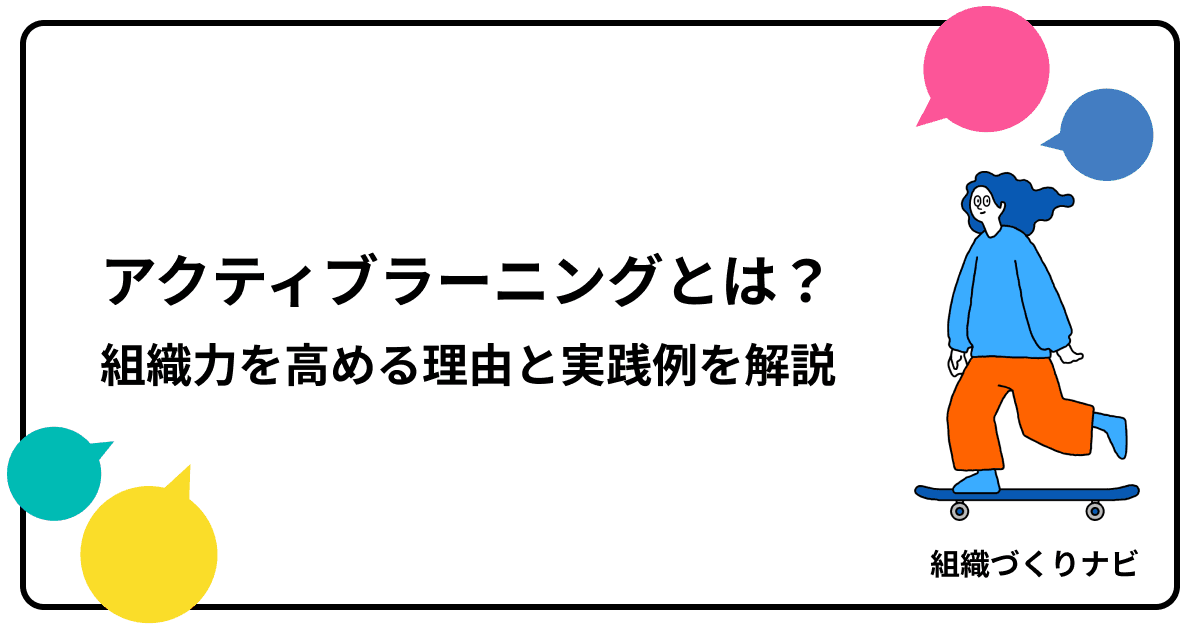
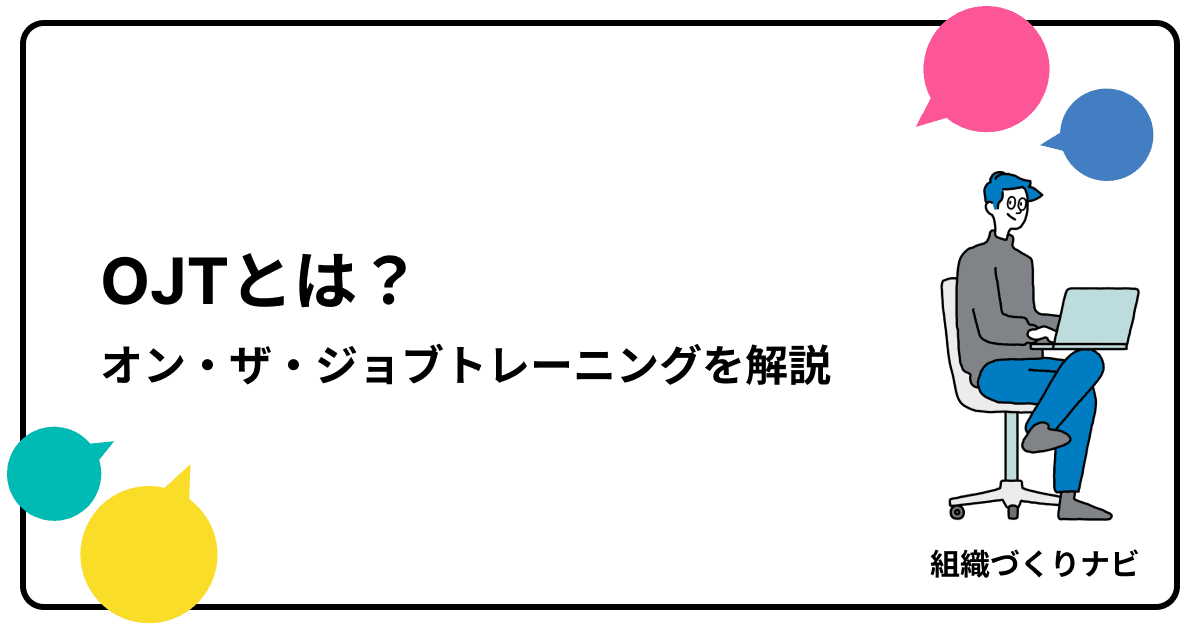
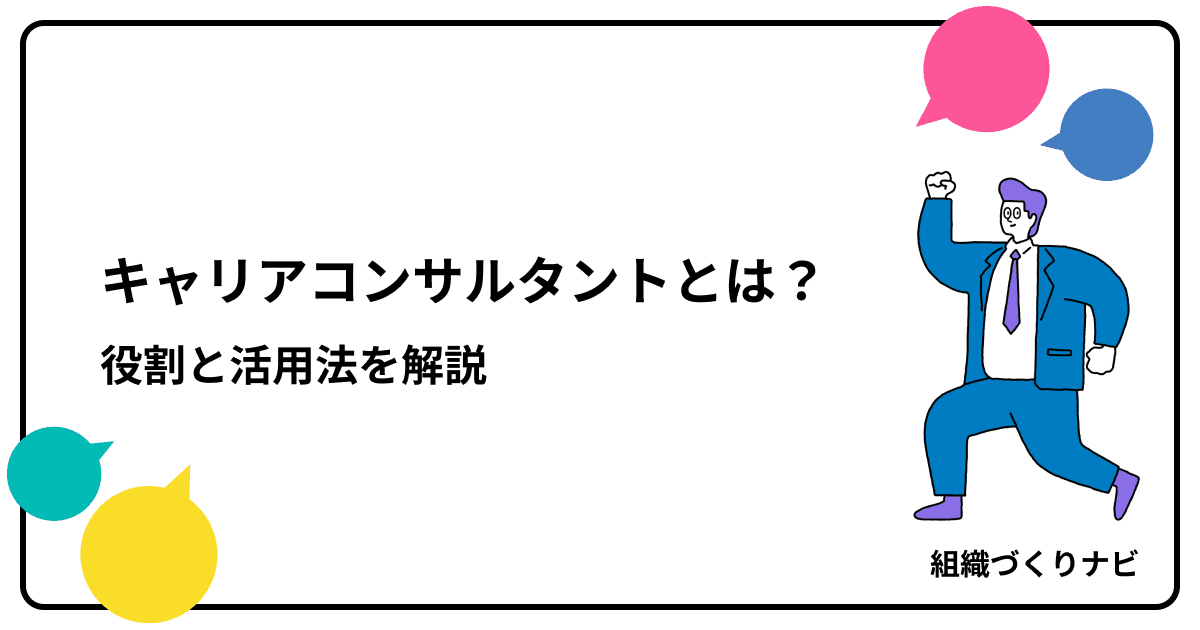



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


