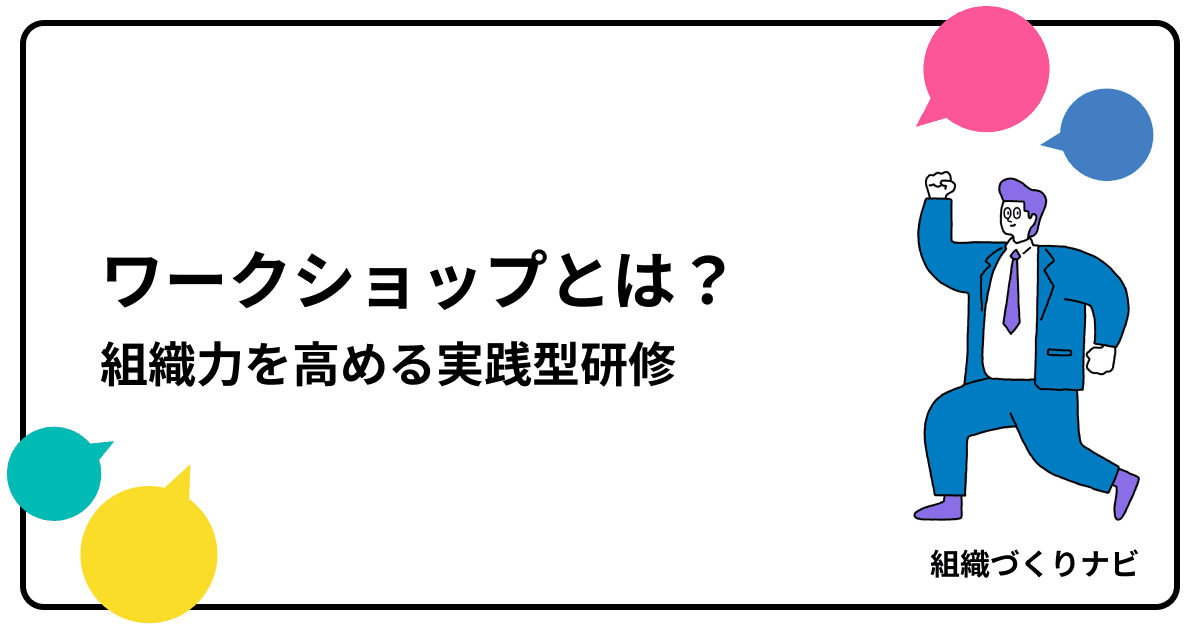
ワークショップとは?組織力を高める実践型研修のすべて
VUCA(ブーカ)と呼ばれる不確実性の高い現代において、企業には社員の主体性や創造性、そして組織のしなやかな対応力が不可欠です。従来の座学中心の研修では得にくいこれらの能力を育む「ワークショップ」が、今、新しい人材育成戦略として注目されています。
ワークショップは、参加者が能動的に協働し、実践を通じて具体的なアイデアや解決策を「創り出す」ことを重視する「アウトプット型学習」の場です。知識のインプットに留まらず、主体性や実践的なスキル、チームビルディング能力、イノベーション創出を促進します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
能動的学習を促すワークショップの核心
ワークショップの語源は、英語の「workshop」、つまり「工房」や「作業場」を意味します。この言葉が示すように、参加者が自ら手を動かし、実践を通じて学びを深める「能動的学習の場」こそが、ワークショップの核心です。一方的な情報伝達に留まらず、参加者自身が課題を「自分ごと」と捉え、アイデアを創造し、具体的な成果物を生み出すプロセスを重視します。この協働の体験は、単なる知識の習得を超え、実践的なスキルやチームビルディング能力、問題解決能力といった、ビジネスに直結する生きた力を育みます。
「自分ごと」として課題に向き合う参加型学習の価値
ワークショップが持つ最大の価値は、参加者が「受け身」ではなく「主体的に」学習プロセスに関与する点にあります。情報の一方的なインプットだけでなく、自ら思考し、発言し、行動する一連のプロセスを通じて、知識はより深く、そして実践的なスキルへと昇華されます。特に、自社の具体的な業務課題や組織目標をテーマに据えることで、参加者は「自分ごと」として課題に向き合い、座学では決して得られないリアルな「気づき」や「発見」を得ることができます。この主体的な体験こそが、個人の成長のみならず、組織全体の変革への第一歩となるのです。
関連する参考記事
尾登:アンバサダーミーティングは、2024年5月から隔月で実施している取り組みです。Wevoxを導入した2023年5月以降、2カ月に1回のサーベイの結果が出たタイミングで各部の部長を集め、振り返り会を実施してきました。一方で、一般社員の中にも「職場のエンゲージメントに課題を感じていて、解決策を考えたい」と言ってくれる人がちらほらと出てきていたので、部長に限らず、エンゲージメント活動に関心のある方をまとめる場として始めました。
各部から合計19名が参加し、私たちエンゲージメント推進チームがEngagement Run!Academyで学んだワークショップに一緒に取り組み、それらを自部署に持ち帰って対話の機会として実践してもらうよう働きかけています。

知識の「インプット」か、実践の「アウトプット」か? セミナーとワークショップの決定的な違い
人事・管理職の皆様が研修を企画する際、セミナーとワークショップの選択で悩むこともあるでしょう。この両者の最も大きな違いは、「学びの質」と「最終的な到達点」にあります。セミナーは、主に講師が専門知識や最新情報を参加者へ「伝える」ことに主眼を置き、参加者は「聞く」ことで知識をインプットします。一方、ワークショップは、知識のインプットに留まらず、参加者自身が「体験する」「話し合う」「創造する」ことを通じて、能動的に学びを「創り出す」ことを目指します。
知識を「知る」から「実践する」への転換点
この「アウトプット」を重視するプロセスこそが、ワークショップの真骨頂です。インプットした情報を基に、自らの意見を表現し、グループで議論を深め、具体的なアイデアや解決策を形にする。この実践的なステップを経て、知識は単なる情報から「使えるスキル」へと昇華され、参加者は「知っている」状態から「できる」状態へと確実にステップアップできるのです。
組織を変革するワークショップのメリットと、乗り越えるべき課題
ワークショップは、組織の人材育成や課題解決に大きな可能性を秘めていますが、その特性を理解した上で活用することが重要です。人事や管理職の皆様が企画を検討する際には、メリットとデメリットの両面を把握しておく必要があります。
参加者と組織にもたらされる多角的なメリット
ワークショップは、参加者個人の成長はもちろん、組織全体にも大きなメリットをもたらします。
主体性・当事者意識の向上:
自ら思考し、発言し、行動する機会が多いため、受け身ではなく積極的に課題解決に取り組む姿勢が育まれます。
実践的なスキルと知識の定着:
体験を通じて学ぶことで、座学では得にくい「生きたスキル」を深く習得し、知識を実務で活かせる力へと変えられます。
チームビルディングとコミュニケーションの強化:
異なる視点を持つ仲間との協働作業は、チーム内の連携を深め、相互理解とコミュニケーション能力の向上に繋がります。
イノベーション創出の促進:
自由な発想でのアイデア出しや、多様な意見のぶつかり合いは、新しいサービスや事業、業務改善のヒントを生み出す土壌となります。
達成感とモチベーション向上:
課題解決や具体的な成果物の創出を通じて得られる成功体験は、参加者の自信とモチベーションを大きく高めます。
関連する参考記事
―ほかにも、ワークショップの効果を感じる点はありますか?
佐藤:各組織長は自組織のスコアのみを見られる設定にしているので、ワークショップは、隣のチームのスコアや取り組みを知り、「同じ仕事をしていてもチームによって特徴があるんだな」「自組織にはできていないことをやってるんだな」といった気づきを得る機会になったのではないかと思います。
三瓶:無関心層にとても効いたワークショップだったと思います。例えば、同じエリアの複数の組織長に集まってもらった回では、かたやWevoxをまったく活用していない組織長がいて、かたや「メンバーに毎月結果を共有すると、こういう気づきや反応をもらいますが、どうリアクションしていくといいですか?」といった高度な質問をする組織長がいる。すると、まったく活用してない組織長も「自分もやらなきゃ」と思わざるを得なくなります。間違いなく底上げに繋がっていると思いますね。

成果を最大化するために認識すべき課題
ワークショップは多くの利点を持つ一方で、主催者側が事前に認識し、対策を講じるべき課題も存在します。
企画・準備における高い専門性:
単なるイベント開催とは異なり、効果的なテーマ設定、緻密なプログラム設計、適切なツールの選定など、企画段階から専門的な知見と時間が必要です。
ファシリテーターの力量への依存:
参加者の主体性を引き出し、議論を建設的に導くファシリテーターのスキルが、ワークショップの成否を大きく左右します。経験不足なファシリテーターでは、議論が停滞したり、期待する成果が得られないリスクがあります。
参加者の意欲と事前準備:
参加者自身の積極的な関与が不可欠なため、モチベーションが低い場合や事前のインプットが不足している場合、効果が半減する可能性があります。
これらの課題は、適切な準備と専門家(プロのファシリテーターなど)の活用により、十分に克服可能です。リスクを事前に把握し、成功への戦略を練ることが重要となります。
ワークショップを成功に導く具体的なステップと実践の鍵
ワークショップを成功に導き、最大限の効果を引き出すためには、計画的な準備と適切な進行が不可欠です。人事や管理職の皆様が企画する際に押さえておくべきポイントをご紹介します。
成功は「目的とゴール」の明確化から始まる
ワークショップを企画する上で、最も根幹となるのが「目的とゴール」の明確な設定です。「このワークショップを通じて何を達成したいのか」「参加者にどのような変化をもたらしたいのか」を具体的に言語化することで、プログラム全体に一貫性が生まれます。
例えば、「DX推進に向けた新規事業アイデアを5つ具体化する」「部署間の連携課題に対する具体的な改善策を3つ立案する」といったように、測定可能で期限が明確なSMARTゴールを設定しましょう。これにより、参加者は集中して取り組み、ファシリテーターは議論を適切に方向付け、ワークショップ終了後の効果測定も容易になります。
プロフェッショナルなファシリテーターが成功の鍵を握る
ワークショップの成否を分ける最も重要な要素の一つが、ファシリテーターの力量です。ファシリテーターは単なる進行役ではなく、参加者一人ひとりの主体性を最大限に引き出し、多様な意見を尊重しながら建設的な議論へと導き、設定されたゴール達成を「促進する専門家」です。
例えば、議論が停滞した際に適切な問いを投げかけたり、意見の対立を乗り越えるための介入を行ったりと、場の空気や参加者の心理状態を読み解く高度なスキルが求められます。経験豊富なプロのファシリテーターを起用することで、参加者全員が安心して意見を交わせる心理的安全性の高い場が確保され、ワークショップの学習効果と成果が格段に向上します。
参加意欲を高めるテーマ設定と効果的なワーク設計
参加者が「自分ごと」として深く関与し、最大限の成果を引き出すためには、テーマ設定とワークの設計が非常に重要です。抽象的で漠然としたテーマは避け、具体的な課題や解決すべき問いかけを用意することで、参加者の思考を深め、実践的なアウトプットへと繋げます。
ワークの進め方としては、まず各自が自由にアイデアを出す「個人ワーク」で多様な視点を引き出し、その後、少人数の「グループワーク」で意見を共有・深掘りし、さらに全体で統合する段階的な設計が効果的です。付箋やホワイトボード、オンラインツールなどを活用し、アイデアを「見える化」することで、議論の活性化と合意形成を促進します。このような設計は、参加者全員がプロセスに貢献できるという満足感にも繋がります。
関連する参考記事
まとめ:ワークショップで組織の未来を創造する
ワークショップは、従来の研修モデルを超え、VUCA時代の組織に求められる「実践力」「創造性」「協働力」を育む、戦略的な人材育成手法です。単なる知識のインプットに留まらず、参加者自らが能動的にアウトプットし、具体的な成果を生み出すプロセスを通じて、知識を「知っている」から「実践できる」レベルへと昇華させることが可能です。
企画・準備には専門性と時間が必要ですが、明確な目的設定、プロフェッショナルなファシリテーターの起用、そして参加型を促す綿密なワーク設計により、期待をはるかに超える変革と成長を組織にもたらすのです。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

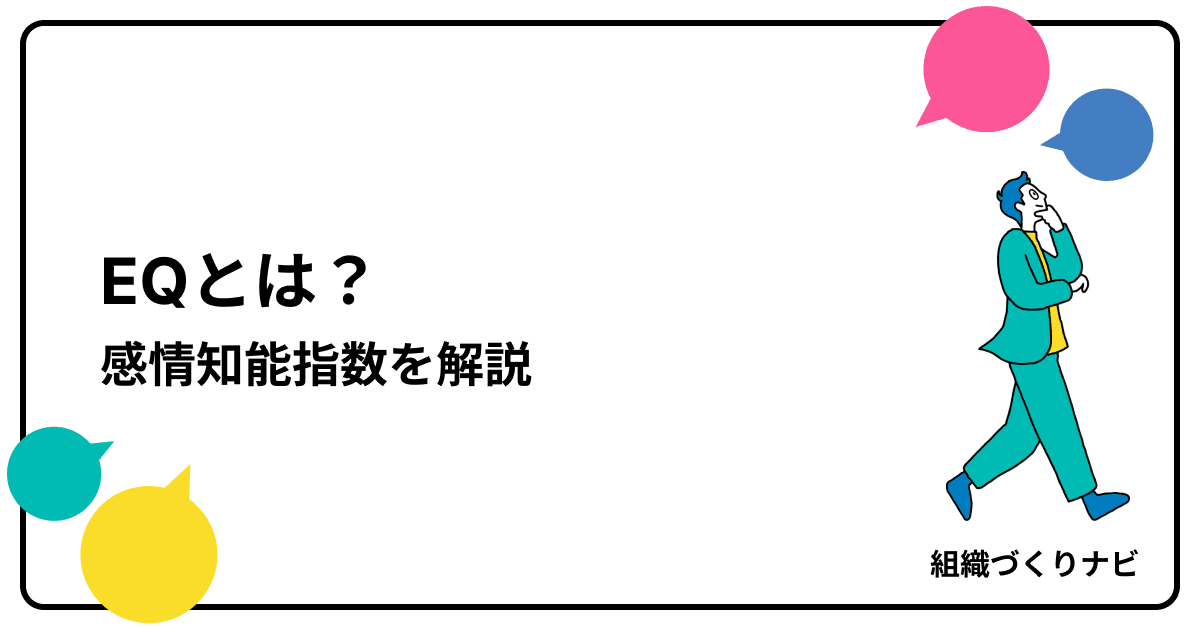
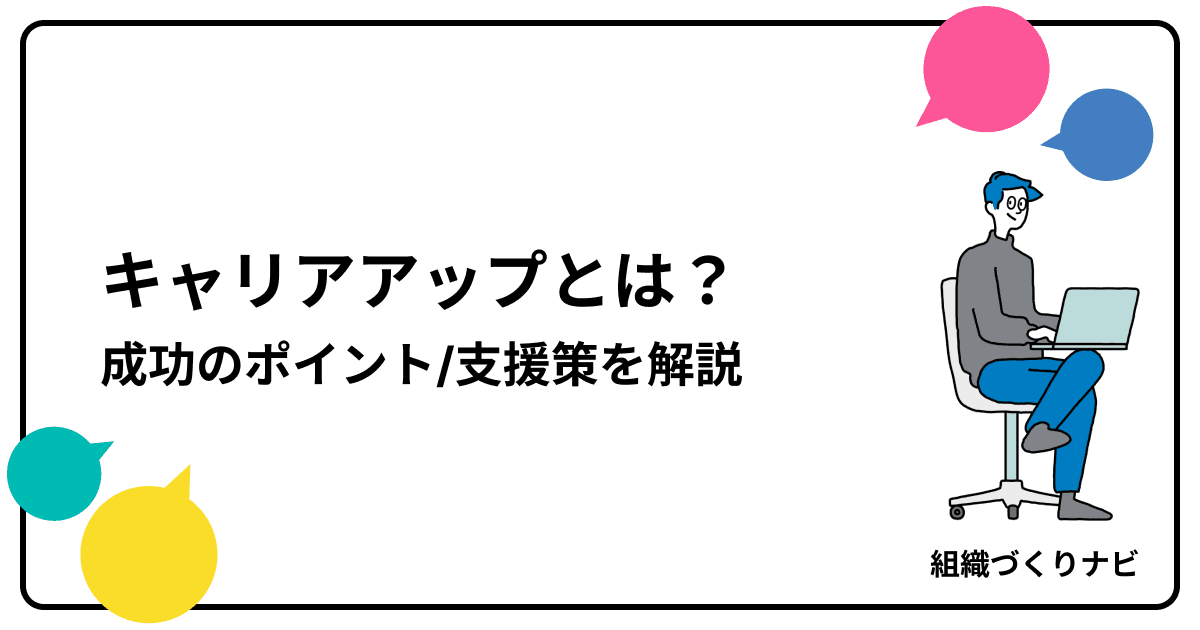
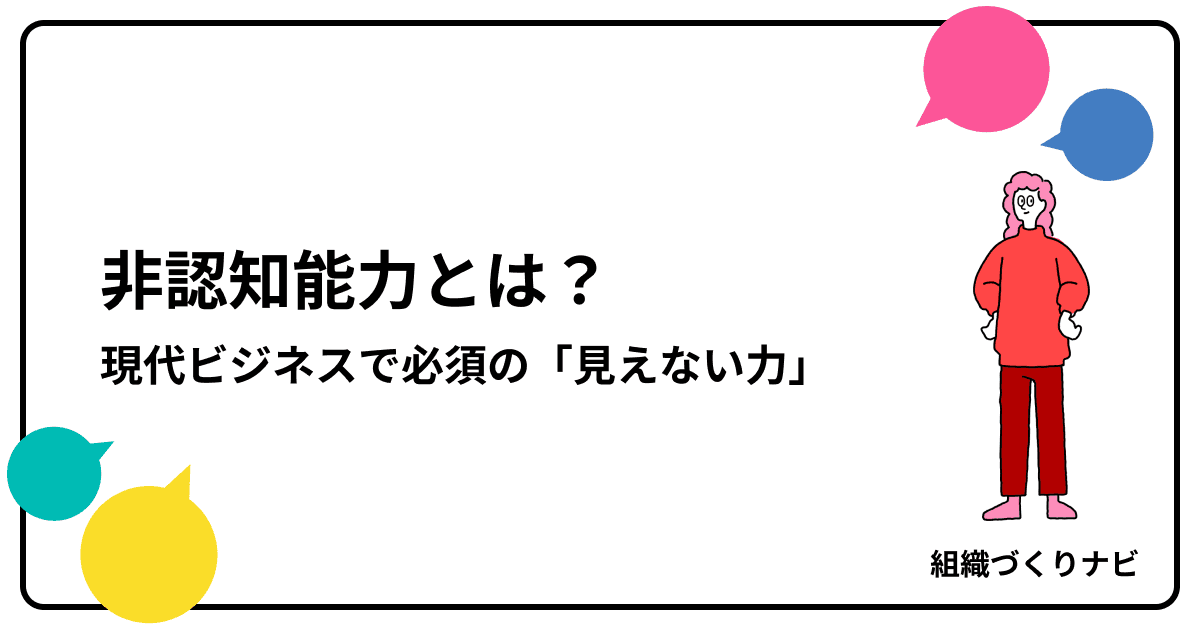
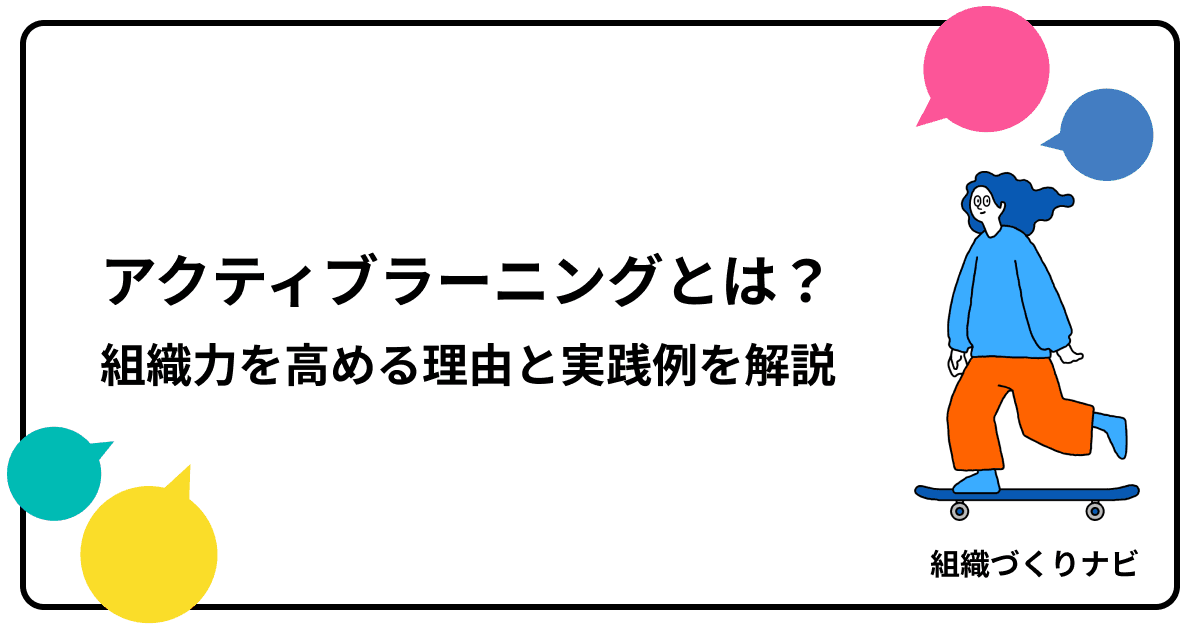
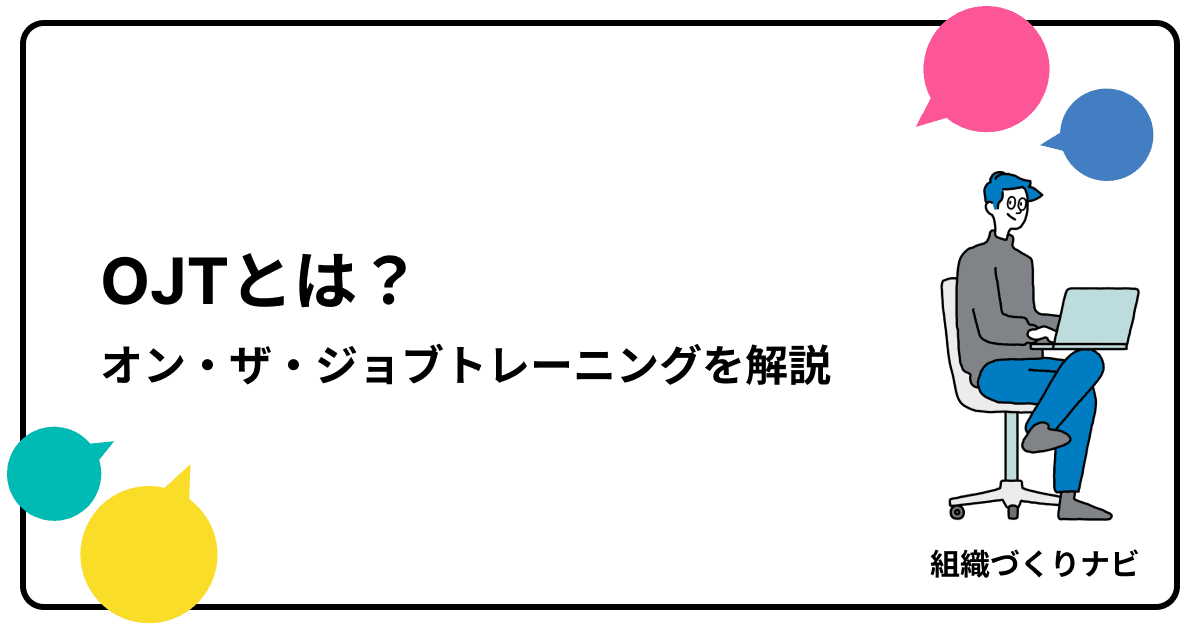
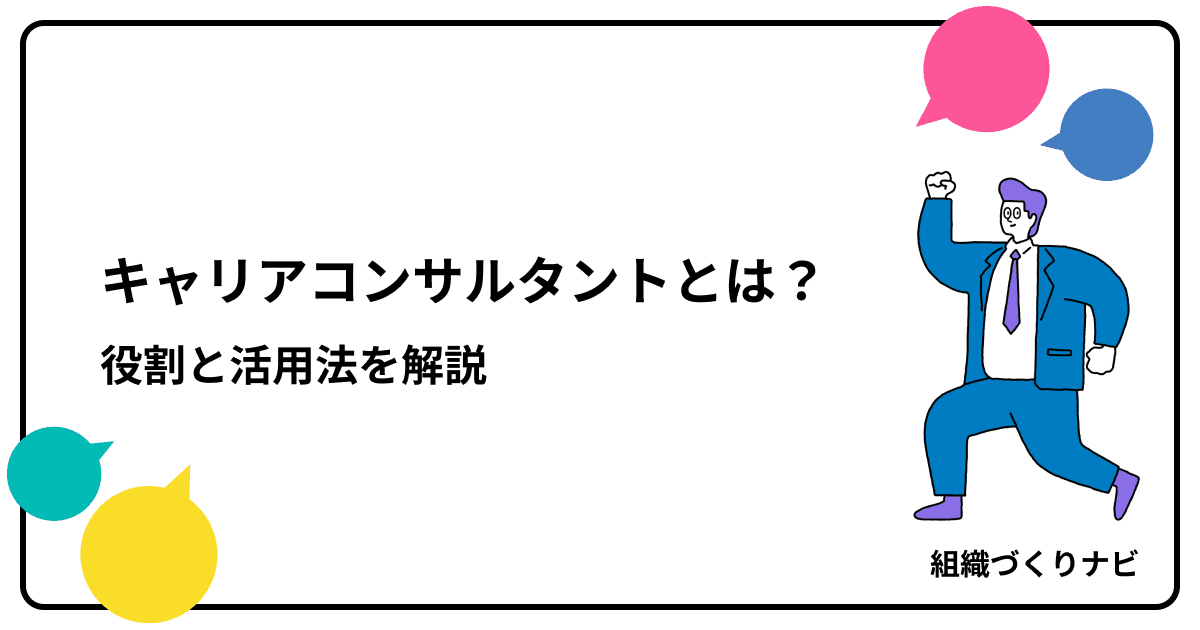



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


