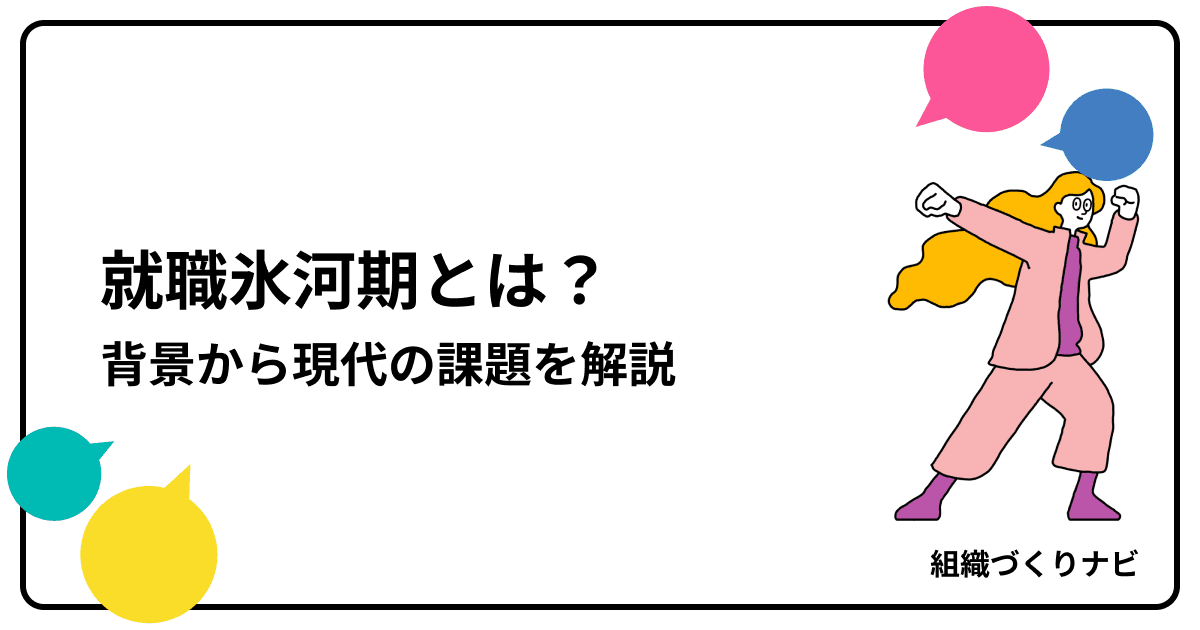
就職氷河期とは? 背景から現代の課題、企業にできることを徹底解説
就職氷河期とは、1990年代半ばから2000年代前半にかけて、バブル崩壊後の不況により新卒採用市場が極端に冷え込んだ時代を指します。この時期を経験した世代は、希望する職に就けず非正規雇用となるなど、キャリア形成に深刻な影響を受けました。現在も賃金や社会保険、スキルアップ機会などの課題を抱える一方、困難を乗り越えた粘り強さや実践的な知恵、危機管理能力といった独自の強みを持っています。企業は、この世代の潜在能力を最大限に引き出すため、公平な評価、リスキリング支援、経験継承の機会提供、心理的安全性の確保などを通じ、組織全体の活性化と持続的成長に繋げることが求められています。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
就職氷河期とは?
「就職氷河期」とは、主に1990年代半ばから2000年代前半にかけて、新卒採用市場が極端に冷え込んだ期間を指す言葉です。この時期は、1991年のバブル経済崩壊後、日本経済が深刻な景気低迷に陥り、多くの企業が採用活動を大幅に抑制しました。まるで植物が育たない「氷河期」のように、大学や専門学校を卒業する若者たちが希望する就職先を見つけるのが非常に困難だったことから、この名前がつけられています。
この世代の多くは、求人の選択肢が著しく少ない中で就職活動に臨み、希望する職種や企業への就職が叶わないという厳しい現実を経験しました。その結果、正規雇用として働く機会を逃し、非正規雇用を選択せざるを得なかった方も少なくありません。この現象は、個人のキャリア形成だけでなく、日本社会全体の構造にも大きな影響を与え、その後の世代にも間接的な影響を及ぼしています。
具体的に何が起きたのか?
就職氷河期には、企業の新卒採用数が劇的に削減されました。例えば、それまでは複数の内定を得る学生も珍しくありませんでしたが、この時期には何十社もの企業に応募しても内定が一つももらえないという状況が一般的となりました。求職者1人あたりの求人の数を示す「求人倍率」は、過去に類を見ない低水準に落ち込み、大企業だけでなく多くの中小企業でも採用は極めて厳しかったのです。
この結果、多くの若者が「浪人」して翌年の就職活動に再挑戦したり、大学院への進学を選んだり、あるいは希望しない職種や雇用形態で働くことを余儀なくされました。特に、一度非正規雇用に就くと、そこから正規雇用に移行することが難しいという「雇用形態の固定化」の問題も生まれ、結果的にこの世代のキャリア形成に大きな影を落とすことになります。社会全体が不況の渦中にあり、企業側も経営維持のために採用を絞るしかなかったという背景がありました。
氷河期世代が抱える課題(現在も)
就職氷河期を経験した世代は、現在もなお様々な課題を抱えています。当時の厳しい状況が原因で、正規雇用としてのキャリアをスタートできなかったり、希望するキャリアを築けなかったりした人が少なくありません。その結果、賃金が伸び悩んだり、ボーナスや退職金といった福利厚生の恩恵を十分に受けられなかったりするケースが見られます。これは、現在の生活水準や老後の資産形成にも影響を与えています。
また、長く非正規雇用が続いたことで、社会保険の加入状況が不安定であったり、キャリアアップに必要なスキルを習得する機会が不足していたりする問題も指摘されています。企業の人事や管理職の皆様にとっては、この世代の従業員が抱える潜在的な不安や、これまでの経験によって培われた粘り強さや危機管理能力といった独自の強みを理解し、それを最大限に引き出すことが、組織全体の活性化や持続的な成長に繋がる重要な視点となります。
企業として、今できること:氷河期世代の潜在能力を引き出す視点
企業として、就職氷河期世代の社員に対して今できることは多岐にわたります。単に過去の困難を埋め合わせるだけでなく、彼らが持つ独自の経験や潜在的な強みを組織の成長に繋げる視点が重要です。
まず、過去の経験によって彼らが自己肯定感を失っていたり、キャリア形成に不安を抱えていたりする可能性を理解することが不可欠です。そのため、以下の具体的な施策を通じて、彼らの活躍を支援し、組織の力を高めていきましょう。
公平な評価とキャリアパスの明確化
これまでの職務経験や培ってきたスキルを正当に評価し、年齢や入社時期に囚われない公平な評価制度を適用することが不可欠です。非正規雇用で働いている社員の正規雇用への転換を積極的に支援し、具体的なキャリアアップの道筋(昇進・昇格の基準など)を明確に提示することで、将来への希望とモチベーションを引き出すことができます。
関連する参考記事
―では、3つ目のToei Career Action Programとはどのような取り組みですか?
西岡:入社年次や年齢に応じたキャリアパス構築の機会を提供し、さらにはキャリ自律を支援するプログラムです。個々の制度に一貫性を持たせたいと思っていたので、一連の取り組みの総称として、Toei Career Action Programと名前をつけました。経営レポートで明らかになった「勤続年数12〜20年目で30代後半にあたる、中核を担う社員層のスコア低迷」という課題や、「キャリア機会の提供」「成長機会」などの項目のスコアの低さに対する打ち手として、元々あった制度の対象を見直したり、新たに制度を設けたりしました。
具体的には、4種類の制度を通じて従業員が①「様々な部門の業務経験を積む」②「自己実現に向けて挑戦する機会を創出する」③「キャリアプランの設計とキャリア形成力を育成する」ことを目指しています。

リスキリング・スキルアップ支援の強化
市場の変化に対応するための新しいスキルや知識を習得する機会を積極的に提供します。外部研修への参加支援、社内での専門スキル講座の開講、資格取得奨励制度の導入などが考えられます。これにより、彼らの市場価値を高め、組織内でより高度な業務を担当できるよう支援します。
経験と知識の継承機会の創出
就職氷河期世代は、厳しい時代を生き抜き、限られた資源の中で工夫を凝らしてきた実践的な経験を豊富に持っています。この困難を乗り越えてきた粘り強さや、現場で培った知恵は、若手社員にとって貴重な学びとなります。メンター制度の導入や、プロジェクトリーダーとしての抜擢など、彼らが持つ経験や知識を若手社員に継承する機会を積極的に設け、世代間の連携を促進しましょう。
心理的安全性とエンゲージメントの向上
安心して意見を言える、失敗を恐れずに挑戦できる心理的に安全な職場環境を構築することは、彼らの潜在能力を最大限に引き出す上で極めて重要です。定期的な面談やフィードバックを通じて、個々の悩みに耳を傾け、貢献を正当に評価することで、組織へのエンゲージメントを高めることができます。
多様な働き方への柔軟な対応
個々のライフステージや状況に応じた柔軟な働き方(時短勤務、リモートワーク、副業推奨など)を受け入れることで、長期的なキャリア形成を支援します。これにより、モチベーションを維持しつつ、企業への貢献意欲を一層高めることが期待できます。
これらの取り組みは、氷河期世代の社員のエンゲージメントと生産性を高めるだけでなく、組織全体のダイバーシティ&インクルージョンを推進し、持続的な成長を実現するための重要な投資となります。
まとめ
就職氷河期は、多くの若者のキャリア形成に大きな影響を与えた時代の出来事であり、その影響は現代にも及んでいます。しかし、この世代は困難な時代を乗り越えてきたからこそ、粘り強さ、危機管理能力、そして限られたリソースで成果を出す知恵といった独自の強みを持っています。
企業として今求められるのは、単に過去の課題を埋め合わせるだけでなく、彼らが持つ潜在能力を最大限に引き出し、組織の貴重な財産として活用する視点です。公平な評価、リスキリング支援、経験の継承機会の創出、そして心理的安全性の高い職場環境づくりを通じて、氷河期世代の社員のエンゲージメントを高め、彼らが輝ける場所を提供することは、組織全体の活性化と持続的な成長に不可欠です。この世代の力を引き出すことが、企業の未来を形作る鍵となるでしょう。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

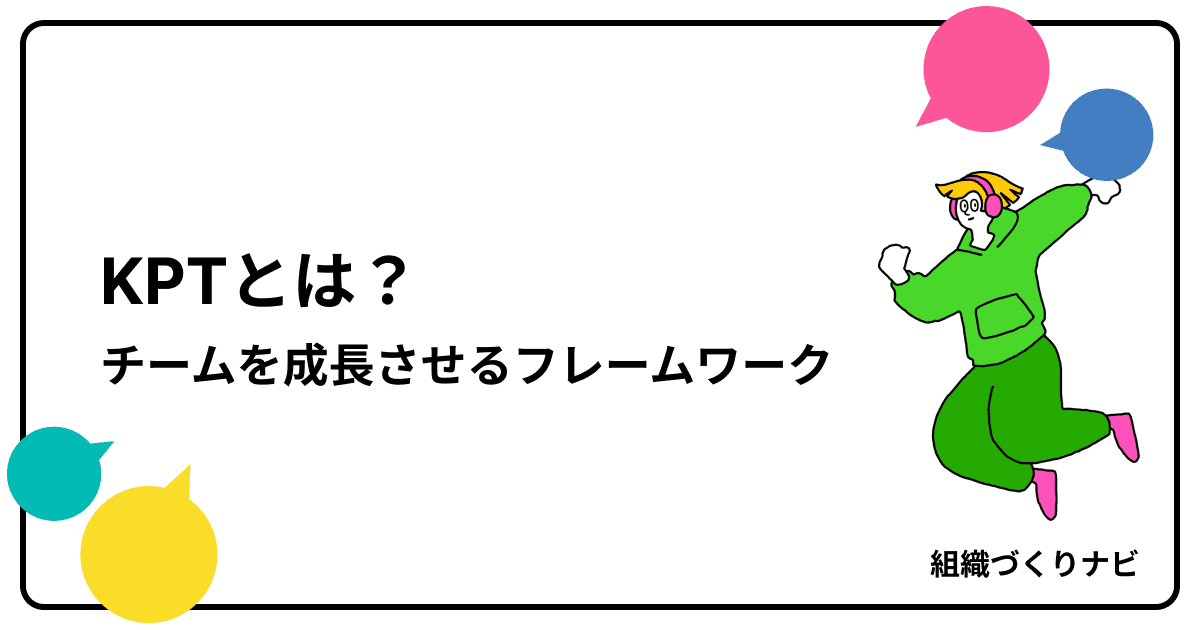
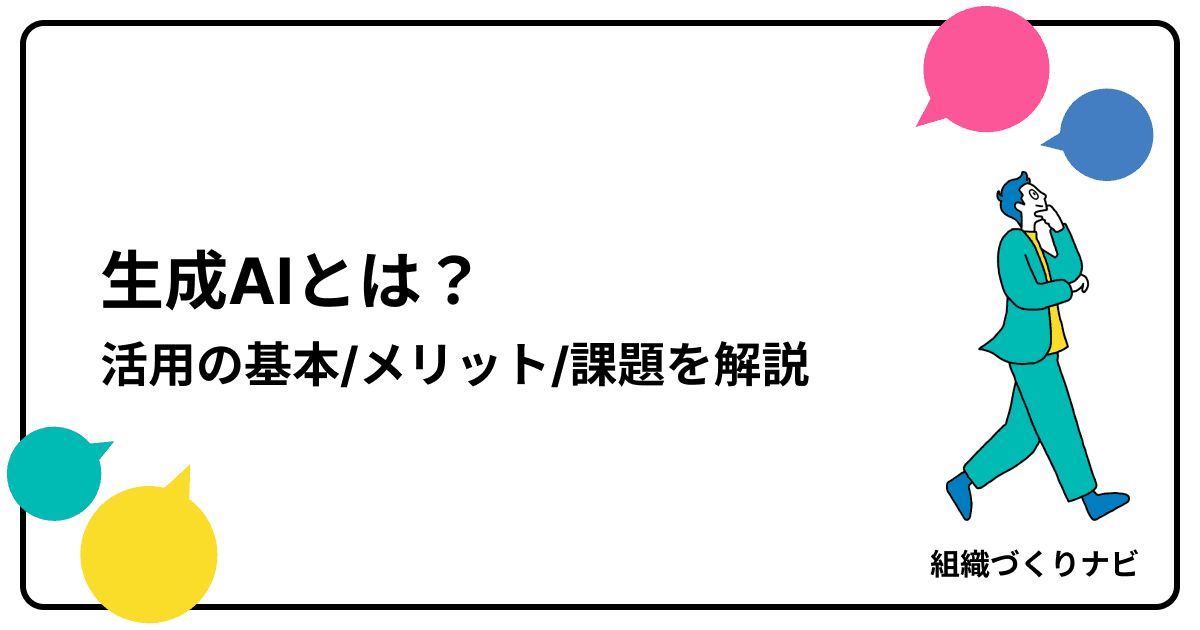
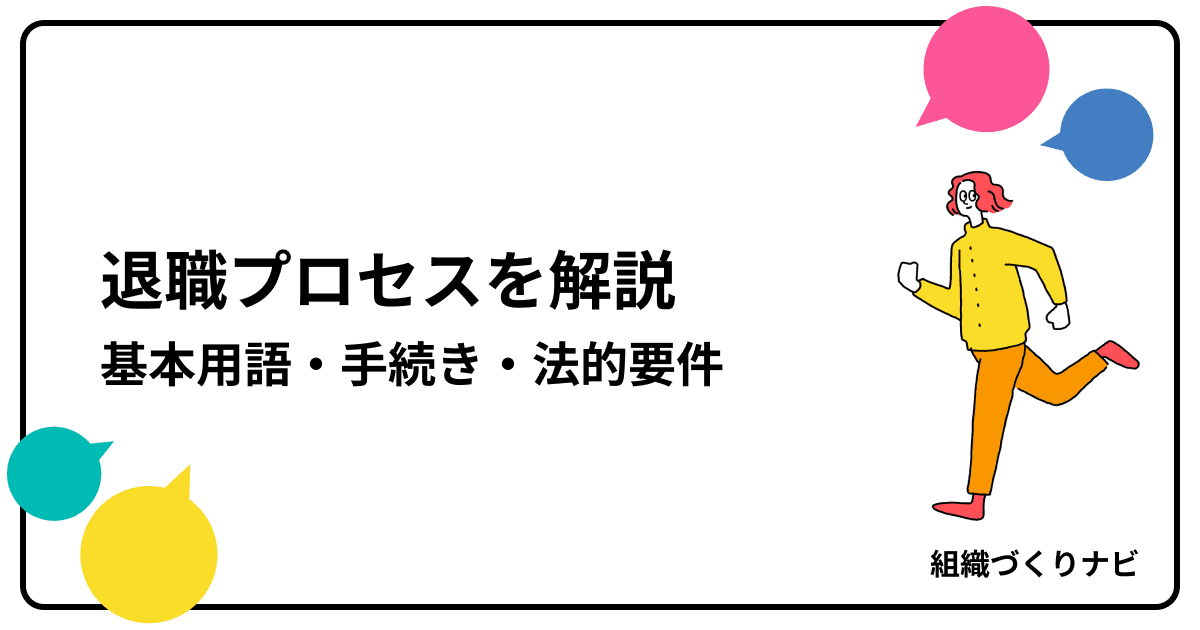
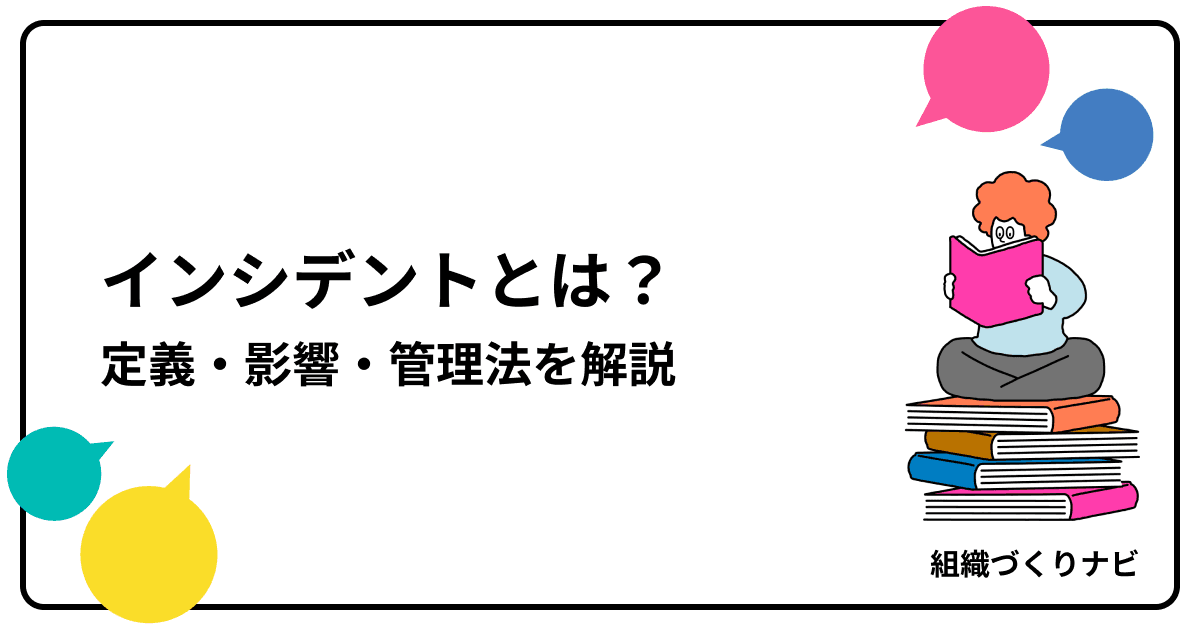
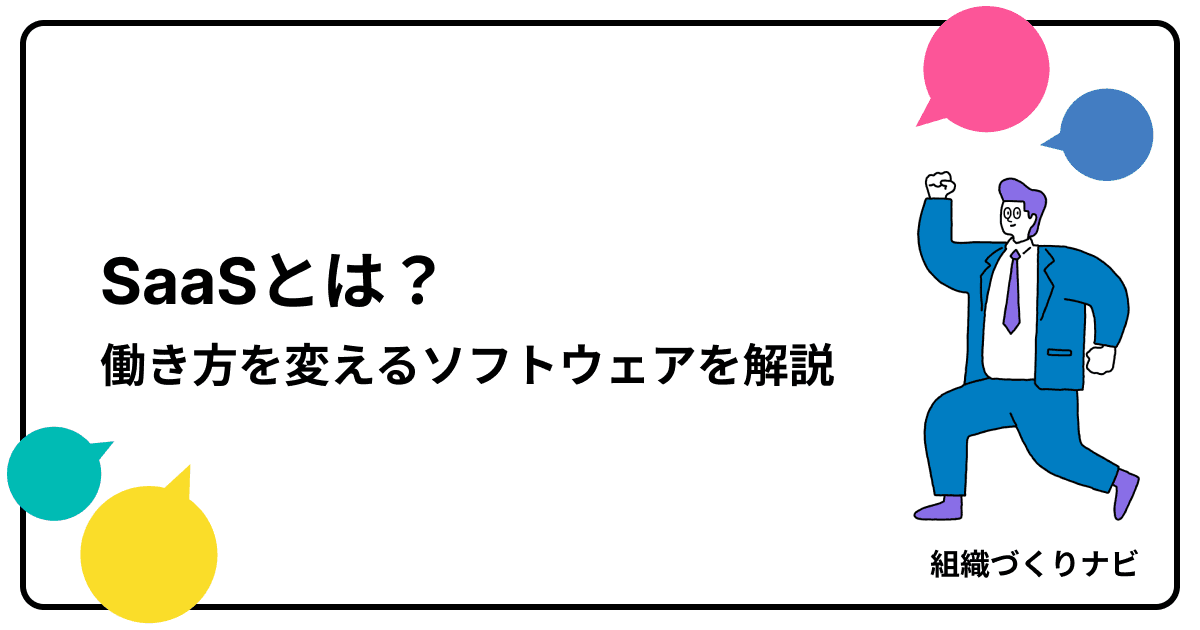
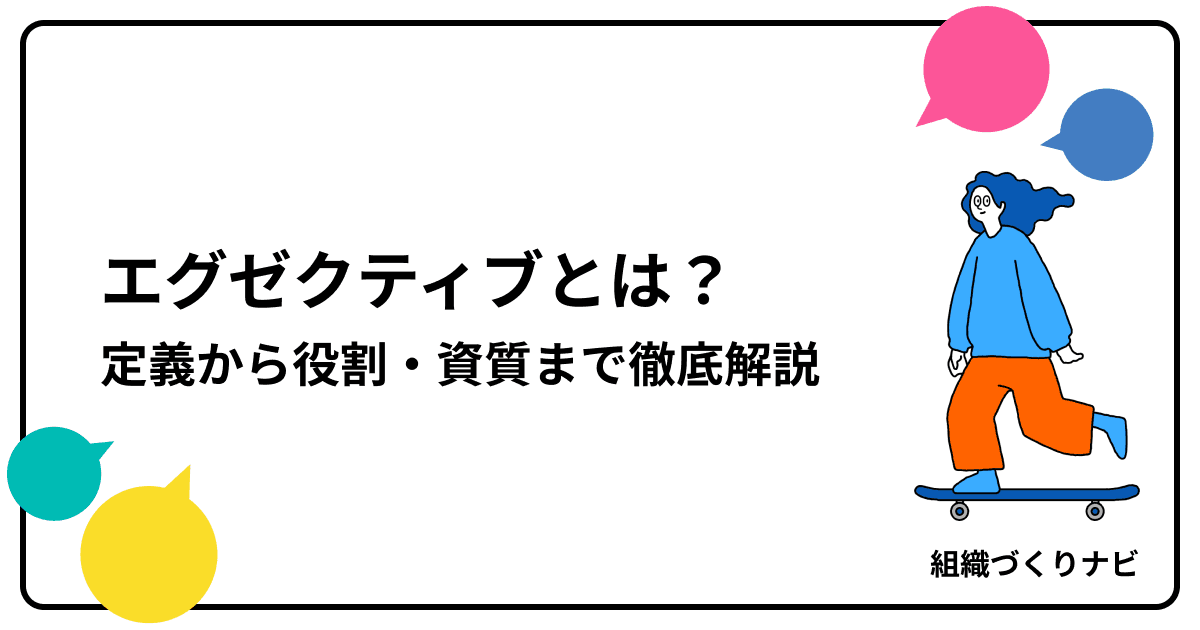



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


