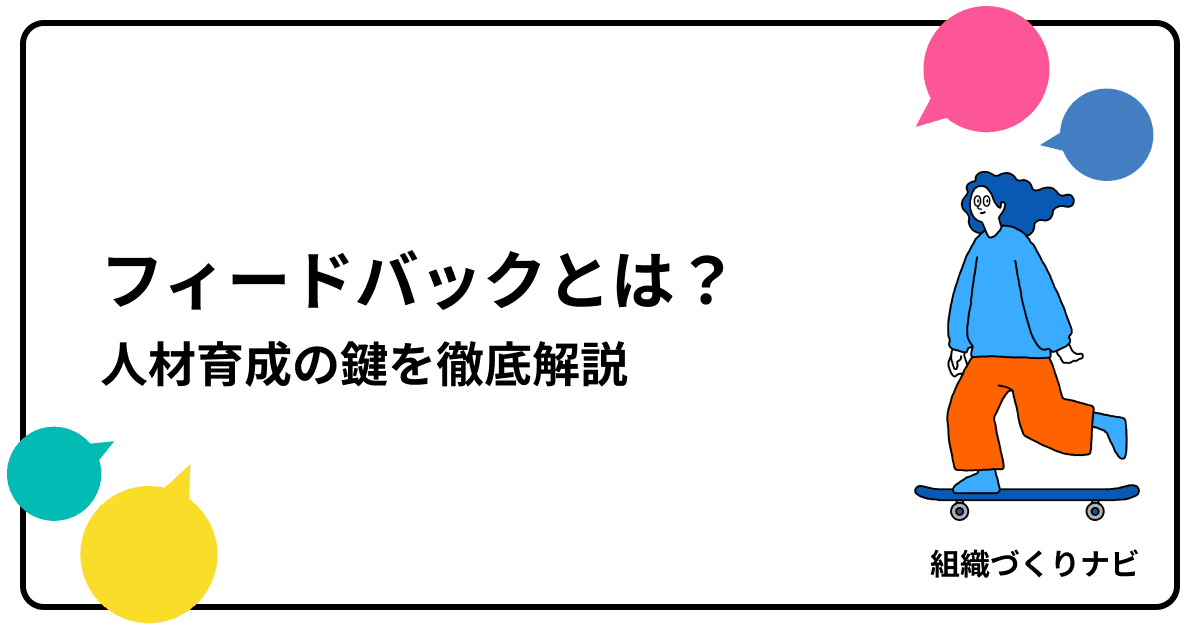
フィードバックとは?目的・効果・実践まで人材育成の鍵を徹底解説
フィードバックは、個人と組織の持続的な成長を促すための重要なコミュニケーションです。日々の行動を評価し、改善点を明確にすることで、パフォーマンスを向上させ、目標達成を加速させます。VUCA時代において、メンバーの自律的な成長、エンゲージメント向上、心理的安全性の確保に不可欠なスキルです。 効果的なフィードバックには、「目標と結びつける」「具体的に伝える」「行動可能にする」「タイムリーに行う」の4つのポイントが重要です。また、サンドイッチ型やSBI型、ペンドルトンルールといった状況に応じた手法を活用し、リモートワークでの工夫も取り入れることで、よりポジティブで生産性の高い対話を実現します。過去の行動を改善する「フィードバック」に加え、未来の行動を支援する「フィードフォワード」の概念も合わせて活用することで、人材育成を効果的に進め、強くしなやかな組織を築くことができます。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
フィードバックとは? 人材育成と組織成長を促す本質
フィードバックは、個人と組織の持続的な成長を促すために不可欠なコミュニケーションです。日々の業務や目標達成において、適切な行動を評価し、改善点を明確にすることで、パフォーマンスを飛躍的に向上させ、より良い結果へと導くための情報伝達を指します。特に人事や管理職の皆様にとって、メンバーの潜在能力を最大限に引き出し、チーム全体の生産性を高めるために、フィードバックは欠かせないスキルと言えるでしょう。この概念はもともとシステム工学の「フィードバック制御」に由来し、目標達成のために「出力を入力に戻す」操作を通じて改善を促すものです。
なぜ今、フィードバックが重要なのか?
現代のビジネス環境は、変化が激しく不確実性が高い「VUCA時代」と呼ばれています。リモートワークの普及やダイバーシティの推進など、働き方も多様化し、従来の指示命令型のマネジメントでは組織の成長が難しくなってきています。このような時代だからこそ、フィードバックは以下の点でその重要性を増しています。
自律的な成長の促進
: 変化の激しい環境では、メンバー一人ひとりが自ら課題を発見し、解決する力が求められます。フィードバックは、その自律的な学習と成長を支援します。
エンゲージメントの向上
: 適切なフィードバックは、メンバーが認められている、期待されていると感じさせ、組織への帰属意識や仕事への意欲を高めます。
心理的安全性の確保
: 定期的なフィードバックを通じて、建設的な対話が日常化することで、メンバーは安心して意見を述べ、チャレンジできる心理的安全性の高いチームが形成されます。
フィードバックを重視した事例↓
評価に関しては、「もう少しわかりやすく説明してほしい」「自分の評価がなぜそうなったのか知りたい」といった声がありました。これを受けて、フィードバックを行うマネージャー陣に対して、評価業務の本質や効果的なフィードバック方法について改めて共有し、改善に取り組みました。

フィードバックの基本的な理解と目的
「フィードバック(Feedback)」は、「Feed(与える)」と「Back(戻す)」という言葉から成り立っており、元々は機械が自らの状態を検知し、目標値に近づけるための制御システムに用いられていました。ビジネスシーンにおいては、個人の行動や成果に対する客観的な「反応」や「意見」を本人に伝え、気づきを促し、次の行動を改善するためのコミュニケーションとして定着しています。
このプロセスを通じて、メンバーは自分の強みや課題を客観的に認識し、自己成長の機会を得ます。管理職にとっては、メンバーの潜在能力を引き出し、自律的な成長を支援するための強力なツールとなります。結果として、以下の目的達成に貢献します。
目標達成の加速
: 個人の行動と設定した目標との間に生じたズレを修正し、早期に軌道修正を促します。
人材育成とスキルアップ
: 具体的な改善点や成長の機会を伝えることで、メンバーのスキルや知識の向上を支援します。
モチベーションとエンゲージメントの向上
: 良い点や努力を適切に承認することで、自己肯定感を高め、さらなる意欲を引き出します。
フィードバックを効果的に行うための3つの要素と4つのポイント
効果的なフィードバックは、一方的な指摘ではなく、対話を通じて相手の成長を支援するプロセスです。そのためには、「フィードアップ」「フィードバック」「フィードフォワード」の3つの要素を意識したサイクルと、実践的な4つのポイントが重要です。
「フィードアップ」「フィードバック」「フィードフォワード」のサイクル
フィードアップ
: フィードバックを行う前に、「何を目指すか」メンバーの目標や期待されていることを事前に確認し、共通認識を持つことが重要です。目標が曖昧では、フィードバックも的を射たものになりません。
フィードバック
: 「現在どうなっているか」実際の行動や成果を振り返り、評価を伝えます。ここでは、具体的な事実に基づいて客観的に伝えることが求められます。
フィードフォワード
: 「次にどうするか」次の行動計画や改善策を共に検討し、未来志向で支援します。過去の行動を改善するだけでなく、将来の成功に向けて具体的なアドバイスを伝えることで、前向きな行動変容を促します。
実践!効果を最大化する4つのポイント
フィードバックを効果的に伝えるためには、以下の4つのポイントを押さえましょう。
目標に結びつける
: なぜこのフィードバックをするのか、
具体的な目標と関連付けて伝える
ことで、相手は目的を理解しやすくなります。「〇〇という目標達成のために、この行動を改善すると良いでしょう」のように説明します。
具体的に伝える
: 抽象的な表現ではなく、「いつ、どこで、どんな行動があり、どんな結果になったか」を
事実に基づいて具体的に指摘
します。「もっと頑張って」ではなく、「前回のプレゼンで、〇〇というデータを用いて説明した部分は非常に説得力がありました」のように伝えます。
行動可能であること
: 相手が次に
何をするべきか明確で、実践できる内容
であるかを確認しましょう。実現不可能な要求は逆効果です。「次回は〇〇の情報を加えた資料を作成してみませんか」といった、具体的な行動提案を含めます。
タイムリーに
: 行動から時間が経たないうちにフィードバックを行うことで、
記憶が新しいうちに改善行動を促し、効果を最大化
できます。時間が経つと、相手はどの行動に対する指摘なのか理解しづらくなります。
エンゲージメント活動におけるフィードバックの事例↓
谷川:主な取り組みとして、職場長の皆さんに主体的に職場改善に取り組んでもらうことを狙いとした、「個別フィードバック会」を行いました。フィードバック会では、事務局と職場長との面談の形で、スコアの結果を見ながらお話ししています。
「スコアが低いよね」という話から入ると、責められたと感じさせてしまう恐れがあるため、はじめにスコアと自身の職場への認識を比べての違和感を聞き、その後で低いスコアの項目に関してヒアリングを行っていきました。ヒアリングの際は、今の職場の状況や、具体的な対応策、そして今の状況が一時的なのか、それとも継続的な要因なのかどうかの考えを聞いています。
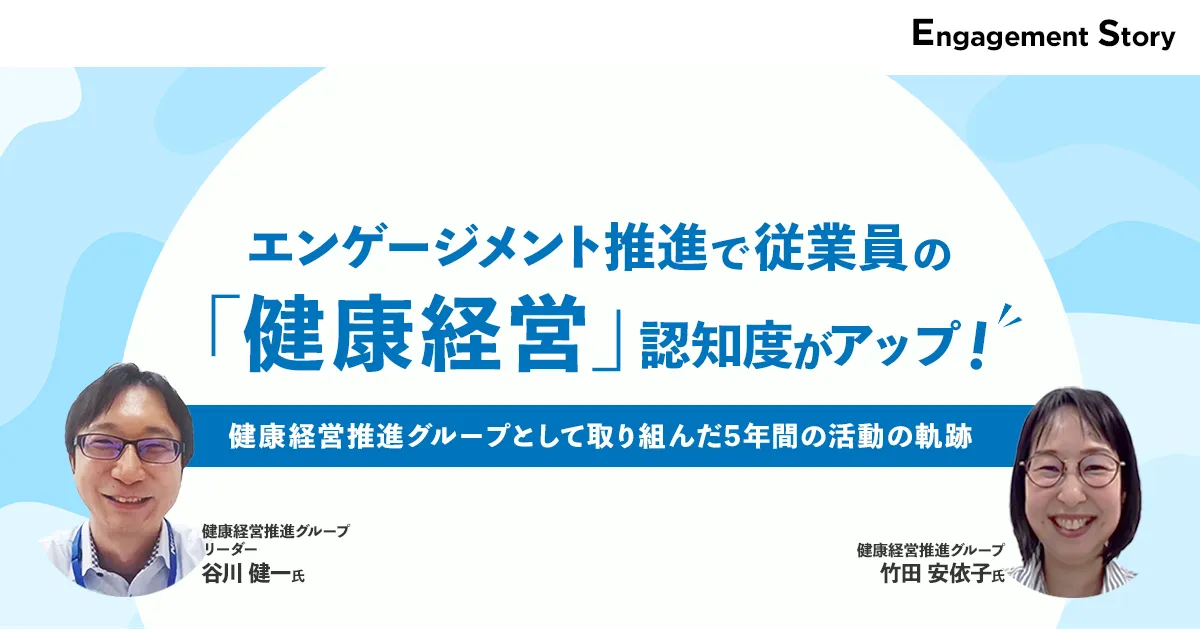
【差別化】リモート環境でのフィードバックのコツ
リモートワークでは、非対面のため相手の状況が把握しづらく、フィードバックが一方的になりがちです。以下の点を意識しましょう。
こまめなチェックイン
: 短時間でもオンラインで定期的に対話の機会を設け、状況を確認します。
チャットやツールを使い分ける
: 緊急性や機密性の高い内容は電話やビデオ会議で、ちょっとした感謝やねぎらいはチャットで伝えるなど、ツールの特性を理解して使い分けます。
表情や声のトーンを意識
: ビデオ会議では、表情や声のトーンが伝わりやすいため、いつも以上にポジティブな姿勢と共感を意識して伝えます。
意図の明確化
: 普段より意図が伝わりにくい可能性があるため、「なぜこのフィードバックをするのか」「何を目指したいのか」をより丁寧に明確に伝えます。
混同しがちな関連用語との違い
フィードバックは、ビジネスにおいてさまざまな関連用語と混同されがちです。ここでは代表的な用語との違いを明確に理解しましょう。
フィードフォワード:未来志向の成長支援
フィードバックが「過去の行動や結果」に焦点を当て、その改善を促すのに対し、フィードフォワードは「未来の行動」に焦点を当てたアドバイスです。「次にこうすれば、もっと良くなる」というように、過去を問わず、未来の行動に対して前向きな示唆や期待を伝える点が異なります。フィードバックで課題が明確になった後、具体的な行動を促す際に特に有効です。
レビュー/チェックバック:品質と要件の確認
これらは主に「成果物や作業内容の確認・評価」を指すことが多いです。例えば、提出された資料やプログラムが要件を満たしているかを確認し、修正指示を出すプロセスです。フィードバックが「行動」や「成長」に重きを置くのに対し、レビューやチェックバックは「品質」や「要件」の適合性に重点が置かれます。もちろん、レビューの結果から行動へのフィードバックに繋がることもありますが、目的が異なります。
まとめ:フィードバックで実現する強い組織
フィードバックは、単なる評価や批判ではなく、個人と組織の成長を促すための強力なツールです。その語源が示すように、行動の結果を適切に伝え、次の行動へと繋げることで、目標達成を加速させ、人材育成を効果的に進めることができます。
効果的なフィードバックは、「目標と結びつけ」「具体的に」「行動可能に」「タイムリーに」伝えることが重要です。また、サンドイッチ型やSBI型、ペンドルトンルールといった手法を状況に応じて使い分け、リモート環境下での工夫も取り入れることで、よりポジティブで生産性の高いコミュニケーションを実現します。
人事や管理職の皆様が、フィードバックを戦略的に活用することで、メンバー一人ひとりの力を最大限に引き出し、変化の激しい時代においても、自律的で強くしなやかな組織を築き上げることができるでしょう。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。





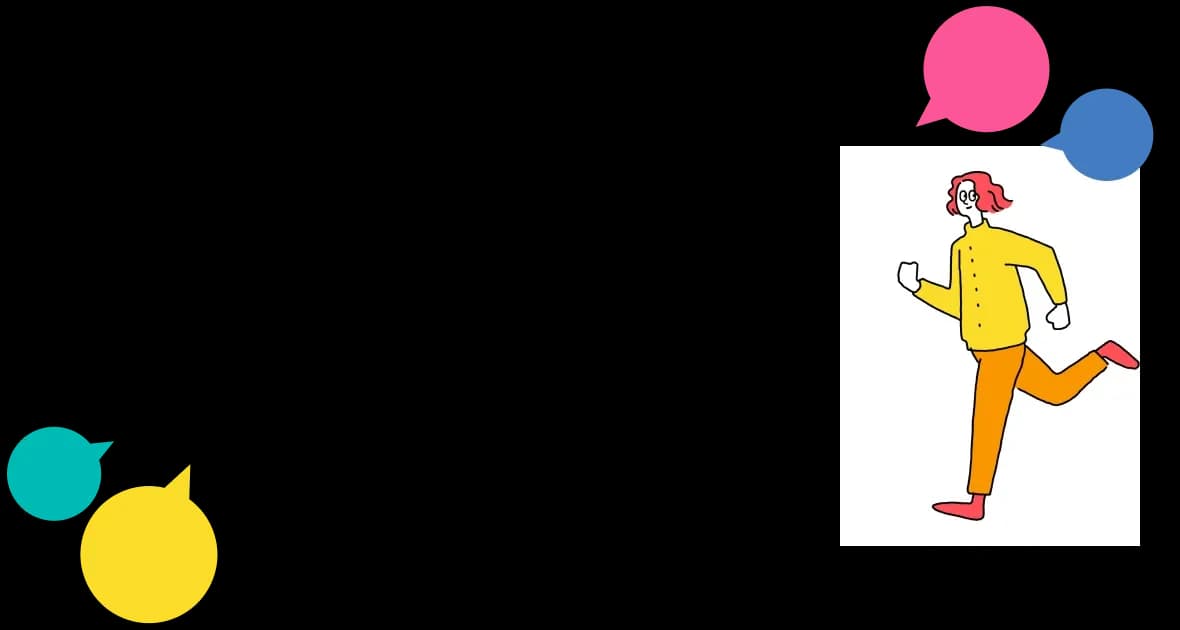



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


