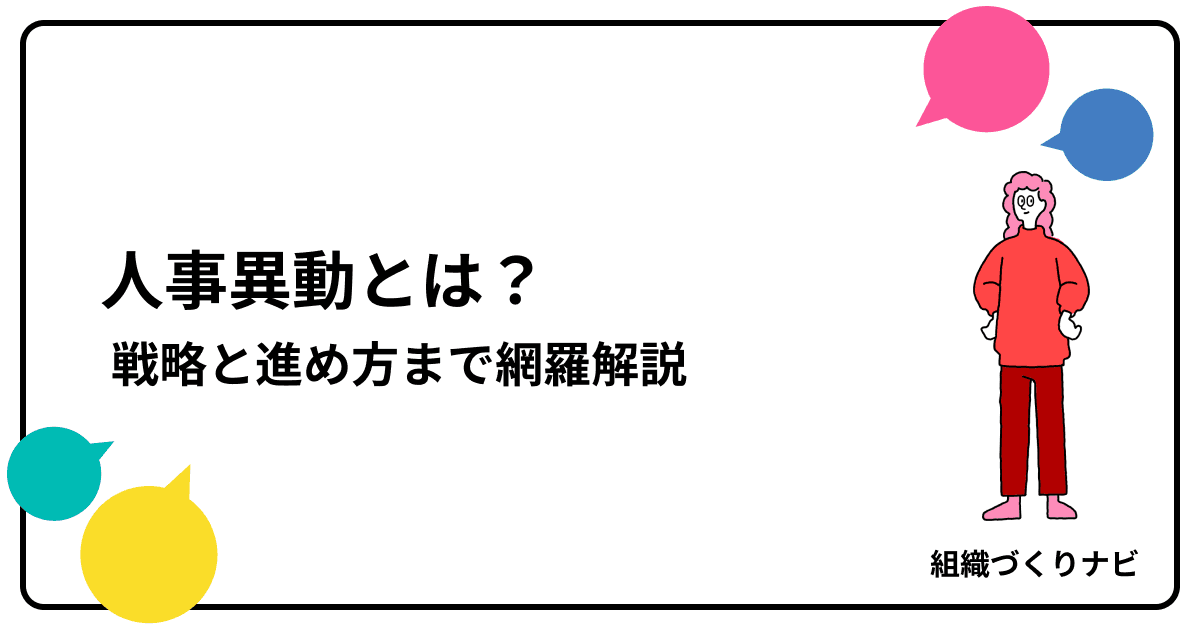
企業成長とエンゲージメントの鍵!人事異動とは?戦略と進め方まで網羅解説
人事異動は、企業の持続的成長と従業員のエンゲージメントを高める戦略的な人材配置です。本記事では、人事異動の基本的な定義から、昇進・配置転換・転勤といった種類、組織活性化や人材育成などの多岐にわたる目的を解説します。企業と従業員双方にとってのメリット・デメリットを深く理解し、適材適所を実現するための具体的な実施手順、円滑な進め方、トラブルを防ぐための注意点、法的側面からの対策を網羅的にご紹介。人事・管理職の皆様が、公平性と透明性を保ち、丁寧なコミュニケーションを通じて人事異動を成功させ、企業全体のパフォーマンス向上と従業員の成長を促すための実践的なヒントや、よくある疑問への回答を提供します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
人事異動とは?企業の成長と従業員のエンゲージメントを高める戦略的な人材配置
「人事異動」は、企業が組織を活性化させ、従業員一人ひとりの成長を促すために行う重要な取り組みです。単なる事務手続きに留まらない、戦略的な人材配置としての重要性に焦点を当て、貴社の人事・管理職の皆様が円滑かつ効果的に人事異動を進めるための実践的なヒントを提供します。本記事を通じて、人事異動が企業と従業員双方にとってより良い結果をもたらすための知見を深めていただければ幸いです。
人事異動の基本的な定義と企業の人事権
人事異動とは、企業が持つ「人事権」に基づき、従業員の職務内容、勤務場所、役職などを変更すること全般を指します。これは、組織の状況や事業戦略、従業員の能力や適性を総合的に考慮して行われるもので、企業経営の根幹を担う戦略的な人材マネジメント施策です。単に「部署が変わる」といった表面的な意味合いだけでなく、従業員のキャリア形成やモチベーション、そして企業全体の生産性にも深く関わる動きであると理解することが重要です。
人事異動の主な種類と目的
人事異動には様々な形があり、それぞれ異なる目的と影響を持ちます。主な種類としては、従業員の職位が上がる「昇進・昇格」、その逆である「降格・降任」、職務内容や部署が変わる「配置転換(配転)」、勤務地が変わる「転勤」があります。また、一時的に他の企業で働く「出向」なども人事異動の一種です。
企業が人事異動を行う目的は多岐にわたりますが、主に組織の活性化、人材育成、適材適所の実現、そして不正の防止が挙げられます。例えば、特定の部署に長く留まることによるマンネリ化を防ぎ、新しい視点やアイデアを組織にもたらすことで、停滞した状況を打破できます。また、様々な職務経験を積ませることで従業員のスキルアップや多角的な視野を養い、将来のリーダー育成にも繋がります。事業拡大・縮小に伴う人員配置の見直しなど、経営戦略上の必要性から実施されることも少なくありません。
人事異動がもたらすメリットとデメリット
人事異動は企業と従業員双方にメリットとデメリットをもたらします。これらの影響を理解し、適切に対処することが、人事異動を成功させる鍵となります。
企業側におけるメリット・デメリット
企業側のメリットとしては、組織の活性化、戦略的な人材育成、業務効率の向上、部門間の連携強化、不正の抑止などがあります。新しい環境で従業員が成長し、組織全体のパフォーマンス向上に繋がることが期待されます。一方でデメリットとしては、異動に伴う引き継ぎコストや研修コスト、一時的な生産性の低下リスク、そして従業員の不満やモチベーション低下による離職リスクなどが挙げられます。これらのデメリットを最小限に抑えるためには、慎重な計画と、従業員エンゲージメントを損なわないための丁寧な対応が不可欠です。
従業員側におけるメリット・デメリット
従業員側のメリットとしては、新たなスキル習得、キャリアパスの拡大、人間関係の刷新、視野の拡大、自己成長の機会などが挙げられます。新しい仕事や環境に挑戦することで、自身の能力を再発見し、キャリア形成に良い影響を与える可能性があります。しかしデメリットとして、環境変化によるストレス、ワークライフバランスの変化、家族への影響、慣れない業務への適応期間における精神的負担などが考えられます。これらの負担を軽減するための企業のサポートと、きめ細やかなコミュニケーションが重要になります。
関連する参考記事
多積:先ほど、エンゲージメントはコミュニケーションづくりの土台ではないかと話しました。実際に2023年10月の人事異動で新たに1名メンバーが増員になった際に、勉強会を開いて学びの共有や自己紹介の時間を取ったところ、スムーズにチームに打ち解けられたので、土台がしっかりとしていれば柔軟に対応できることを確信しました。今後も、ジョブローテーションや異動があった際には、同じように心理的安全性の高い状態で進めていきたいなと考えています。

人事異動の実施手順と円滑な進め方
人事異動は、以下の一般的な手順で進められます。各ステップで透明性と公平性を保ち、従業員への配慮を忘れないことが、円滑な実施に繋がります。
人員配置目標の設定:
企業全体の経営戦略や事業計画に基づき、どのような人材をどこに配置すべきか、具体的な目標を設定します。
異動案の作成:
従業員の能力、適性、過去の実績、キャリア志向などを踏まえながら、具体的な異動案を作成します。ここでは、複数の候補を検討し、多角的な視点から最適な配置を模索します。
内示と意見聴取:
異動対象者には「内示」という形で非公式に打診を行い、異動の目的や背景を説明します。従業員からの意見や懸念を丁寧に聞き取り、可能な範囲で配慮する姿勢が重要です。
辞令交付:
内示を経て最終的な異動が決定したら、正式に「辞令交付」が行われます。この際も、異動の趣旨を改めて説明し、従業員が納得感を持って受け入れられるよう努めます。
事後フォロー:
異動後も、新しい環境での従業員をサポートするための「事後フォロー」は欠かせません。新しい業務への適応支援、人間関係の構築サポート、定期的な面談などを通じて、従業員の定着と活躍を促します。
トラブルを未然に防ぐ!人事異動における注意点と対策
人事異動を円滑に進め、従業員とのトラブルを未然に防ぐためには、法的な側面とコミュニケーションの側面双方からの対策が不可欠です。
就業規則の明確化:
最も重要なのは、
就業規則に人事異動に関する規定を明確に設けておくこと
です。これにより、企業の人事権行使の根拠が明確になり、従業員に異動命令に従う義務があることを周知できます。異動の範囲(勤務地、職種など)や、拒否できる特別な事情についても記載しておくべきでしょう。
公平性と透明性の確保:
異動対象者の選定基準は、公平かつ客観的であるべきです。恣意的な判断ではなく、業務上の必要性、能力、適性に基づいていることを明確に説明できるよう準備しておくことが重要です。選定基準の透明性が、従業員の納得感に繋がり、不満の発生を抑えます。
丁寧なコミュニケーション:
内示の段階から、異動の目的、期待する役割、異動先でのサポート体制などを具体的に説明し、従業員の不安を解消するための対話を重ねることが極めて重要です。一方的な命令ではなく、従業員のキャリア形成の一部であることを意識した説明が求められます。
ハラスメント・権利濫用の回避:
異動命令が、特定の従業員に対する嫌がらせや、退職強要などの不当な目的で行われたと判断されるケースでは、法的トラブルに発展する可能性が高まります。企業の人事権は、業務上の必要性がある場合にのみ認められるものであり、
権利の濫用
とみなされる行為は厳に慎むべきです。特に、育児や介護など、従業員の生活に重大な影響を与える異動については、より一層の配慮と丁寧な説明が求められます。
相談窓口の設置:
従業員が異動に関する不安や疑問を気軽に相談できる窓口を設置することも有効です。これにより、問題が深刻化する前に対応し、トラブルへの発展を防ぐことができます。
まとめ:人事異動は組織成長とエンゲージメントの要
人事異動は、単なる従業員の配置換えではなく、企業が持続的に成長し、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮するための戦略的な人事施策です。組織の活性化、人材育成、適材適所の実現、そして従業員エンゲージメントの向上といった多岐にわたる目的を持ち、企業と従業員双方に大きな影響を与えます。
人事・管理職の皆様には、人事異動の目的を深く理解し、種類ごとの特性を把握した上で、透明性のある公平な運用を心がけていただきたいと願っています。従業員との丁寧なコミュニケーションを通じて、異動への不安を軽減し、前向きな挑戦へと導くことが、人事異動を成功させ、ひいては企業全体の成長を加速させる鍵となります。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

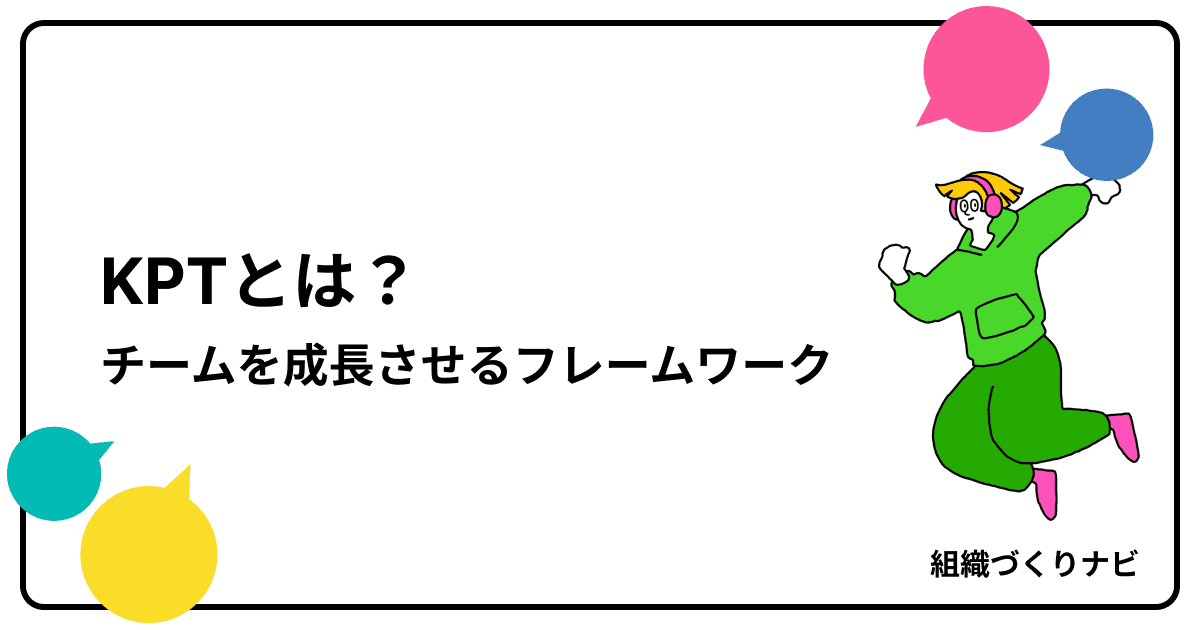
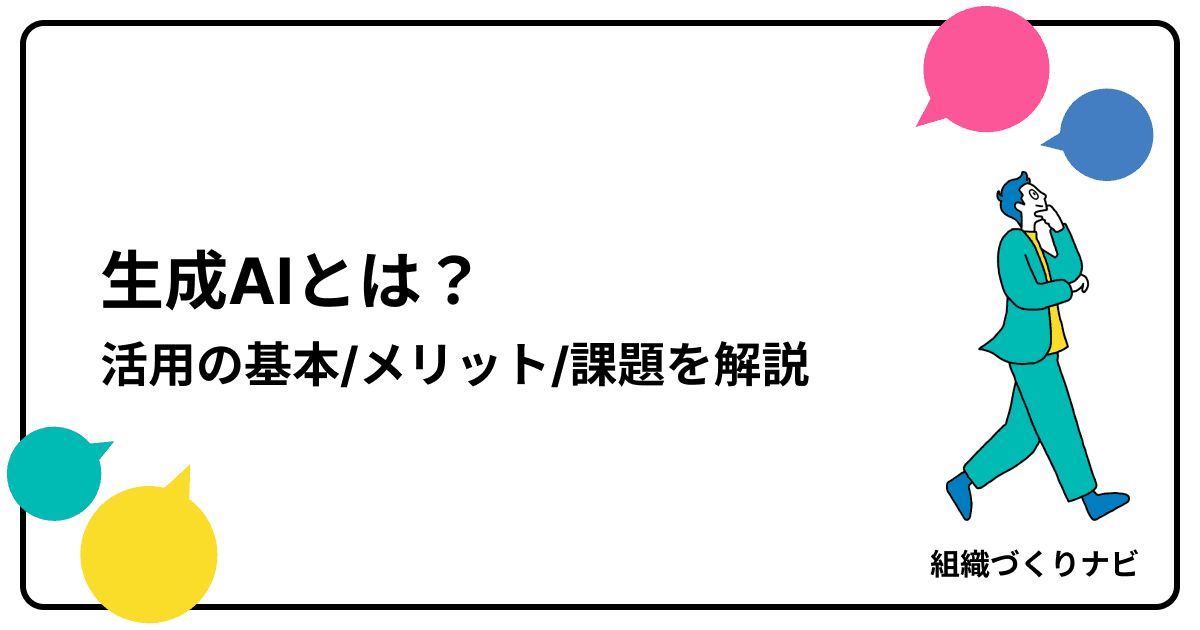
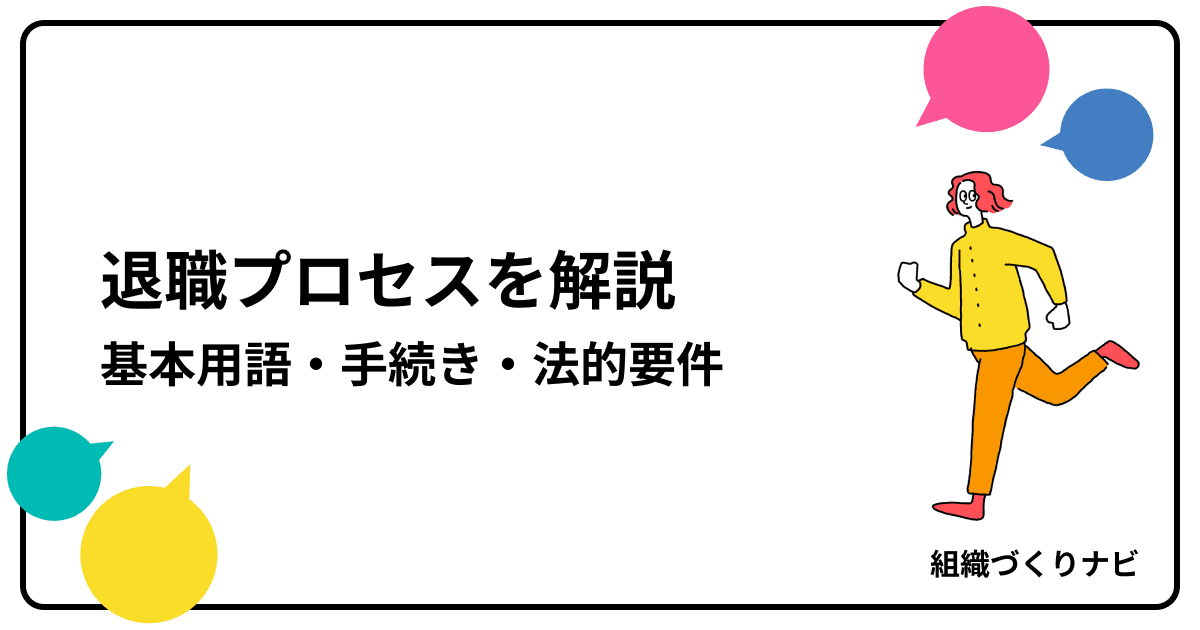
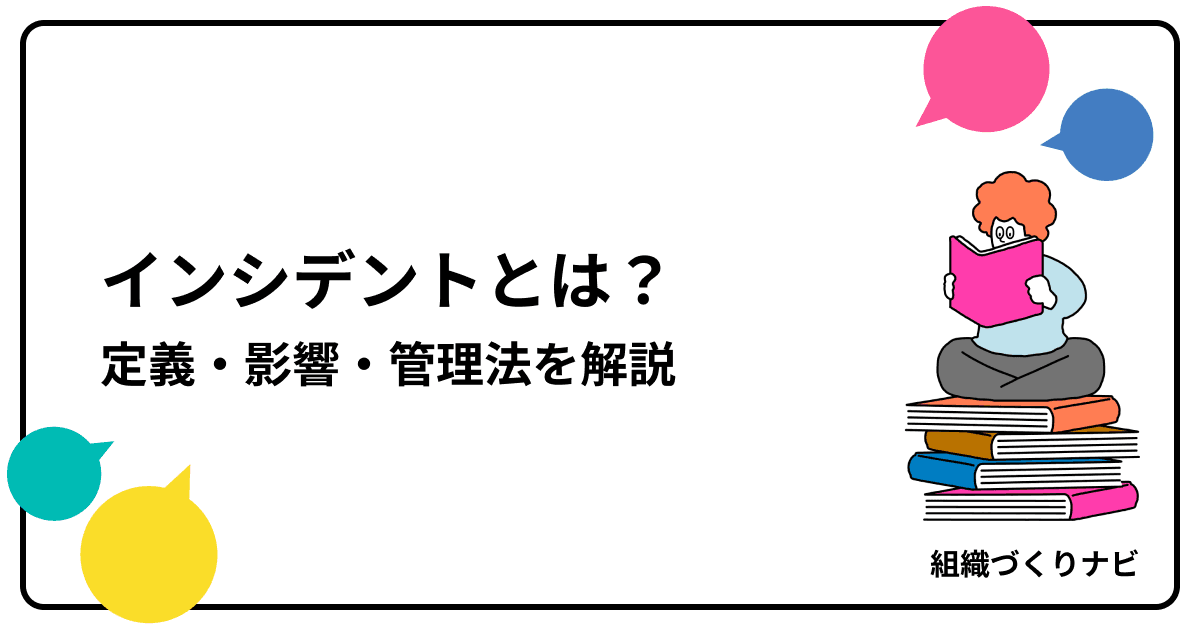
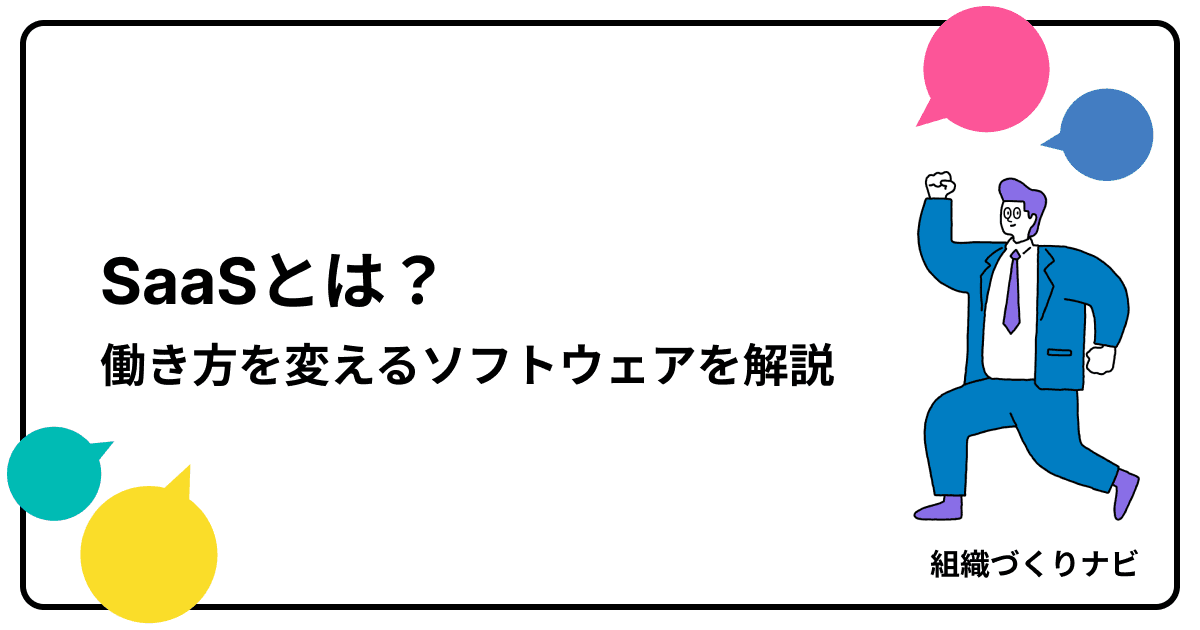
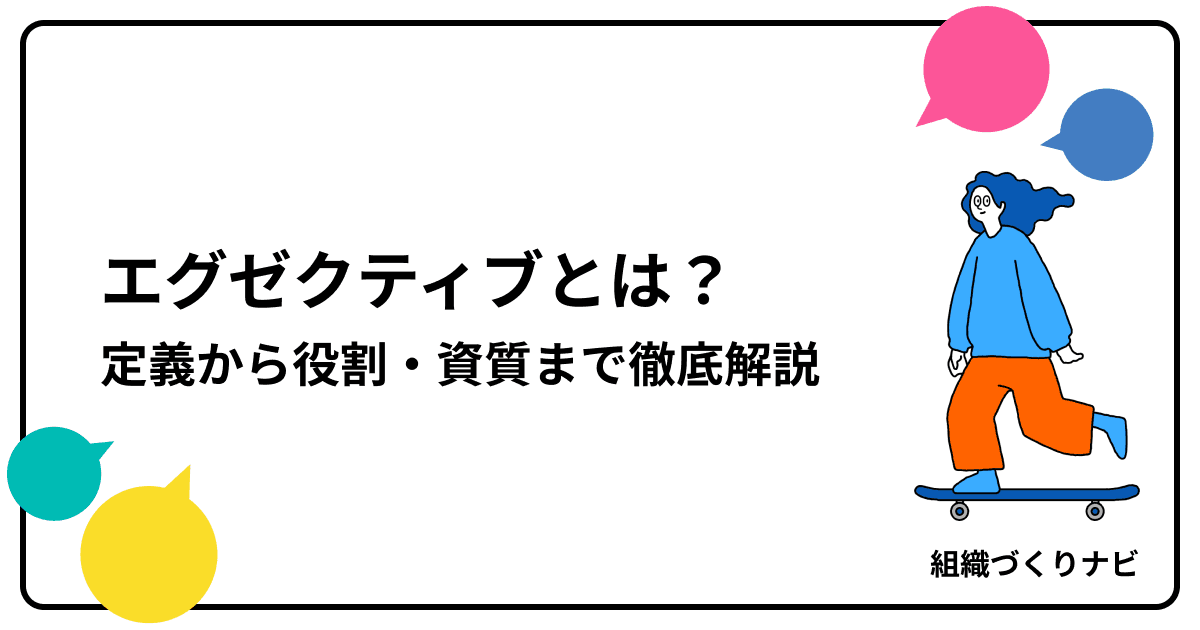



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


