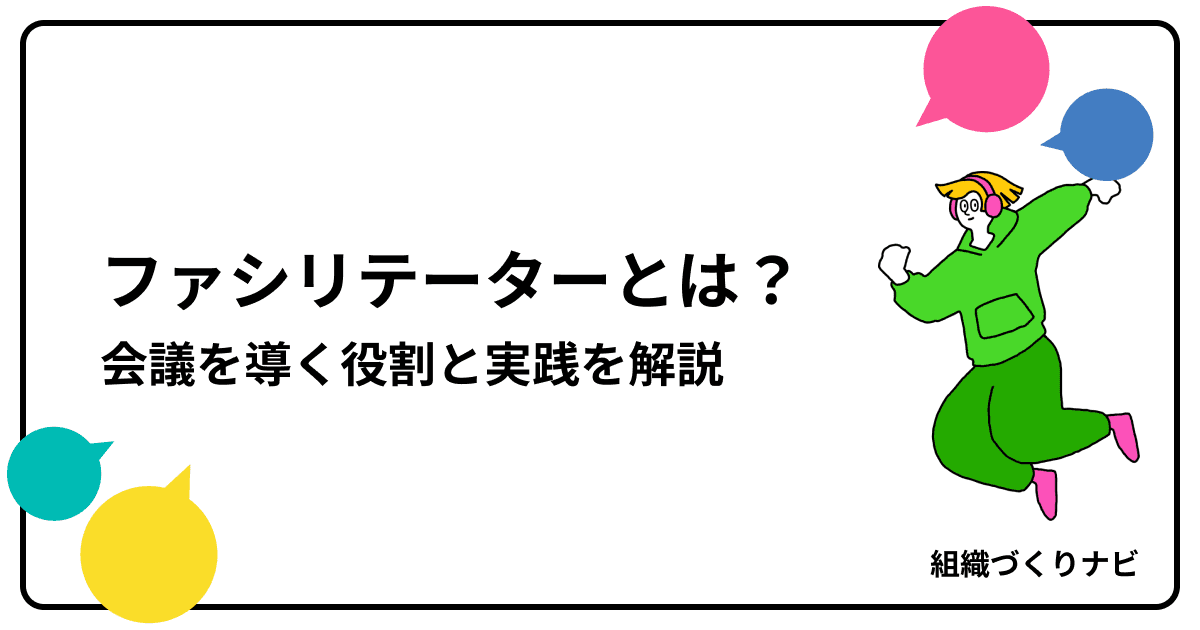
ファシリテーターとは?会議を成功に導く役割と実践を徹底解説
ファシリテーターは、会議やチーム活動で参加者全員が活発に意見を出し、目的達成と納得の合意形成を支援する重要な役割を担います。ファシリテーターの定義や司会との違いから、会議やチームにもたらす具体的なメリット、ゴール設定、雰囲気づくり、意見引き出し、合意形成といった必須スキル、さらに今日から実践できる具体的な進め方、育成方法までを網羅的に解説します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
ファシリテーターとは?会議やチームを成功に導く役割とスキル、実践方法を徹底解説
「会議がいつも長引く」「議論がなかなかまとまらない」「一部の人ばかりが発言して、新しいアイデアが出にくい」――。人事や管理職の皆さんは、このような悩みを抱えていませんか?その解決の鍵を握るのが、「ファシリテーター」という存在です。
ファシリテーターは、単なる司会進行役ではありません。会議や話し合いの場において、参加者全員が活発に意見を出し合い、設定された目的を達成し、納得感のある合意形成ができるように、中立的な立場で議論のプロセスをサポートする重要な役割を担います。
この記事では、ファシリテーターの基本的な意味から、司会との違い、求められるスキル、そして明日から実践できる具体的な進め方まで、人事・管理職の皆さんがチームや組織のパフォーマンスを高めるために必要な知識を網羅的に解説いたします。この記事を読めば、あなたのチームの会議が生産的な場へと大きく変わるはずです。
チームビルディング(エンゲージメント)活動において、ファシリテーターを重視する事例↓
―他社の方も含めて、チームビルディング活動を検討されている方に対してアドバイスがあればお願いします。
礒端:対話に取り組む際に、リーダーやファシリテーターが下手に目指すゴールに誘導しないことが大事かなと思います。そうなると、みんながリーダーやファシリテーターの考えに傾いてしまいます。全員の対話の中でアイデアを出し合って、チームとして同じ方向を向いて活動を進めていけるといいと思います。

ファシリテーターとは?チームの可能性を最大限に引き出すその本質
「ファシリテート」の語源と基本的な意味
ファシリテーターは、英語の「facilitate(ファシリテート)」から来ています。この言葉には、「物事を容易にする、促進する、助けになる」といった意味があります。つまり、ファシリテーターとは、会議やプロジェクト、チーム活動において、参加者一人ひとりの能力や知恵を最大限に引き出し、目標達成への道のりをスムーズにするための「推進役」や「支援者」を指します。特定の意見に肩入れすることなく、中立的な立場で、誰もが安心して発言できるような場を作り、議論を深めていくことがその本質です。
司会やネゴシエーターとの明確な違い
ファシリテーターは、しばしば「司会」や「ネゴシエーター」と混同されがちですが、その役割には明確な違いがあります。 司会は、事前に決められたプログラムに沿って進行を管理し、時間通りにイベントを終えることが主な目的です。 一方、ネゴシエーターは、自身の交渉目標や特定の利害を持って、自己の利益に資する合意形成を目指します。 これに対し、ファシリテーターは、特定の意見を持たず、中立の立場で、参加者全員が納得できる質の高い結論を導き出すことを目指します。議論の「内容」ではなく、議論が「どう進められるか」というプロセスに焦点を当て、誰もが建設的に話し合える環境を整えることがその最大の役割です。
なぜ今、ファシリテーターが組織で重要なのか
現代のビジネス環境は複雑化し、不確実性が高まっています。多様なバックグラウンドを持つ人々が協力し合う場面が増える中で、一方的な指示や情報伝達だけでは、チームのパフォーマンスを最大限に引き出すことは困難です。 ファシリテーターがいることで、それぞれの専門知識や経験がスムーズに共有され、新たなアイデアが生まれやすくなります。また、異なる意見がぶつかった際に、感情的な対立を避け、建設的な解決策を見つけ出す助けとなります。これにより、組織全体の意思決定の質が向上し、生産性の向上や従業員エンゲージメントの強化にも繋がるため、その重要性が高まっているのです。
ファシリテーターがもたらす、会議・チームへの具体的なメリット
ファシリテーターが介入することで、会議やチーム活動には多くのポジティブな変化が生まれます。単なる時間の消費ではなく、価値創造の場へと変貌させることが可能です。
会議の目的・ゴールが明確になります
: 始まる前に目的を共有し、議論の方向性を見失わないよう常に軌道修正を促すため、参加者全員が集中して取り組めます。
多様な意見が引き出されます
: 一部の人だけでなく、参加者全員が安心して発言できる雰囲気を作り、普段表に出にくい隠れた意見や画期的なアイデアも引き出します。
議論が深まり、質の高いアイデアが生まれます
: 漠然とした意見を掘り下げ、異なる視点や情報を結びつけることで、より創造的で実用的な解決策や方針を見つける手助けをします。
合意形成がスムーズになります
: 意見の対立があった場合でも、共通の目標を再確認したり、複数の選択肢を客観的に比較検討したりして、参加者全員が納得できる結論へと導きます。
時間の無駄がなくなります
: 不要な脱線を防ぎ、設定された時間内に議論をまとめ、次の行動へと繋げることで、会議の生産性を大幅に向上させ、参加者の貴重な時間を有効活用できます。
参加者のエンゲージメントが高まります
: 自分の意見が尊重され、議論に貢献していると感じることで、参加者のモチベーションや会議への満足度が向上し、主体的な行動を促します。
会議やチームを成功に導く!ファシリテーターに求められる重要なスキル
ゴール設定と共通認識の醸成
ファシリテーターにとって最も重要なのは、会議や議論の「ゴール(目的)」を明確にし、それを参加者全員で共有することです。ゴールが曖昧なままでは、議論は発散し、時間ばかりが過ぎてしまいます。 会議の冒頭で「今日のゴールは〇〇です」と明確に提示し、参加者の認識を合わせます。そして、議論の途中で目的から逸れそうになった時には、「私たちのゴールは〇〇でしたね」と優しく軌道修正を促すことで、常に生産的な方向へ議論を進めることができます。このスキルは、時間管理や効率的な意思決定に直結します。
場の雰囲気づくりと対話の促進
参加者全員が安心して発言できる心理的安全性の高い場を作ることは、ファシリテーターの重要な役割です。 会議の冒頭でアイスブレイク(軽い雑談)を取り入れたり、グランドルール(話し合いの基本的なルール)を設定したりすることで、参加者の緊張を和らげ、オープンな対話を促します。 例えば、「相手の意見を尊重する」「まずは否定せず、受け止める」といったルールを設けることで、多様な意見が活発に飛び交う環境を作り出します。発言の少ない人には優しく問いかけ、誰もが議論に参加できるよう促す配慮も求められます。
「対話の促進」を重視する事例↓
9月のエントリーでは、チャレンジ選出のための対話がスムーズにできる部門と、人数や人員構成によってできない部門もあると思い、対話からチャレンジを導き出すヒントになるようなフローを作成して公開しました。また、事務局メンバーを各部門の担当に割り振っていたので、希望があればファシリテーターとして対話に入ったりチャレンジ選出の相談に乗ったりといったことも行いました。
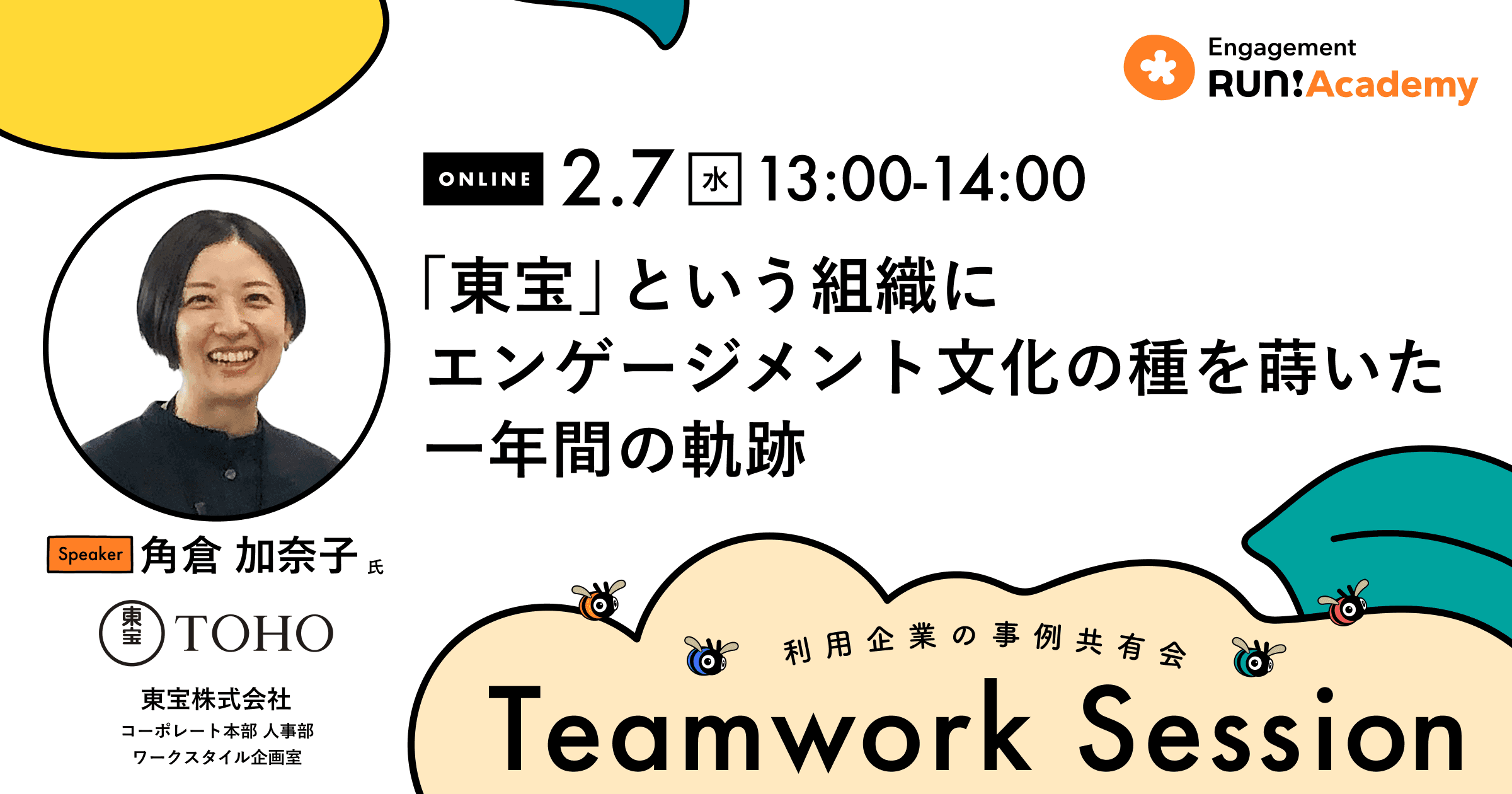
意見を引き出し、構造化する力
ファシリテーターは、単に意見を聞くだけでなく、参加者の多様な意見を効果的に引き出し、それを整理・構造化する力が必要です。 例えば、「なぜそう考えたのですか?」「具体的にはどのようなことでしょうか?」といったオープンな質問を投げかけ、発言の真意や背景を探ります。出てきた意見はホワイトボードや付箋を使って視覚的にまとめ、「これは課題」「これはアイデア」といった形で分類し、議論の全体像を分かりやすく提示します。これにより、参加者は議論の現在地を把握しやすくなり、次のステップへと進むための土台ができます。
合意形成と行動計画へのまとめ
議論が盛り上がり、多くの意見が出た後には、それらを具体的な合意へと結びつけ、次の行動計画を明確にする役割がファシリテーターには求められます。 出た意見の中から共通点や優先順位を見出し、参加者全員が納得できる形で結論を導き出します。多数決に頼るだけでなく、「この結論で本当に全員が納得できるか?」「不安な点はないか?」と確認することで、質の高い合意形成を促します。そして、「誰が」「何を」「いつまでに」行うのかという具体的なアクションプランを明確にし、会議で決まったことが確実に実行に移されるようサポートします。
タイムマネジメントと円滑な進行
会議や議論が予定通りに進むよう、時間配分を常に意識し、進行を調整するスキルは非常に重要です。 議題ごとに時間を区切り、その時間内で議論が進むように促します。議論が脱線しそうになったり、特定の話題に偏りすぎたりした場合には、「この議題にはあと〇分しかありませんので、本題に戻りましょう」などと冷静に促し、効率的な進行を維持します。また、会議の冒頭で提示したゴールを常に意識させ、不要な長時間の会議を防ぐことで、参加者の集中力を保ち、生産性を高めます。
傾聴力と質問力
ファシリテーターは、参加者の発言を傾聴する力と、適切な質問を投げかける力が不可欠です。 相手の言葉だけでなく、表情や声のトーンからも真意を汲み取ろうと意識して聞くことで、より深い理解に繋がります。また、「それについて、他に意見はありますか?」「この問題を解決するために、何か違う視点はありますか?」といった多角的な質問をすることで、議論を広げたり深めたりすることができます。特に、建設的な対話を促す「イエス、アンド(相手の意見を肯定し、さらに自分の意見を付け加える)」のような質問テクニックも有効です。
ロジカルシンキングと全体像の把握
議論が複雑になったり、多くの情報が飛び交ったりする中で、ファシリテーターは論理的に思考し、議論の全体像を把握する能力が求められます。 話の筋道が通っているか、意見と事実が混同されていないかなどを客観的に判断し、必要に応じて「つまり、〇〇ということですね?」と要約したり、「その意見の根拠は何でしょうか?」と問いかけたりします。これにより、感情的な対立を防ぎ、論理に基づいた建設的な議論へと導くことができます。常に「私たちは何のためにここにいるのか」という目的意識を持ち、議論の全体を俯瞰することが重要です。
今日から実践!ファシリテーションの具体的な進め方
【事前準備】目的・ゴール設定とアジェンダ作成
会議が始まる前の準備が、成功の半分を決めると言っても過言ではありません。 まず、「この会議で何を達成したいのか?」という目的とゴールを明確に設定します。例えば、「〇〇問題の解決策を決定する」など、具体的にします。次に、そのゴールに到達するためのアジェンダ(議題)を作成し、各議題に適切な時間配分を割り当てます。このアジェンダは、参加者全員に事前に共有し、会議への心構えを促しましょう。また、使用する資料やツール(ホワイトボード、付箋など)の準備も怠らないようにします。
【会議開始時】アイスブレイクとグランドルール設定
会議の冒頭では、参加者の緊張をほぐし、誰もが発言しやすい雰囲気を作るための「アイスブレイク」を取り入れましょう。例えば、簡単な自己紹介や「最近あった良いこと」などを共有する時間です。 次に、議論を円滑に進めるための「グランドルール」を設定します。例えば、「他者の意見を最後まで聞く」「批判ではなく、建設的な意見を出す」「時間厳守」など、全員で合意形成してルールを決めます。これにより、心理的安全性が確保され、活発な意見交換の土台が築かれます。
【意見出し・議論時】多様な意見を引き出す工夫
議論が始まったら、ファシリテーターは積極的に参加者の意見を引き出すことに努めます。 例えば、発言の少ない人には「〇〇さんはいかがですか?」と名指しで問いかけたり、「このテーマについて、他にどんなアイデアがありますか?」と全体に問いかけたりします。 また、出てきた意見はホワイトボードなどに書き出し、「見える化」することで、思考を整理しやすくします。否定的な意見が出た場合でも、「なぜそう思うのか」と深掘りし、対立を避けつつ背景を理解しようと努めることが重要です。「イエス、アンド」の考え方を取り入れ、肯定的に意見を受け止め、発展させる姿勢を示しましょう。
【意見整理・合意形成時】議論をまとめる技術
多くの意見が出た後には、それらを整理し、合意形成へと導く段階に入ります。 書き出した意見をグループ化したり、優先順位をつけたりして、議論の焦点を見極めます。意見が対立している場合は、それぞれの意見の共通点や妥協点を探るよう促したり、メリット・デメリットを洗い出したりします。最終的には、「この方向性で進めて良いか?」「全員が納得できるか?」と最終確認を行い、参加者全員が納得できる形で結論をまとめます。結論が曖昧にならないよう、具体的な言葉で表現することが大切です。
【会議終了時】次の行動への繋げ方
会議で決まったことを無駄にしないためには、次の行動への繋げ方が非常に重要です。 結論が出たら、具体的なアクションプラン(誰が・何を・いつまでに・どうするのか)を明確にします。例えば、「Aさんが、Bの件について、来週金曜日までにCに連絡する」といった具合です。 また、会議の成果や決定事項を簡潔にまとめ、参加者全員で再確認します。最後に、会議のプロセスやファシリテーター自身へのフィードバックを求める時間を作ることで、今後の改善に繋げることができます。これにより、会議が「決めるだけの場」ではなく、「具体的な行動を生み出す場」となります。
ファシリテーターを育成するには?スキルアップと組織への浸透
実践を通じて経験を積む重要性
ファシリテーターのスキルは、座学だけでなく、実践を通じて磨かれるものです。 まずは、小規模なミーティングやチーム内でのちょっとした話し合いから、意識的にファシリテーター役を担ってみましょう。 最初から完璧を目指す必要はありません。会議の目的を明確にする、時間管理を意識する、発言の少ない人に声をかけるなど、一つひとつのスキルを意識しながら実践を重ねることが重要です。場数を踏むことで、様々な状況に対応できる応用力が身につき、自信もついてくるでしょう。
専門知識や研修を効果的に活用する
ファシリテーションに関する専門的な知識を学ぶことも、スキルアップに繋がります。 書籍やオンラインコースで理論を学んだり、専門機関が開催しているファシリテーション研修に参加したりするのも良い方法です。 例えば、日本ファシリテーション協会のような団体では、ファシリテーションに関する様々な情報提供や、スキルアップのための講座が開催されています。体系的に学ぶことで、自身のファシリテーションの引き出しが増え、より複雑な状況にも対応できるようになります。
社内でのファシリテーター育成と文化醸成
組織全体でファシリテーションの文化を根付かせるためには、社内でのファシリテーター育成が不可欠です。 特定の管理職だけでなく、若手社員にも機会を与え、定期的な研修や勉強会を実施することで、組織全体のコミュニケーション能力や問題解決能力が向上します。 ファシリテーションスキルは、会議だけでなく、日々の業務におけるチーム間の連携や顧客とのコミュニケーションにも活かせるため、従業員一人ひとりのビジネススキル向上にも繋がります。社内での横断的なファシリテーターコミュニティを作ることも、スキルアップや情報共有に役立つでしょう。
ファシリテーターが直面する課題と注意点
ファシリテーターの力量への依存と対処法
ファシリテーションの質は、ファシリテーター自身のスキルや経験に大きく依存します。経験の浅いファシリテーターでは、議論が発散したり、特定の意見に偏ったりするリスクがあります。 また、ファシリテーターが一人で全ての責任を背負いすぎると、大きなプレッシャーや負担を感じてしまうこともあります。 このような課題を解決するためには、チームでファシリテーションスキルを共有し、状況に応じて役割を交代したり、複数の人が協力してファシリテーションを行う「共同ファシリテーション」を取り入れたりすることが有効です。
客観性と中立性を維持するための意識
ファシリテーターが最も注意すべき点は、議論において客観性と中立性を保つことです。 自分の意見や感情を議論に持ち込んだり、特定の参加者の肩を持ったりすると、参加者からの信頼を失い、議論が不公平に進んでしまう可能性があります。 あくまで「議論のプロセスを支援する人」という立場を徹底し、特定の結論に誘導しないよう常に意識する必要があります。時には、感情的になりそうな参加者に対して、冷静に事実を確認したり、別の視点を提供するよう促したりすることも求められます。公平な態度を貫くことが、質の高い合意形成には不可欠です。
まとめ:ファシリテーターが切り開く、組織の生産性向上とより良い未来
ファシリテーターは、単なる会議の進行役ではありません。参加者一人ひとりの声に耳を傾け、多様な意見を尊重し、建設的な議論を通じてチームの可能性を最大限に引き出す存在です。
この記事で解説したように、ファシリテーターには、明確な目的設定、心理的安全性の高い雰囲気づくり、多角的な意見の引き出し、納得感のある合意形成、効果的な時間管理など、多岐にわたるスキルが求められます。これらのスキルは、実践と学びを繰り返すことで必ず身につけることができるのです。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

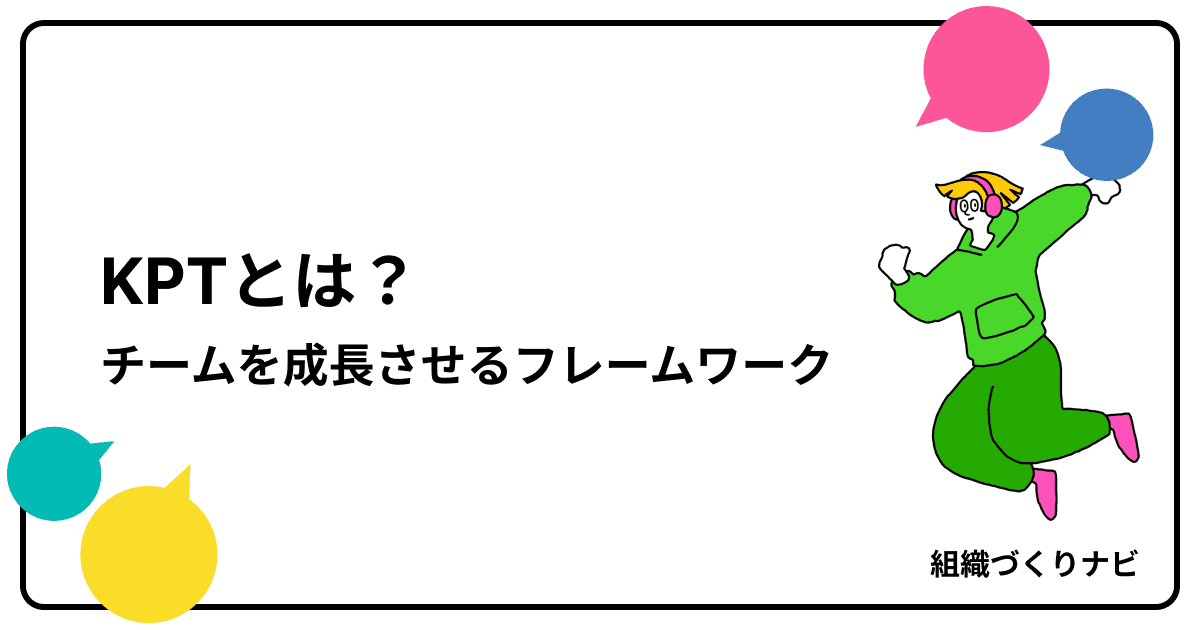
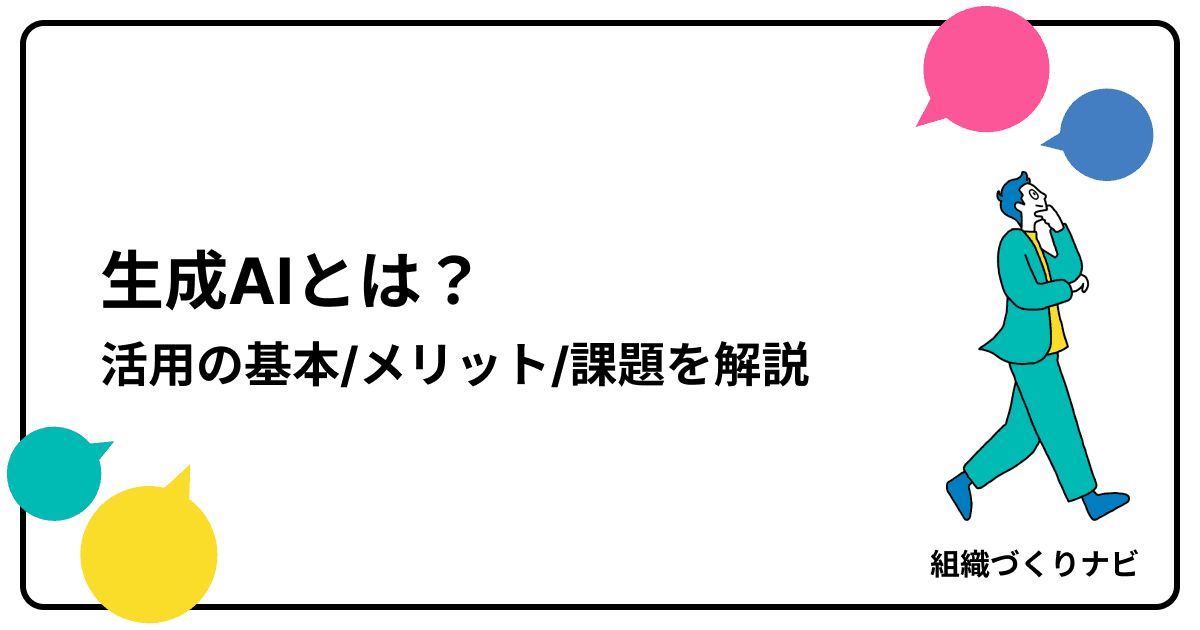
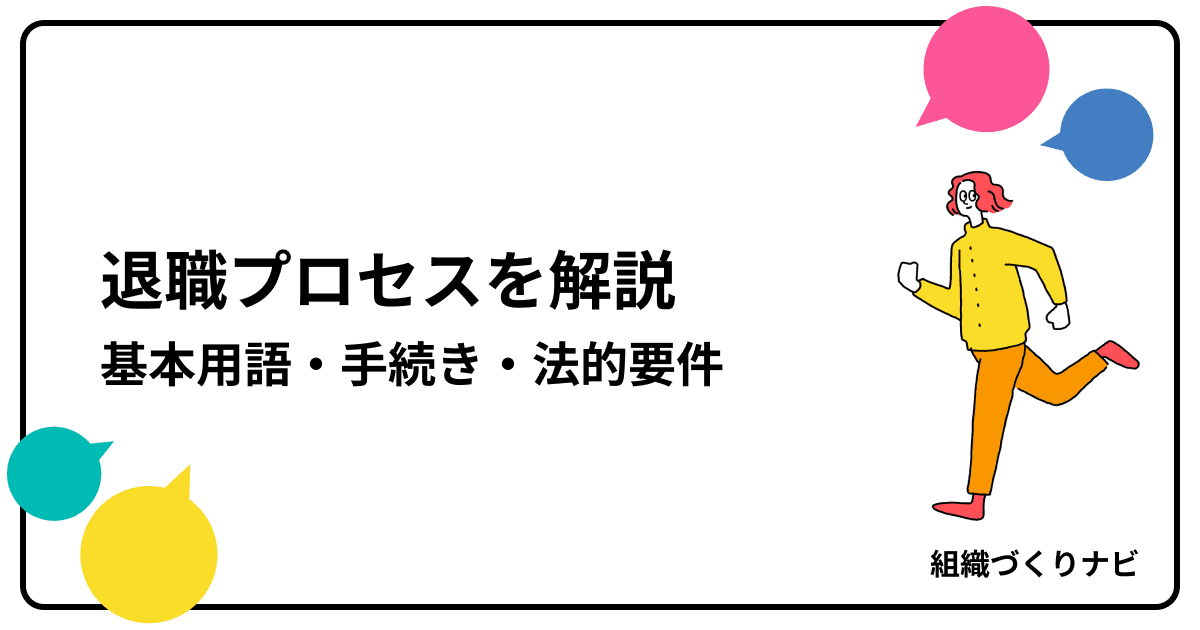
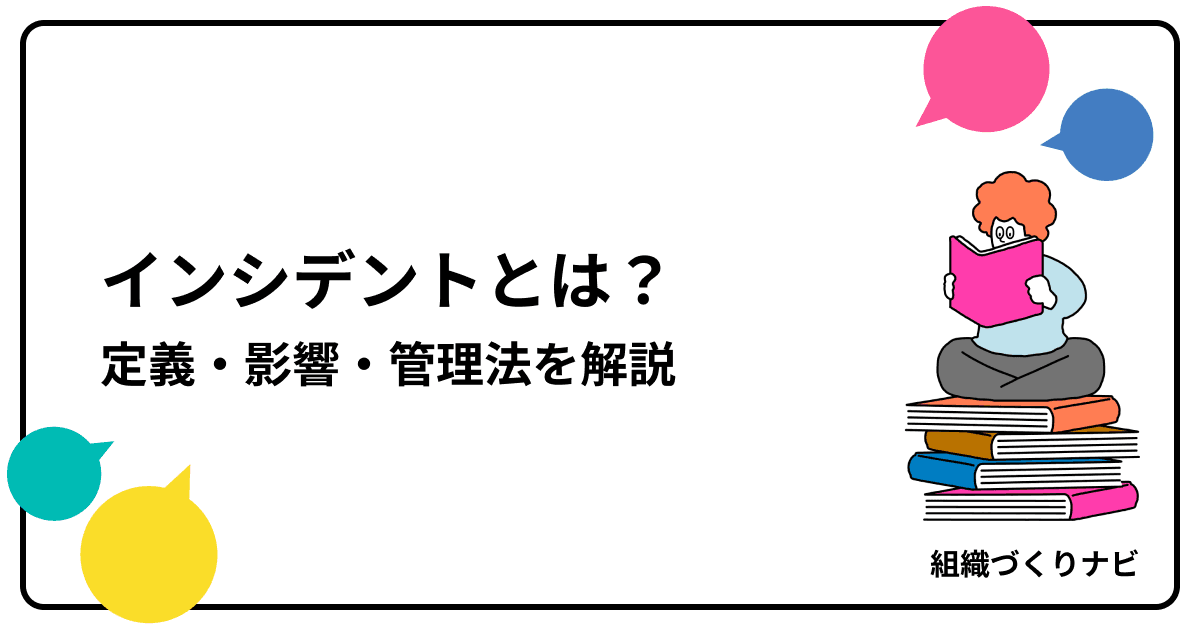
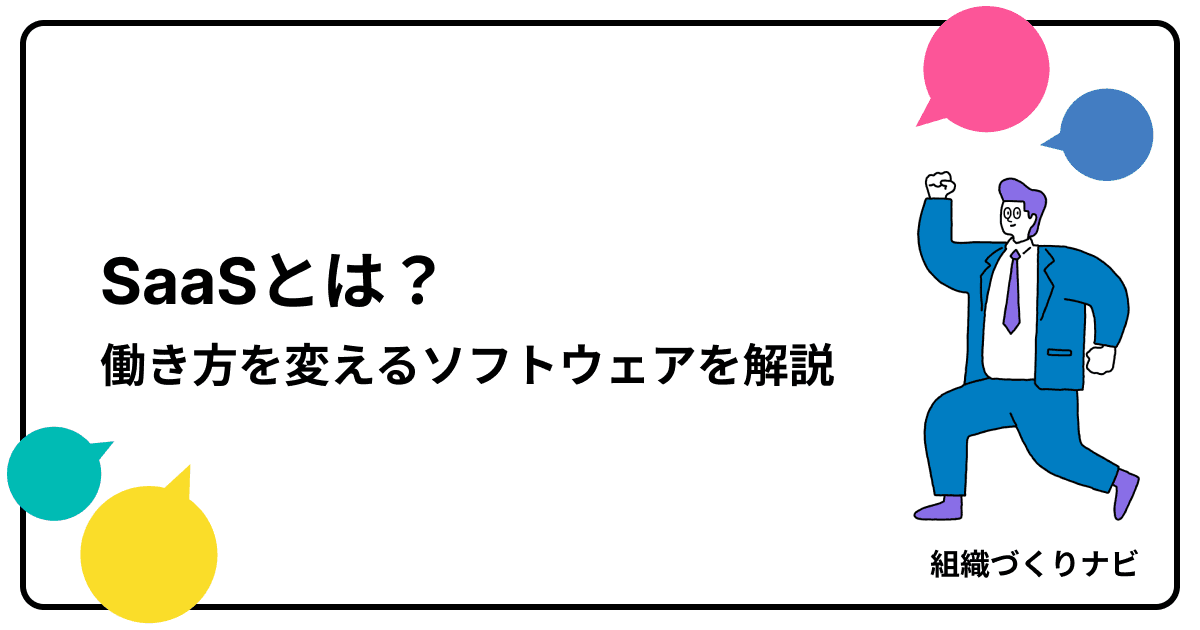
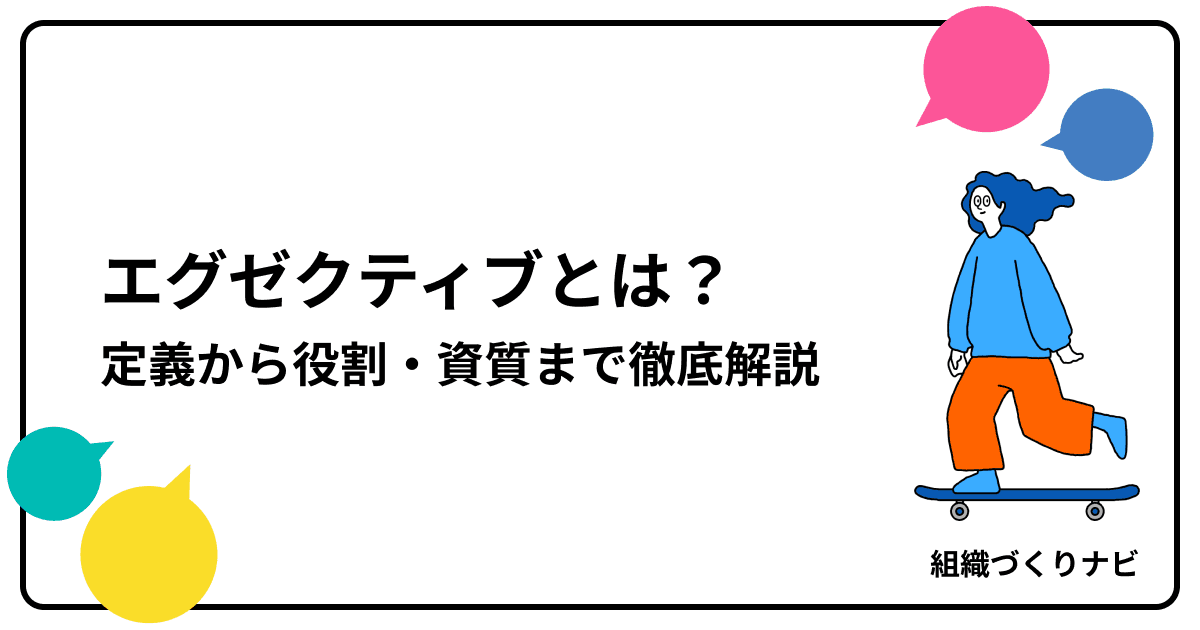



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


