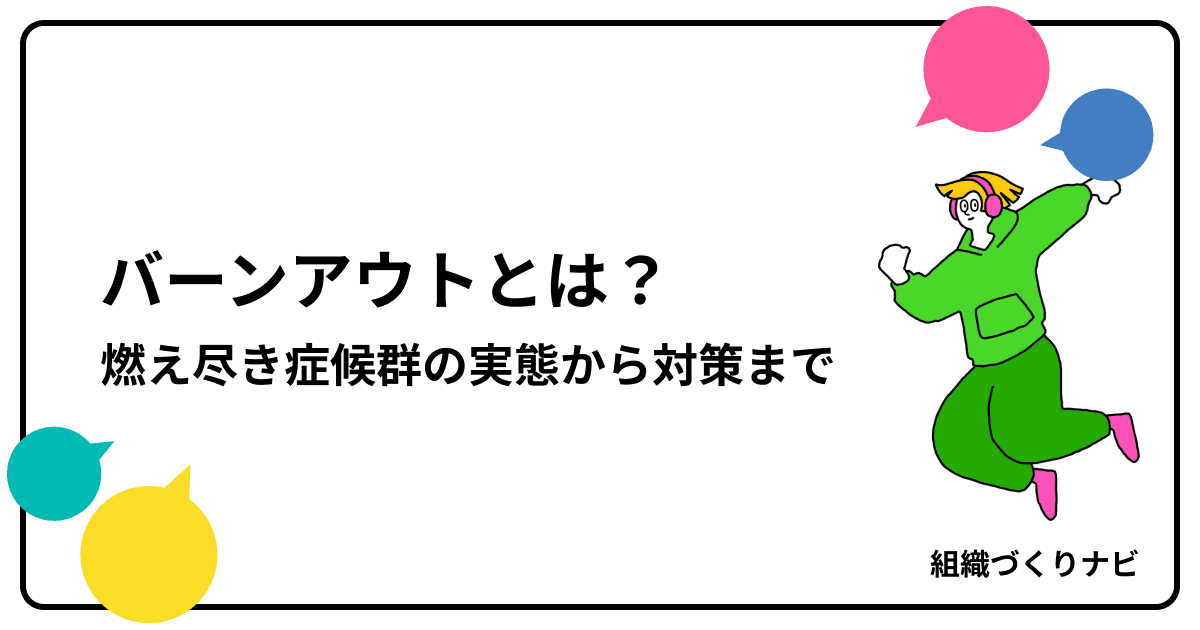
バーンアウトとは?燃え尽き症候群の実態・原因・対策を解説
バーンアウト(燃え尽き症候群)とは、仕事への熱意を失い、心身が疲れ果てる状態。真面目で責任感が強い人ほど陥りやすく、放置すれば組織の生産性低下や離職に直結します。情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下が主な症状で、長時間労働や人間関係、過度な責任感が原因に。人事・管理職は、業務負担の調整、心理的安全性の高い職場作り、柔軟な働き方推進、メンタルヘルス相談窓口の設置など、多角的なアプローチで予防・対処が求められます。従業員のウェルビーイングを優先し、組織全体でバーンアウトと向き合うことが、持続的な企業成長の鍵となります。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
バーンアウトとは?企業が軽視できないその実態
バーンアウトは、心理学者のハーバート・フロイデンバーガー氏によって提唱された概念で、**「それまで意欲的に取り組んでいた仕事や活動において、極度の心身の疲労と意欲の喪失に陥ってしまう状態」**を指します。日本では「燃え尽き症候群」とも呼ばれ、文字通りエネルギーが尽きて心が燃え尽きてしまったような状態です。
これは医学的な診断名ではありませんが、現代の企業が直面する大きな課題の一つであり、従業員の生産性、エンゲージメント、ひいては企業のブランドイメージにまで影響を及ぼす可能性があります。うつ病と混同されがちですが、バーンアウトは「仕事や活動への過剰な投入」が背景にあることが多く、仕事から離れると一時的に回復が見られることがあります。しかし、放置すればうつ病へと発展する可能性も高いため、早期の発見と組織的な対応が不可欠です。
従業員が発するSOSサイン:見逃してはならない3つの主要症状
バーンアウトには、主に3つの特徴的な症状があると言われています。人事・管理職の皆様は、これらのサインを見逃さないよう、日頃から従業員の様子に注意を払う必要があります。
情緒的消耗感
: 心身のエネルギーが完全に枯渇し、感情的に疲れ果ててしまう状態です。以前は楽しかった仕事にも喜びを感じられなくなり、常に疲労感がつきまといます。「もう何も残っていない」と感じるほどの消耗感で、日々の業務に集中できなくなったり、感情が不安定になったりする兆候が見られます。
脱人格化(非人間的な対応)
: 顧客や同僚、部下など、仕事で関わる相手に対して、まるで感情のないロボットのように冷淡な態度を取ってしまうことです。相手への共感や思いやりが薄れ、時には批判的、攻撃的になることもあります。これは、自分自身を守るために感情を麻痺させようとする、無意識の防衛反応と言えます。
個人的達成感の低下
: 自分の仕事が意味のあるものだと思えなくなり、「何をしても無駄だ」「自分は役に立たない」といった自己肯定感の低下を招きます。これまで築き上げてきたスキルや経験に自信が持てなくなり、仕事の質が低下したり、新しい挑戦を避けたりするようになるでしょう。
これらの主要症状のほかにも、原因不明の頭痛、不眠、胃腸の不調といった身体的な兆候や、イライラ、集中力の低下、やる気の喪失といった精神的な兆候が見られることもあります。従業員の些細な変化にも気を配り、サインを見逃さないことが早期対応の鍵となります。
あなたの職場にも潜む危険:バーンアウトを引き起こす複合的な原因
バーンアウトの原因は一つではありません。従業員の個々の性格や働き方、そして職場の環境が複雑に絡み合って発生します。特に、企業として認識すべきは以下の要因です。
個人要因
: 真面目で責任感が強く、完璧主義な人ほどバーンアウトに陥りやすい傾向があります。「自分が何とかしなければ」と一人で抱え込み、他者に頼ることが苦手なタイプも注意が必要です。また、仕事とプライベートの境界線が曖昧で、休息を十分にとらない人も危険性が高まります。
環境要因
: 長時間労働や過剰なノルマ、業務量の多さは直接的な原因となります。また、上司や同僚との衝突、ハラスメントといった
人間関係の悩み
や、自分の裁量で仕事を進められないといった
コントロール感の欠如
も大きなストレス源です。さらに、医療・介護・教育といった、人との深い関わりや感情的な労働が求められる「
感情労働職」の従業員は、感情の消耗が激しいため特にバーンアウトに陥りやすい傾向にあります。
これらの要因が重なり、長期間にわたってストレスが解消されない状態が続くと、心身のエネルギーが枯渇し、バーンアウトへと繋がってしまいます。企業としては、これらの要因を組織課題として捉え、改善策を講じる必要があります。
組織と個人の両輪で防ぐ:効果的な予防と対処法
バーンアウトの予防と対処には、個人と組織の双方からのアプローチが不可欠です。特に人事・管理職の皆様には、組織としての具体的な対策が求められます。
組織が取り組むべき予防・対処法(人事・管理職の役割)
業務負担の継続的なチェックと調整
: 定期的に従業員の業務量や残業時間を把握し、ストレスチェックの結果も活用しながら、必要に応じて業務配分を見直しましょう。タスクの見える化や適切な人員配置も効果的です。
心理的安全性のあるコミュニケーションの活性化
: 1on1ミーティングなどを通じて、従業員の悩みやストレスを傾聴し、共感と思いやりのある職場文化を醸成することが重要です。誰もが安心して意見を言え、助けを求められるような心理的安全性の高い環境作りが、早期発見・早期対応に繋がります。
多様な働き方の導入とワークライフバランスの推進
: フレックスタイム制やテレワーク、時短勤務など、柔軟な働き方を導入することで、従業員が自身のライフスタイルに合わせてワークライフバランスを保ちやすくなります。これは、従業員満足度向上にも寄与します。
メンタルヘルス相談窓口の設置と周知
: 従業員が安心して相談できる社内外の専門家による窓口を設置し、その存在を定期的に周知徹底しましょう。匿名性を確保するなど、利用しやすい環境を整えることが重要です。
適切な復職支援プログラムの整備
: もしバーンアウトに陥って休職した場合でも、休職中のフォローアップから、段階的な職場復帰プログラムを用意するなど、安心して復帰できるようなサポート体制を整えましょう。これにより、再燃を防ぎ、持続的な就労を支援します。
関連する参考記事
現代の仕事にもう少し創意工夫や人間関係などの要素を取り入れることで、仕事自体の面白さを取り戻すことができるのではないでしょうか。与えられた仕事のやり方を自分なりに工夫し、仕事をするための人間関係にこだわってみる。仕事の捉え方を工夫して、見えない客や仲間への貢献を意識する。.....お気づきの方もいると思いますが、こうした試みは「ジョブ・クラフティング」とも呼ばれます。
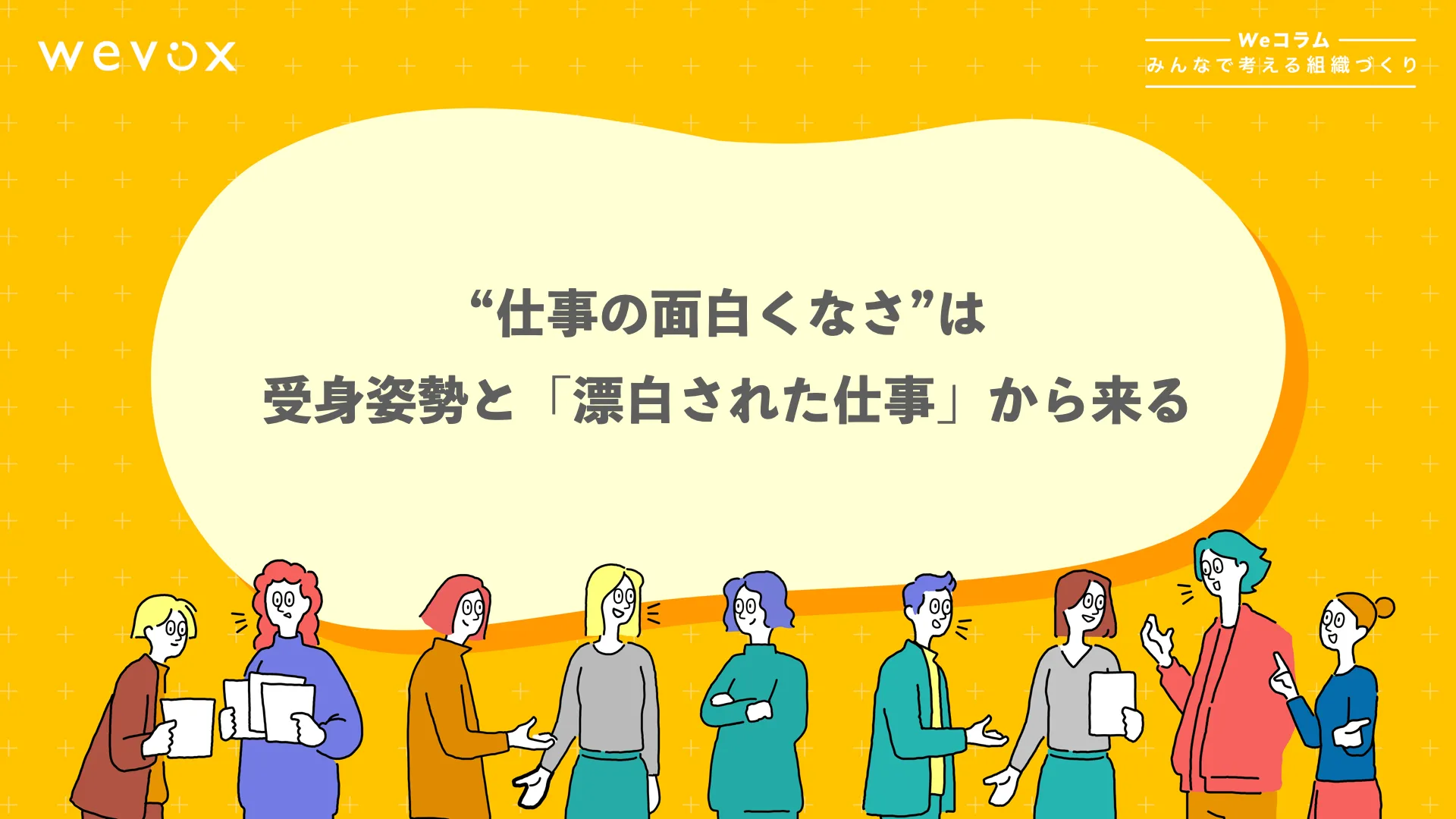
個人の予防・対処法(組織として支援すべきこと)
十分な休息の確保
: 意識的に休憩を取り、休日には仕事から完全に離れてリフレッシュする時間を持つよう促しましょう。質の良い睡眠が心身の回復に不可欠であることを啓発することも重要です。
仕事とプライベートの切り替え
: 趣味や運動など、仕事以外の活動に時間を使い、ストレスを解消する方法を見つけることを奨励しましょう。企業が福利厚生として、リフレッシュを促進するプログラムを提供することも有効です。
専門家への相談の奨励
: 疲れを感じたら、心療内科やカウンセリングなど、専門機関への相談をためらわないよう促しましょう。早期に専門家のサポートを受けることで、症状の悪化を防ぎ、回復への道筋が見えてくることを周知することが大切です。
まとめ:バーンアウトは組織全体の課題として向き合うべき
バーンアウトは、真面目な従業員ほど陥りやすい、心身のエネルギーが枯渇する深刻な状態です。これは個人の問題として片付けられるものではなく、企業の生産性低下や離職率上昇に直結する、組織全体で取り組むべき重要な課題と言えます。
人事・管理職の皆様には、従業員の小さな変化を見逃さず、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下といったSOSサインにいち早く気づき、対応することが求められます。長時間労働の是正、心理的安全性の確保、柔軟な働き方の推進、そして相談しやすい環境の整備など、多角的なアプローチで予防と対策を講じることが、従業員一人ひとりが活き活きと働き続けられる職場環境を築き、企業の持続的な成長を実現する鍵となります。従業員のウェルビーイングを最優先に考え、具体的な行動を起こすことで、より強く、より魅力的な組織を創造できるでしょう。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

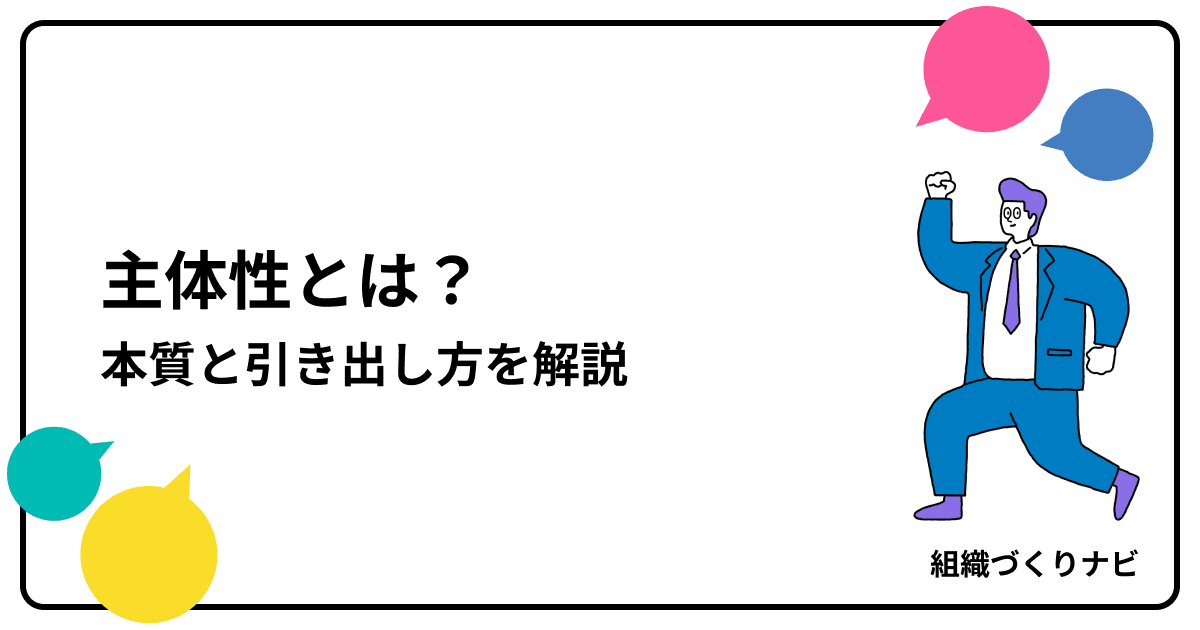
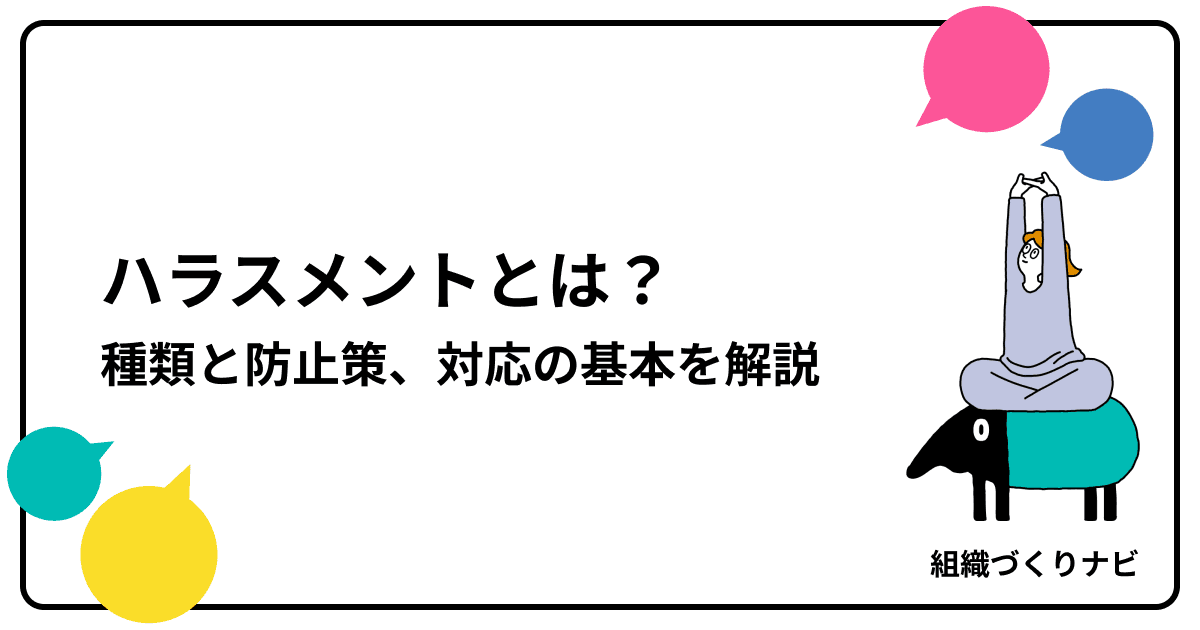


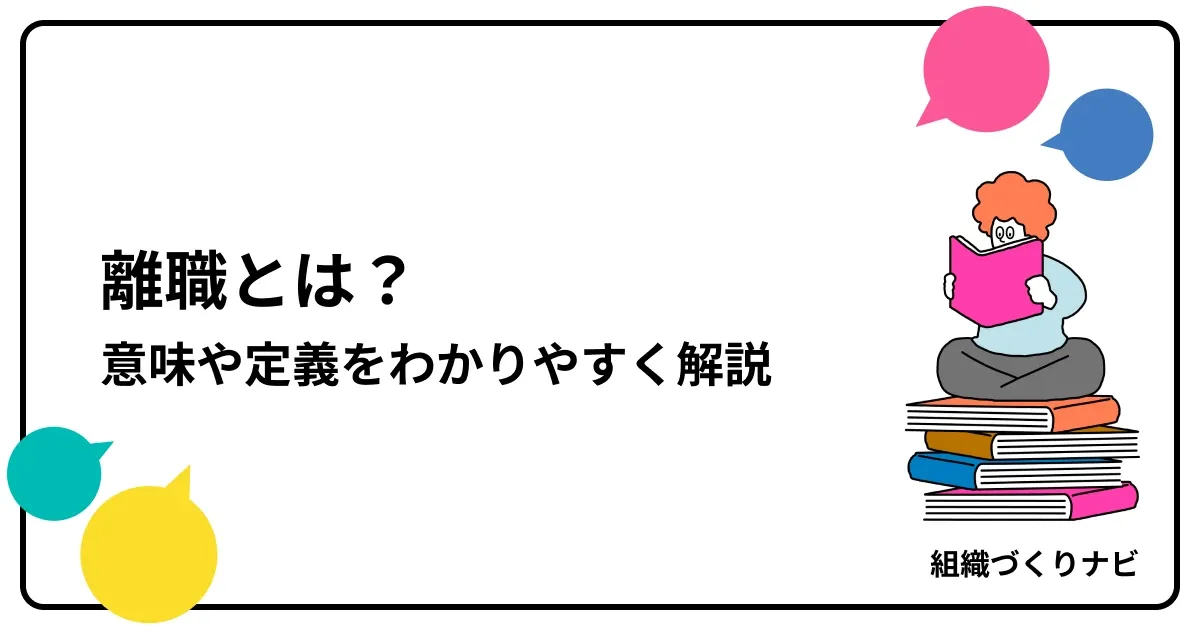




 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


