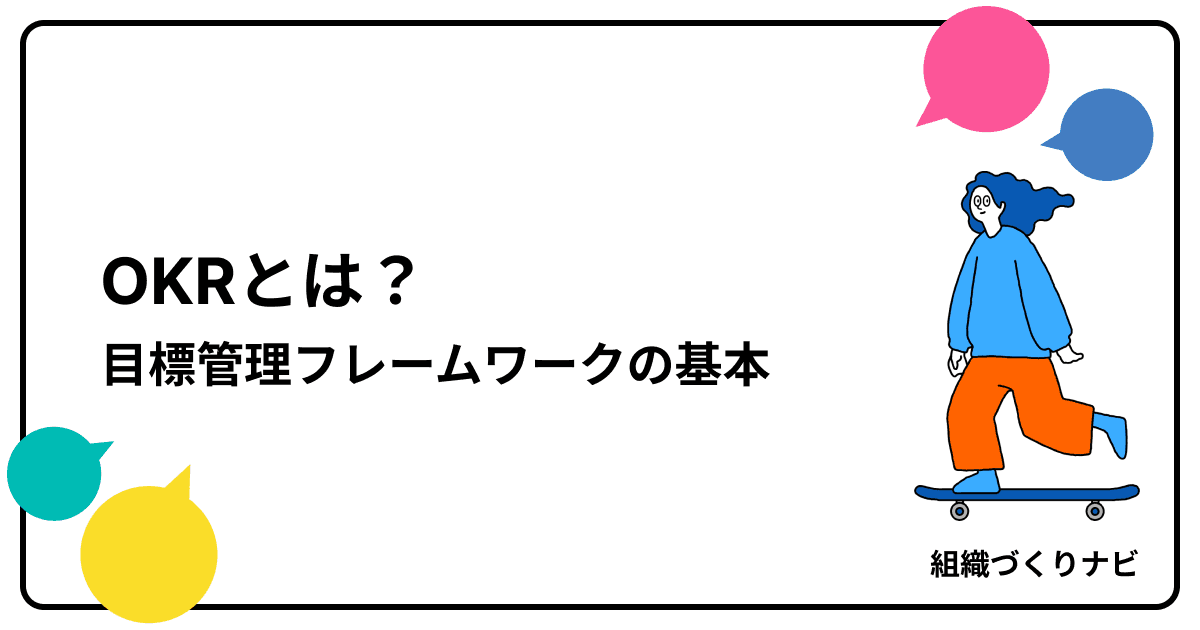
OKRとは?ワクワクする未来を描き成果を出す目標管理フレームワークの基本をわかりやすく解説
OKRとは? GoogleやIntelも導入する目標設定・管理フレームワークの基本を解説。組織の目標を明確にし、チームや個人の力を引き出すOKR(目標と主要な結果)の定義から、具体的な導入方法、成功事例、KPI・SMARTゴールとの違い、デメリットと対策まで網羅。曖昧な目標や連携不足、エンゲージメント低下といった課題を解決し、挑戦的な目標と計測可能な成果指標で組織全体の集中力と透明性を向上。人事・管理職の皆様が持続的成長と競合優位性を確立するためのOKR活用法を、この記事で明確にします。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
OKRとは?基本的な定義と目的
OKR(Objectives and Key Results)は、**「目標(Objective)」と「主要な結果(Key Results)」**という二つの要素からなる目標設定・管理フレームワークです。これは、組織全体の大きな目標を定め、それを達成するための具体的な進捗指標を明確にすることで、全員が同じ方向を向き、高い意欲を持って業務に取り組めるように設計されています。元々はIntel社で開発され、Googleなどの企業で採用されて大きく広まりました。
OKRの主な目的は、組織の戦略的な方向性を明確にし、目標達成への集中力を高めることにあります。あいまいな目標ではなく、**意欲的で挑戦的な目標(Objective)と、その達成度を測る具体的で計測可能な指標(Key Results)**を組み合わせることで、組織内の透明性を高め、チームや個人のコミットメントを引き出し、組織全体の生産性を向上させます。OKRは、単に目標を「設定する」だけでなく、その「達成」に向けた継続的な推進と改善を促す、動的なフレームワークなのです。
OKRの構成要素:ObjectiveとKey Resultsの具体的な解説
OKRは「Objective(目標)」と「Key Results(主要な結果)」という二つの要素で構成されます。これらを正しく理解し、効果的に設定することがOKR成功の鍵となります。
Objective(目標)
Objectiveは、「何を達成したいのか」という、定性的で挑戦的な目標を指します。これは、チームや個人の意欲を高め、インスピレーションを与えるような、少し背伸びをしないと届かないような目標であるべきです。具体的な数字で測れるものではなく、達成したときに「すごい!」「素晴らしい!」と感じられるような、ワクワクする未来の状態を描きます。例えば、「業界で最も信頼される企業になる」「顧客が当社製品を心から愛するようにする」といった抽象的で意欲的な表現が適しています。Objectiveは、組織のビジョンやミッションに沿った、向かうべき「北極星」となるものです。
Key Results(主要な結果)
Key Resultsは、Objectiveの達成度を測るための、具体的で計測可能な指標です。Objectiveが「どこへ向かうか」を示す羅針盤だとすれば、Key Resultsは「どれくらい進んだか」を示す進捗メーターのようなものです。通常、1つのObjectiveに対して2~5個のKey Resultsを設定します。これらのKey Resultsは、達成したかどうかが数字で明確に判断できるものである必要があります。例えば、「顧客満足度を80%以上にする」「製品の月間アクティブユーザー数を20%増加させる」「ソーシャルメディアでのポジティブな言及数を30%増加させる」といった、具体的な数値目標がこれにあたります。Key Resultsは、ただのタスクリストではなく、「結果」に焦点を当てた指標でなければなりません。
良いOKRと悪いOKRの例:
良いOKR例:
Objective: 「顧客が当社製品を心から愛するようにする」
Key Results:
顧客満足度アンケートでスコア80%以上を達成する。
製品の月間アクティブユーザー数を20%増加させる。
ソーシャルメディアでのポジティブな言及数を30%増加させる。
悪いOKR例:
Objective: 「売上を増やす」 (定性的ではない、目標が不明確)
Key Results: 「〇〇プロジェクトを完了する」 (数値で測れないタスクであり、結果ではない)
OKRを導入するメリットと競合との差別化
OKRを導入することで、組織は様々なメリットを享受でき、特に人事や管理職の方々にとっては、チームのパフォーマンス向上や組織風土の改善、ひいては競合優位性の確立に大きく貢献するでしょう。
まず、最大のメリットは**「戦略的なアラインメント(方向性の合致)」です。組織全体の大きな目標が明確になることで、各チームや個人の目標もそこに紐付き、全員が同じ方向を向いて業務に取り組めます。これにより、部署間の連携不足や目標の食い違いが減り、組織全体の力が一つにまとまります。この全社的な目標連携の強化は、競合他社に先駆けて市場の変化に対応し、迅速な意思決定を下す上で決定的な差別化要因**となります。
次に、**「集中と優先順位付け」**が進みます。OKRは通常、挑戦的な目標を設定するため、限られたリソースの中で最も重要なことに集中し、優先順位を明確にする助けとなります。これにより、無駄な作業が減り、生産性が向上します。重要なプロジェクトへの集中的なリソース投入は、競合が追随できないスピードでのイノベーションや市場投入を可能にし、競争力の源泉となります。
さらに、**「透明性と連携」**が促進されます。OKRは基本的に全社に公開されるため、誰が何を目指しているのかが明確になり、相互理解が深まります。これにより、部門間の協力や情報共有が活発になり、組織全体の連携がスムーズになります。オープンなコミュニケーションと連携の文化は、従業員のエンゲージメントを高め、組織全体のレジリエンス(回復力)を強化し、離職率の低下にも繋がるため、これもまた人材面での競合優位性となるでしょう。
最後に、**「社員のエンゲージメント向上」と「成長の加速」**も期待できます。自分の仕事が組織全体の目標にどう貢献しているかが明確になることで、社員は自身の業務に意義を感じやすくなります。また、挑戦的な目標を達成した際の達成感は、次の目標への意欲へとつながります。OKRを通じて得られる従業員の主体性と達成感は、自律的な人材育成を促進し、組織全体の学習能力を高めます。これは、変化の激しい現代において、持続的に成長し続けるための企業文化を築き、長期的な競争力を確保するために不可欠です。
関連する参考記事
喜多井:経営側の観点でいうと、毎週開催される役員会の中で、月に1度のWevoxの結果を確認しながら、いろいろな活動、施策の影響を振り返るようにしています。例えば、2020年は組織体制を大きく変えたこともあり、丁寧にスコアを見ながら振り返る必要がありました。具体的には、OKR評価の導入に加えて、健康経営にも力を入れたり、コロナ禍に伴ってWebで実施するイベントや会議体を増やしたりしたことが挙げられます。そうした施策が社員にどう影響しているのかということをWevoxの結果で確認することで、次の施策に繋げられるようにしました。
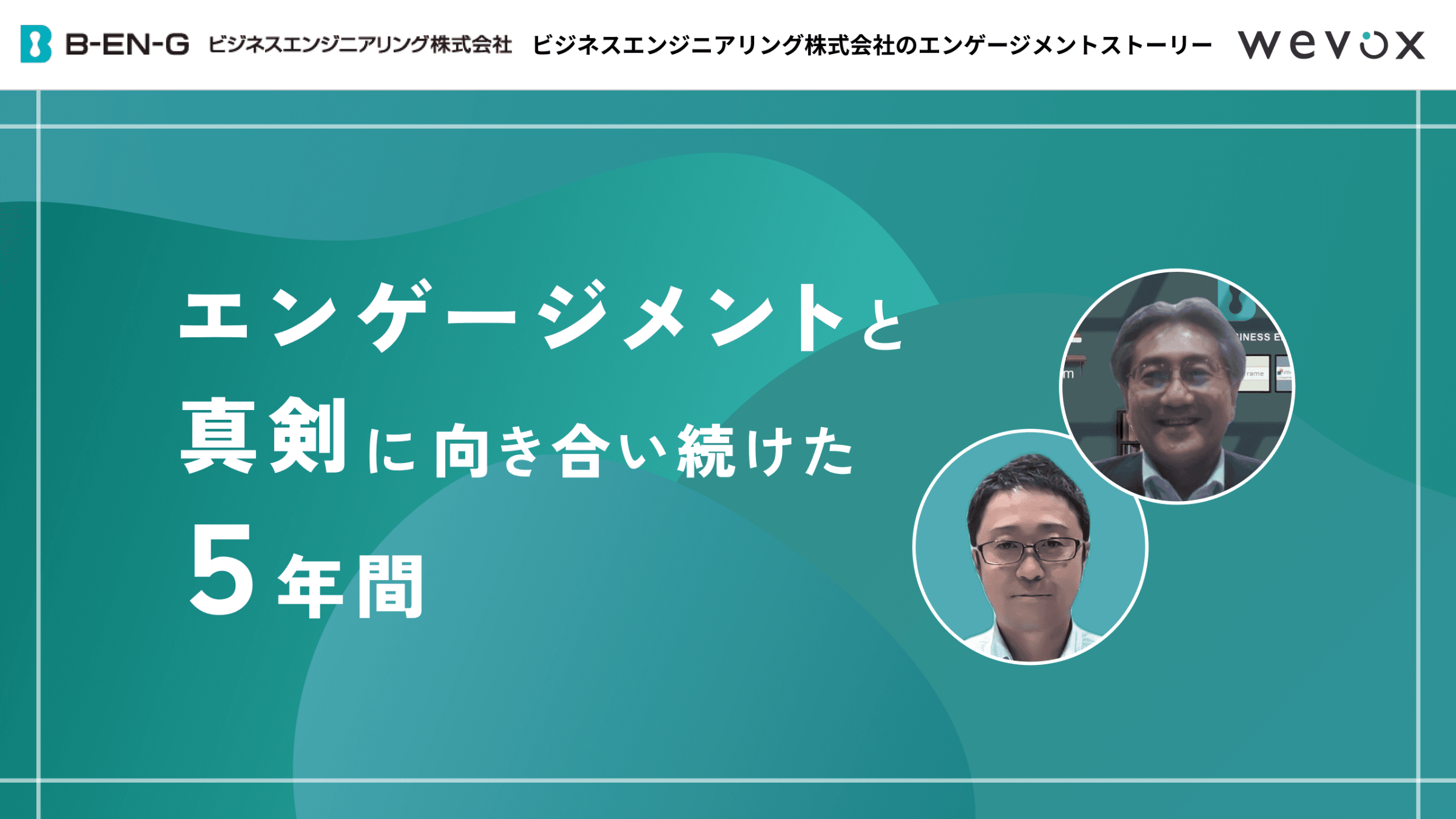
OKRのデメリット・陥りやすい課題と対策
OKRは多くのメリットをもたらしますが、その導入と運用にはいくつかの課題や注意点も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることで、OKRをより効果的に機能させることができます。
まず、**「導入の難しさ」**が挙げられます。OKRは単なる目標設定シートではなく、組織文化やマネジメントスタイルに影響を与えるフレームワークです。初めて導入する際は、適切な目標設定の仕方を学ぶ必要があり、OKRが持つ「挑戦的」な性質を理解し、運用に慣れるまでには時間と労力がかかります。
対策:
経営層からの強いコミットメントと、初期段階での専門家によるサポートや社内トレーナーの育成が不可欠です。まずは少数のチームでパイロット運用を行い、成功体験を積み重ねて全社展開へと広げるアプローチも有効です。
次に、**「パフォーマンス評価との混同」**というリスクがあります。OKRは本来、個人のパフォーマンス評価に直接結びつけるべきではありません。OKRを達成できなかったとしても、そのプロセスから何を学び、どのように改善したかが重要です。しかし、OKRの達成度を直接個人の評価や報酬に結びつけてしまうと、社員が挑戦的な目標を設定することを避け、達成しやすい低い目標を設定してしまう可能性があります。これではOKR本来の「ストレッチゴール」という意図が失われてしまいます。
対策:
OKRは「未来の成長」を促すツール、人事評価は「過去の貢献」を測るツールとして、明確に役割を分離しましょう。OKRはキャリア開発や能力開発の対話の材料とし、評価や報酬は別の指標(例えば、日々の業務遂行度や行動評価など)を基に行うことが重要です。
さらに、Key Resultsが**「単なるタスクリスト化してしまう危険性」**もあります。Key Resultsはあくまで「目標の達成度を測る指標」であり、日々の具体的なタスクそのものではありません。もしKey Resultsが「〇〇を完了する」といったタスクの羅列になってしまうと、OKRは形骸化し、本来の目標達成への集中力を高める効果が薄れてしまいます。
対策:
Key Resultsは「結果(成果)」に焦点を当て、達成時に「何がどう変わるのか」が数字で明確に示せるように設定することを徹底しましょう。設定時には「何をするか」ではなく「何を達成するか」を問い、具体的な行動はKey Results達成に向けた「活動」として別に管理します。
OKRとKPI・SMARTゴールの違い
OKR、KPI、SMARTゴールは、いずれも目標管理や成果測定に関連する概念ですが、それぞれ異なる目的と役割を持っています。これらの違いを理解することは、適切な目標設定と運用を行う上で非常に重要です。
OKR(Objectives and Key Results)は、「何を達成したいか(Objective)」という意欲的で挑戦的な目標と、「どう測定するか(Key Results)」という具体的な成果指標をセットで設定するフレームワークです。OKRは主に「方向性」と「集中」を促し、組織やチームがストレッチゴール(背伸びをした目標)に挑戦することを目的とします。四半期など比較的短いサイクルで設定・評価されることが多く、将来の成長や変革、イノベーションを目指す際に特に有効です。未達成であっても学びがあれば良しとする文化が求められます。
*KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)**は、**日々の業務やプロジェクトの「重要活動指標」
です。これは、事業の健全性や目標達成に向けたプロセスが適切に進んでいるかを測るための指標であり、
「現在のパフォーマンスをどう測定するか」**に焦点を当てます。例えば、Webサイトの「コンバージョン率」や営業の「リード獲得数」、製品の「バグ報告数」などがKPIにあたります。KPIは、定常的な業務の進捗や状態を管理するために用いられ、必ずしも挑戦的な目標ではありません。OKRが「新しい山を登る」ための目標だとすれば、KPIは「今の道を安定して進む」ための指標と言えます。
SMARTゴールは、目標設定の原則を示すものです。目標が**S (Specific:具体的に)、M (Measurable:測定可能に)、A (Achievable:達成可能に)、R (Relevant:関連性があり)、T (Time-bound:期限がある)**であるべきだという考え方です。SMARTゴールは、どのような種類の目標を設定する際にも活用できる汎用的なフレームワークであり、OKRやKPIを設定する際にも、それぞれの目標や指標がSMARTの原則に沿っているかを確認することで、より質の高い目標設定が可能になります。つまり、SMARTゴールはOKRやKPIを設定するための「チェックリスト」や「ガイドライン」として機能する概念だと言えるでしょう。
これら3つの概念は、排他的なものではなく、相互に補完し合う関係にあります。OKRで挑戦的な目標を掲げ、KPIで日々の業務の健全性を確認し、SMARTゴールの原則に沿ってそれらを具体的に設定していくことで、より効果的な目標管理を実現できるでしょう。
OKRの設定方法(具体的なステップ)
OKRを効果的に導入し運用するためには、具体的な設定手順を踏むことが重要です。ここでは、組織全体の目標から個人の目標まで、OKRを設定する際のステップを解説します。
1. 組織全体のOKRを設定する
まず、組織が向かうべき方向を明確にするために、企業全体のOKRを設定します。これは、経営層が数ヶ月から1年程度の期間で「会社として何を達成したいのか」という意欲的なObjectiveと、その達成を測るKey Resultsを決定するプロセスです。このOKRは、すべてのチームや個人のOKRの基盤となるため、明確で分かりやすいものにすることが重要です。この段階で、組織のビジョンやミッションを再確認し、それらに沿った挑戦的な目標を設定しましょう。企業OKRは、全社に共有され、浸透されることで、各部署・個人の行動を方向づける羅針盤となります。
2. チーム・個人のOKRを設定する
企業全体のOKRが設定されたら、次は各チームや個人のOKRを設定します。この際、企業OKRと連携していることが不可欠です。チームや個人は、企業OKRの達成に貢献する形で、自分たちのObjectiveとKey Resultsを設定します。このプロセスは、トップダウンだけでなく、チームや個人が主体的に考え、提案するボトムアップのアプローチも取り入れることで、納得感と当事者意識を高めることができます。上司と部下が対話し、目標の擦り合わせを行う「キャリブレーション」も重要です。この対話を通じて、OKRが単なる指示ではなく、個人の成長と組織貢献を両立させるツールとして機能するように調整します。
3. 定期的な進捗確認(チェックイン)
OKRを設定したら、それで終わりではありません。**定期的に進捗状況を確認する「チェックイン」**を設けましょう。週次や隔週で短いミーティングを行い、Key Resultsの進捗や達成状況、課題などを共有します。このチェックインは、あくまで進捗確認と問題解決のための場であり、個人の成績を評価したり、厳しく問い詰めたりする場ではありません。目標達成に向けたサポートや軌道修正を行い、チーム全体で目標達成を後押しする機会として活用します。マネージャーはコーチングの視点から、メンバーの自律的な問題解決を促す役割が期待されます。
4. OKRの評価と振り返り
OKRサイクル(通常は四半期ごと)の終了時には、設定したOKRの達成度を評価し、振り返りを行います。各Key Resultsの達成度を数値で評価し、Objectiveがどの程度達成できたかを検証します。重要なのは、達成できたかできなかったかだけでなく、なぜ達成できたのか、なぜ達成できなかったのか、そこから何を学んだのかを深く掘り下げることです。この振り返りを通じて得られた教訓は、次のOKRサイクルや組織の成長に活かされます。成功体験は次への自信に、失敗体験は改善点として捉え、組織全体の学習と進化を促進する機会としましょう。
関連する参考記事
2021年4月からDNP価値目標制度(DVO制度)というMBOにOKR的要素を組み入れた目標管理の制度を開始しました。具体的には、価値創造に向けてトップダウン目標だけではなくボトムアップのチーム目標も立て、1on1やチェックイン・チェックアウト(CICO)ミーティングと3点セットでまわしていくことによって、一人ひとりの強みを伸ばすとともにチームの力を最大限に高めていくことを目的としています。ミーティングのやり方については、それぞれのチームや課に裁量を持たせているので、皆さんのヒントになるのではと思います。
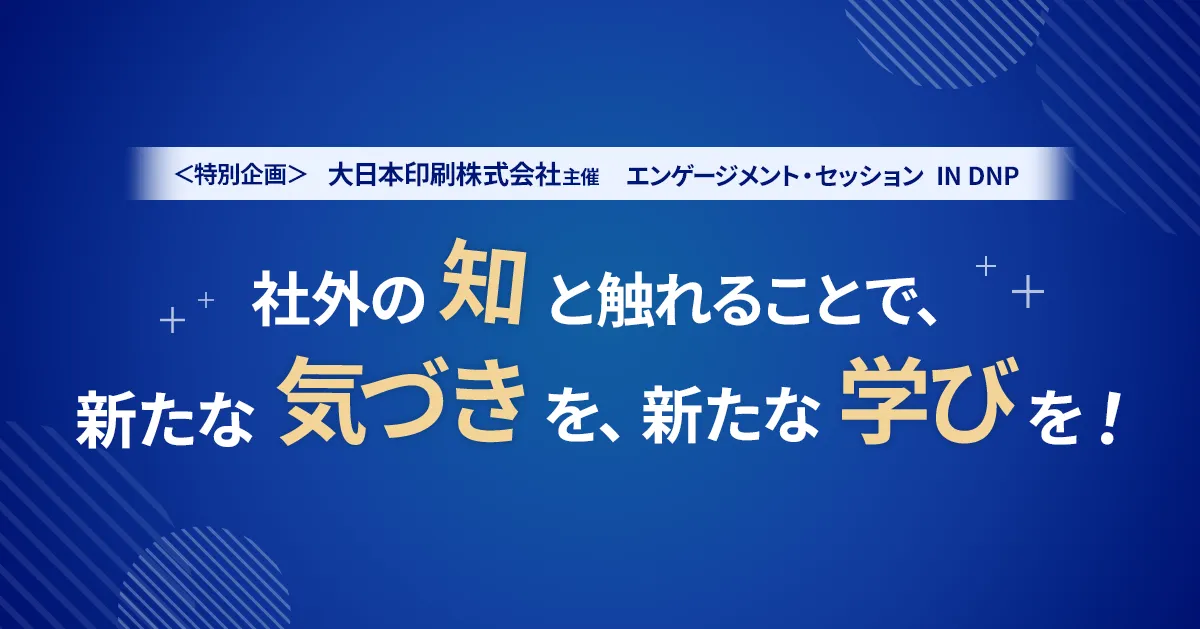
まとめ
この記事では、OKR(Objectives and Key Results)について、その定義、構成要素、導入するメリットとデメリット、KPIやSMARTゴールとの違い、具体的な設定方法、そしてGoogleやIntelといった企業の成功事例を詳しく解説しました。
OKRは、組織の目標を明確にし、従業員一人ひとりの力を最大限に引き出すための強力な目標設定・管理フレームワークです。**挑戦的な「目標(Objective)」と、その達成度を測る具体的な「主要な結果(Key Results)」**を組み合わせることで、組織全体の方向性を一致させ、集中力を高め、透明性を向上させ、最終的には社員のモチベーション向上に繋がります。これにより、変化の激しいビジネス環境において競合他社よりも迅速な意思決定やイノベーションを実現し、持続的な成長を遂げるための強力な差別化要因となるでしょう。
導入には課題も伴いますが、適切な設定手順を踏み、パフォーマンス評価との混同を避け、定期的な進捗確認と振り返りを行うことで、そのデメリットを克服し、大きな成果を生み出すことができます。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

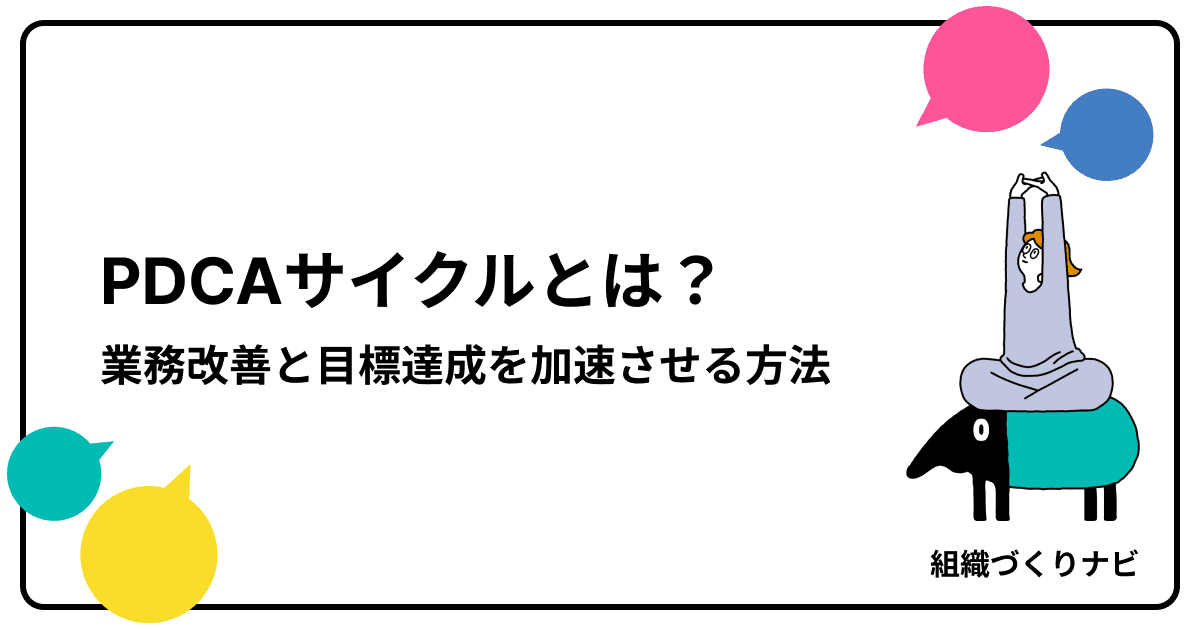
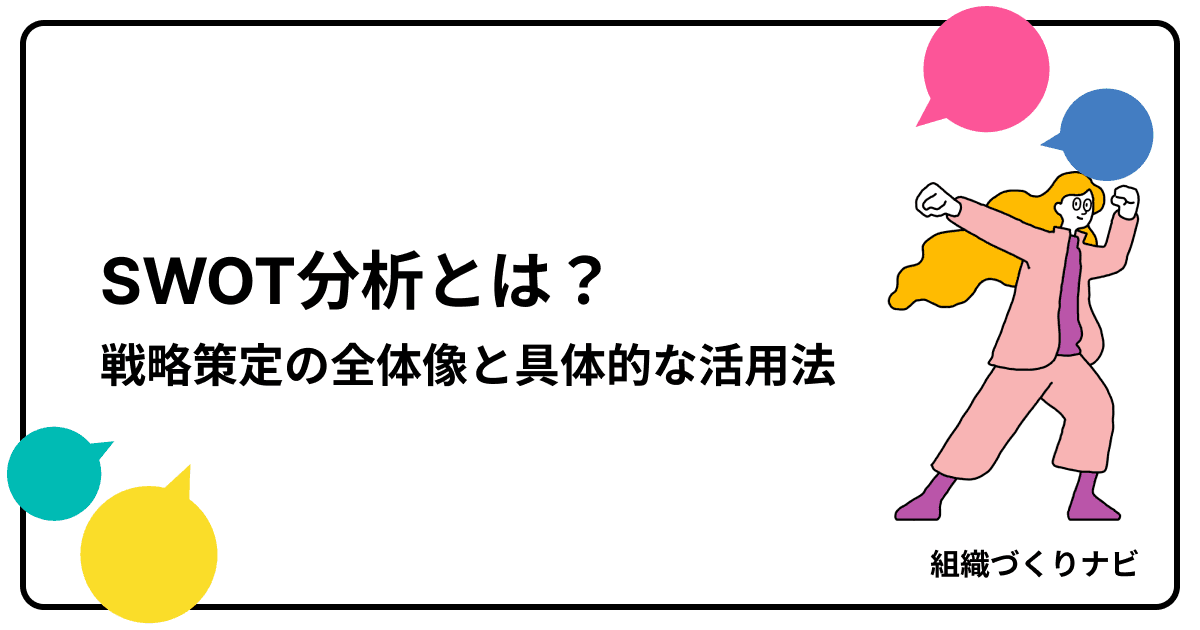
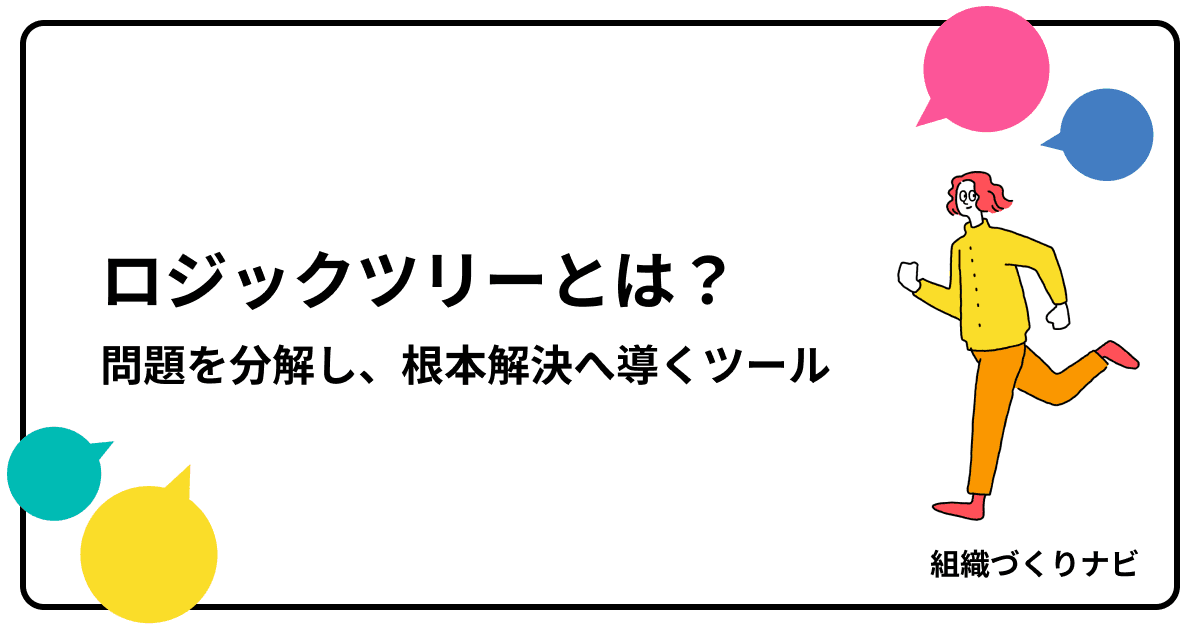
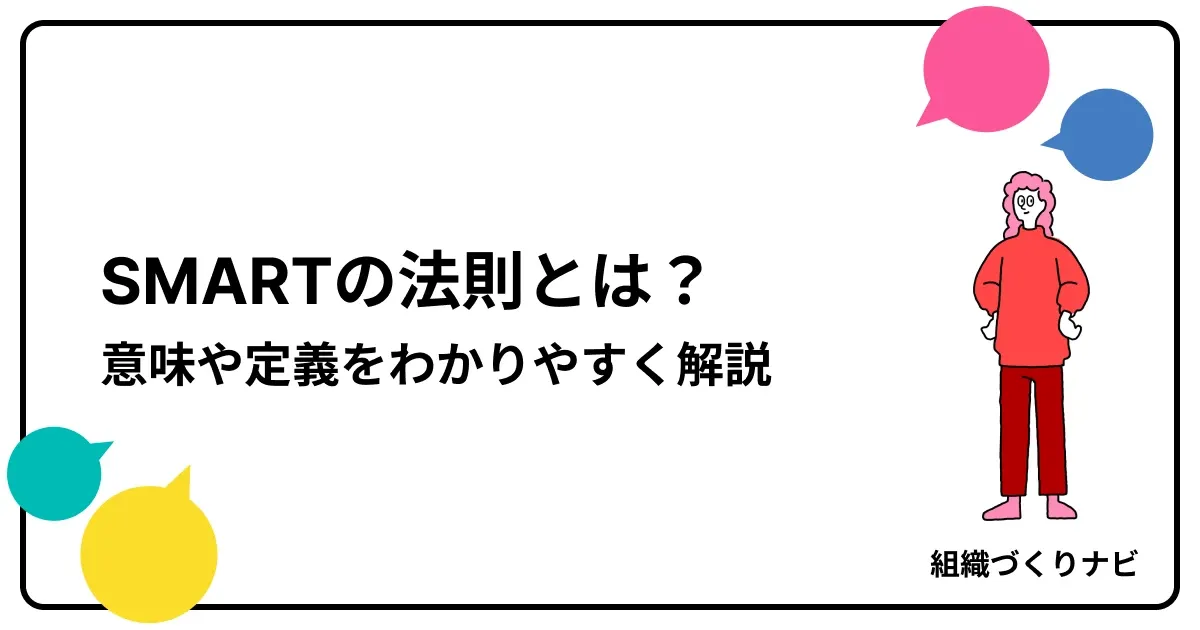
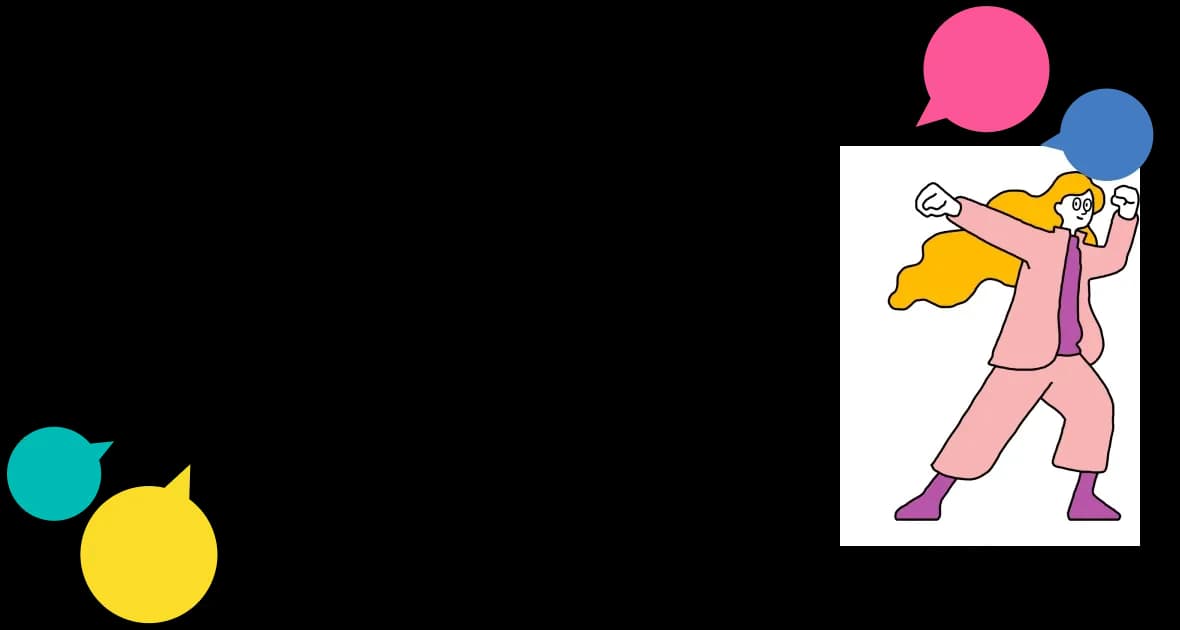




 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


