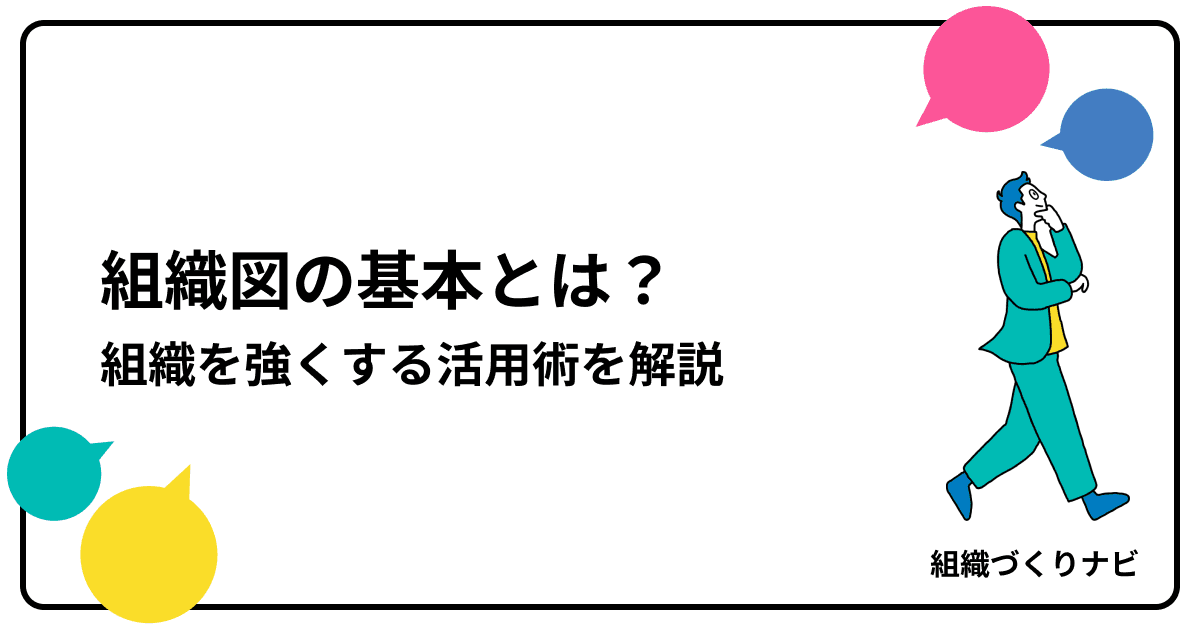
組織を強くする羅針盤「組織図」の基本と活用術
組織図は、人事・管理職にとって組織の力を最大限に引き出し、成長を導く羅針盤です。会社全体の構造、各部署の役割、指揮命令系統を明確にし、従業員の自身の立ち位置理解、モチベーション向上、最適な人材配置、部門間の円滑なコミュニケーションを促進します。階層型・マトリックス型・フラット型などの種類を理解し、WordやExcelで効果的に作成。さらに、定期的な更新・共有、組織変更シミュレーション、人材育成やキャリアパス形成に戦略的に活用することで、組織全体の生産性向上と持続的な成長に繋がります。貴社の組織を強くするための組織図の基本から活用術まで解説します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
組織図の基本から活用まで徹底解説!組織を強くする羅針盤
導入
「組織図」と聞いて、あなたはどのようなイメージを持つでしょうか?単なる会社の構造を示す図、と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、組織図は企業が成長し、変化する現代において、組織の力を最大限に引き出すための重要なツールです。特に人事や管理職の方々にとって、組織図は従業員の配置、役割分担、意思決定の円滑化、そして組織全体の生産性向上に直結する羅針盤となります。
この記事では、組織図の基本的な定義から、その主要なメリット、さまざまな種類、効果的な作成方法、そして最大限に活用するための戦略的ポイントまで、人事・管理職の皆様が組織をより強く、より効率的に運営するためのヒントを徹底的に解説します。貴社の組織を成功に導くために、ぜひこの記事をご活用ください。
組織図とは?
組織図とは、会社や団体の構造を視覚的に表現した図のことです。具体的には、誰が誰の上司で、どの部署がどのような役割を担い、互いにどのように連携しているのか、といった関係性を一目でわかるように示します。まるで会社の全体像を上空から見下ろすようなイメージです。
この図があることで、新入社員は自分の立ち位置や会社の全体像を素早く理解でき、既存の社員は部署間の連携や指示系統を確認できます。また、経営層や管理職にとっては、現在の組織が抱える課題を発見し、より効果的な人員配置や組織体制を検討するための重要な情報源となります。組織図は、組織が円滑に機能するための骨格とも言えるでしょう。
組織を強くする羅針盤!人事・管理職が知るべき組織図のメリット
組織図は、ただ会社の形を示すだけでなく、人事・管理職の皆様が組織を強力に推進するための、多岐にわたる重要なメリットをもたらします。
1. 組織構造と機能の明確化による効率向上
組織図は、会社全体の構造や各部門の配置、それぞれの機能と役割を視覚的に明確にします。これにより、誰がどの部署に所属し、どのような責任と権限を持っているのかが一目で把握できます。例えば、製品開発、営業、顧客サポートといった各部門が、どのような役割を担い、お互いにどのように貢献し合っているのかが分かり、業務の重複を防ぎ、責任の所在をはっきりさせることが可能です。これにより、組織全体の生産性が向上し、意思決定のスピードも加速します。
2. 個人の立ち位置と役割の理解促進とエンゲージメント向上
社員一人ひとりが、組織図を見ることで自身の部署や役職が会社全体の中でどのような位置にあり、どのような役割を果たすのかを理解できます。自分の業務が全体のどの部分を担っているのかを把握することは、仕事へのモチベーション向上や主体性の醸成に繋がります。特に、中小企業においては、社員が自身の働く会社全体を理解し、その一員であるという帰属意識を高める効果が期待できます。これは、社員エンゲージメントの向上や離職率の低下にも繋がる重要な要素です。
3. 人材配置・採用計画の最適化
組織図は、現在の社員配置状況を明確にし、将来的な人材戦略を立てる上での重要な基盤となります。どの部署に人員が不足しているのか、あるいは過剰なのかを可視化することで、最適な人材配置を検討したり、採用計画を効率的に立案したりすることが可能になります。また、新規事業立ち上げ時など、新たな役割や部署を設ける際のシミュレーションにも役立ち、戦略的な組織編成をサポートします。
4. スムーズなコミュニケーションと連携の促進
組織図は、上司や部下、同僚との関係性を明確にするため、円滑なコミュニケーションや指示・報告系統の確立に役立ちます。また、各部署や個人が互いにどのように連携し、影響し合っているのかを示すことで、部門間のサイロ化(孤立化)を防ぎ、より効果的な協業体制を築くことができます。例えば、営業部門が顧客から得た情報を開発部門に伝え、それが新製品の開発に活かされるといった、部門間の協力関係や情報の流れを理解するのに不可欠です。
5. 評価・育成制度の公平性と透明性の確保
各役職の責任と権限が組織図を通じて明確になることで、評価基準の設定や育成計画の策定がしやすくなります。職務記述書(ジョブディスクリプション)と連携させることで、社員は自身の目標とキャリアパスを具体的にイメージしやすくなり、人事評価の公平性と透明性も高まります。これは、社員の納得感を高め、成長意欲を引き出す上で非常に有効です。
組織図の種類と特徴
組織図には、その組織の目的や規模、文化に応じていくつかの異なる種類があります。それぞれの特徴を理解することで、自社に最適な形を選ぶことができます。
1. 階層型組織図
最も一般的で、伝統的な組織の形です。トップに社長などの最高責任者がいて、その下に部長、課長、一般社員といった形で段階的に権限が委譲されていくピラミッド型の構造をしています。指揮命令系統が非常に明確で、誰が誰に指示を出し、誰に報告するのかが分かりやすいのが大きな特徴です。特に大規模な組織や、業務の標準化が求められる場合に適していますが、意思決定がトップに集中しやすく、変化への対応が遅れるデメリットもあります。
2. マトリックス型組織図
プロジェクト型の業務が多い企業や、複数の事業領域を持つ企業で採用されることがあります。これは、「職能別」と「事業・プロジェクト別」の2つの軸を組み合わせて構成されるのが特徴です。例えば、営業部という職能部門に所属しながら、同時にAプロジェクトにも参加するといった形です。メリットは、専門知識を持つ人材を複数のプロジェクトで柔軟に活用できる点や、部門横断的な連携を促進できる点です。一方、指揮命令系統が二重になるため、混乱が生じやすいというデメリットもあります。
3. フラット型組織図
階層が少なく、経営層と現場社員の間の距離が非常に近い組織の形です。権限が下位の社員にも比較的多く委譲される傾向にあり、社員一人ひとりの裁量が大きく、自律性が重視されます。スタートアップ企業や少人数の組織、変化の速いIT業界などで採用されることが多いです。意思決定が迅速に行え、社員の主体性や創造性を引き出しやすいメリットがありますが、管理職の役割が不明確になったり、社員間の連携が希薄になるリスクもあります。
組織図の作成方法
組織図を効果的に作成するには、事前の準備と手順をしっかりと踏むことが重要です。
1. 作成前の準備
組織図を作成する前に、「なぜ組織図を作るのか」という目的を明確にしましょう。新入社員のオンボーディングのためか、業務改善のためか、はたまた組織再編の検討のためか。目的がはっきりしていれば、どのような情報を盛り込み、どのような形式にするべきかが決まります。次に、組織に関する正確な情報を収集します。具体的には、部署名、役職名、氏名、各部署の主要な役割、そしてそれぞれの報告・指揮系統などをリストアップします。これらの情報が最新かつ正確であることが、有効な組織図作成の土台となります。
2. 作成手順
準備が整ったら、以下の手順で作成を進めます。
組織構造の決定
: まず、自社がどのような組織構造(階層型、マトリックス型など)を採用するか、あるいは採用しているかを明確にします。
部署・役職の洗い出し
: 会社のすべての部署と役職を漏れなくリストアップします。
担当者の配置
: 各役職に現在担当している社員の氏名を配置します。空白の役職があれば、それも明記しましょう。
関係性の線引き
: 各部署や役職、個人間の指揮命令系統や報告ルートを線で結び、関係性を明確にします。誰が誰の直属の上司で、誰が誰の部下なのかを視覚的に表現します。
これらの手順を一つずつ丁寧に行うことで、正確で分かりやすい組織図が完成します。
3. ツール別作成ガイド
組織図を作成するためのツールはいくつかありますが、ここでは身近なWordとExcelを使った方法をご紹介します。
Wordで作成する
Microsoft Wordには、SmartArt機能が搭載されており、これを使うと効率的に組織図を作成できます。「挿入」タブから「SmartArt」を選択し、「階層構造」の中から組織図に合ったレイアウトを選びます。あとはテキストボックスに部署名や氏名を入力し、必要に応じて図形の追加や削除、配置の変更を行うだけで、プロフェッショナルな組織図が作成できます。直感的な操作で、見栄えの良い図を作成できるのが特徴です。
Excelで作成する
Microsoft Excelも組織図作成に適しています。Wordと同様にSmartArt機能が利用できますし、セルを使って情報を整理し、罫線や図形を組み合わせて手動で作成することも可能です。また、Excelのテンプレート機能を利用すれば、あらかじめデザインされた組織図のひな形をダウンロードして、そこに情報を入力するだけで簡単に作成できます。データ入力や管理が得意な方は、Excelでの作成がスムーズに進むでしょう。
組織を成長させる!人事・管理職のための戦略的組織図活用術
組織図は、一度作成したら終わりではありません。組織が常に変化し続けるように、組織図もまた「生きたツール」として活用し、戦略的に組織成長に繋げることが重要です。
1. 定期的な更新と情報共有の徹底
組織図は、人事異動、部署の新設・廃止、組織再編など、組織に変化があった際に必ず更新するようにしましょう。情報が古いままだと、その役割やメリットが失われてしまいます。少なくとも半年に一度、または年に一度は全体を見直し、必要に応じて修正を加えるサイクルを設けることをお勧めします。常に最新の状態を保つことで、組織図は真に役立つ情報源として機能します。
また、作成した組織図は一部の人だけでなく、全社員がいつでもアクセスできるように共有し、その存在を浸透させることが大切です。社内ポータルサイトに掲載したり、新入社員研修で活用したりするなど、意識的に共有の機会を作りましょう。社員が自分の立ち位置や会社の全体像を常に確認できる環境を整えることで、理解が深まり、組織図が持つ本来の価値が最大限に発揮されます。
2. 組織変更シミュレーションと課題発見に活用する
組織図は、現在の組織構造を示すだけでなく、将来の組織変更をシミュレーションするための強力なツールとなります。例えば、M&Aや事業再編、新規プロジェクト立ち上げの際に、組織図上で仮想的な変更を行い、その影響を事前に評価できます。また、組織図を俯瞰することで、特定の部署への負担集中、権限の偏り、情報のボトルネックなど、潜在的な組織課題を発見しやすくなります。これにより、問題が顕在化する前に、先手を打って解決策を検討することが可能です。
3. 目標管理と部門横断プロジェクトを活性化させる
各部署や個人の目標を、組織図上の位置づけや役割と連携させることで、組織全体の目標達成に向けた一体感を醸成できます。組織図で示された部署間の連携ルートを活用し、部門横断的なプロジェクトチームを編成したり、共同目標を設定したりすることで、これまで以上に活発なコミュニケーションと協働が生まれます。組織図をコミュニケーションの起点として活用し、部署間の壁を取り払う意識を持つことが重要です。
4. 人材育成・キャリアパス形成の道しるべとする
組織図は、社員が自身のキャリアパスを描く上での有効な道しるべとなり得ます。現在の役職からどのようなステップアップが可能なのか、どの部署でどのような経験を積むことでスキルアップできるのかを組織図を通じて示すことで、社員の成長意欲を刺激し、具体的な育成計画の策定に役立ちます。人事・管理職の皆様は、組織図を基にキャリア面談を行うことで、社員のエンゲージメントと定着率の向上に貢献できます。
まとめ
この記事では、人事や管理職の皆様に向けて、組織図の基本から、組織を強くするための戦略的な活用方法までを解説しました。組織図は単なる構造を示す図ではなく、組織の全体像を可視化し、各社員の役割を明確にし、部門間の連携を促進する、極めて重要な経営ツールであり、組織を成長させる羅針盤です。
正しく作成し、定期的に更新し、そして何よりも全社員が活用できる「生きた情報」として共有することで、組織全体のコミュニケーションが円滑になり、意思決定が迅速化し、結果として生産性の向上と組織の継続的な成長に繋がるのです。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

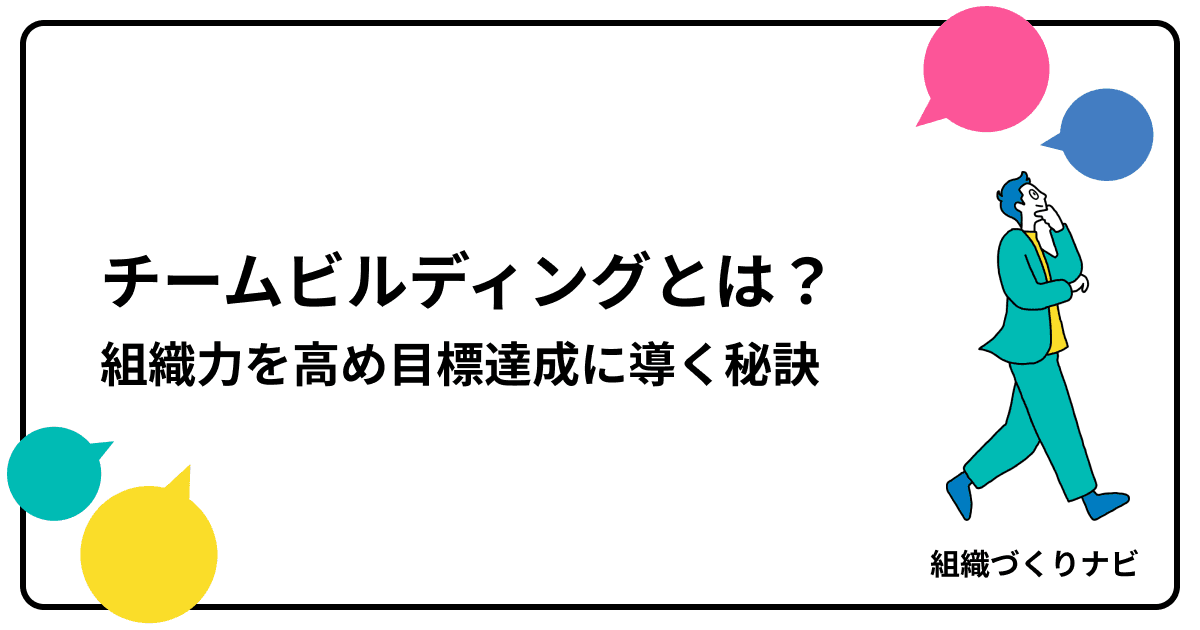



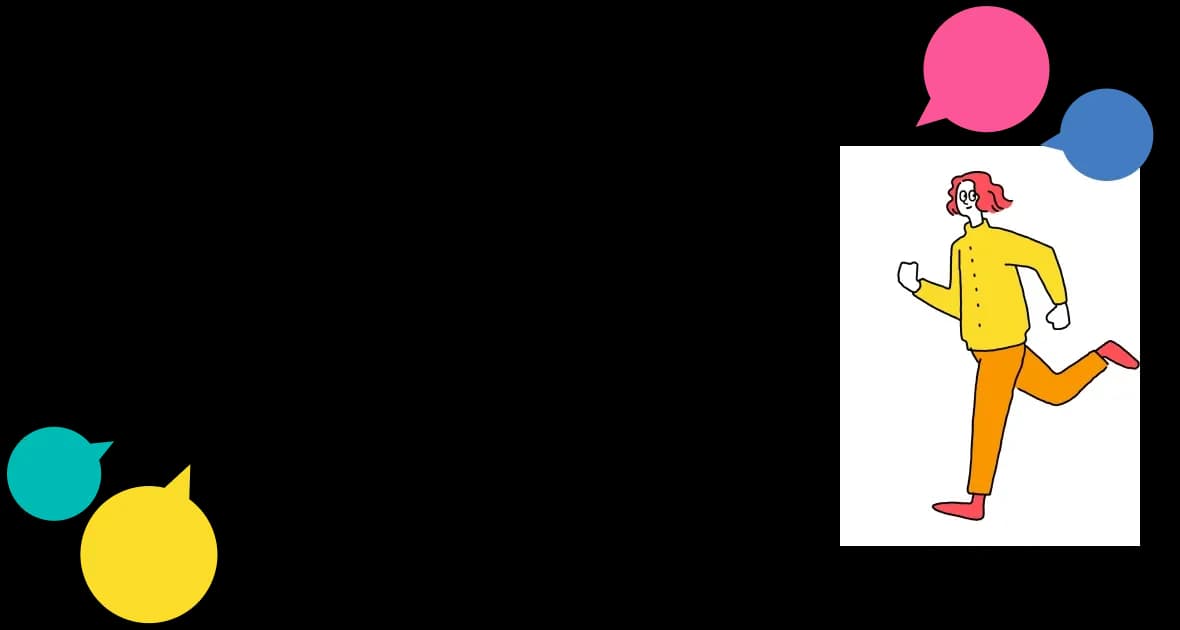
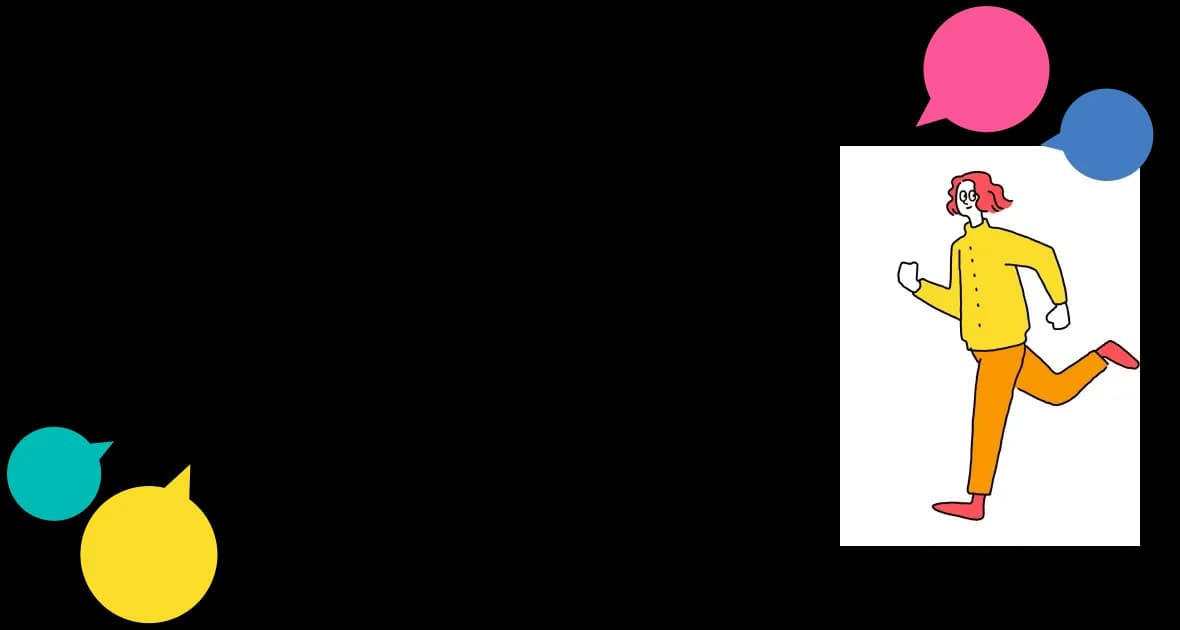



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


