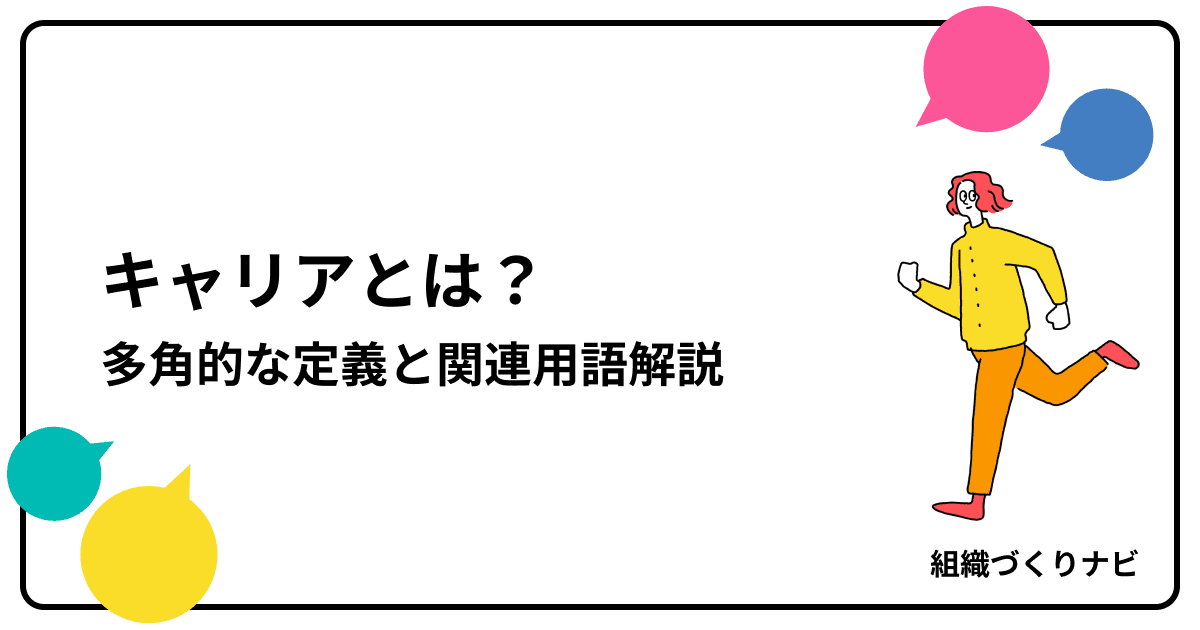
「キャリア」の基礎知識|多角的な定義と関連用語解説
「キャリア」は単なる職務経歴ではなく、人生全体の道のりや自己実現の歩みを指す多面的な概念です。人事・管理職の皆様が社員一人ひとりの成長を支援し、組織全体の力を高めるには、この「キャリア」の本質を理解し、多角的な視点を持つことが不可欠です。 本記事では、キャリアアップ、キャリアプラン、キャリアデザイン、キャリアパスといった基本用語から、個人の価値観を重視するキャリアアンカー理論、予期せぬチャンスを活かすプランド・ハプンスタンス理論、変化に適応するプロティアン・キャリアといった現代理論までを分かりやすく解説。社員の自己理解を促し、仕事だけでなく育児や介護、学習、趣味を含む「ライフキャリア」全体を支援することの重要性を説きます。 社員の豊かなライフキャリア支援は、エンゲージメント向上、離職率低下、多様な人材確保、生産性向上に直結します。変化の激しい時代に、社員が自律的に未来を切り拓き、充実したキャリアを築けるよう導くための実践的な視点とヒントを提供します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
「キャリア」の本質とは?人事・管理職が知るべき多角的な定義
狭い意味で捉えられがちな「キャリア」ですが、その本質は「人生の道のり」や「歩む道そのもの」といった広範な概念を含んでいます。私たちは人生の中で様々な選択をし、経験を積み重ねていきますが、その全てが自身のキャリアを形成する要素となります。仕事上の役割はもちろん、家族との関係、地域活動、趣味、学習など、人生のあらゆる側面が相互に影響し合い、個人の成長を促す道のりこそがキャリアなのです。
現代社会において、「キャリア」の概念は公的機関によっても定義され、その重要性が認識されています。例えば、厚生労働省では、「キャリア」を「人が生涯にわたって継続的に遂行するさまざまな役割の連鎖及びその過程での自己実現の連鎖」と定義しています。ここには、単に職業活動だけでなく、家庭、地域、学習といった多岐にわたる役割が含まれており、それらが人生全体で相互に影響し合いながら、個人の成長や自己実現に繋がるという考え方が示されています。
社員のキャリアを考える際には、仕事だけでなく、彼らの人生全体にわたる多様な役割と経験を尊重する多面的な視点を持つことが、より本質的な支援へと繋がります。この公的な定義を理解することで、社員の多様なライフイベントを考慮したキャリア支援の重要性を再認識し、より戦略的な人材育成や制度設計に役立てることができるでしょう。
「キャリア」関連用語の基本
「キャリア」という言葉の周辺には、多くの関連用語が存在します。これらの言葉を正しく理解することは、社員とのキャリア面談や育成計画を立てる上で非常に重要です。
キャリアアップ
「キャリアアップ」とは、専門性やスキル、経験を高め、自身の市場価値を向上させることを指します。具体的には、より上位の役職に就くことや、異なる部署で新たなスキルを身につけること、あるいは資格取得や専門分野の学習を通じて能力を高めることなどが含まれます。単に給与が上がるだけでなく、職務内容の質を高め、自身の成長を実感できる状態を目指します。
社員のキャリアアップを支援するために、適切な研修機会の提供、ジョブローテーションによる多様な経験の機会、メンター制度の導入など、具体的な育成施策を検討しましょう。社員の「成長したい」という意欲に応えることで、エンゲージメントの向上にも繋がります。
キャリアプラン
「キャリアプラン」とは、自身の将来の目標や理想像を設定し、その目標達成に向けた具体的な行動計画を立てることです。どのようなスキルを身につけ、どのような経験を積み、どのような役割を担いたいのか、といった中長期的な見通しを立てます。この計画は、個人の能力開発だけでなく、ワークライフバランスや人生設計全体を見据えたものとなります。
社員が自身のキャリアプランを明確に描けるよう、定期的な1on1面談を通じて目標設定をサポートし、その実現に向けた道筋を一緒に考えることが重要です。彼らの「will(やりたいこと)」を深く掘り下げ、現在の「can(できること)」を活かし、組織として「must(すべきこと)」とどう接続できるかを共に探る姿勢が求められます。
キャリアデザイン
「キャリアデザイン」は、自身の「キャリアプラン」を能動的に描き、それを実現するために自ら選択し、行動していくプロセス全体を指します。単に計画を立てるだけでなく、自分の価値観や興味、強みなどを深く理解し、変化する環境に適応しながら、自律的にキャリアを築いていくという考え方です。一度立てたプランに固執するのではなく、偶発的な出来事もキャリアの糧として取り入れながら、柔軟に修正していく視点も含まれます。
社員が主体的にキャリアデザインに取り組めるよう、自己分析の機会や多様なロールモデルとの接点を提供し、自律的な成長を促す環境を整えることが求められます。内省を深める研修やキャリアカウンセリングの活用も有効です。
キャリアパス
「キャリアパス」とは、組織内で特定の役割や職位に到達するために必要な、職務の経験やスキルの順序立てられた道のりを指します。これは、企業側が社員に提示する、昇進や昇格、異動などの具体的なルートです。社員が自身の将来像を描きやすくし、目標達成に向けたモチベーションを高める役割があります。明確なキャリアパスを示すことで、社員は「次に何をすべきか」を理解し、自身の能力開発に計画的に取り組むことができます。
組織の戦略と個人の成長を両立させるために、透明性のあるキャリアパスを設計し、社員がそれを活用できるよう説明とサポートを行うことが重要です。定期的な見直しと、必要に応じた柔軟なパスの提示も、現代の多様な働き方には不可欠です。
現代のキャリア理論とその実践的応用
現代社会の急速な変化に対応するためには、従来の直線的なキャリア観だけでなく、多様なキャリア理論を理解し、人事・マネジメントに活かすことが重要です。
キャリアアンカー理論
「キャリアアンカー理論」は、人が仕事を選ぶ上で、譲れない価値観や欲求(アンカー=錨)が存在するという考え方です。例えば、「専門能力」「管理能力」「自律・独立」「安定」「奉仕」「純粋な挑戦」「ライフスタイル」「起業家精神」などが挙げられます。アメリカの心理学者エドガー・ヘンリー・シャインが提唱した理論です。
プランド・ハプンスタンス理論(計画された偶発性理論)
「プランド・ハプンスタンス理論」は、キャリアの8割が予期せぬ偶発的な出来事によって形成されるという考え方です。スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツによって提唱されました。重要なのは、その偶発性を単なる幸運として待つのではなく、自ら積極的に行動し、チャンスを引き寄せる準備をすることだと説きます。具体的には、「好奇心」「持続性」「柔軟性」「楽観性」「リスクテイク」という5つの行動特性が重要とされます。
社員が偶発的な機会を恐れず、むしろ積極的に捉えられるよう、新しい挑戦を奨励し、失敗を許容する文化を醸成することが求められます。部署横断的なプロジェクトや社外交流、越境学習の機会を提供し、「やってみよう」という行動を後押しすることで、予期せぬイノベーションや個人の成長が促される可能性があります。
プロティアン・キャリア
「プロティアン・キャリア」とは、ギリシャ神話の変幻自在な神「プロテウス」に由来し、環境の変化に合わせて自律的に形を変えながらキャリアを築いていくという考え方です。アメリカの心理学者ダグラス・T・ホールが提唱しました。組織に依存せず、自身の価値観や能力に基づいてキャリアを再定義し、社内外を問わず変化していくことを重視します。この理論では、「学習」と「適応能力」が不可欠とされます。
社員が常に学び続け、変化に対応できるスキルを身につけられるよう、多様な学習機会の提供や、部署横断的なプロジェクトへの参加、リスキリング支援を促すことが重要です。社員の「キャリア自律」を支援する姿勢は、組織全体の適応力を高め、持続的な成長に繋がるだけでなく、多様な働き方を推進する上でも不可欠な要素となります。
自己理解が拓くキャリアの可能性:社員の成長を支援する視点
キャリアを自律的に形成していく上で、最も基本となるのが「自己理解」です。自分の「価値観」「興味」「強み」「弱み」「目標」などを深く理解していなければ、どのような道を歩みたいのか、どのような役割が自分に合っているのかを明確にすることはできません。自己理解が深まることで、自分にとって何が大切なのか、どんな仕事にやりがいを感じるのかが明確になり、ブレないキャリアの軸が確立されます。
社員が自己理解を深めるプロセスを支援することは、個人の充実だけでなく、組織のパフォーマンス向上にも直結する不可欠な要素です。
定期的な1on1ミーティング
: 傾聴と問いかけを通じて、社員の内省を促しましょう。「どんな時にやりがいを感じるか」「今後どんな自分になりたいか」といった質問が有効です。
自己分析ツールや研修の活用
: 強みや価値観を客観的に把握できるアセスメントツールや、自己理解を深めるキャリア研修を推奨しましょう。
フィードバックの提供
: 社員の良い点や改善点を具体的に伝え、自己認識を深める手助けをしてください。
社員が自身の「will(やりたいこと)」「can(できること)」「must(すべきこと)」を言語化できるようサポートすることで、彼らは自身の成長を実感し、組織への貢献意欲も高まるでしょう。
仕事だけではない「ライフキャリア」の支援が組織を変える
「キャリア」を考える際、私たちはどうしても「仕事」に限定しがちですが、本来は人生全体を包括する概念です。アメリカのキャリア研究者ドナルド・E・スーパーが提唱した「ライフキャリアレインボー」の概念のように、私たちは人生の様々な時期に「働く人」「学ぶ人」「家庭人」「市民」「余暇を楽しむ人」といった複数の役割を担っています。これらの役割は、人生の段階や個人の状況によって重要度が変化し、互いに影響し合いながら、私たちの生き方そのもの、つまり「ライフキャリア」を形成しています。
社員のキャリアを考える上で、彼らの仕事以外の側面にも目を向ける必要があります。育児、介護、病気、学習、ボランティア、趣味といった経済活動外のキャリアも、個人の成長や幸福感に大きく寄与します。これらの多様な役割を尊重し、柔軟な働き方や支援制度を整えることは、組織に多くのメリットをもたらします。
エンゲージメントの向上
: ライフキャリア全体を支援することで、社員は会社が自分を大切にしていると感じ、組織への忠誠心が高まります。
離職率の低下
: ライフイベントに合わせた支援があることで、社員は安心して長く働き続けることができます。
多様な人材の確保
: 柔軟な働き方は、多様な背景を持つ人材にとって魅力的な職場環境となり、採用競争力を高めます。
生産性の向上
: 仕事とプライベートのバランスが取れることで、社員は心身ともに健康を保ち、集中力や創造性が向上します。
多様なライフイベントを考慮した柔軟な働き方(リモートワーク、フレックスタイムなど)や、育児・介護支援制度、リフレッシュ休暇、キャリアカウンセリングなどを整えることで、社員は仕事とプライベートのバランスを取りながら、より豊かで充実したライフキャリアを築くことができ、結果として組織の持続的な成長に貢献するでしょう。
語源から深く理解する「キャリア」の背景
「キャリア(career)」という言葉のルーツをたどると、その深みがより理解できます。この言葉は、ラテン語の「carraria(荷馬車の通り道)」に由来し、古フランス語の「carriere(競技場、道)」を経て、現在の英語「career」となりました。つまり、元々は「進んでいく道筋」や「競争する場」といった意味合いが強かったのです。中世ヨーロッパでは、人生を競走や馬車の道のりに例えることがあり、目標に向かって進む過程や、そこでの経験そのものを指していました。
この語源からも、「キャリア」が単なる結果としての「職務経歴」ではなく、「能動的に歩み、経験を積み重ねていく道のり」であるという本質が見えてきます。
社員のキャリアを考える際には、彼らがどのような「道を歩んできたか」、そして「これからどのような道を歩んでいきたいか」という、過去から未来へと続く「道のり」としての視点で対話することが、深い理解に繋がるでしょう。単なる現在地だけでなく、そのプロセス全体に目を向けることで、社員の潜在能力や成長の可能性をより深く探ることができます。
まとめ:「キャリア」の未来
「キャリア」という言葉は、単なる職務経歴や仕事の道のりを超え、個人の人生そのものの歩みと成長を意味する多面的な概念です。その語源や公的な定義、現代の理論を理解することは、人事・管理職の皆様が社員一人ひとりの「生き方」を尊重し、その潜在能力を最大限に引き出すための重要な視点となります。
社員の自己理解を促し、キャリアアップ、キャリアプラン、キャリアデザイン、キャリアパスといった概念を活用しながら、多様なキャリア観を支援することは、個人の幸福感や組織へのエンゲージメントを高めるだけでなく、変化の激しい時代を生き抜く組織の柔軟性や競争力を強化することに直結するのです。
関連する参考記事
より多くの人に、自分の能力を使いながら役割を果たす、与えられた仕事を達成するまでやり切る、仕事の楽しさを知ってほしいです。職員みんなが、「自分の仕事によってこれを達成できた」という感覚を持ってもらえるようになるといいなと思っています。そうして、「仕事の責任は管理職にある」ではなく、一人ひとりがその仕事で達成したいことに対して主役として取り組むような感覚を持っている世界になるといいなと思っています。

記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

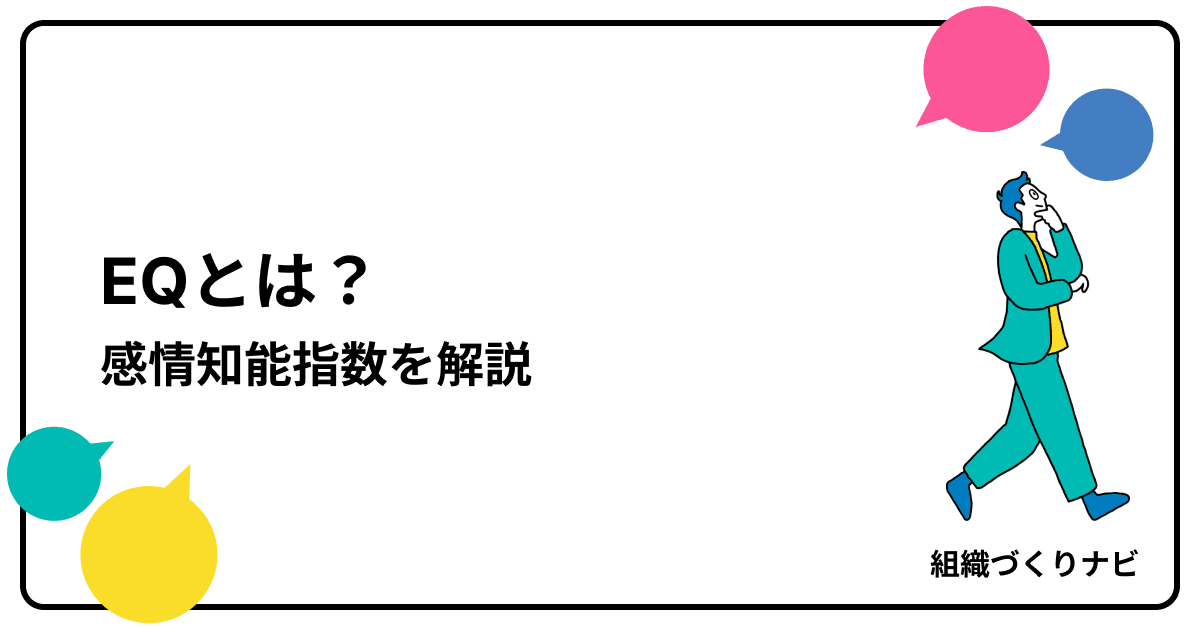
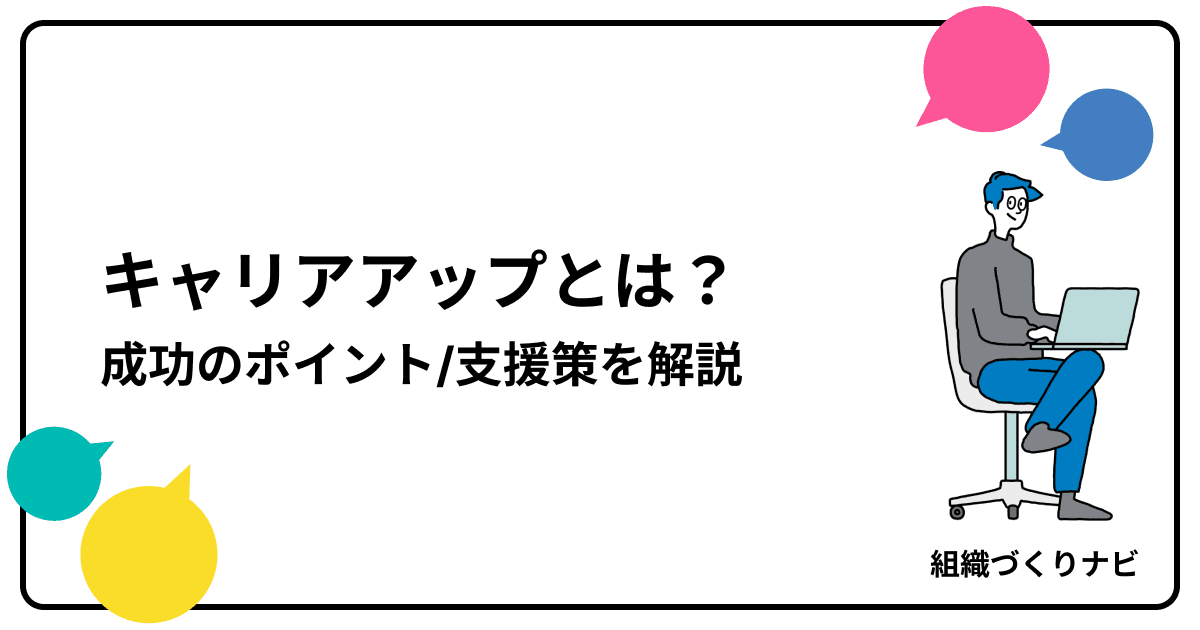
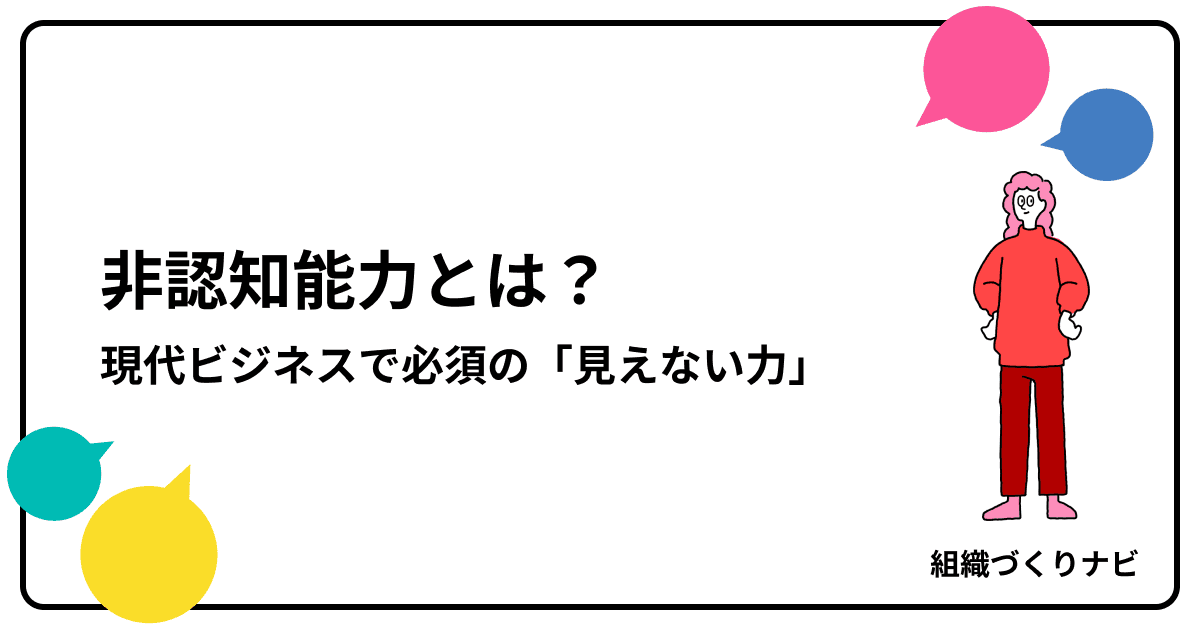
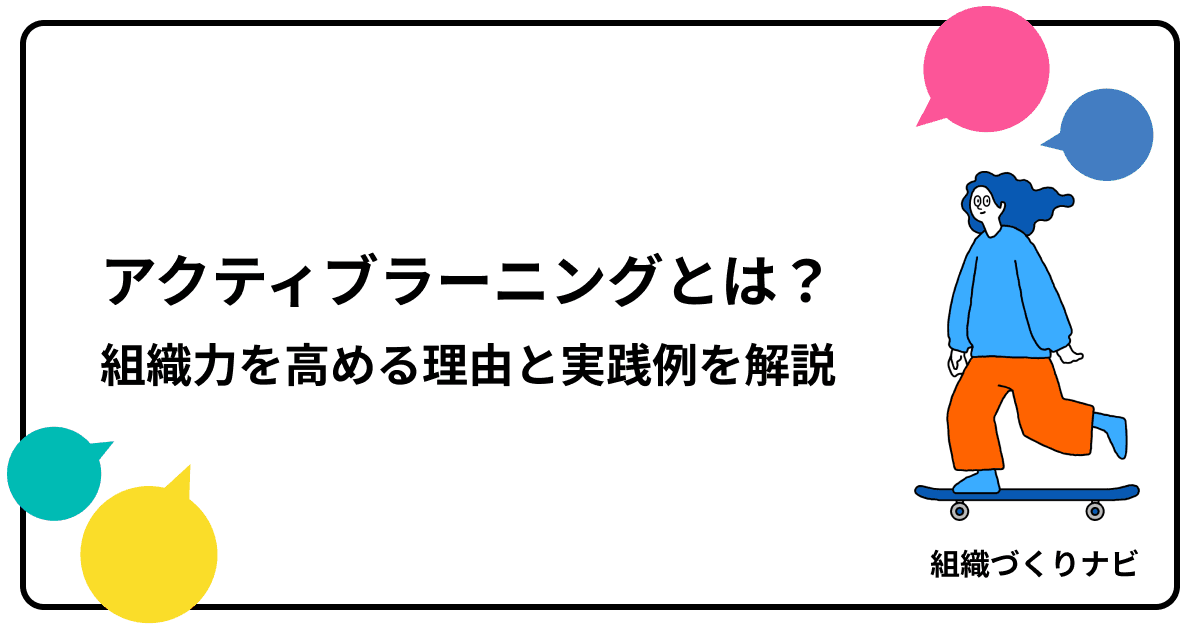
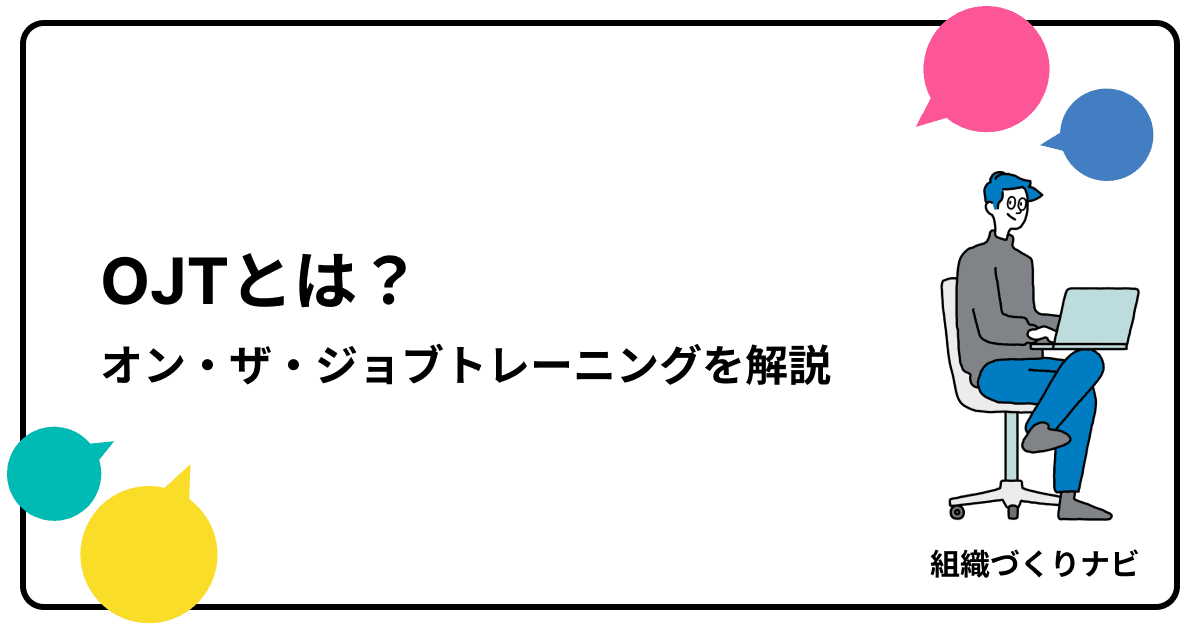
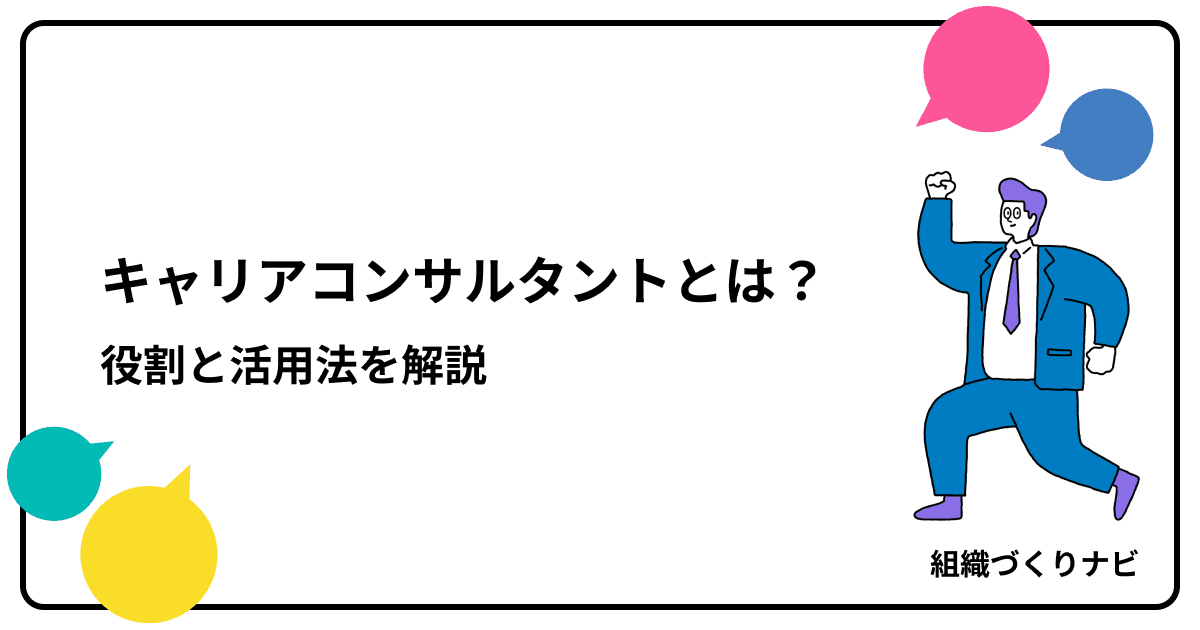



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


