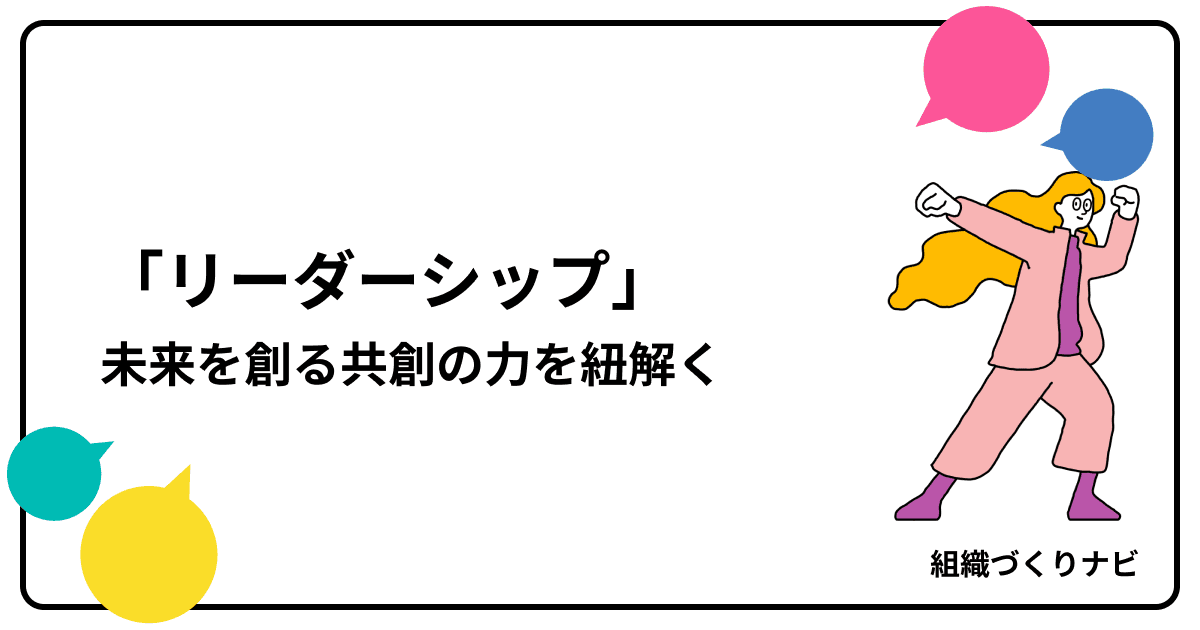
「リーダーシップ」とは?未来を創る共創の力を分かりやすく紐解く
現代のビジネス環境で求められるリーダーシップの本質とは何か?
本稿では、単なる指示出しではなく、チームの明確な方向性を示し、メンバーとの深い信頼関係を築き、内発的動機付けを促す「共創型リーダーシップ」の重要性を解説します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
リーダーシップとは?未来を創る「共創の力」
人事や管理職の皆様、日々の業務の中で「リーダーシップ」という言葉を耳にする機会は多いでしょう。しかし、それは単に「チームを引っ張っていく力」や「指示を出す立場」を指すだけではありません。現代において、リーダーシップはもっと深く、多様な意味を持つようになっています。激しく変化するビジネス環境でチームを目標に導き、メンバー一人ひとりの力を最大限に引き出すために不可欠なのが、この「リーダーシップ」なのです。本稿では、その本質と、明日から実践できる具体的な行動について、誰にでもわかる言葉で解説していきます。
現代のビジネス環境で求められるリーダーシップの本質
かつてのリーダーシップは、カリスマ性を持った一人が前線に立ち、強い権限でチームを統率するイメージが強かったかもしれません。しかし、情報が溢れ、価値観が多様化する現代において、その形は大きく変化しています。今のリーダーシップとは、決して「上司であること」や「命令すること」だけを指すものではありません。むしろ、チームや組織が「どこへ向かうべきか」という明確な方向性を示し、そして、その目標に向かって進む中で、メンバーとの間に揺るぎない信頼関係を築き、共に行動する力こそがリーダーシップの真髄と言えます。この信頼は、リーダーの人柄や誠実さ、そしてメンバーの意見に耳を傾ける姿勢から生まれるものです。
現代のリーダーシップは、メンバーに指示を出すだけではなく、彼らの内発的な動機付けを促し、自律的な行動を引き出すことに重きを置いています。特に「共創型リーダーシップ」は、心理的安全性の高い環境を築き、多様な意見が自由に飛び交うことで、チーム全体の創造性と問題解決能力を高めるアプローチです。メンバーのエンゲージメントを高め、組織全体の成長を加速させるための、まさに「未来を創る力」であると言えるでしょう。
明日から実践できる!リーダーシップを高める具体的な行動
リーダーシップは生まれ持った才能だけではありません。日々の意識と行動で、誰でも高めていくことができます。ここでは、明日から実践できる3つの行動をご紹介します。
1. オープンなコミュニケーションで信頼を築き、心理的安全性を育む
メンバーとの信頼関係は、オープンなコミュニケーションから生まれます。積極的にメンバーの話に耳を傾け、彼らの意見や懸念を真摯に受け止める「傾聴の姿勢」が大切です。自分の考えや判断基準を隠さずに共有することで、透明性が高まり、メンバーはリーダーをより理解し、信頼するようになります。
さらに重要なのは、心理的安全性を意識することです。「何を言っても大丈夫」という安心感は、メンバーが恐れずに意見を表明し、新しいアイデアを提案する土壌となります。定期的な1on1ミーティングや、ちょっとした雑談の機会も、そうした関係性を深める大切な場となるでしょう。
「メンバーの話に耳を傾ける」ことを重視した事例↓
屋代: 他部署のマネージャーの話を聞く中で、自分よりもメンバーの本音を引き出せているなと感じたことがありました。
それに対して、私はいつも自分の考えを喋りがちで、もしかしたら意見を押し付けてしまっている可能性もあると感じました。ですから、その後の1on1では以前よりも聞くことを意識して、メンバーの正直な気持ちを聞けるように取り組んでいきました。
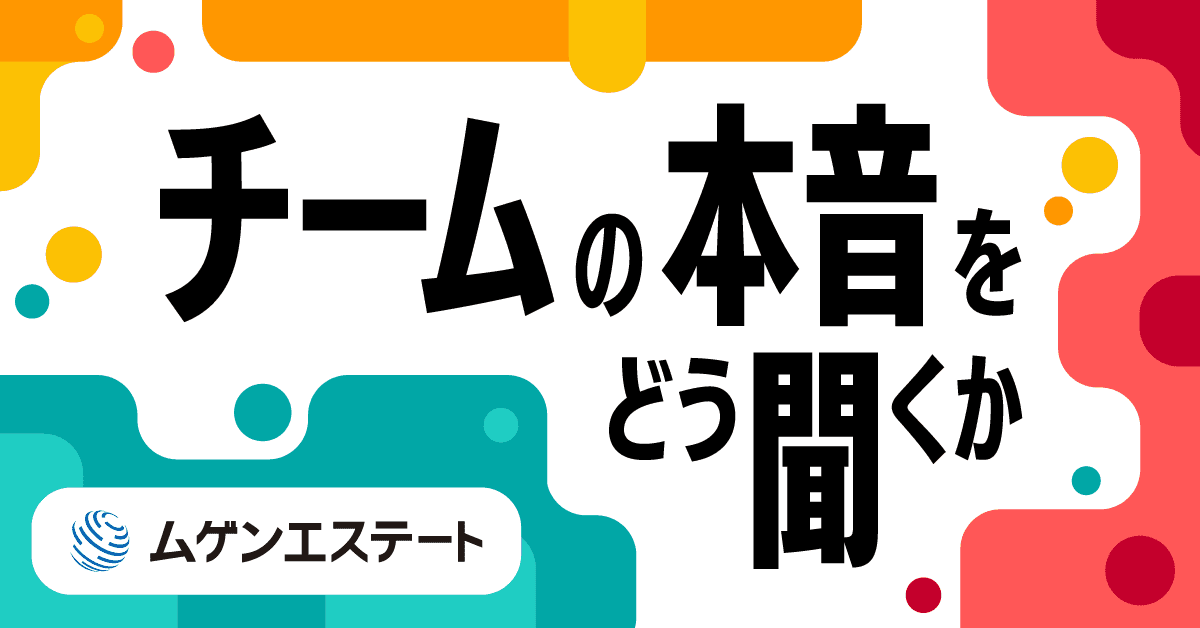
2. メンバーの意見を尊重し、意思決定に「共創」を促す
チームの目標達成には、メンバー一人ひとりの「自分ごと」意識が不可欠です。リーダーがすべてを決定するのではなく、重要な意思決定プロセスにメンバーを巻き込むことで、彼らは当事者意識を持ち、より積極的に貢献しようとします。これは単なる意見聴取に留まらず、メンバーの多様な視点や専門知識を活かし、より良い解決策を共に探す「共創」のアプローチです。
たとえ最終的な決定がリーダーによるものであっても、メンバーの意見をしっかり聞き、その上で理由を説明することで、納得感が生まれ、チームのエンゲージメント向上につながります。
3. 自ら学び、変化の「羅針盤」となる姿勢を示す
リーダー自身が「学び続ける姿勢」を示すことは、チーム全体に良い影響を与えます。新しい知識やスキルを積極的に吸収したり、自身の失敗を認め、そこから学ぼうとする姿勢は、メンバーにとっても「自分も挑戦していいんだ」「失敗してもそこから学べばいい」という安心感を与えます。
AIなどの新しい技術が普及し、ビジネスモデルの変革が加速する中で、リーダーが率先して探求し、適応していく姿を見せることは、チームに未来への指針と希望を与えます。リーダーこそが、変化の波を乗りこなし、チームの「羅針盤」となるべき存在です。
チームの可能性を最大限に引き出す!現代リーダーに不可欠な3つの視点
現代のビジネスシーンでは、これまでの常識が通用しない場面も増えています。そんな中で、リーダーシップを発揮するためには、以下の3つの視点を持つことが不可欠です。
ビジョン提示力:未来を共に描く「羅針盤」となる
不確実な時代だからこそ、リーダーにはチームが進むべき未来を明確に描き、それを分かりやすくメンバーに伝える力が求められます。単に「売上目標を達成しよう」と言うだけでなく、「なぜその目標を達成するのか」「達成することで、チームや社会にどんな価値をもたらすのか」という“意義”を語ることが重要です。
この「羅針盤」があるからこそ、困難な状況でもチームは迷わず進み続けられます。メンバーが目標に共感し、自分たちの仕事が組織や社会にどう貢献するのかを理解することで、日々の業務へのモチベーションも高まるでしょう。
育成・支援力:メンバーの成長を促す「伴走者」となる
現代のリーダーは、メンバーを「指示通りに動かす駒」ではなく、「自ら考え、行動する主体」と捉えるべきです。そのためには、メンバー一人ひとりの強みや得意なことを見つけ出し、それを活かせる機会を与えることが重要になります。
また、時には耳の痛いフィードバックも、成長への期待を込めて建設的に伝えることで、メンバーは自身の課題に気づき、より大きく成長できます。リーダーは、メンバーが安心して挑戦できる環境を整え、彼らが持っている無限の可能性を引き出す「伴走者」としての役割を担うのです。
メンバーの強みを引き出す施策例↓
島崎:私たちのグループの場合、個々に業務や技術が確立していて、個人で仕事をしている人が集まっているような形のグループなので、チームワークという言葉があまり当てはまりません。お互いにほめ合う機会もなく、そもそもほめられることに美点を見出してない人が多いグループです。だから、単純に個の良さをほめ合っても響かないだろうとマネジメント層が判断し、「今後も継続したり、伸ばしたりしていけるといい強みや利点は何か?」という観点でお互いに話をすることにしました。
結果、他の人から見た自分の評価を改めて知れて、お互いにそれを言い合える時間としてすごく有意義だったと感じています。元々「自分はここが強いんだろうな」という認識を持っている人も多いので、それを後押ししてもらえるような言葉がもらえて「やっぱりこれでいいんだ」とより自信を持てたのではないかと思います。
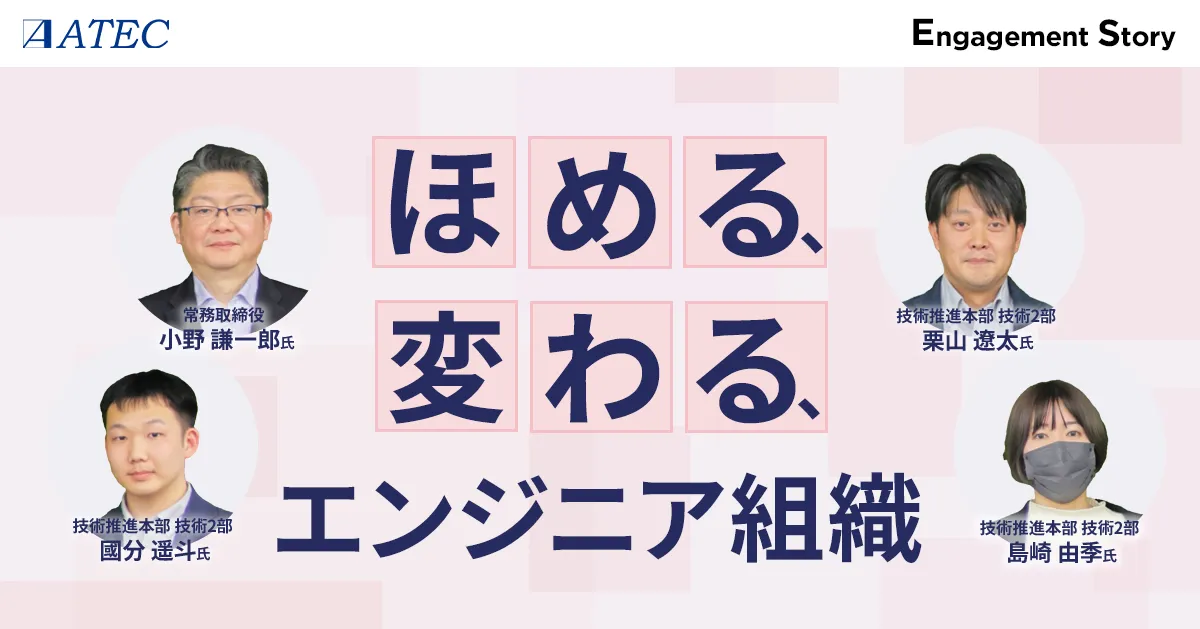
適応力:変化を好機に変える「しなやかさ」を持つ
ビジネス環境は常に変化し、予期せぬ事態も頻繁に起こります。このような状況下でリーダーに求められるのは、固定観念にとらわれず、新しい情報や状況に柔軟に対応する力です。例えば、新しい技術が導入されたり、市場のニーズが変わったりした際に、「これまで通り」に固執するのではなく、率先して学び、変化を受け入れる姿勢を見せることで、チーム全体も前向きに変化に対応できるようになります。
リーダー自身が「しなやか」であることこそが、変化の波を乗りこなし、チームを成功に導く鍵となるでしょう。
リーダーシップは「役割」であり、誰もが発揮できるものです
リーダーシップは、特定の役職や肩書きを持つ人だけのものではありません。チームの中で「誰かが動かなければ」という場面で、自ら進んで行動を起こし、周りを良い方向に導こうとする「役割」として、誰もが発揮できるものです。
上司がメンバーの「フォロワーシップ」に支えられ、メンバーがまた別の場面でリーダーシップを発揮するといった、相互作用の中でチームは成長していきます。立場や経験に関わらず、一人ひとりが「共創」の意識を持って行動することで、組織全体にリーダーシップが浸透し、より強くしなやかな組織文化を育むことができるでしょう。
まとめ:組織と個人の成長を促す「共創型リーダーシップ」
リーダーシップとは、明確なビジョンでチームの方向性を示し、メンバーとの深い信頼関係を築きながら、彼らの可能性を引き出し、変化に柔軟に対応していく「共創の力」です。それは、特別な才能ではなく、日々の意識と行動で磨き上げられるものです。
本稿でご紹介した視点と具体的な行動を実践することで、チームの生産性を向上させるだけでなく、メンバー一人ひとりの成長とエンゲージメントを最大化できるのです。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

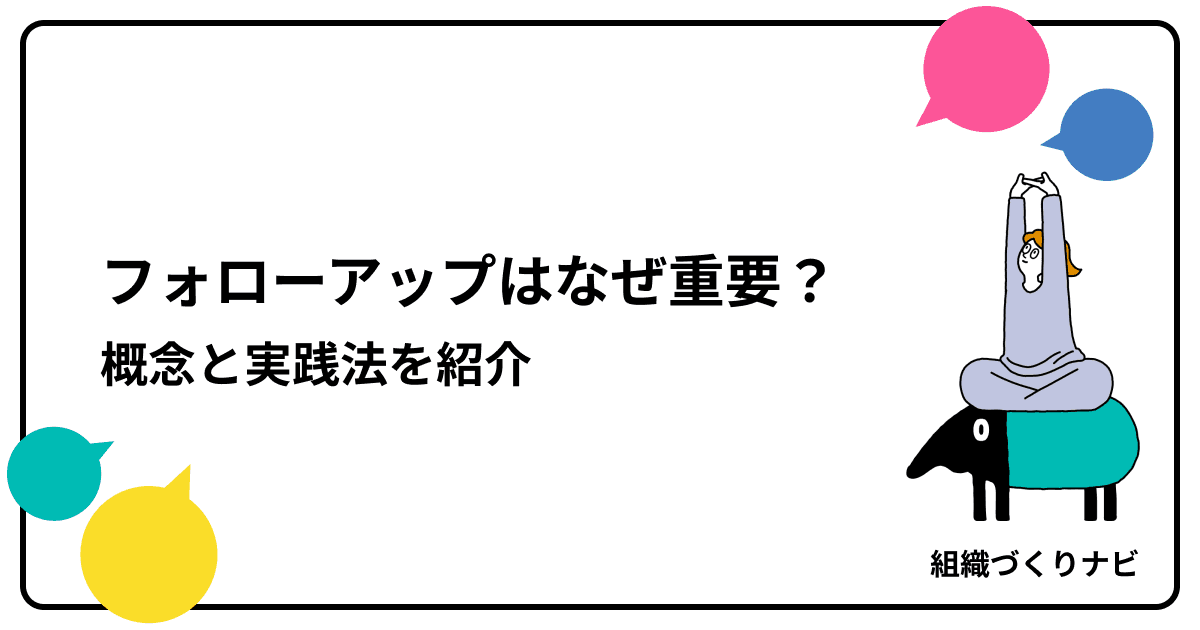
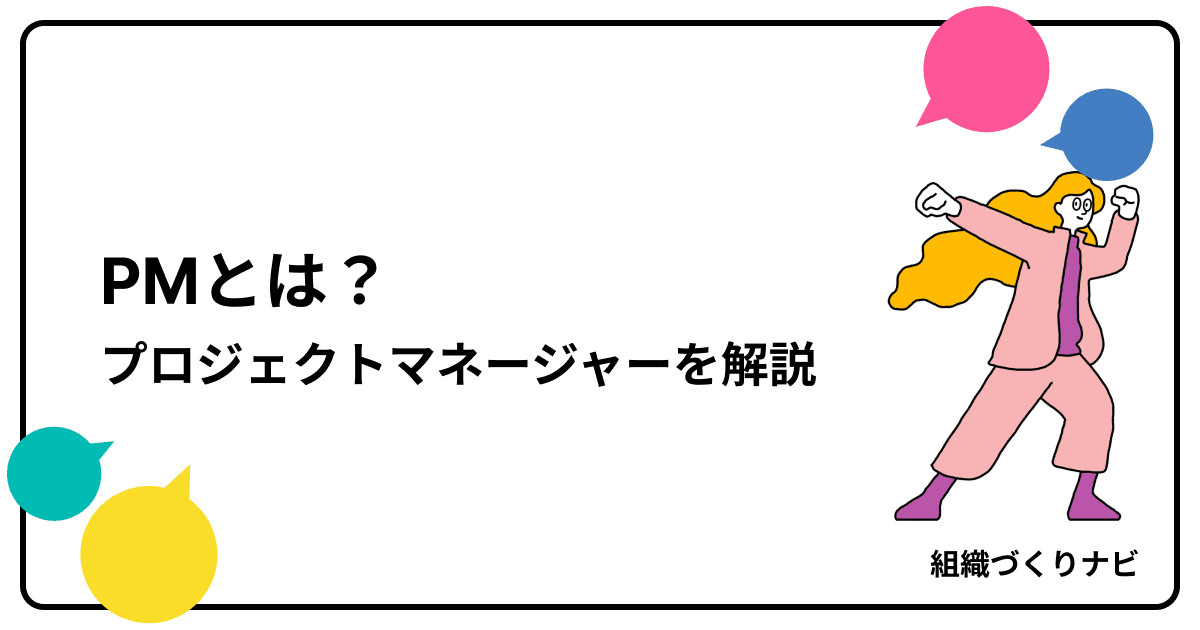
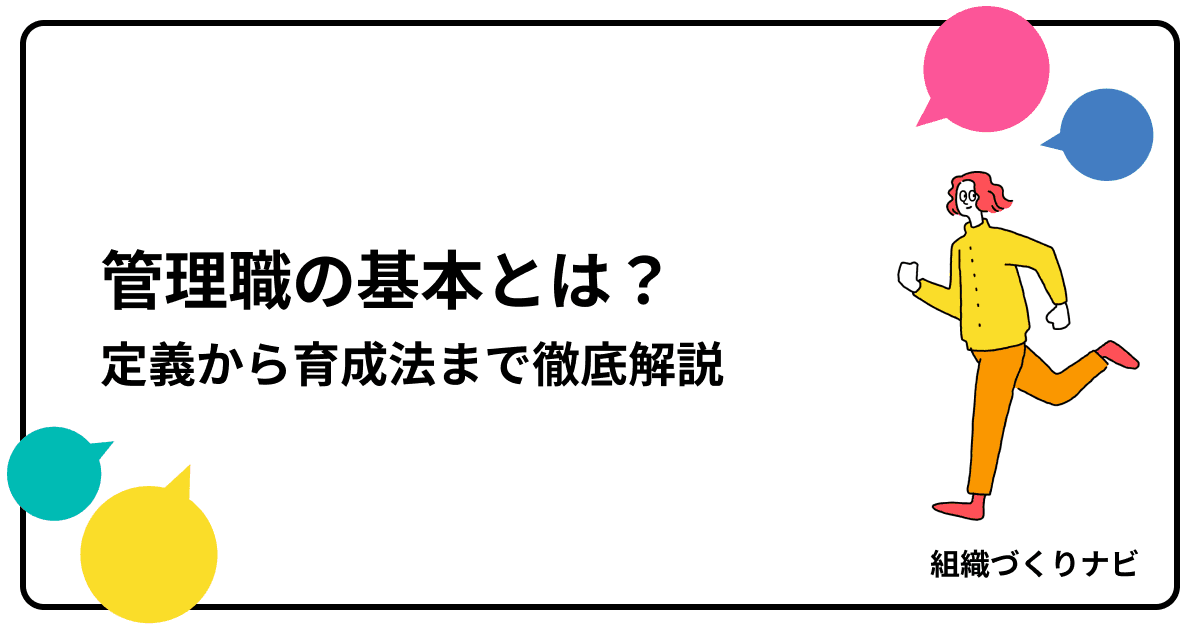
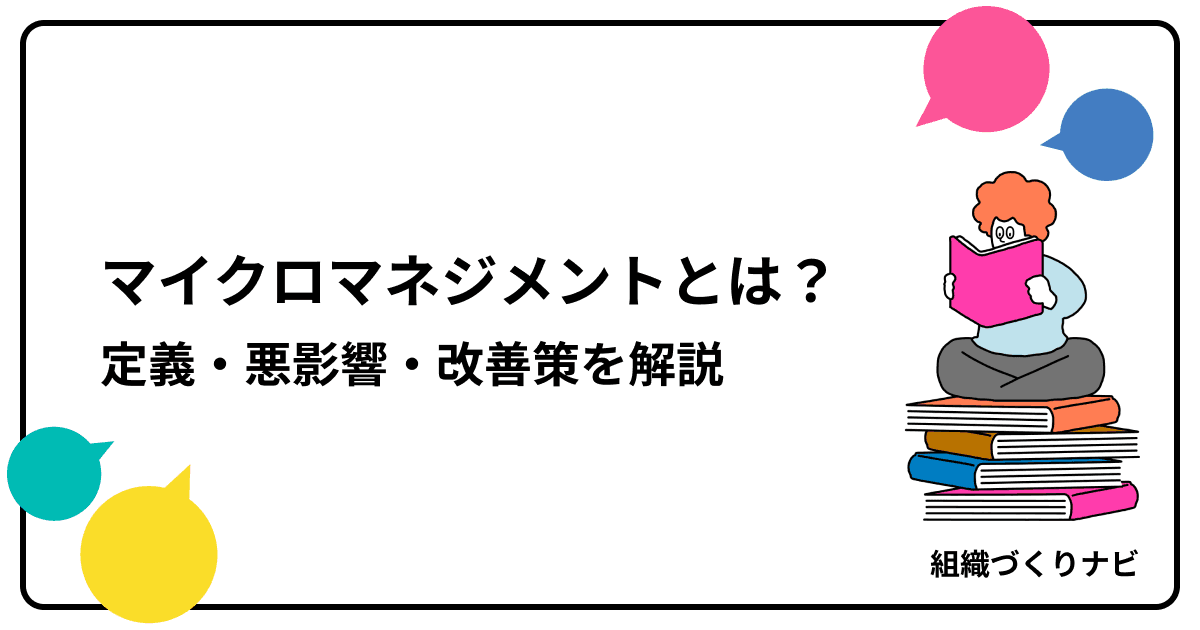
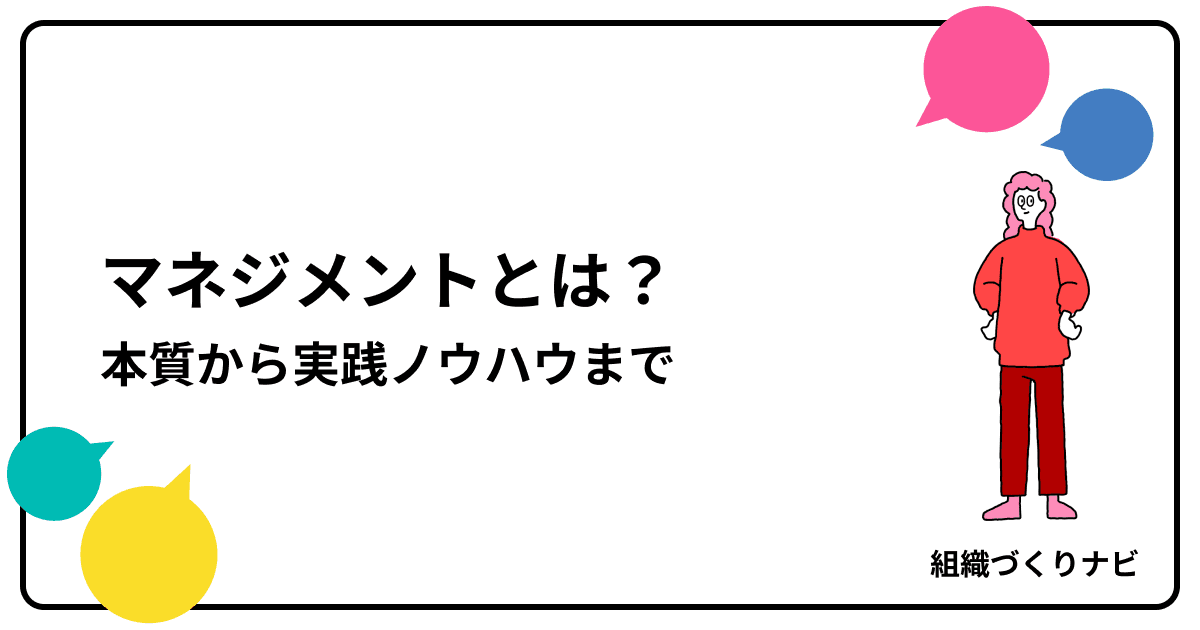
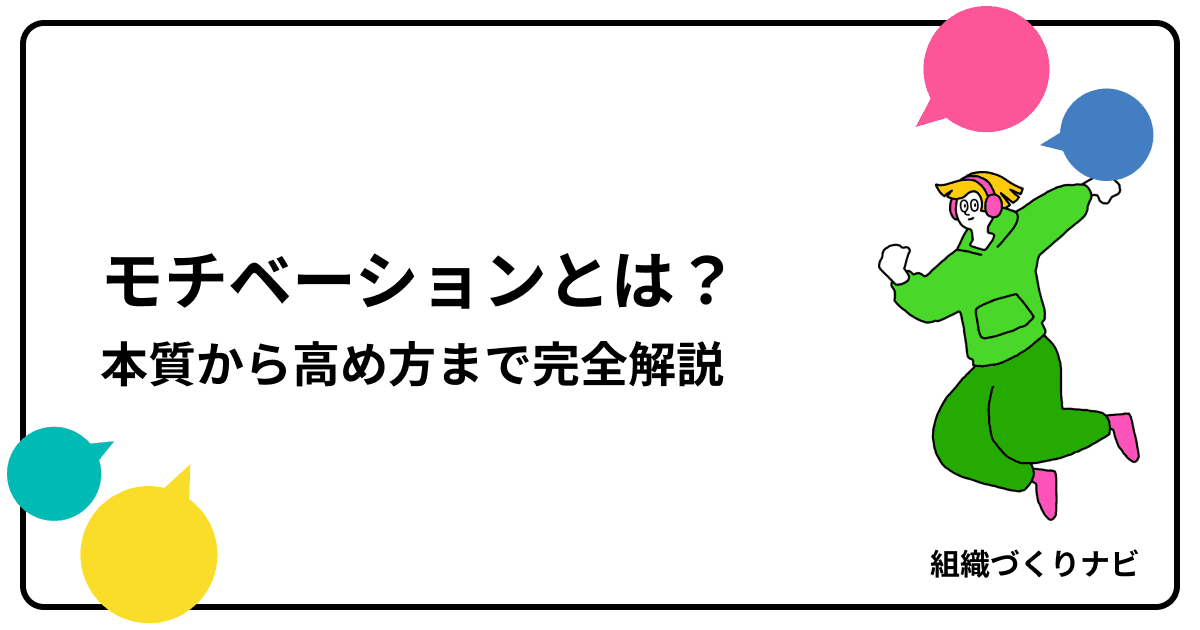



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


