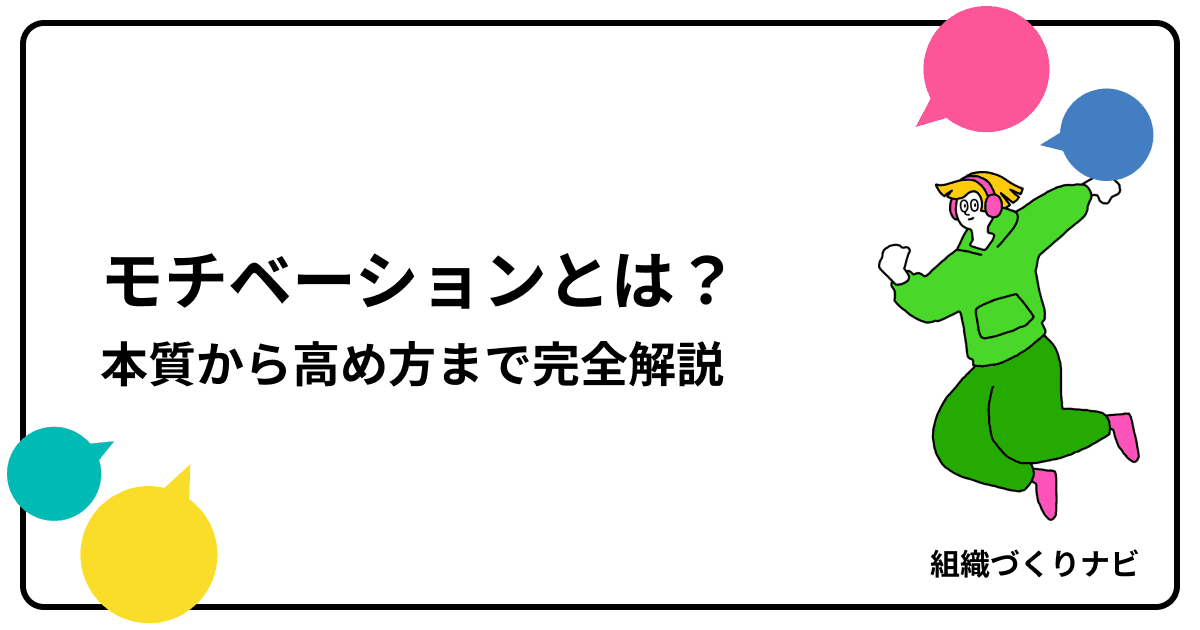
「モチベーション」とは?本質から高め方まで完全解説
「モチベーション」は単なるやる気ではなく、個人のパフォーマンスや組織の成長を左右する重要な心理的プロセスです。仕事そのものに価値を見出す「内発的動機づけ」と、報酬や評価など外部刺激による「外発的動機づけ」の二種類、そして人それぞれ異なる「やる気の源」を理解することが重要です。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
モチベーションとは?〜「やる気」を科学する視点〜
人事や管理職の皆様が日々の業務で耳にする「モチベーション」という言葉。単なる「やる気」や「士気」といった曖昧な意味で使われがちですが、実は人の行動や成果を大きく左右する、非常に重要な心理的プロセスです。ここでは、その「モチベーション」について、基礎から具体的な活用方法まで、人事・管理職の皆様が明日から実践できる視点とともに解説いたします。
モチベーションとは何か?
モチベーションとは、人が何かをしたい、目標を達成したいという「意欲」や「動機づけ」のことです。私たちは、仕事や私生活で様々な行動を起こしますが、その行動の源には必ず「こうなりたい」「これを成し遂げたい」という内面的な推進力が隠されています。これがモチベーションの本質です。
この概念がなぜ重要かというと、個人の仕事の成果や成長、ひいてはチーム全体の生産性や組織の活気に直接結びつくからです。人事や管理職の皆様は、部下やメンバーのこの「意欲の源」を深く理解し、適切に働きかけることで、個人のパフォーマンスを最大限に引き出し、組織全体の目標達成を強力に後押しすることができます。
モチベーションが組織にもたらす良いこと
従業員のモチベーションが高い状態は、個人だけでなく組織全体に様々な好影響をもたらします。
まず、個人の面では、仕事への集中力や意欲が高まるため、生産性の向上や業務の質の向上に直結します。新しいアイデアが生まれやすくなり、困難な課題にも前向きに取り組むようになります。 次に、チームや組織の面では、活発なコミュニケーションが促進され、協力体制が強化されます。
結果として、職場全体の雰囲気が明るくなり、離職率の低下にも繋がり、組織の安定と成長を支える基盤となります。高まったモチベーションは、変化への適応力や問題解決能力も向上させ、持続的な組織発展の原動力となるのです。
モチベーションを理解する「3つの視点」
モチベーションには、主に二つの種類と、その人の個性という視点があります。これらを理解することで、メンバー一人ひとりに合わせた効果的なアプローチが可能になります。
内側から湧き出る力(内発的動機づけ)
これは、仕事そのものに「面白い」「楽しい」「成長できる」といった価値を見出し、自ら進んで取り組む気持ちのことです。例えば、「この仕事をすることでスキルが向上する」「自分のアイデアが形になるのが嬉しい」「チームに貢献できることに喜びを感じる」といった感情がこれにあたります。
内発的動機づけは、報酬や評価がなくても行動を促し、持続性が高く、質の高い成果に繋がりやすいという特徴があります。部下には、仕事の「やりがい」や「意味」を伝え、自律性や成長の実感を持たせることが大切です。
外からの影響で生まれる力(外発的動機づけ)
こちらは、昇進、報酬、表彰、あるいは評価といった、外部からの刺激によって生まれるやる気を指します。例えば、「昇給のために頑張ろう」「良い評価を得たいから努力しよう」「上司に褒められたい」といった気持ちが外発的動機づけにあたります。
目標達成へ向けて一時的に集中力を高める効果が期待できますが、その刺激がなくなると、やる気が失われやすいという側面もあります。外発的動機づけは強力な後押しになりますが、「なぜその報酬があるのか」という納得感を伴うことが重要です。
人それぞれ違う「やる気の源」
モチベーションの源は、万人に共通するものではありません。ある人は「新しい挑戦」に燃えるかもしれませんし、別の人は「安定した環境」に安心感を覚えるかもしれません。また、ある人は「人との協力」に喜びを感じ、別の人は「個人で黙々と集中する」ことに価値を見出すでしょう。
管理職としては、部下一人ひとりの価値観や興味、現在の状況を理解し、何に「やる気」を感じるのかを見極めることが重要です。例えば、仕事の裁量権を求めるタイプ、成長機会を重視するタイプ、人とのつながりを大切にするタイプなど、多様な動機が存在します。個々の特性に合わせたコミュニケーションや仕事の割り振りを通じて、それぞれの「やる気の源」を大切に育むことが求められます。
管理職がモチベーションを高めるためにできること
管理職は、部下のモチベーションを左右する重要な役割を担っています。具体的な行動を通じて、メンバーのやる気を引き出し、高めることができます。
1.適切な目標設定をサポートする
部下が「少し頑張れば届く」と感じるような、現実的でありながら挑戦的な目標設定を共に考えましょう。目標が不明確だとやる気が湧きませんし、高すぎても諦めてしまいます。目標達成が個人の成長や組織貢献にどう繋がるか、その「意味」を明確に伝えることがモチベーション維持に不可欠です。
2.適切なフィードバックと承認を欠かさない
部下の努力や成果を具体的に認め、言葉で伝えることは非常に効果的です。褒める際は「よくやった」だけでなく、「〇〇のプロセスが特に素晴らしかった」のように具体的に伝えましょう。良い点だけでなく、改善点についても成長を期待する視点で丁寧にフィードバックすることで、部下は自身の行動を振り返り、次へと繋げる糧とすることができます。「見ているよ」というメッセージが安心感と意欲を育みます。
「承認」を重視した施策事例↓
竹田:「成果に対する承認」が低い傾向にある背景から、2024年1月14日からの一週間を『いいよ!週間』と称し、同僚間での褒め合いを後押しするイベントを行いました。日頃良いなと思っている点や感謝の気持ちをメッセージカードに書いてもらい、健康チョコレートと一緒に渡し合ってもらうという内容です。
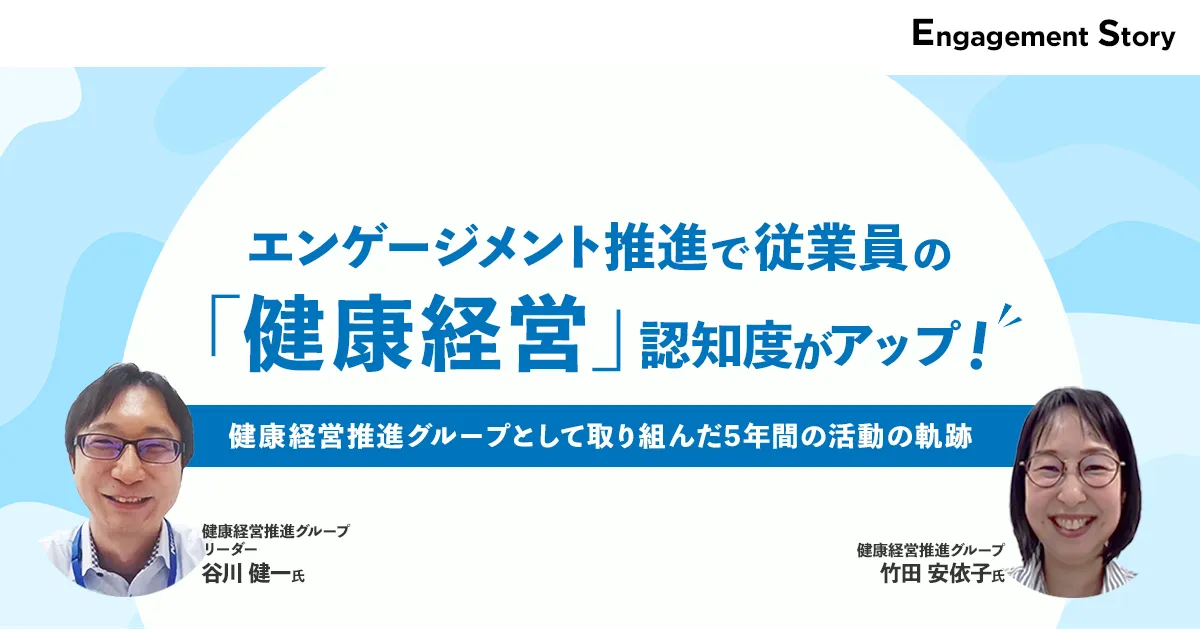
3.成長の機会を提供する
新しい役割や業務への挑戦、スキルアップのための学習機会など、部下が「成長している」と実感できる機会を提供しましょう。人は成長を実感できると、さらなる意欲が湧きます。少し難しいと感じるくらいの仕事(ストレッチアサインメント)を任せることも、自信と能力向上に繋がり、内発的動機づけを高めます。
4.コミュニケーションを密にする
部下の話に耳を傾け、彼らが抱える不安や困難を理解し、サポートする姿勢を見せましょう。日頃からオープンなコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことで、部下は安心して仕事に取り組めます。「いつでも相談できる」という安心感が、やる気を下支えします。定期的な1on1ミーティングなども有効です。
「1on1」を重視した企業事例↓
―1on1を実施してきて、どのようなチームの変化を感じているのでしょうか?
新屋:「今日の何時頃なら時間ありますか?」「1on1をお願いします」と、部下から声をかけてくれることが増えてきました。
最初はなかなか声を掛けられることはなかったのですが、「1on1では部下であるあなたが主役なんだ」と伝え続けることで、信頼関係が生まれたり、価値を感じてもらえるようになったのかなと思います。

5.公平な評価と公正な待遇
評価基準を明確にし、感情ではなく事実に基づいて公平に評価することは、部下の納得感と信頼を得る上で不可欠です。透明性のある評価プロセスは、部下が自身の努力が正当に評価されると実感し、モチベーションを維持する重要な要素となります。また、努力や成果に見合った待遇を検討することも、「頑張りが報われる」という外発的モチベーションに繋がります。
まとめ
モチベーションは単なる「やる気」ではなく、個人のパフォーマンス、チームの生産性、そして組織の持続的成長を左右する重要な心理的要素です。内発的・外発的な動機づけを理解し、一人ひとりの「やる気の源」を見極めること。そして、管理職として「適切な目標設定」「丁寧なフィードバック」「成長機会の提供」「密なコミュニケーション」「公平な評価」を実践することが、部下の「心の意欲」を最大限に引き出す鍵となります。モチベーションを科学的に理解し、日々のマネジメントに活かすことが、活力ある組織を築く第一歩となるでしょう。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

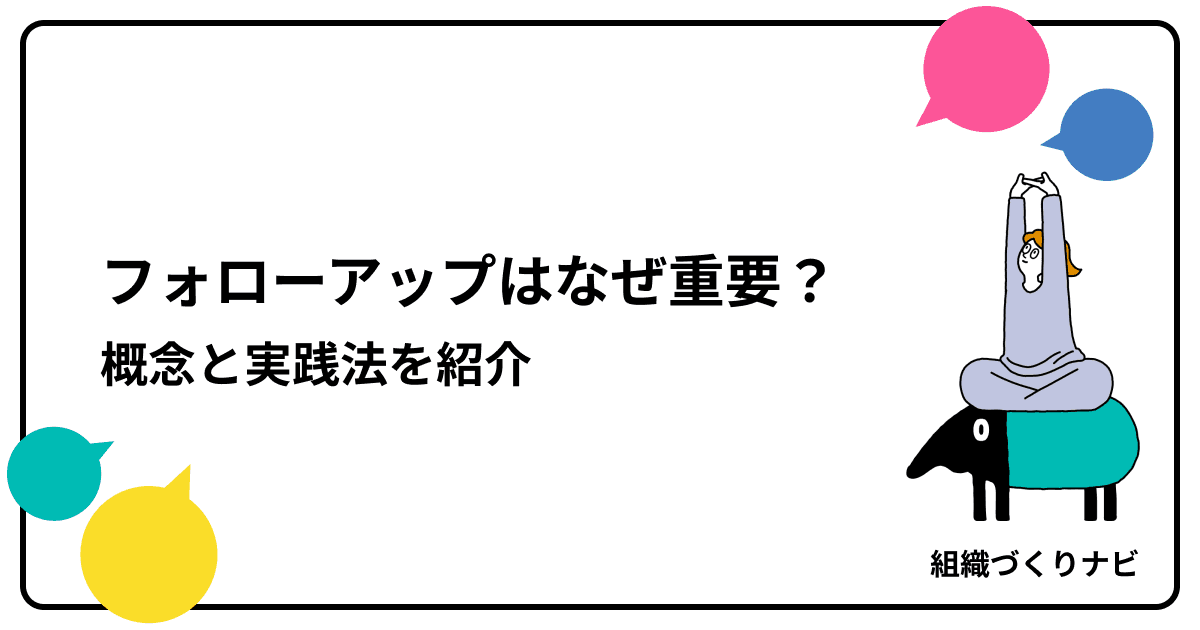
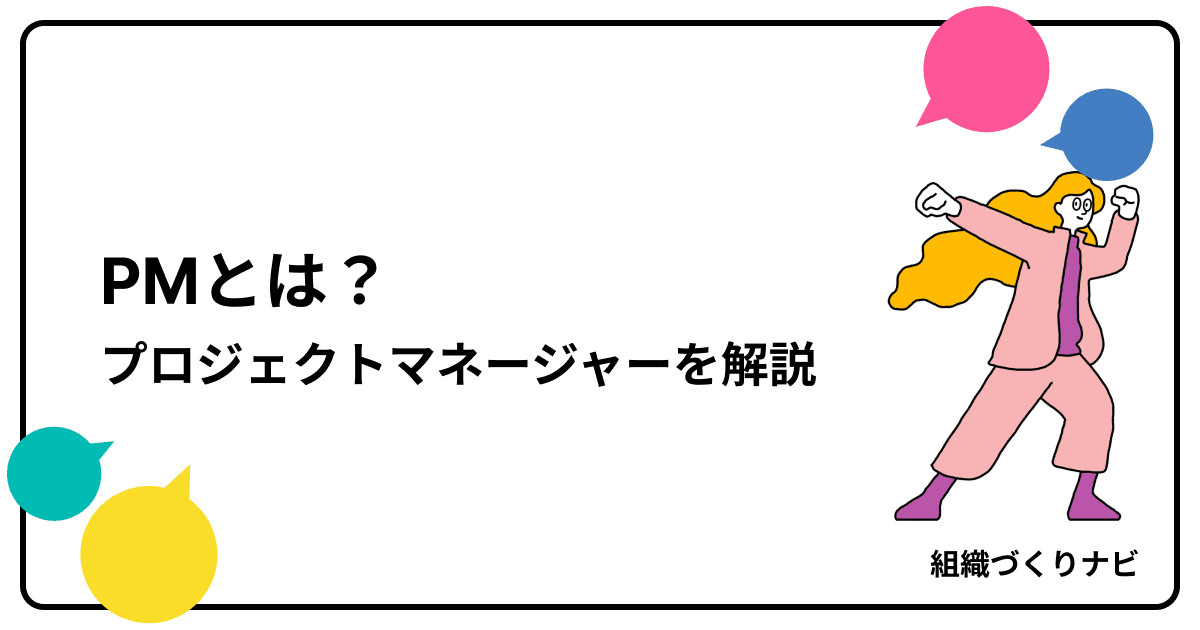
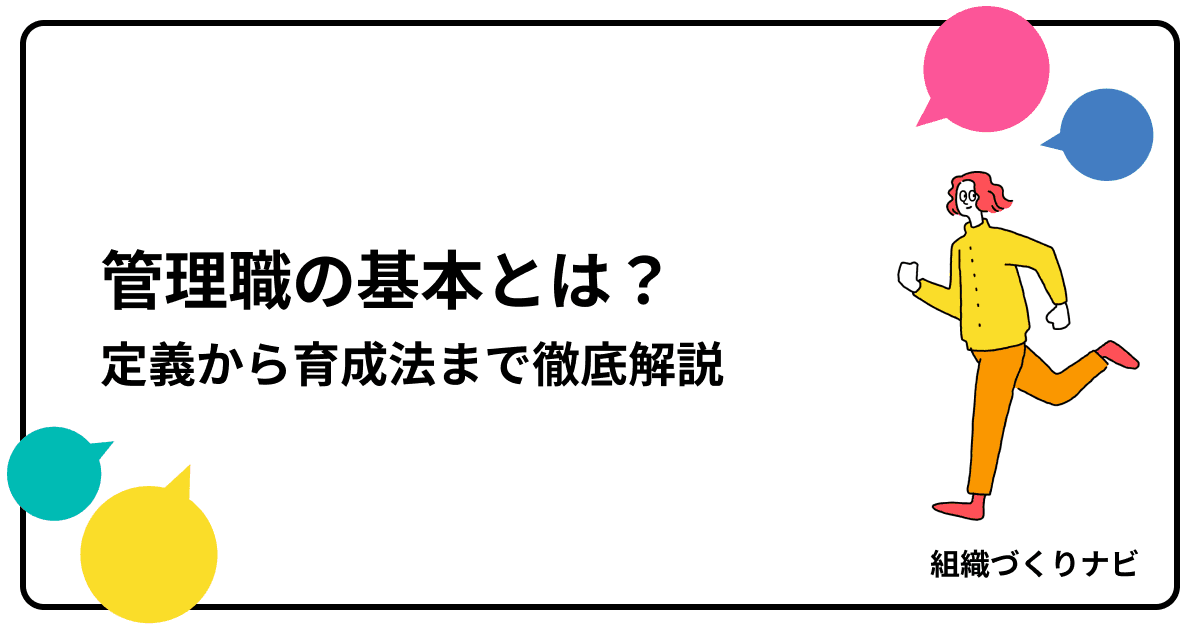
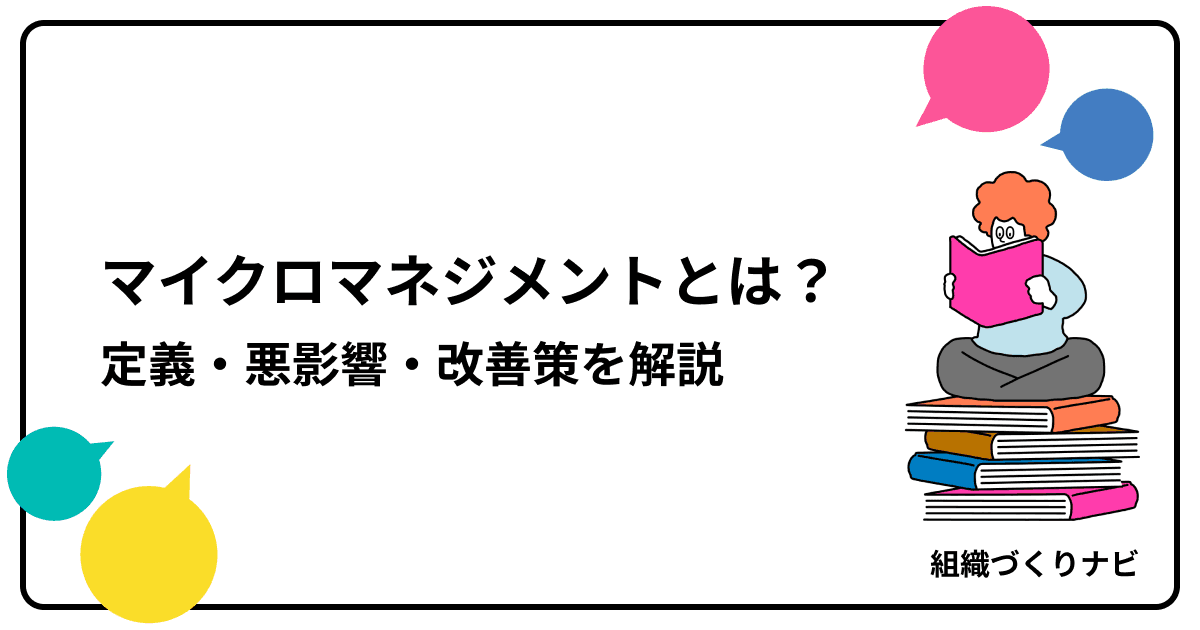
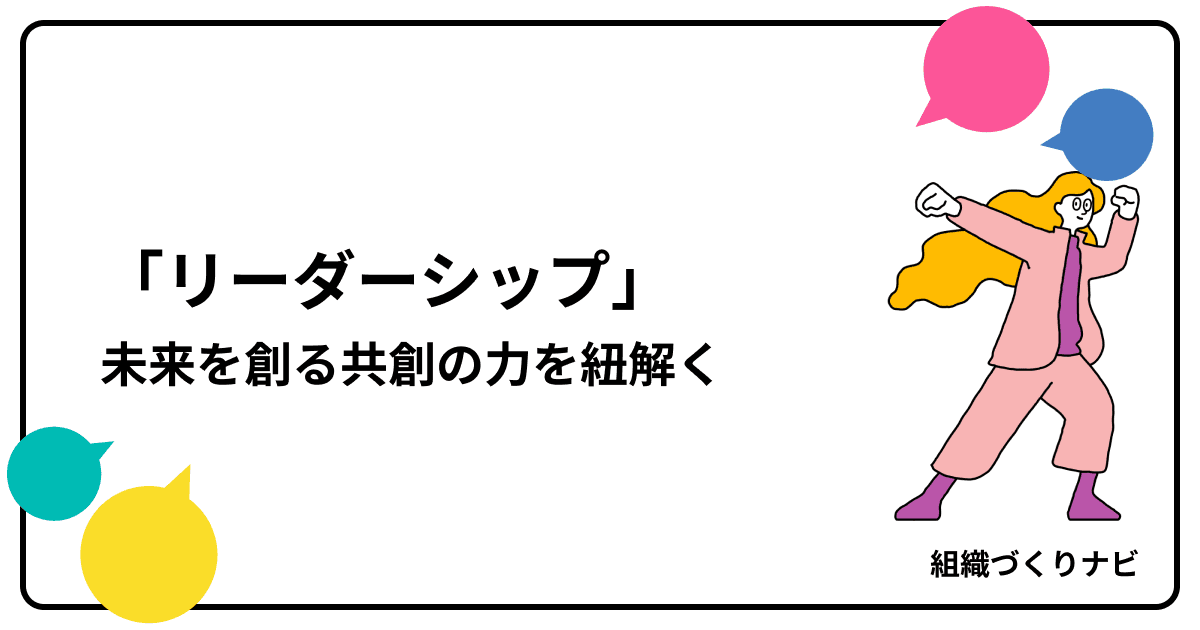
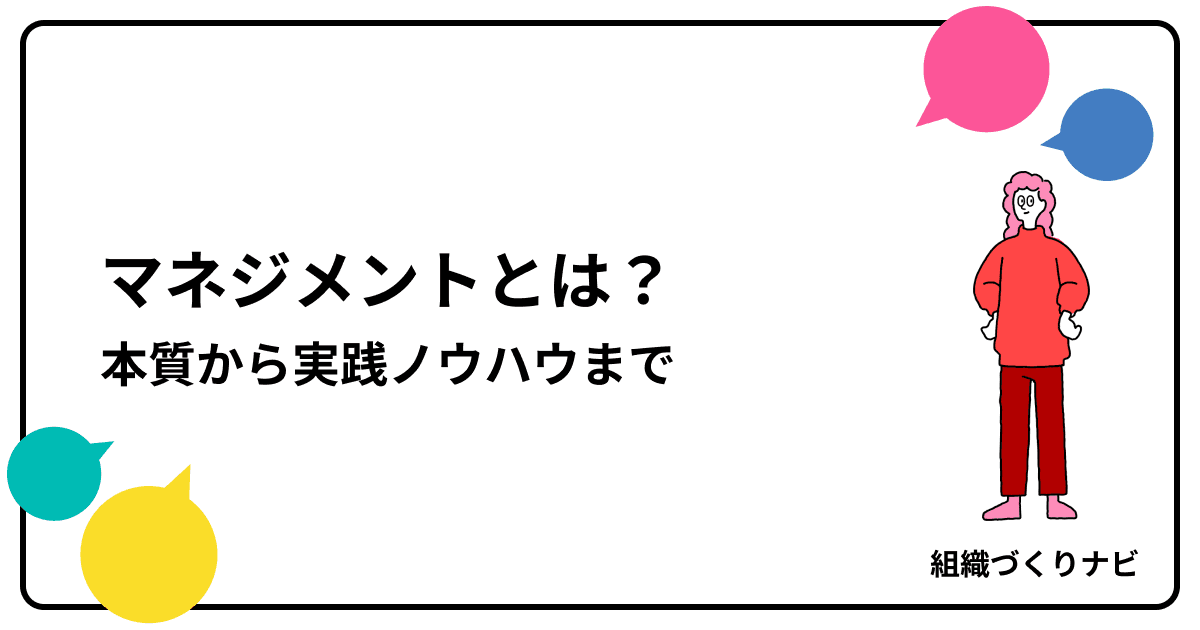



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


