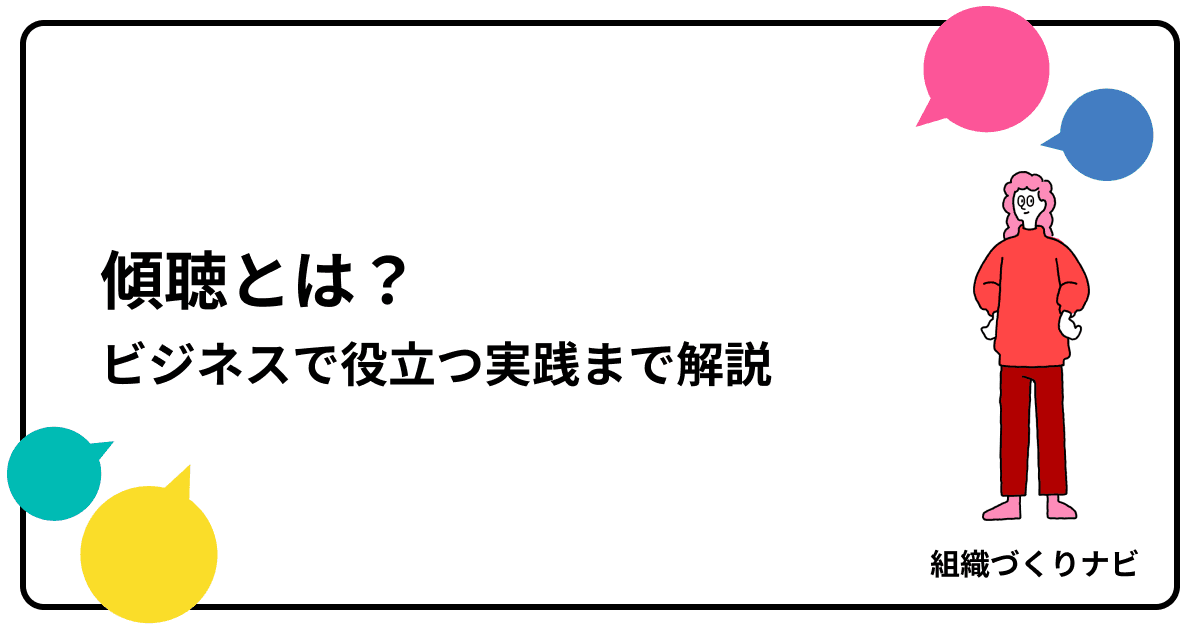
傾聴とは?基本から実践まで!ビジネスで役立つコミュニケーションスキルを徹底解説
傾聴とは、単に相手の話を聞くのではなく、耳・目・心すべてを使い、相手の感情や真のニーズを深く理解しようと努める高度なコミュニケーション技術です。現代ビジネスにおいて、経済産業省も注目する社会人基礎力の一つとして、信頼関係構築や複雑な課題解決に不可欠。非言語コミュニケーション、言葉の繰り返し、言い換え、効果的な質問などを活用し、カール・ロジャーズの提唱する「自己一致、共感的理解、無条件の肯定的関心」を土台とします。部下育成、チームビルディング、顧客対応など多様なビジネスシーンで活用され、組織の生産性向上や人間関係改善に貢献。形だけの傾聴ではなく、真摯な姿勢が重要です。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
傾聴とは?なぜ今、ビジネスで注目されているのか?
傾聴とは、単に相手の話を「聞く」のではなく、相手に心を寄せ、耳・目・心のすべてを使って深く理解しようと努める高度なコミュニケーション技術です。元々はカウンセリング分野で発展しましたが、近年ではビジネスシーンにおいて、より強固な人間関係を築き、複雑な課題を解決するために不可欠なスキルとして、その価値が再認識されています。
特に、経済産業省が提唱する社会人基礎力の一つとしても「傾聴力」が挙げられるように、多様な価値観が共存する現代社会で、相手を深く理解し、揺るぎない信頼関係を構築する上で極めて重要とされています。この「アクティブリスニング」のスキルは、個人の能力開発はもちろん、組織の力を最大限に引き出すための要となるでしょう。
傾聴の目的と効果:何のために傾聴するのか?
傾聴の最大の目的は、相手の言葉の裏に隠された感情、意図、そして真のニーズを深く「理解する」ことにあります。これは、単に情報を「聞く」ことや、質問で事実を「訊く」こととは一線を画します。私たちは「なぜそう感じるのか」「何を本当に伝えたいのか」という話し手の内面に焦点を当てることで、多くのメリットを得られます。
話し手は、心ゆくまで話すことで自身の考えや感情が整理され、自己理解が深まります。これにより、問題解決の糸口を自分自身で見つけやすくなることも少なくありません。一方、聴き手は、相手との信頼関係を強固に構築でき、相手の自己肯定感を高める手助けができるだけでなく、チーム全体のコミュニケーションの質向上や、より良い意思決定に貢献できます。
関連する参考記事
メンバーに対して働きかける際にメールで一斉に伝えたとしても、意見があっても言えない人や嫌だなと思っている人は必ずいるはずです。そうした感情を抱いている人は、表情などを見ればわかるので、個別に困っていることや何を不安に思っているかを聞き出します。そうしてそれぞれが抱える問題に寄り添った上で「ここまでならできる」という方法を提案すると、困りごとは解消できることを実感しました。その試行錯誤が自分自身の学びにもなりましたし、エンゲージメントの理解を深めることに繋がったと思います。

傾聴の具体的な実践方法とテクニック
傾聴は、意識的に実践できる具体的なテクニックを通じて効果を発揮します。これらのスキルを身につけることで、あなたのコミュニケーションは飛躍的に向上するでしょう。
非言語コミュニケーションの活用
うなずき、アイコンタクト、穏やかな表情、そして相手に開かれた姿勢で、「あなたの話に関心があります」というメッセージを明確に送ります。これにより、話し手は安心感を抱き、より本音を話しやすくなります。
言葉の繰り返し(リフレイン)
相手の言葉の中から特に重要な部分や感情を表す言葉を選び、「〇〇だと思っていらっしゃるのですね」と、そのままの言葉で返します。これは、相手の話を注意深く聞いていることを示し、理解を深めるための確認にもなります。
言い換え(パラフレーズ)
相手の話全体を自分の言葉で要約し、「つまり、こういうことでしょうか?」と返します。これにより、認識のズレがないかを確認し、相手の考えを整理する手助けにもなります。
効果的な質問の活用
具体的な状況を尋ねる「具体化質問」や、別の視点から考える「視点を変える質問」で、相手の思考を深める手助けをします。ただし、質問攻めにならないよう、相手が自ら話すのを促すオープンな質問が基本です。
沈黙への対応
相手が考えを巡らせている際の沈黙は、貴重な思考の時間です。焦って口を挟まず、じっと待つことも大切なコミュニケーションの一部と考えましょう。沈黙を肯定的に受け止めることで、相手は安心して内面と向き合えます。
ミラーリング、ペーシング
相手の話し方や声のトーン、呼吸のペース、あるいはジェスチャーに自然に合わせることで、無意識レベルで親近感を高め、安心感を築きます。これは、相手との心理的な距離を縮める上で非常に有効なテクニックです。
傾聴の土台となる基本原則:「積極的傾聴」の3要素
心理学者カール・ロジャーズが提唱した「積極的傾聴(アクティブリスニング)」には、傾聴の土台となる三つの大切な原則があります。これらは、単なるテクニックではなく、相手と向き合う上での心の持ち方を示しています。
自己一致(真摯な態度)
偽りなく、ありのままの自分で相手と向き合うことを指します。表面的な技術としてではなく、心の底から相手に関心を持ち、誠実な姿勢で接することが、真の信頼関係を築く上で最も重要です。
共感的理解(相手の立場に立つ)
相手の感情や考えを、まるで自分のことのように理解しようと努めることです。「もし自分が相手の立場だったらどう感じるだろう?」と想像力を働かせ、相手の目線で物事を捉える姿勢が不可欠となります。
無条件の肯定的関心(評価しない)
相手がどのような感情や考えを抱いていても、それを善悪や好き嫌いで判断せず、そのまま受け入れることを意味します。相手の存在そのものを尊重し、受容する心が傾聴の根幹を成します。
ビジネスにおける傾聴の活用シーンとメリット
ビジネスにおいて、傾聴は多岐にわたる場面でその真価を発揮し、組織のパフォーマンス向上に直結します。
部下育成・マネジメント
部下の悩みや本音に耳を傾け、信頼関係を築くことで、彼らの潜在能力を引き出し、自律的な成長を促します。1on1ミーティングなどで傾聴を実践することは、適切なアドバイスやサポートに繋がり、エンゲージメント向上にも貢献します。
チームビルディング・組織活性化
メンバー全員が安心して意見を言える心理的安全性の高い環境を作り出すことが可能です。これにより、活発な議論が生まれ、チーム全体のコミュニケーションと生産性が向上します。異なる意見も尊重される文化が醸成されるでしょう。
顧客対応・営業
顧客の表面的な要望だけでなく、その背景にある真のニーズを傾聴によって深く把握することで、より顧客に寄り添った最適な提案が可能となります。これは顧客満足度を飛躍的に高め、長期的な信頼を獲得する上で不可欠です。
ハラスメント対策や相談窓口
相談者が安心して話せるよう、共感的な傾聴で受け止めることが極めて重要です。安易な評価やアドバイスをせず、まずは相手の気持ちに寄り添うことで、相談者は安心して自身の問題と向き合い、解決への第一歩を踏み出すことができます。
傾聴を習得するメリットと効果的な学習方法
傾聴を身につけることは、個人的なコミュニケーション能力の向上だけでなく、キャリア形成や組織全体の活性化にも大きく貢献します。
習得するメリット
人間関係の改善:
プライベート・ビジネス問わず、周囲との信頼関係が深まり、より円滑なコミュニケーションを築けるようになります。
リーダーシップの向上:
管理職やリーダーは、部下の本音を引き出し、モチベーションを高めることで、より効果的なリーダーシップを発揮できます。
問題解決能力の向上:
相手の真の課題を理解することで、より本質的な問題解決に導くことができます。
自己成長の促進:
他者の多様な価値観に触れ、共感することで、自身の視野を広げ、人間的な深みを増すことができます。
効果的な学習方法傾聴は座学で理論を学ぶだけでなく、実践的なトレーニングが不可欠です。
専門研修・セミナーへの参加:
社内研修や外部の専門家が開催するセミナーに参加し、体系的な知識と実践的なロールプレイングを通じてスキルを磨きます。
書籍・オンライン教材での学習:
傾聴に関する書籍やオンライン教材で基礎知識を習得し、様々なケーススタディから学びを深めます。
日常での意識的な実践:
最も重要なのは、日々のコミュニケーションの中で意識的に傾聴を実践することです。家族や友人、同僚との会話で、うなずきや言い換え、沈黙への対応などを試み、その効果を振り返りながら改善していきます。
コーチング・カウンセリングスキルの学習:
より専門的なコーチングやカウンセリングのスキルを学ぶことで、自身の傾聴力をより深く、多角的に発展させることができます。
傾聴を行う上での重要な注意点
傾聴は強力なツールですが、その実践にはいくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておくことで、より効果的かつ倫理的に傾聴を進めることができます。
形だけの傾聴は逆効果
単なるテクニックをなぞるだけでは、傾聴は効果を発揮しません。最も大切なのは、相手への共感と温かさが伴っていることです。心のない傾聴は、かえって相手に不信感を与えかねません。
自分の責任範囲を意識する
相手の話を聞く中で、自分の責任範囲を超えた問題であると判断した場合は、無理に抱え込まず、適切な専門部署や専門機関への橋渡しを検討することも重要です。全ての解決を一人で背負い込む必要はありません。
聴き手自身の心のケア
深く相手の感情に寄り添う傾聴は、聴き手にとってもエネルギーを消耗する行為です。相手の感情に引きずられすぎないよう、自身の心のケアを意識することが不可欠です。疲労が蓄積しないよう、適度な休息や気分転換を心がけましょう。
守秘義務の遵守傾聴
によって得た情報は、極めて個人的な内容を含むことがあります。安易に他言せず、守秘義務を遵守することは、信頼関係を維持する上で最も基本的なルールです。細心の注意を払う必要があります。
これらの注意点を踏まえ、倫理観と自己認識を持って傾聴に臨むことが、その効果を最大化し、健全な関係性を築く上で不可欠です。
まとめ
傾聴は、単に相手の話を聞き流すのではなく、耳・目・心のすべてを使って相手の内面を深く理解しようとする、極めて人間味あふれるコミュニケーション技術です。心理学者カール・ロジャーズが提唱した三原則(自己一致、共感的理解、無条件の肯定的関心)を土台に、うなずきや質問、言い換えなどの具体的なテクニックを実践することで、その真価が発揮されます。
ビジネスシーンにおいては、部下育成、チームビルディング、顧客対応、そしてハラスメント対策など、多岐にわたる場面で傾聴力が求められ、組織の生産性向上と強固な信頼関係構築に不可欠なスキルなのです。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

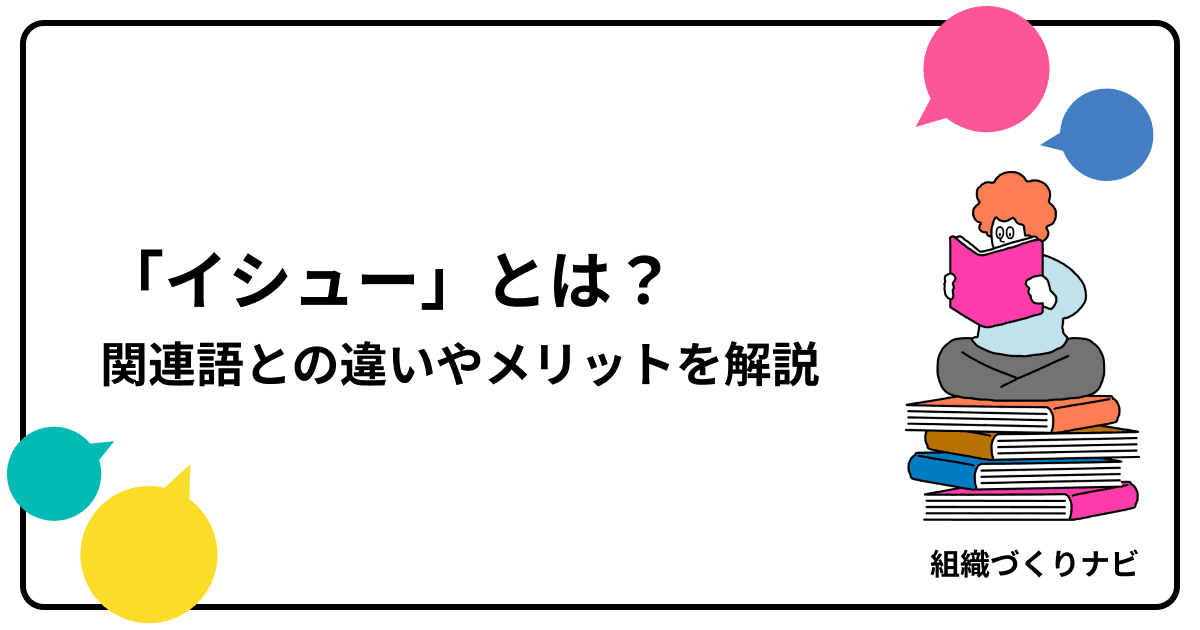
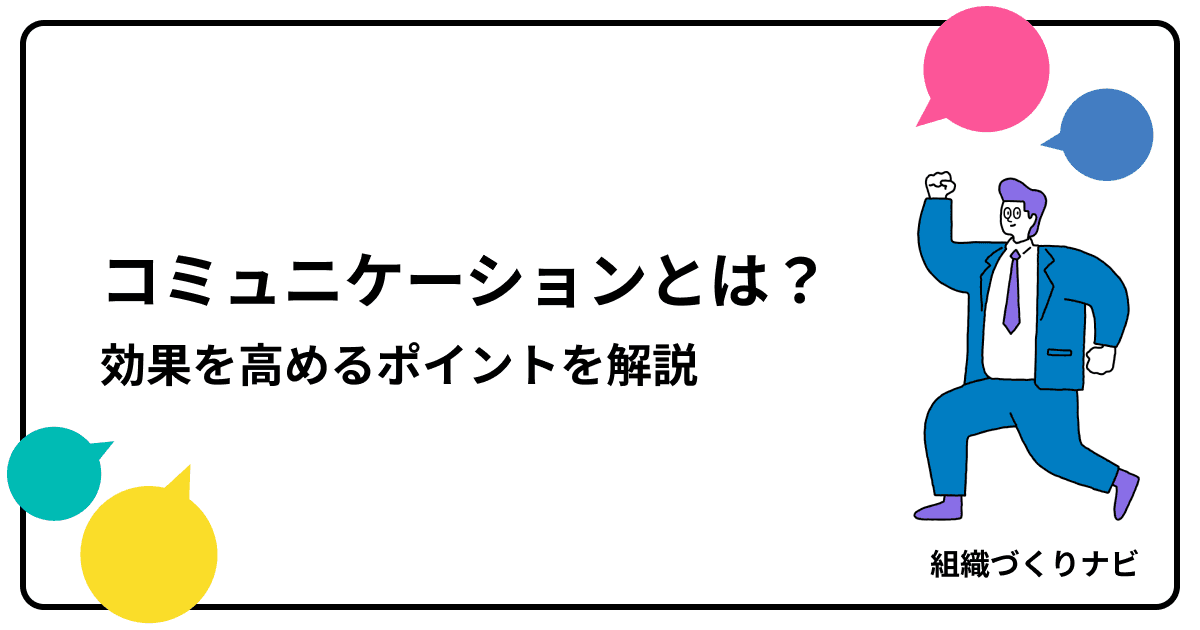
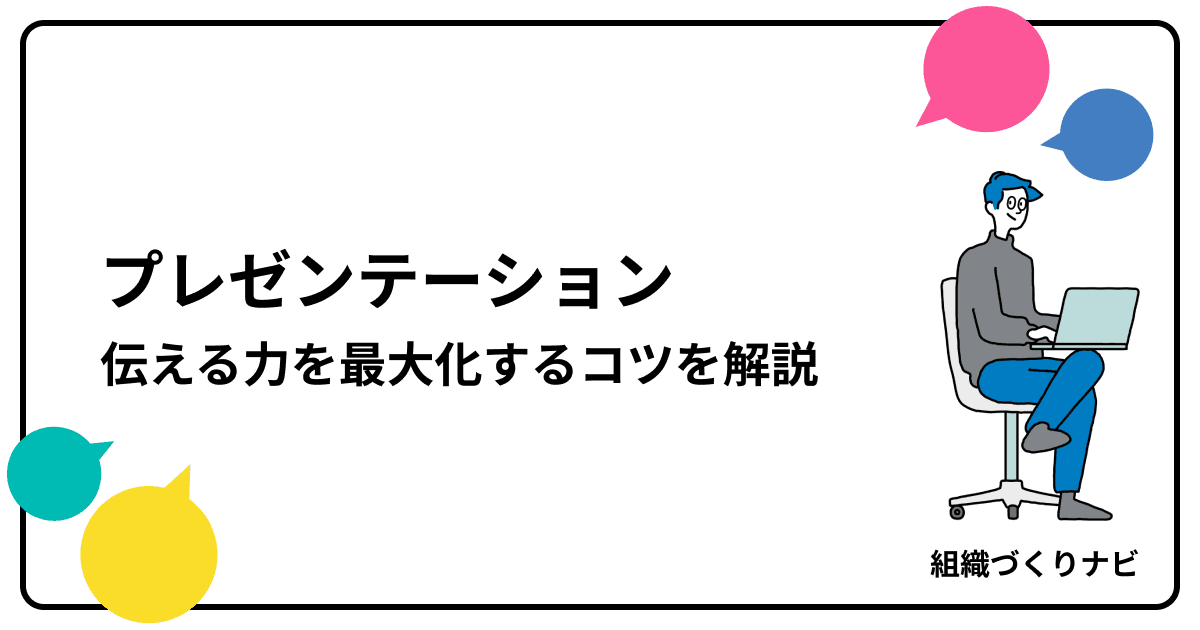
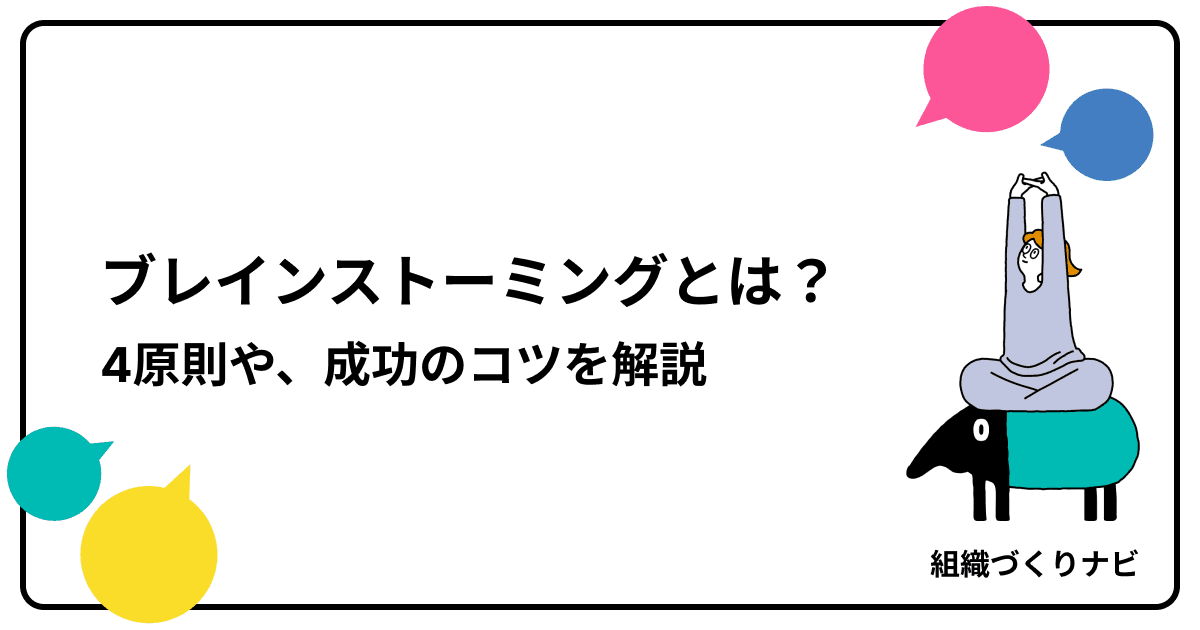
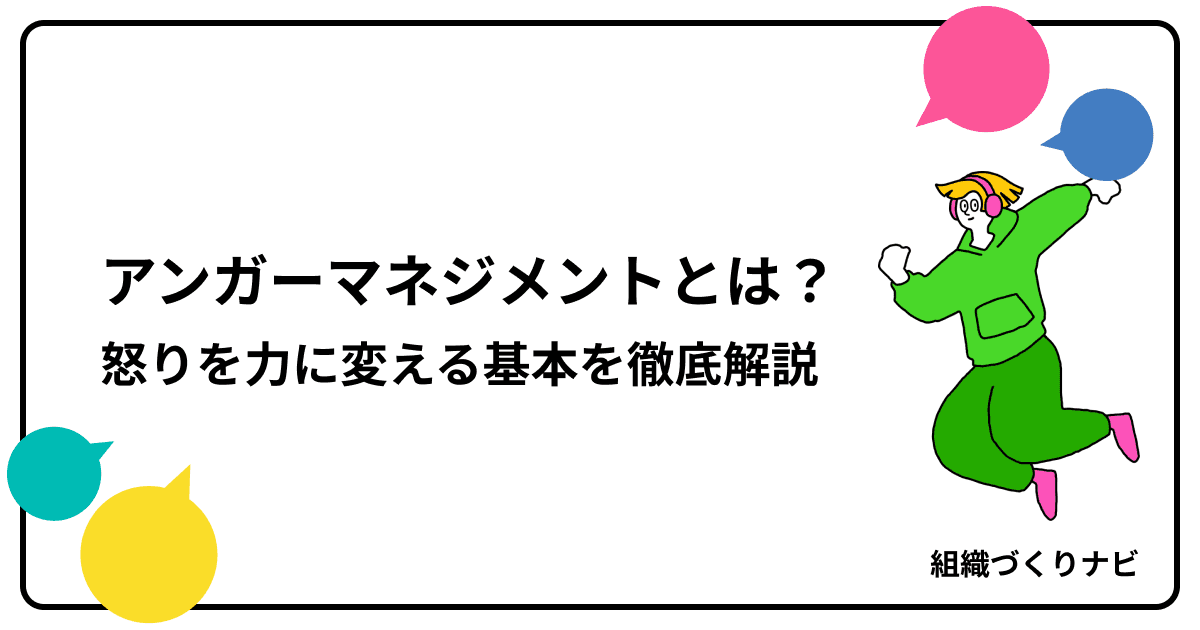
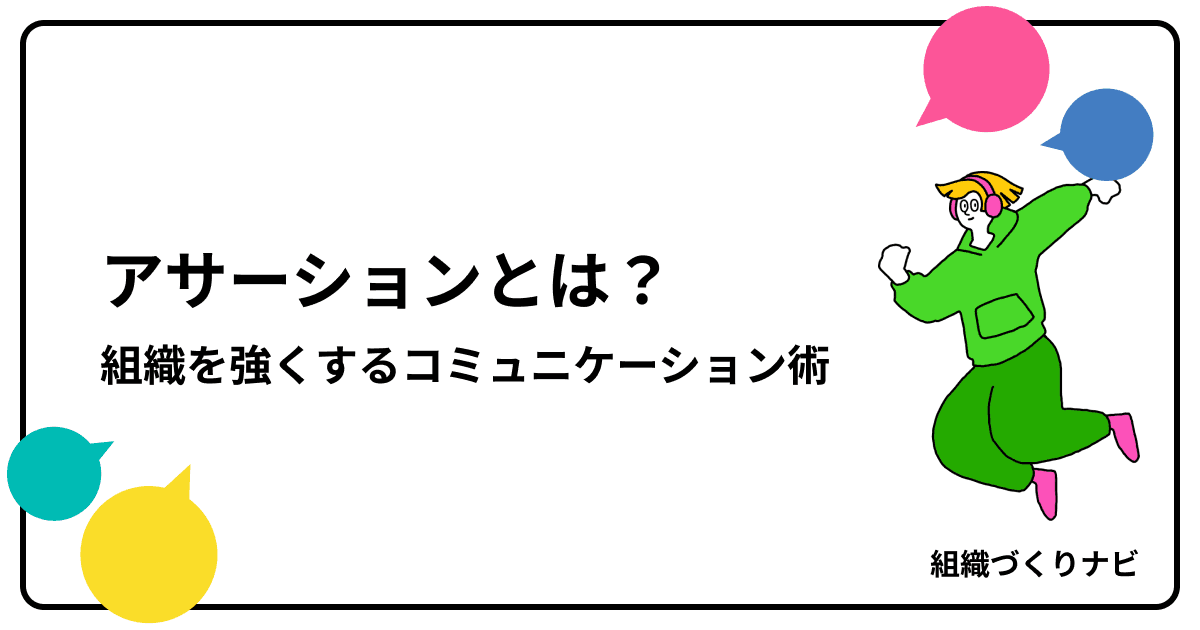



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


