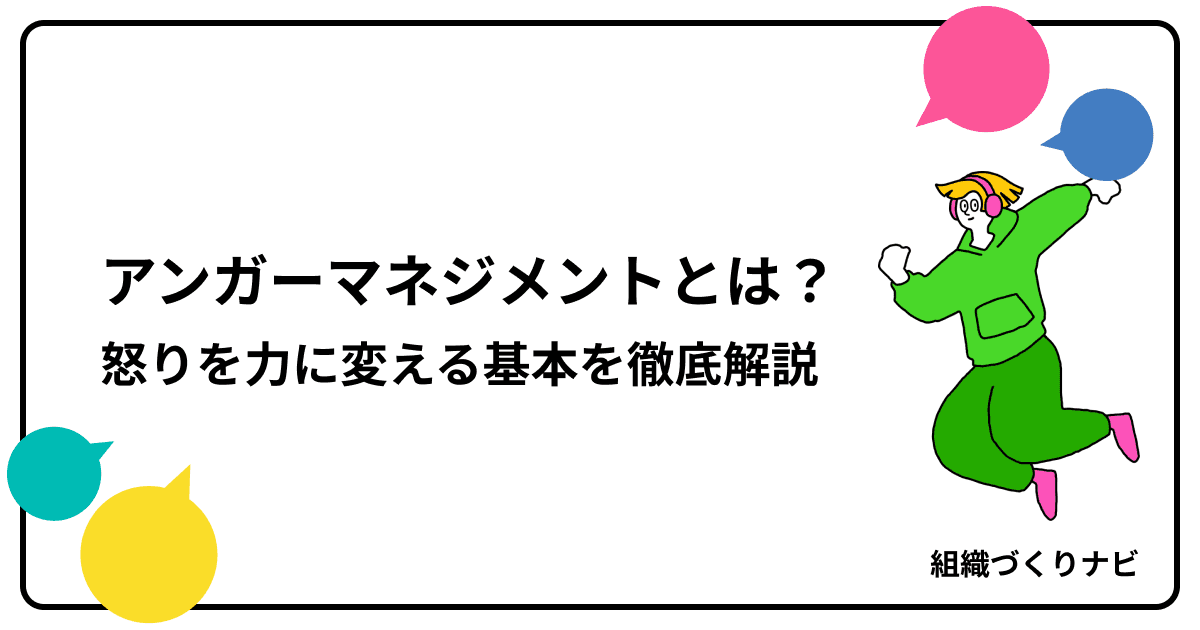
「アンガーマネジメント」とは?職場の怒りを力に変える基本を徹底解説
職場のイライラや衝突に悩む人事・管理職の方へ。アンガーマネジメントは、怒らないことではなく、怒りの感情と上手に付き合い、建設的に表現するための心理スキルです。本記事では、怒りのメカニズムや「べき論」との関係、「怒りの6秒ルール」を解説。ハラスメント予防やチーム力向上に不可欠な理由を掘り下げ、衝動をコントロールする実践テクニックやアンガーログによる自己分析法も紹介します。自身の怒りの傾向を知り、感情を客観視することで、ストレスを軽減し、健全で生産性の高い職場環境と風通しの良い企業文化を実現するヒントが満載です。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
職場の「イライラ」を解消し、生産性を高めるアンガーマネジメントの力
日々の業務で「ついついイライラしてしまう」「部下や同僚との衝突が多い」「自分の感情がコントロールできず、後で後悔する」といった悩みを抱える人事担当者や管理職の方は少なくないでしょう。職場の人間関係の悩みやハラスメント問題の背景には、「怒り」の感情が関係していることが多くあります。しかし、アンガーマネジメントは「怒らないこと」ではありません。この記事では、怒りの感情と上手に付き合い、建設的に表現するための心理トレーニング「アンガーマネジメント」について、その基本から具体的な実践方法までを解説します。この記事を読むことで、あなた自身のストレス軽減はもちろん、より円滑な人間関係を築き、健全で生産性の高い職場環境を実現するためのヒントが得られるでしょう。
アンガーマネジメントとは?「怒らない」のではなく「怒りと向き合う」心理スキル
アンガーマネジメントは、1970年代にアメリカで生まれた、怒りの感情を上手に管理するための心理トレーニングです。このスキルは、怒りの感情そのものをなくすのではなく、怒りの衝動をコントロールし、建設的な方法で表現できるようになることを目的としています。私たちは「怒ってはいけない」と思いがちですが、怒りは人間が持つ自然な感情の一つであり、時として重要なサインとなることもあります。アンガーマネジメントを学ぶことで、怒りの感情に振り回されることなく、冷静かつ適切に対処する力が身につきます。また、怒りの根底には、不安や悲しみ、落胆などの「第一次感情」が隠れていることが多く、怒りはそれらが表面化した「第二次感情」であるというメカニズムを理解することも重要です。
なぜ今、職場でアンガーマネジメントが不可欠なのか?ハラスメント予防からチーム力向上まで
現代社会において、アンガーマネジメントはますますその重要性を増しています。特に職場においては、パワハラやモラハラといったハラスメント問題が深刻化する中で、怒りの感情を適切に管理するスキルは、良好な人間関係を築き、健全な職場環境を維持するために不可欠です。管理職の方々にとっては、自身の感情をコントロールして部下との信頼関係を築き、冷静な判断を下すことで、チームの生産性向上や従業員満足度の向上に直結します。個人のストレス軽減にも繋がり、心身の健康を保つ上でも役立ちます。アンガーマネジメントは、個人のウェルビーイング向上だけでなく、組織全体のエンゲージメントを高め、風通しの良い企業文化を醸成する強力なツールとなるのです。
関連する参考記事
また、振り返り会が愚痴を言い合う場になってしまったケースもありました。その時は、一度意見を否定せずに受け止めるように心がけ、その後で改善策をみんなで話し合うようにしました。それによって、以前より建設的な意見が出やすくなったと思っています。
建設的な意見が出ることで、身近な業務からの改善に取り組むことができました。当たり前にやっていたチェック作業の一つが無駄な業務だということに気づき、大幅に時間を削減できた事例がありました。

関連する参考記事
前田: あとはエンゲージメントアンバサダーのメンバーに、各施策を進める上での注意点などを助言してきました。例えば、「座談会が、ただの愚痴大会になると意味が無いので、次に繋がる建設的な意見を出し合う場にすること」とか、「出てきた各意見は、ただ聞くだけではなくて、きちんと改善・解決に向けて動かないと逆効果になる」とかですね。
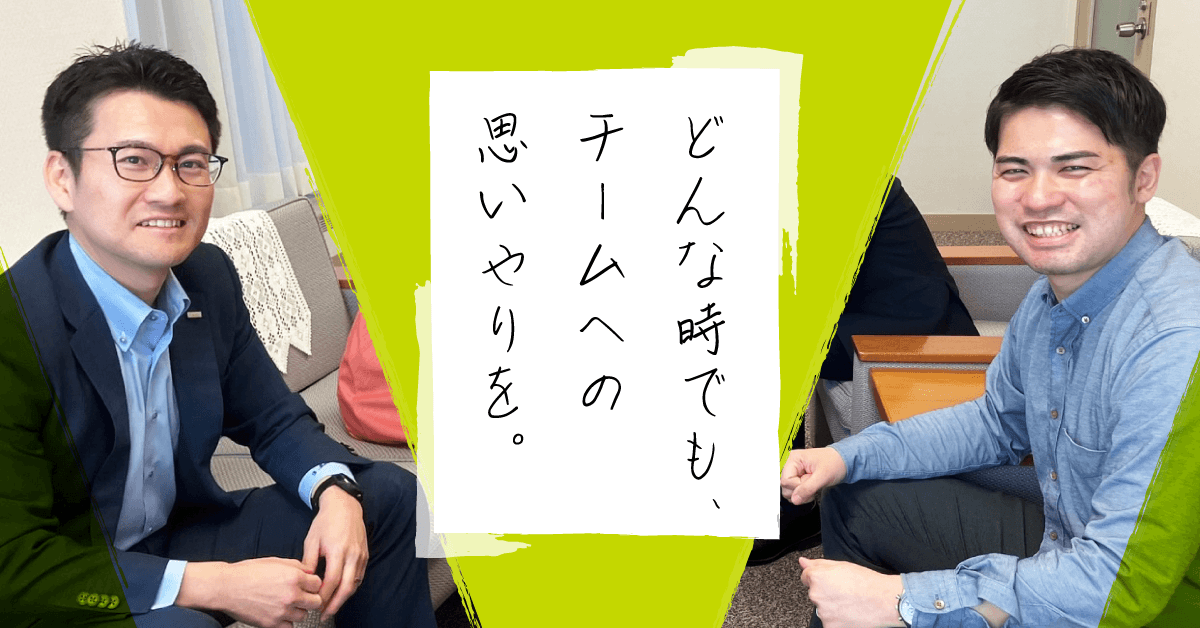
怒りの感情を客観視する:知っておきたい怒りのメカニズムと「6秒ルール」
怒りの感情がどのように発生するかを知ることは、それをコントロールする上で非常に重要です。私たちの怒りの多くは、「〜するべきだ」「〜であるべきだ」といった自分の中の強い「べき論」が裏切られたときに生じやすいと言われています。例えば、「部下は上司の指示に従うべきだ」「会議は時間通りに始まるべきだ」といった固定観念が崩れると、不満や不快感が増し、それが怒りへと発展することがあります。また、怒りの衝動は、実はそれほど長く続かないという事実も知っておきましょう。脳科学の研究では、怒りのピークは一般的に約6秒程度で収まるとされており、これを「怒りの6秒ルール」と呼びます。この短期間を冷静にやり過ごすことが、感情的な反応を避ける第一歩となるのです。
今日からできる!職場でのアンガーマネジメント実践テクニック
怒りの感情に効果的に対処するための実践的なテクニックをいくつかご紹介します。これらは職場でもすぐに実践できるものばかりです。
「怒りの6秒ルール」を乗り切る方法:
怒りを感じたら、すぐに反応せず、
心の中で6秒数える
、深呼吸を3回する、その場を少し離れる(トイレ休憩など)、
「ストップ!」と心の中で唱えて思考を止める
など、時間を稼ぐ行動を取りましょう。会議中や商談中でも実践できる簡単な工夫です。
「べき」を手放す/許容範囲を広げる:
自分の「べき」が常に正しいわけではないと認識し、
多様な価値観や状況を受け入れる柔軟性
を持つことが大切です。特に職場では、異なる世代やバックグラウンドを持つ人々が集まるため、「こうでなくても良い」と許容範囲を広げることが、衝突の予防に繋がります。
怒りの感情を客観視する:
怒りの度合いを
0点から10点の尺度で評価する
練習をしてみましょう。「今、自分は6点の怒りを感じているな」と点数化することで、感情を少し冷静に捉え、客観視できるようになります。これにより、衝動的な行動を抑える一助となります。
クールダウン方法を見つける:
ストレス解消法として、運動、音楽鑑賞、瞑想、読書など、
自分に合った気分転換の方法
を複数見つけておきましょう。怒りを感じた時にすぐに使える「心の逃げ場」を持つことが、冷静さを保つ上で非常に重要です。職場でできる簡単なストレッチや、席を立って水を飲むだけでも効果があります。
アンガーログ(怒りの記録):
怒りを感じた状況、強さ(点数)、原因、その時どう対処したかなどを記録する「アンガーログ」をつけることで、
自分の怒りのパターンや傾向を客観的に把握
し、予防策を立てるのに役立ちます。特に、どんな状況で怒りを感じやすいかを知ることは、職場での人間関係を改善する上で大きなヒントになります。
自分の「怒りの傾向」を知り、より効果的に感情をコントロールする
自身の怒りの傾向を理解することは、適切な対処法を見つける上で非常に有効です。アンガーマネジメントでは、怒りのタイプをいくつか分類することがあります。例えば、「正義感が強く、不公平を許せない公明正大タイプ」や、「完璧主義で、知識不足や非効率を嫌う博学多才タイプ」、「人間関係の調和を重んじ、波風を立てることを嫌うがゆえに鬱積しやすい八方美人タイプ」などがあります。自身のタイプを知ることで、「なぜ自分はこんなに怒りやすいのか」という疑問に答えが見つかり、タイプに合わせた具体的な対策を立てやすくなります。簡単なチェックリストを活用したり、専門の講座で自己分析を深めたりすることで、自身の怒りの感情とより深く向き合う第一歩を踏み出せるでしょう。
まとめ:感情を力に変え、より良い職場環境を築きましょう
この記事では、アンガーマネジメントが「怒らないこと」ではなく、「怒りの感情と上手に付き合い、建設的に表現するスキル」であることをご紹介しました。職場のハラスメント防止、良好な人間関係の構築、ストレス軽減、生産性向上など、その必要性は多岐にわたります。怒りのメカニズムを理解し、「6秒ルール」や「べき論の見直し」、そして「アンガーログ」といった具体的な実践テクニックを取り入れることで、あなたは感情に振り回されることなく、より穏やかで前向きな日常を送ることができるようになります。この知識を活かし、ぜひ今日から実践してみてください。あなた自身と職場の未来のために、怒りの感情と上手に付き合う最初の一歩を踏み出し、リーダーシップを発揮することで、従業員のウェルビーイング向上に貢献しましょう。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

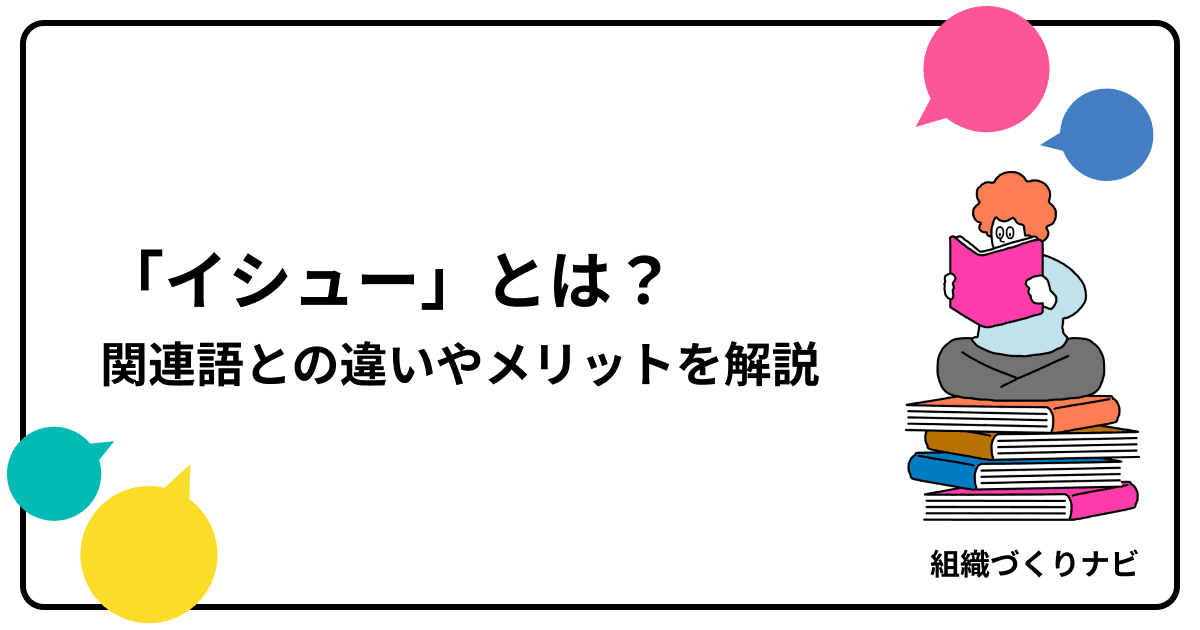
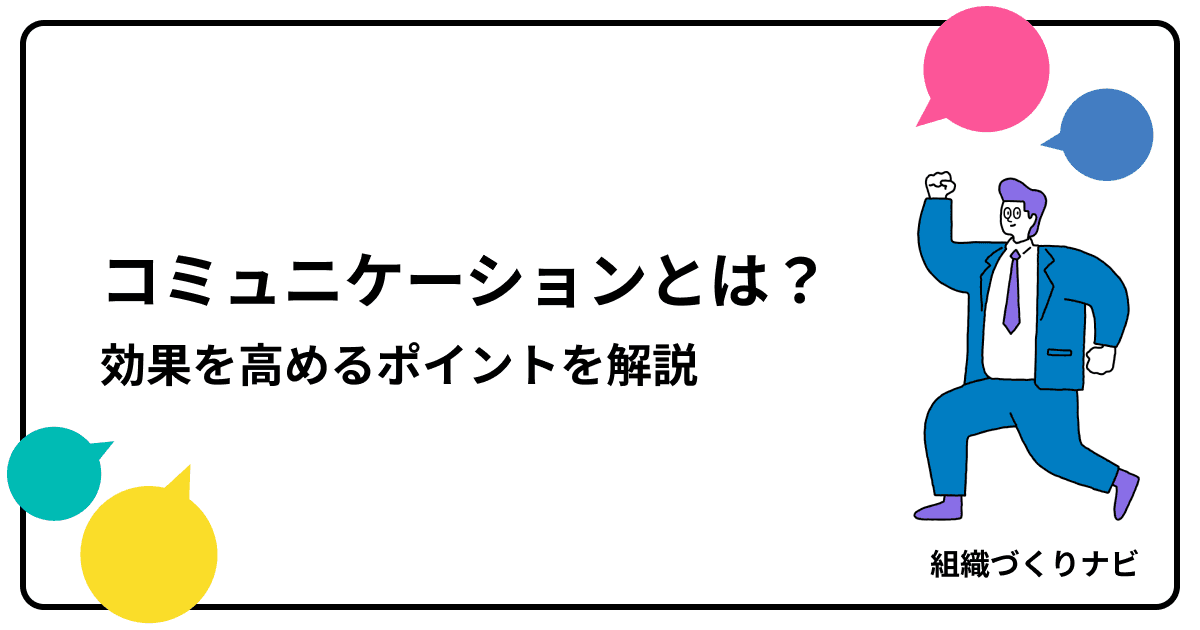
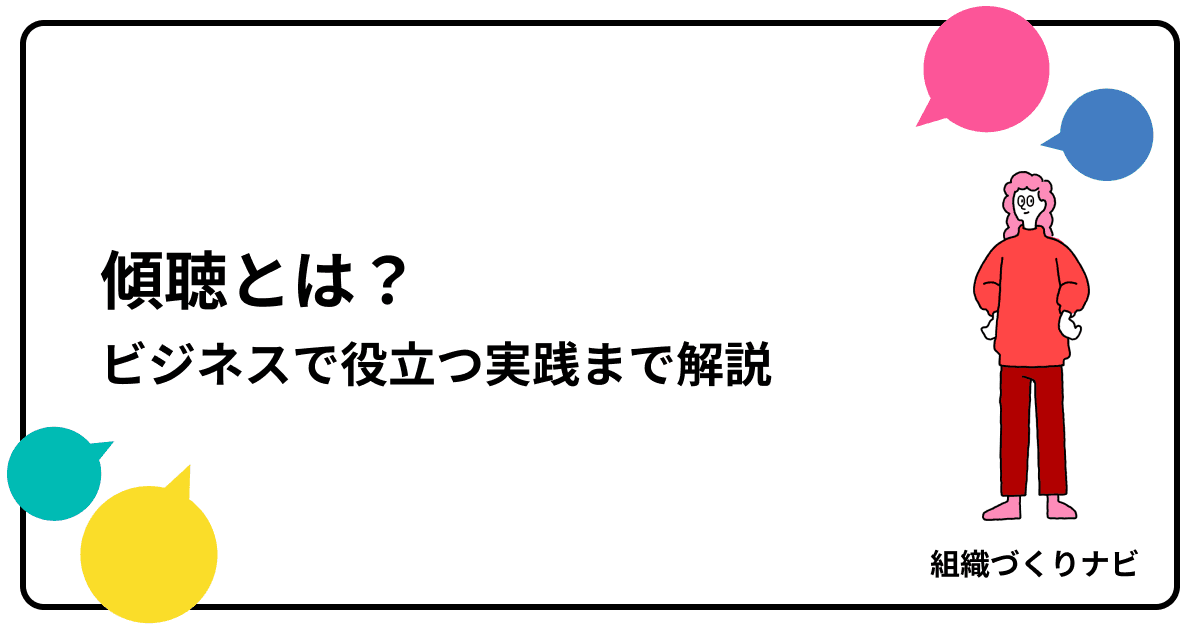
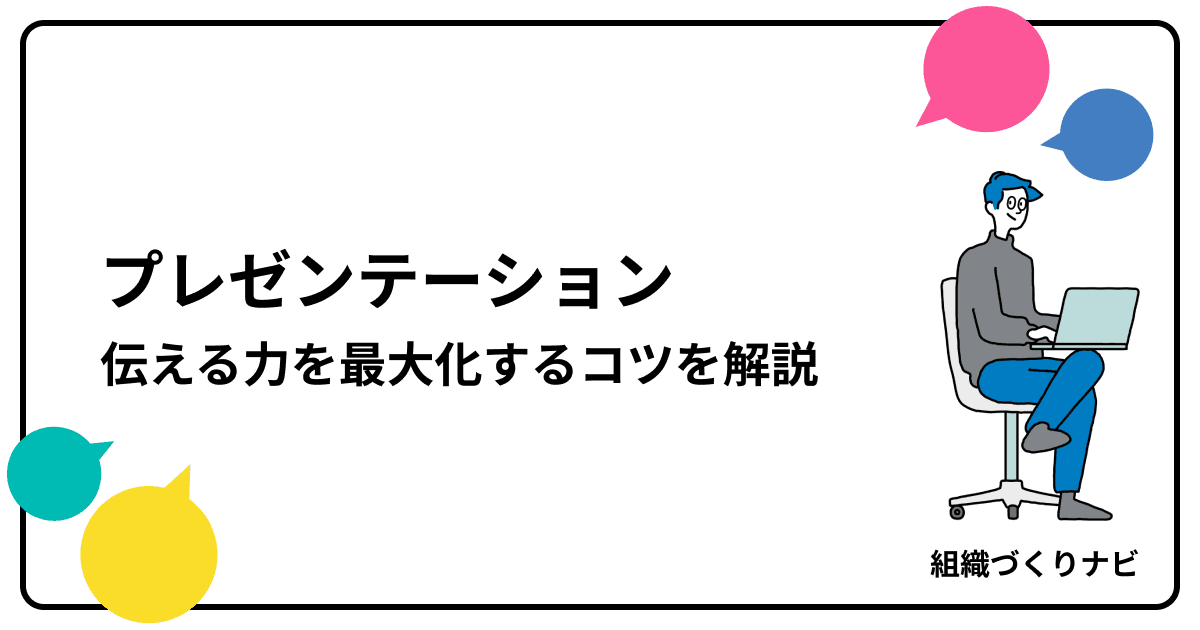
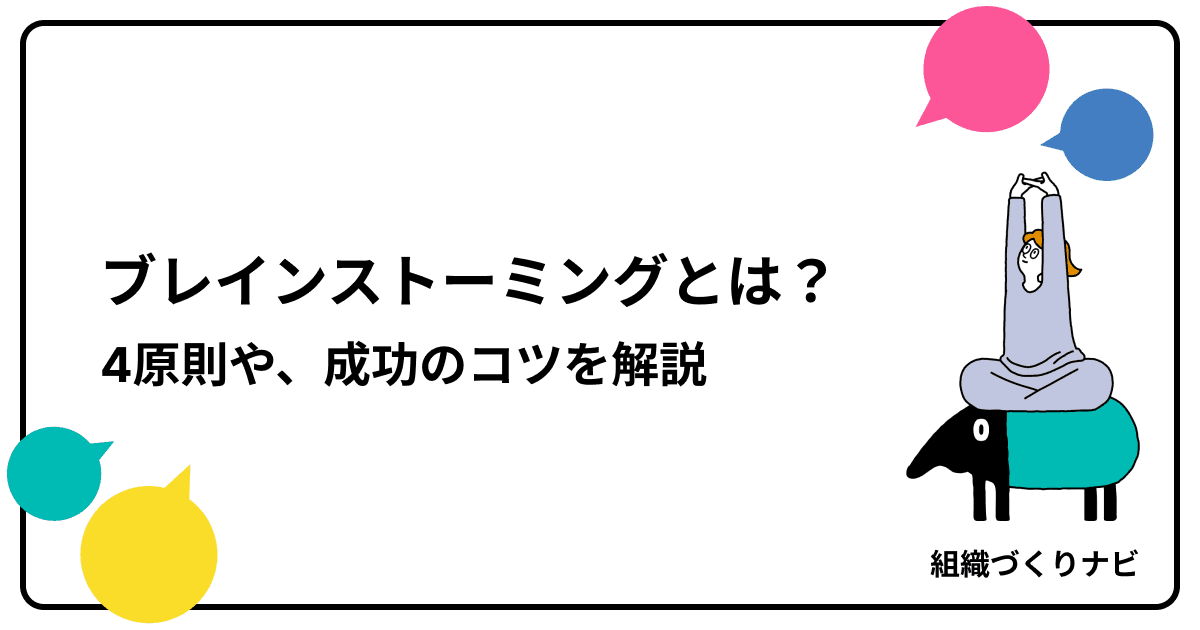
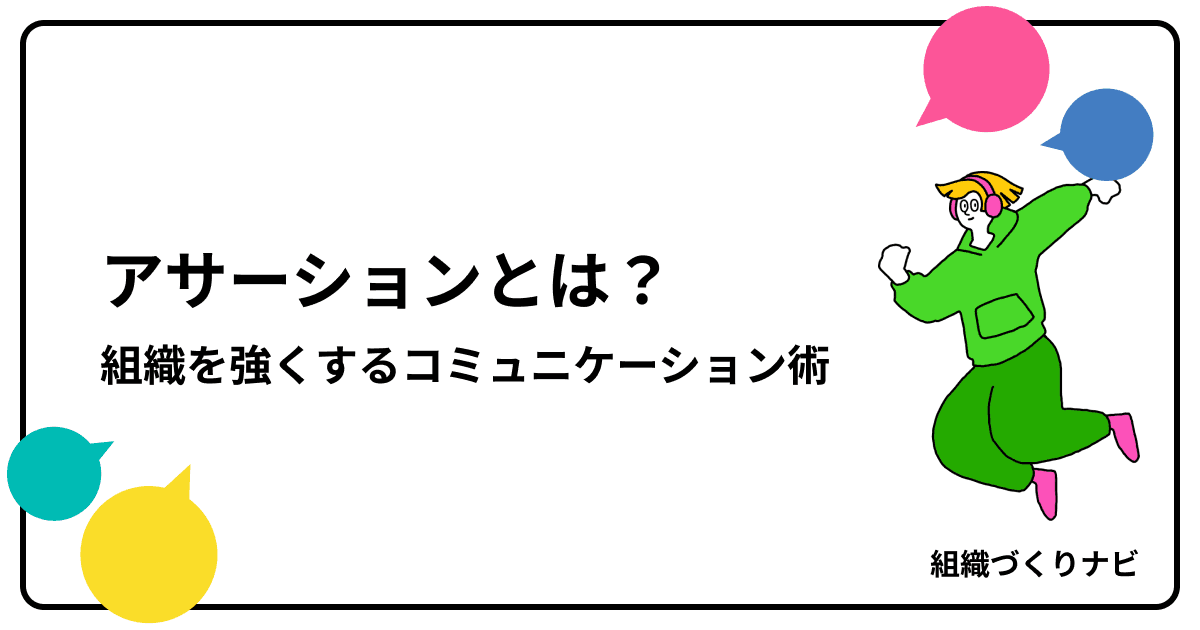



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


