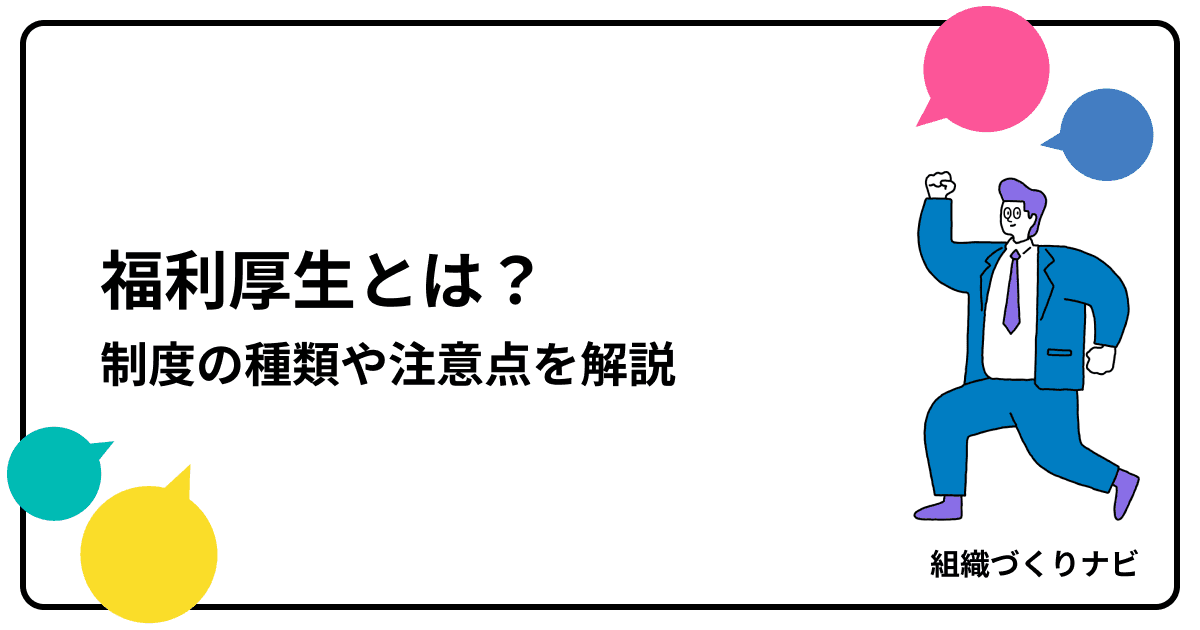
福利厚生とは?企業成長に欠かせない制度を種類・メリット・注意点まで解説
福利厚生は、企業が従業員とその家族のために提供する給与以外の制度やサービスの総称です。単なる費用ではなく、企業の競争力強化や持続的な成長を促す戦略的な「投資」として重要視されています。本記事では、健康保険や厚生年金などの「法定福利厚生」と、住宅手当や自己啓発支援といった企業独自の「法定外福利厚生」の2種類を徹底解説。採用力強化や離職率低下、生産性向上といった導入メリットから、コストや運用負担といったデメリット、導入目的の明確化や従業員ニーズの把握といった運用時の注意点まで、人事・管理職の皆様が福利厚生制度を効果的に設計・活用するための情報を網羅的にご紹介します。自社に最適な福利厚生を見つけ、従業員と企業の未来を支える基盤を構築しましょう。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
福利厚生とは?企業と従業員を支える大切な制度を徹底解説
企業を経営する上で、従業員の皆様が安心して、そして意欲的に働ける環境を整えることは非常に重要です。そのために「給与」や「賞与」とは別に、会社が従業員やその家族のために提供するさまざまな制度やサービスの総称が福利厚生です。単なる「コスト」や「おまけ」ではなく、企業の魅力や競争力を高め、従業員満足度や生産性の向上に大きく貢献する、企業成長への戦略的な「投資」と言えます。
人事や管理職の皆様は、福利厚生について深く理解し、自社に最適な形で導入・運用することで、優秀な人材の獲得や離職率の低下、さらには企業全体の活性化へとつなげることが可能です。本記事では、福利厚生の基本から種類、導入のメリット・デメリット、そして運用時の注意点まで、分かりやすく解説してまいります。
福利厚生の種類:法定福利厚生と法定外福利厚生
福利厚生には、法律で定められた「法定福利厚生」と、企業が独自に提供する「法定外福利厚生」の2種類があります。この違いを理解することが、福利厚生制度を検討する上での第一歩です。
法定福利厚生とは?
法定福利厚生は、国が法律によって企業に導入を義務付けている制度です。これは、従業員が病気や怪我、失業、老齢になった際などに、最低限の生活を保障するための社会保障制度の一環として位置づけられています。企業はこの制度を導入し、従業員と共に保険料を負担することが義務付けられています。
主な法定福利厚生には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険、子ども・子育て拠出金があります。これらの費用は、健康保険法や厚生年金保険法などの関連法規に基づき、企業と従業員がそれぞれ定められた割合で負担するのが一般的です(労災保険料や子ども・子育て拠出金は基本的に全額企業負担)。これらはすべての企業にとって必須の項目であり、導入しない選択肢はありません。
法定外福利厚生とは?
法定外福利厚生は、法律で定められておらず、企業が任意で提供する福利厚生全般を指します。企業の理念や従業員のニーズに合わせて、非常に多種多様な制度が存在するのが特徴です。これらは、従業員の生活の質を高めたり、スキルアップを支援したり、ワークライフバランスを向上させたりすることを目的として導入されます。
具体的な例としては、通勤手当、住宅手当、食事補助、健康診断の補助、育児・介護支援制度(ベビーシッター補助など)、自己啓発支援(資格取得費用補助、研修費用補助)、財産形成支援(従業員持株会、確定拠出年金など)、慶弔見舞金、リフレッシュ休暇、社員旅行やレクリエーションなどが挙げられます。また最近では、リモートワーク手当、副業支援、ワーケーション手当など、多様な働き方に対応した制度も増えてきています。法定外福利厚生は、企業の個性や魅力を打ち出し、従業員にとって働きやすい環境を構築する上で非常に重要な役割を果たします。
福利厚生を導入するメリット・デメリット
福利厚生制度の導入は、企業と従業員の双方にとって多くのメリットをもたらしますが、同時にデメリットも存在します。これらを理解し、バランスの取れた制度設計を行うことが成功の鍵です。
企業が福利厚生を導入するメリット
企業にとっての最大のメリットは、採用力強化と従業員の定着率向上です。魅力的な福利厚生は、求職者にとって企業選びの重要な要素となり、優秀な人材の獲得につながります。特に、給与水準が同程度の競合他社と比較された際、福利厚生の充実度が差別化要因となり得ます。また、既存従業員のモチベーションやエンゲージメント(会社への愛着)を高め、長期的なキャリア形成を支援することで、離職率の低下に寄与します。結果として、従業員が安心して働くことで生産性の向上が期待でき、企業のブランドイメージ向上にもつながります。さらに、一部の法定外福利厚生費用は損金計上が可能なため、節税効果も期待できる場合があります。
福利厚生の導入・運用におけるデメリット
一方で、福利厚生の導入にはコストが発生する点がデメリットとして挙げられます。制度の維持・管理には費用と人手がかかり、特に多様な制度を導入するほどその負担は大きくなります。また、一度導入した制度を廃止する場合、従業員のモチベーション低下や不満につながる可能性があるため、慎重な検討が必要です。さらに、導入した福利厚生が従業員に十分に利用されず、費用対効果が見えにくいケースや、特定の制度が一部の従業員にしか利用されず、従業員間の利用格差が生じる可能性も考慮する必要があります。これらのデメリットを最小限に抑えるためには、事前の綿密な計画と定期的な見直しが不可欠です。
関連する参考記事
1つ目は、働きやすさのみを追求することの限界です。事業成長のスピードを上回るペースで福利厚生の充実が進み、最初こそみんな喜んでくれていましたが、次第にそれが当たり前になってしまいました。働きやすくはなりましたが、会社との関係性の希薄化によって、社員の主体性や、共同体感覚の喪失が少なからず起きていると考えています。現在では、経営を中心に「働きやすさと事業成長は両輪である」との考え方が浸透し始めて、働きやすさは重要だと捉えつつも、やりがいにフォーカスした働きがい推進への転換を図っているところです。
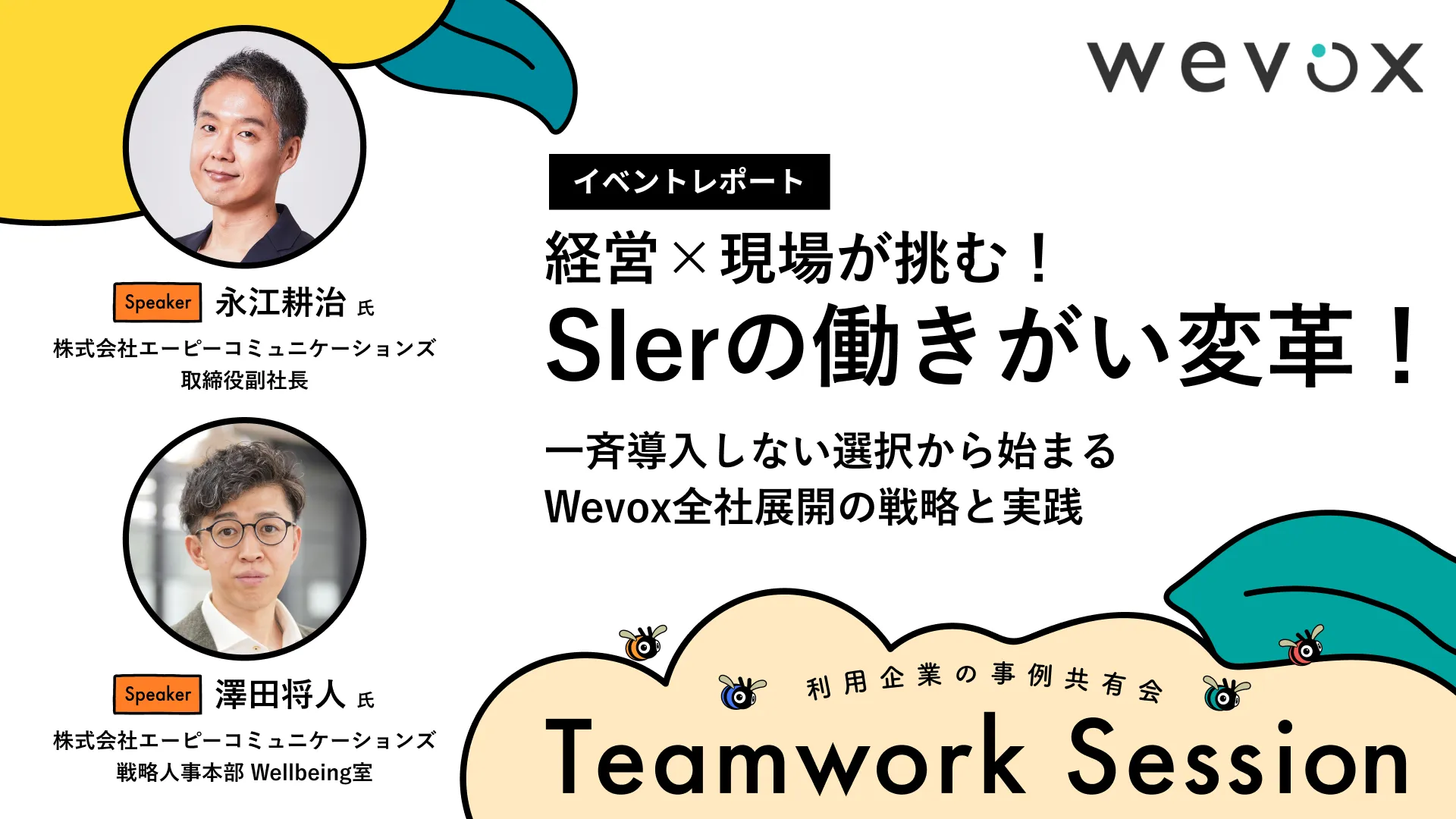
福利厚生を導入・運用する際の注意点
福利厚生制度を効果的に機能させるためには、単に導入するだけでなく、戦略的な視点を持って運用していくことが重要です。
まず、最も大切なのは福利厚生導入の目的を明確にすることです。「なぜこの制度を導入するのか」「導入によって何を達成したいのか(例:離職率10%削減、社員満足度15%向上など)」をはっきりとさせることで、費用対効果の高い制度設計が可能になります。次に、従業員のニーズを正確に把握することが欠かせません。アンケートやヒアリング、座談会などを通じて、従業員が本当に求めている福利厚生は何かを調査し、実態に即した制度を導入することで、利用率を高められます。時代や世代によってニーズは変化するため、定期的な調査が重要です。
また、導入した制度は従業員にしっかりと周知徹底する必要があります。どんなに良い制度があっても、知られていなければ意味がありません。社内報や説明会、イントラネット、定期的なメールマガジンなどを活用し、制度の内容や利用方法を丁寧に伝えることが大切です。特に、利用手続きが複雑でないかを確認し、利用しやすい仕組みを整えることも利用促進には不可欠です。最後に、社会情勢や従業員のライフスタイル、企業のフェーズの変化に合わせて、定期的に制度を見直し、改善していく柔軟な姿勢も求められます。陳腐化した制度は利用されなくなり、期待する効果が得られなくなってしまいます。
効果的な福利厚生の導入を検討するなら
福利厚生の導入や運用には、多大な時間と専門知識が必要となる場合があります。特に、中小企業や人事担当者のリソースが限られている企業では、自社ですべてを賄うのは難しいかもしれません。そのような場合に有効な選択肢となるのが、福利厚生代行サービスの活用です。
福利厚生代行サービスは、企業の代わりに福利厚生制度の企画・運営をサポートしてくれるサービスです。サービス提供会社が用意するパッケージプランを利用すれば、多岐にわたる福利厚生を効率的に導入でき、従業員は豊富なメニューから自分の好きなサービスを選べるカフェテリアプランも手軽に導入可能です。これにより、自社の運用負担を大幅に軽減しながら、専門的な知見に基づいた質の高い福利厚生を従業員に提供できます。コストはかかりますが、従業員満足度の向上や採用競争力の強化という側面から、費用対効果の高い「投資」として検討する価値は大いにあるでしょう。
まとめ
福利厚生は、単なる従業員へのサービスや義務的な費用ではありません。従業員の生活を支え、モチベーションを高め、企業へのエンゲージメントを深めることで、企業の競争力強化と持続的な成長を促すための戦略的な「投資」です。
法定福利厚生を遵守しつつ、自社の従業員のニーズに合致した法定外福利厚生を戦略的に導入・運用することは、優秀な人材の獲得・定着、生産性の向上、そして企業イメージの向上に直結します。導入・運用の際は、目的を明確にし、従業員のニーズを正確に把握し、効果的な周知と定期的な見直しを欠かさないことが鍵となるのです。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

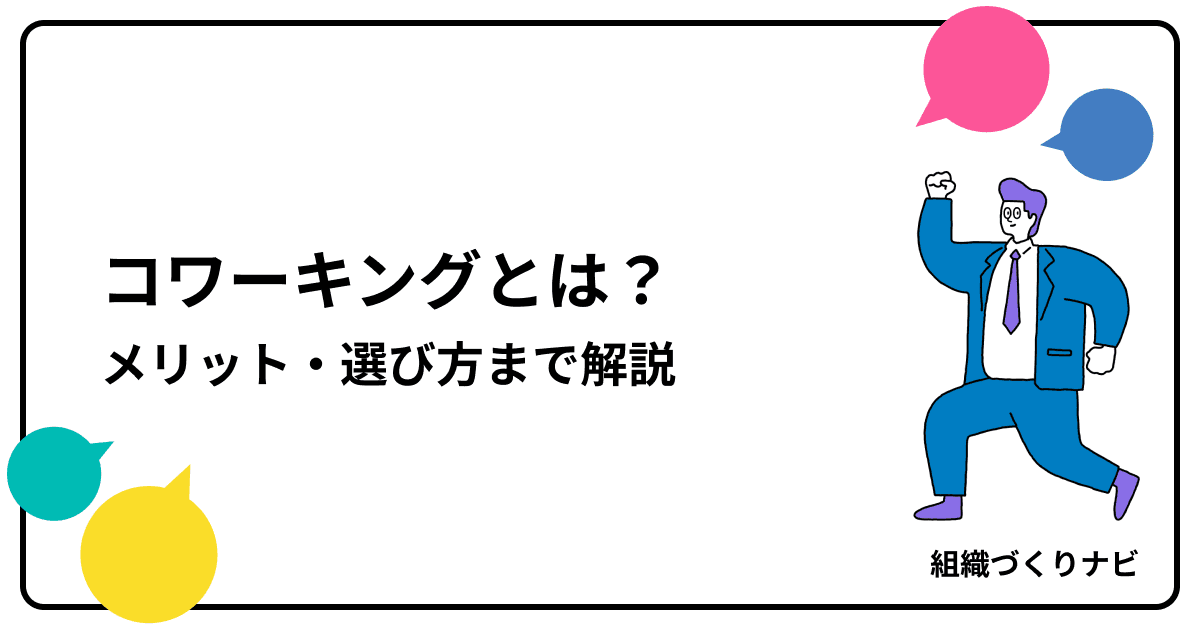
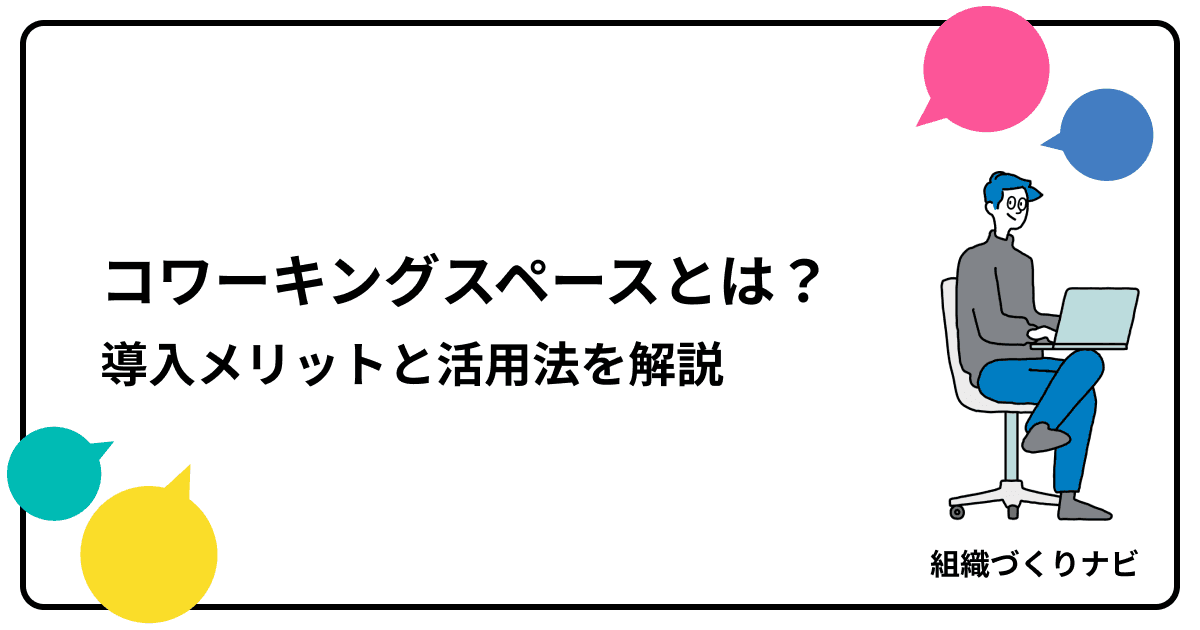
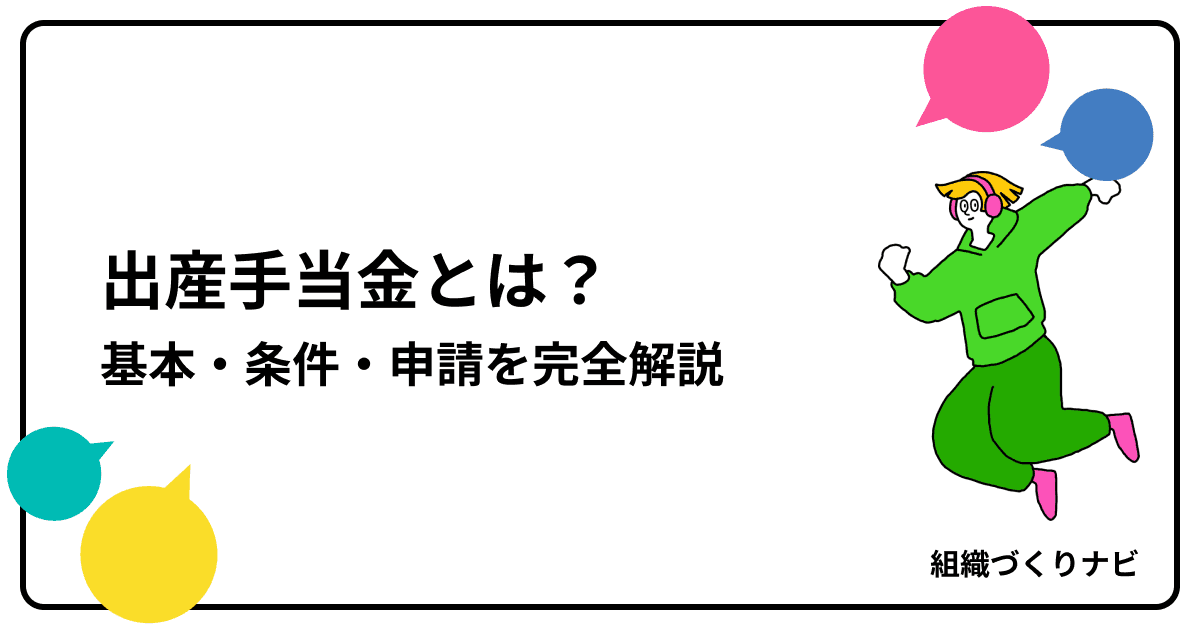
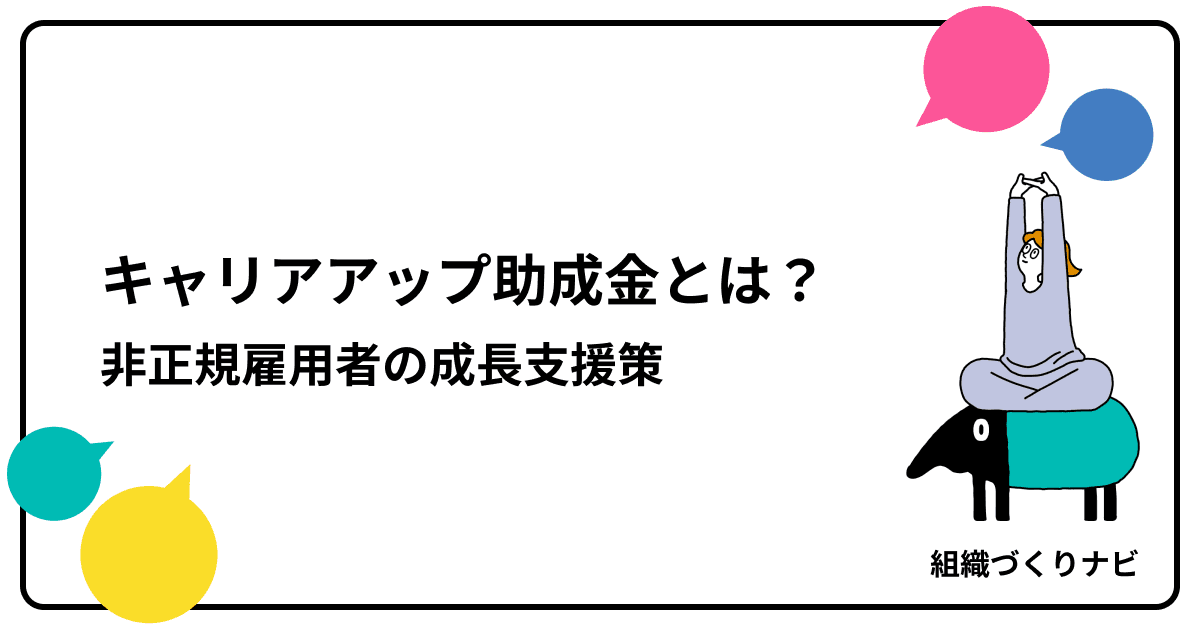
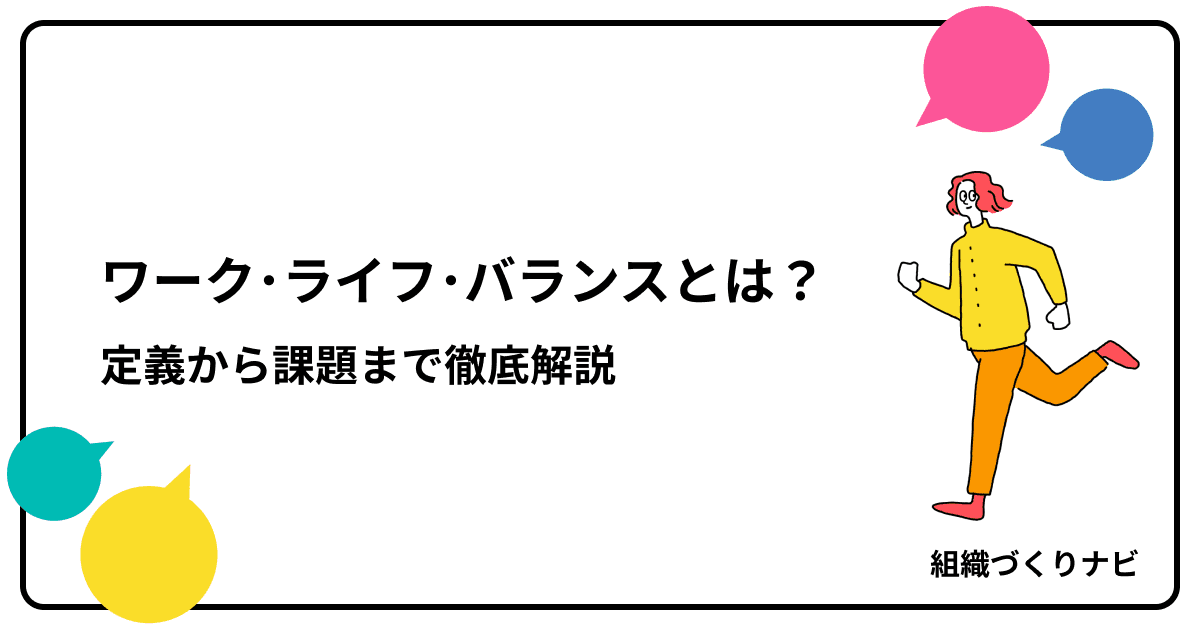
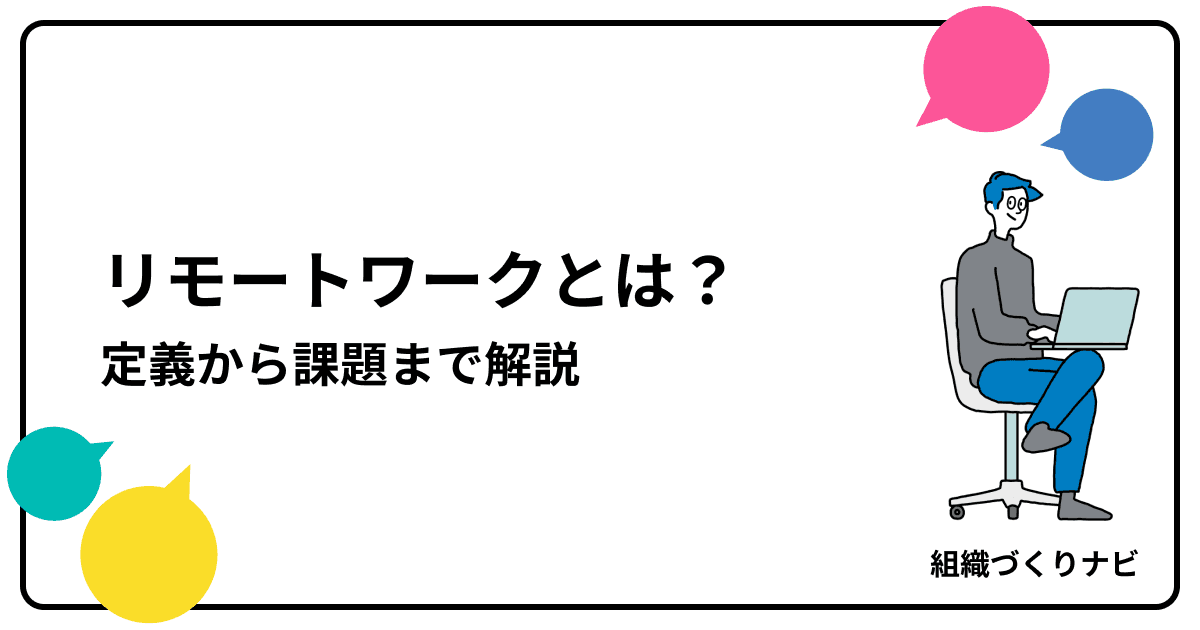



 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


