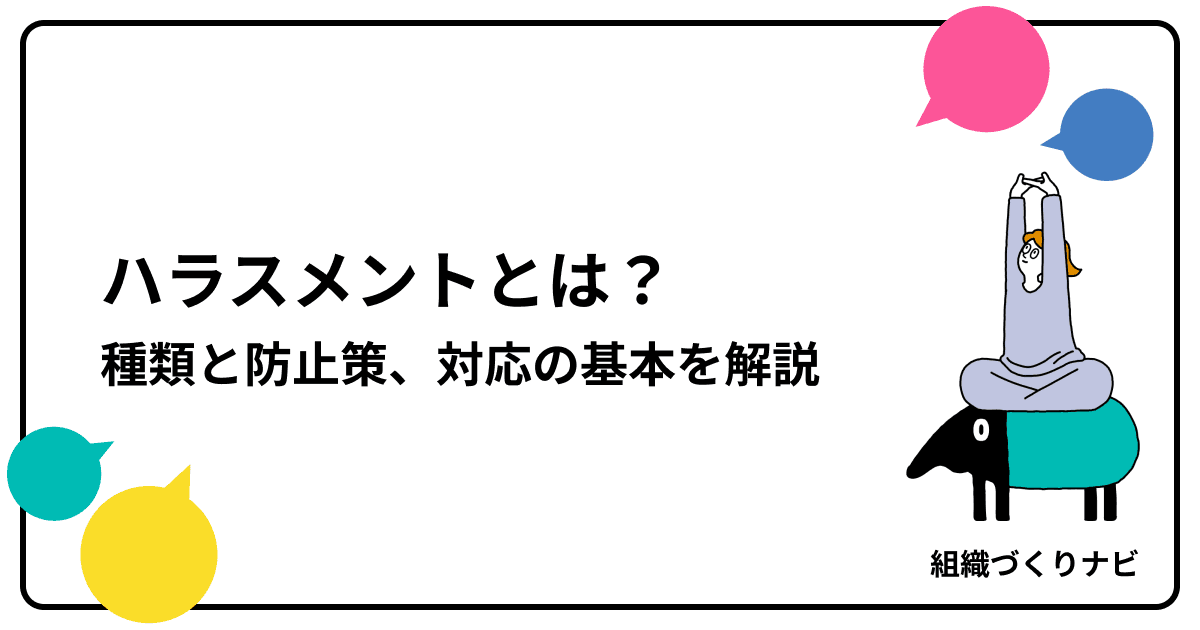
ハラスメントとは?種類と防止策、対応の基本を徹底解説
人事・管理職の皆様へ。健全な職場環境の維持に不可欠なハラスメントの正確な理解と適切な対応について解説します。この記事では、ハラスメントの定義から、従業員のモチベーション低下や企業の評判失墜など組織に与える深刻な影響を詳述。パワハラ、セクハラ、マタハラといった主要な種類に加え、リモハラ、ロジハラ、カスハラなど多様化するハラスメントの具体例と背景も紹介します。企業に課せられた法的責任、トップメッセージ、相談窓口設置、適切な対応、再発防止策といった実践的な防止策、そして被害発生時の相談窓口についても解説。ハラスメントのない明確な企業文化を醸成し、優秀な人材が定着する競争力ある職場を築くための指針を提供します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
ハラスメントとは?人事・管理職が知るべき基本と組織への影響
ハラスメントとは、職場や社会生活において、特定の個人に対して行われる「嫌がらせ」や「いじめ」といった不快な言動の総称です。これは、個々の属性(性別、年齢、役職、性格など)に関連する不適切な言動が原因で、相手に精神的・身体的な苦痛や不快感を与えたり、不利益をもたらしたりすることで、人の尊厳を損なう行為を指します。
人事や管理職の皆様にとって、ハラスメントの正確な理解と適切な対応は、健全な職場環境を維持し、従業員のモチベーションや生産性を高める上で極めて重要です。ハラスメントは、個人の能力発揮を妨げるだけでなく、組織全体の士気を低下させ、離職率の増加や企業の評判低下にも繋がりかねない深刻な問題です。単なる法令遵守に留まらず、企業文化としてハラスメントのない環境を構築することが、これからの企業経営には不可欠です。
ハラスメントの定義と企業に与える深刻な影響
ハラスメントとは、特定の個人に対する不適切な言動が、相手に精神的・身体的な苦痛や不快感を与えたり、不利益をもたらしたりすることで、人の尊厳を損なう行為を指します。行為者にその意図がなかったとしても、受け手が不快に感じた場合はハラスメントに該当する可能性があります。
企業にとってハラスメントは、単に個人の問題に留まりません。
従業員のモチベーション・生産性低下
:被害者は集中力を失い、業務効率が著しく低下します。
企業全体の士気低下と離職率の増加
:ハラスメントが横行する職場では、他の従業員も不安を感じ、優秀な人材の流出に繋がります。
企業の評判・ブランドイメージの失墜
:ハラスメント事案が外部に漏れることで、社会的信頼を失い、採用活動にも悪影響を及ぼします。
法的責任と損害賠償リスク
:企業はハラスメント防止義務を怠ったとして、訴訟リスクや多額の損害賠償責任を負う可能性があります。
健全な職場環境は、従業員のエンゲージメントを高め、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
職場で発生しやすい主要なハラスメントの種類と具体例
ハラスメントには様々な種類がありますが、ここでは特に職場で見られる主要なハラスメントとその具体例をご紹介します。人事・管理職の皆様は、それぞれの特徴を理解し、業務指導との線引きを明確にすることが重要です。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワハラとは、職場における優越的な関係を背景とした言動により、業務の適正な範囲を超えて、労働者の就業環境を害する行為を指します。上司から部下だけでなく、同僚間や部下から上司に行われるケースもあります。 具体例:
身体的・精神的な攻撃
:殴る・蹴るといった暴力、大声での叱責、人格否定、他の従業員がいる前での執拗な非難、無視。
人間関係からの切り離し
:特定の従業員を業務から外す、部署内で孤立させる、情報共有から意図的に排除する。
過大な要求
:到底達成不可能な業務量の強要、不必要な業務の押し付け、私的な用事を命じる。
過小な要求
:能力に見合わない単純作業のみを与える、誰でもできる雑用ばかりを指示する、仕事を与えない。
個の侵害
:プライベートな連絡先を勝手に共有する、趣味や交友関係を執拗に詮索する、職場外での行動を監視する。
人事・管理職が注意すべき点:
業務指導とパワハラの線引きは、「業務上の必要性」と「言動の相当性」で判断されます。適切な指導は必要ですが、人格を否定したり、過度に精神的苦痛を与えたりする言動はパワハラに該当します。具体的な基準を社内で明確に共有し、従業員への研修を徹底することが求められます。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクハラとは、職場における性的な言動により、労働者に不利益を与えたり、就業環境を害したりする行為です。性別に関わらず起こりうるものであり、被害者が不快に感じればセクハラに該当する可能性があります。 具体例:
性的な冗談、からかい
:外見や服装に関する不適切なコメント、性的な話題を振る、下ネタを話す。
身体への不必要な接触
:肩や腰に触れる、抱きつく、じろじろと体を見る。
プライベートな性的情報に関する執拗な質問
:交際関係、婚姻状況、性的指向、性自認についてしつこく尋ねる。
性的なうわさを流す
:個人のプライベートな情報や誤った噂を広める。
職務上の地位を利用した性的な誘い
:食事やデートにしつこく誘う、断ると業務に不利益を与えるかのような態度をとる。
人事・管理職が注意すべき点:
セクハラは、相手の意図ではなく「受け手の感じ方」が重要です。「このくらいは大丈夫だろう」という安易な思い込みが、深刻な問題に発展する可能性があります。性に関するデリケートな話題や身体的接触は、相手がどう感じるかを常に配慮し、不快感を与えないよう細心の注意を払うべきです。
妊娠・出産・育児・介護に関連するハラスメント(マタハラ・パタハラ・ケアハラ)
これらのハラスメントは、妊娠・出産、育児、介護といったライフイベントを理由に、労働者に対して不利益な取り扱いをしたり、嫌がらせをしたりする行為です。
マタニティハラスメント(マタハラ)
:主に女性が妊娠・出産をきっかけに受ける嫌がらせ。降格や解雇の示唆、時短勤務への不理解、心無い言葉で退職を促す。
パタニティハラスメント(パタハラ)
:男性が育児休業の取得を理由に、嫌がらせや不利益な扱いを受けるケース。育休取得を妨害する、取得後に不当な異動や降格をする。
ケアハラスメント(ケアハラ)
:介護を理由とした嫌がらせ。介護休業の取得を妨害したり、介護休暇の申請に不満を表明したりする行為、介護を理由に嫌がらせをする。
人事・管理職が注意すべき点:
従業員が仕事と家庭を両立できるよう支援することは、企業の重要な責任であり、法的義務でもあります。これらのハラスメントは、個人のキャリアを阻害するだけでなく、少子高齢化が進む社会において、企業のダイバーシティ&インクルージョン推進を妨げる深刻な問題です。育児・介護休業制度の周知徹底、取得しやすい職場雰囲気の醸成、制度利用者の業務分担への配慮など、積極的な支援体制の構築が求められます。
知っておきたい!多様化するハラスメントとその背景
社会の変化や働き方の多様化に伴い、ハラスメントの種類も多様化しています。ここでは、近年注目されるハラスメントとその背景をご紹介します。
モラルハラスメント(モラハラ)
モラハラとは、精神的な嫌がらせによって、相手の尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める行為です。言葉や態度、表情など、直接的な暴力ではなく精神的な攻撃が中心となります。 具体例: 無視、仲間外れ、陰口、人格否定、執拗な批判、侮蔑的な視線、ため息など。被害者は孤立し、自信を失いやすい特徴があります。パワハラと重なる部分も多いですが、モラハラは地位の優劣に関わらず、人間関係のなかで精神的な支配をしようとする傾向が強い点が特徴です。 背景: 職場での人間関係の希薄化や、個人の心の健康への意識の高まりとともに、精神的な攻撃の深刻さが認識されるようになりました。
新しい働き方におけるハラスメント
リモートハラスメント(リモハラ):リモートワーク環境下で発生するハラスメント。
例
:Web会議中の画面外での指示、業務時間外の過度な連絡、プライベート空間への過度な干渉(部屋の様子を執拗に詮索するなど)、オンライン上での無視や仲間外れ。
背景:
リモートワークの普及により、勤務時間とプライベートの境界線が曖昧になりやすく、コミュニケーション不足から誤解が生じやすい環境で発生します。
ロジカルハラスメント(ロジハラ):正論を振りかざし、相手を感情的に追い詰める行為。
例
:相手の状況や感情を無視し、ただ正論で批判し続ける、完璧なロジックで相手を言い負かし、精神的な苦痛を与える。
背景:
論理的思考が重視される社会において、行き過ぎた論理展開が感情を無視した攻撃になり得るという認識が広まりました。
時短ハラスメント(ジタハラ):時短勤務者への嫌がらせ。
例
:時短勤務を申請しているにも関わらず、定時後に仕事を振る、時短勤務を理由に陰口を言う、評価を下げる。
背景:
働き方改革により、短時間勤務やフレックスタイム制度が普及する一方で、制度利用者への不理解や偏見から発生します。
フキゲンハラスメント(フキハラ):不機嫌な態度で周囲に気を遣わせる行為。
例
:上司が不機嫌な顔で黙っていることで、部下が過度に萎縮し、業務に支障が出る。
背景:
個人の感情表現が他者に与える影響への意識が高まり、職場における感情のコントロールも求められるようになりました。
外部からのハラスメント
カスタマーハラスメント(カスハラ):顧客からの理不尽な要求やクレーム、暴言など。
例
:従業員の人格や尊厳を傷つける暴言、長時間の拘束、土下座の要求、金銭的な不当要求。
背景:
企業と顧客の関係性の変化やSNSによる情報拡散の影響もあり、従業員が顧客からの過度な要求に晒されるケースが増加しています。企業は従業員を守る責任があります。
これらの新しいハラスメントは、社会や働き方の変化、価値観の多様化を背景に生まれており、人事・管理職は常に最新の情報をキャッチアップし、自社の状況に合わせた対策を講じる必要があります。
企業に求められる法的責任と実践的なハラスメント防止策
企業には、ハラスメントを防止し、健全な職場環境を維持するための法的義務が課されています。人事や管理職の皆様は、これらの義務を理解し、適切に対応することが求められます。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)、男女雇用機会均等法、育児介護休業法などにより、事業主はハラスメント対策を行うことが義務付けられています。これらの義務を怠ると、企業の責任が問われ、社会的信用失墜や損害賠償請求に繋がる可能性があります。
効果的な防止策の導入と運用
単にルールを設けるだけでなく、実効性のある防止策を導入し、PDCAサイクルで運用していくことが重要です。
トップメッセージによる方針の明確化と周知・啓発:
ハラスメントは許されない行為であることを、経営層が明確なメッセージとして発信します。
就業規則にハラスメント防止規定を明記し、全従業員に周知徹底します。
定期的なハラスメント研修を実施し、従業員一人ひとりの意識向上を図ります。特に、行為者になりうる管理職層には、具体的な事例を交え、業務指導との線引きを学ぶ機会を提供します。
相談窓口の設置と適切な運用:
被害者が安心して相談できる社内外の窓口(人事部、コンプライアンス窓口、産業医、外部機関など)を設置します。
相談者のプライバシー保護を徹底し、不利益な取り扱いをしないことを明示します。
相談を受けた際の対応マニュアルを作成し、担当者間で共有します。
迅速かつ適切な対応と再発防止策の実施:
ハラスメントが発生した場合、相談内容に応じて迅速に事実確認を行います。被害者と加害者双方から丁寧にヒアリングし、客観的な証拠収集に努めます。
事実が確認された場合、就業規則に基づき加害者への適切な処分(注意、配置転換、懲戒処分など)を行います。
被害者に対しては、心身のケアや配置転換など、状況に応じたきめ細やかなサポートを提供します。
再発防止のため、組織風土の改善や研修内容の見直しなど、根本的な対策を講じます。
これらの措置は、単なる法的義務の履行に留まらず、従業員が安心して働ける環境を整備し、企業の競争力向上にも繋がる投資であると認識することが大切です。
もしハラスメントが発生したら?適切な対応と相談窓口
万が一、ハラスメントの被害に遭ってしまった場合、一人で抱え込まず、適切な対処をすることが重要です。人事や管理職の皆様は、被害者から相談を受けた際に、これらの情報を提供できるよう備えておきましょう。
被害者が取るべき行動
ハラスメントの状況を詳細に記録する
:いつ、どこで、誰が、どのような言動をしたのか、具体的に何と言われたか、身体的にどう感じたか、心理的にどう影響があったかなどを、時系列でメモに残します。
証拠を保全する
:メール、チャット履歴、録音データ、目撃者の証言、診断書など、客観的な証拠を集めます。
一人で抱え込まず、信頼できる人に相談する
:友人、家族、同僚など、まずは身近な人に話すことで精神的な負担が軽減されることがあります。
これらの記録や証拠は、事実確認や問題解決の際に非常に役立ちます。
企業が提供すべき相談窓口と支援
被害者を決して孤立させず、適切な支援につなぐことが、人事や管理職の役割です。
社内相談窓口:
人事部:ハラスメントに関する制度や対応に詳しい部署です。
コンプライアンス窓口:社内の規定違反全般に対応します。
産業医・保健師:心身の健康面でのサポートや、専門機関への連携が可能です。
労働組合:従業員の権利を守る立場から相談に乗ります。
社外相談窓口:
労働基準監督署:労働基準法に基づく相談・指導を行います。
都道府県労働局(総合労働相談コーナー):ハラスメントを含むあらゆる労働問題の相談が可能です。
弁護士:法的な観点からアドバイスや代理交渉を行います。
ハラスメント相談窓口(NPO法人など):専門の相談員が対応します。
被害者への対応は、二次被害を防ぐためにも、慎重かつ共感的な姿勢が求められます。秘密保持を徹底し、被害者の意向を最大限に尊重しながら、迅速な解決を目指しましょう。
まとめ:ハラスメントのない健全な職場環境のために
ハラスメントは、個人の尊厳を傷つけ、組織全体の生産性を低下させる深刻な問題です。人事・管理職の皆様には、ハラスメントの正しい理解と防止策の実施、そして問題発生時の早期解決に向けたリーダーシップが求められます。
単に法的な義務を果たすだけでなく、ハラスメントを許さないという明確な企業文化を醸成することが、競合との差別化を図り、優秀な人材を惹きつけ、定着させる上で不可欠です。
誰もが安心して、自分の能力を最大限に発揮できる健全な職場環境を築くことは、企業の持続的な成長に不可欠です。この記事が、ハラスメントのない社会を目指すための一助となれば幸いです。
関連する参考記事
例えば、パワハラ防止のための教育を実施した結果、管理職が現場の社員と適切にコミュニケーションを取ることが難しくなることがあります。管理職がパワハラを恐れて指導ができなくなり、逆にエンゲージメントが低下するというケースです。
ここでの問題は、パワハラ防止の教育が、本来では問題にならないはずの指導や注意にまで及ぶかのようになってしまうことです。伝える側が現場の実情を細やかに理解し、どのようにコミュニケーションを取れば良いのかを管理職側に明確に示すことは困難です。実はここで、「公助」を使いながらも、現場のケースバイケースの問題を自身で判断していくという力が必要になります。
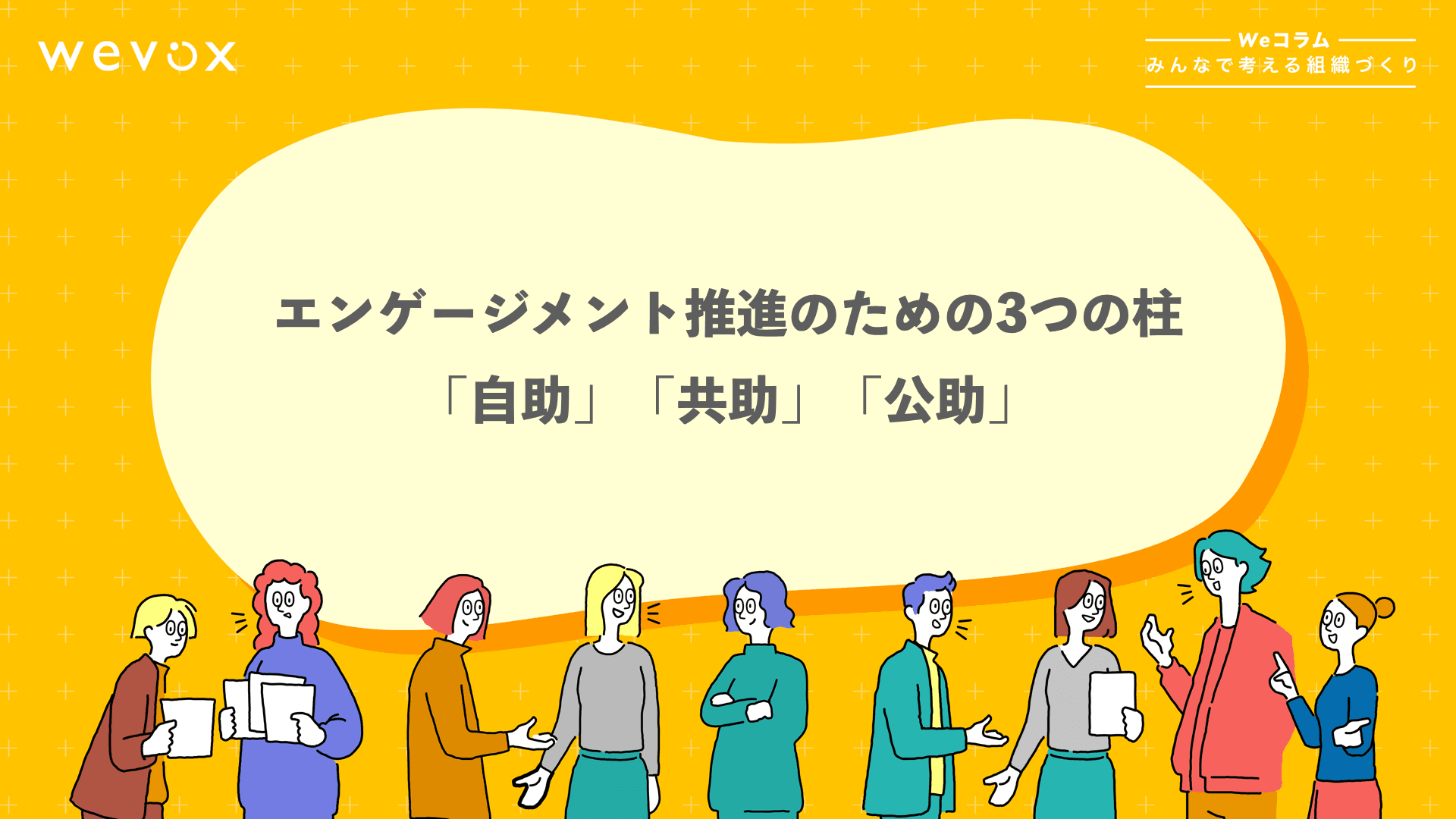
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

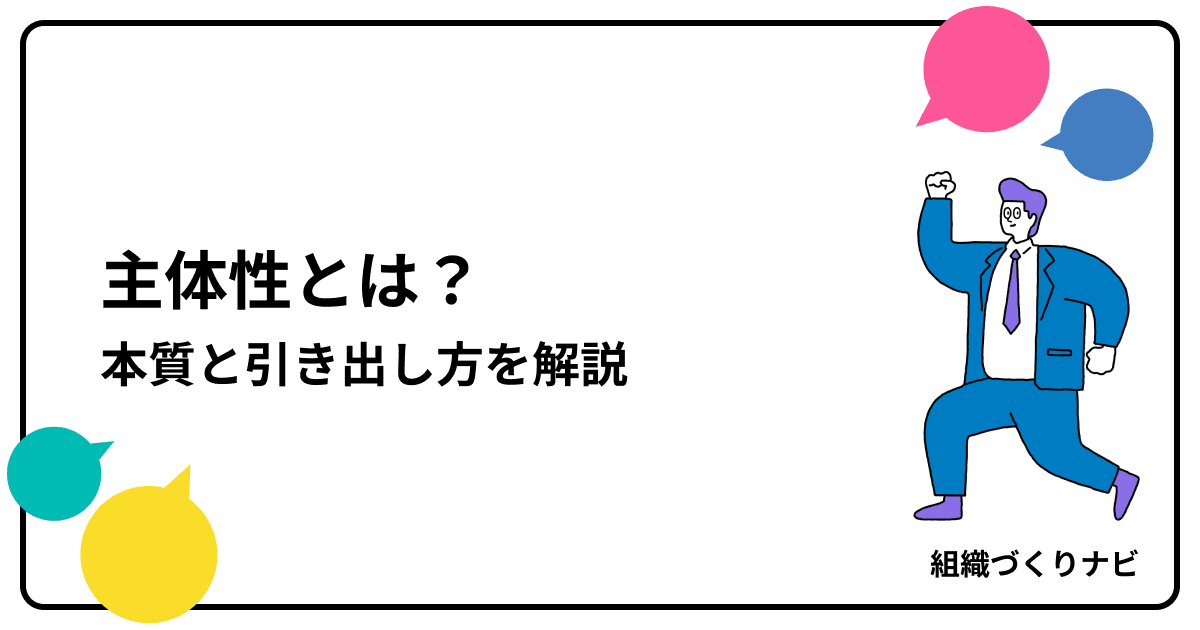
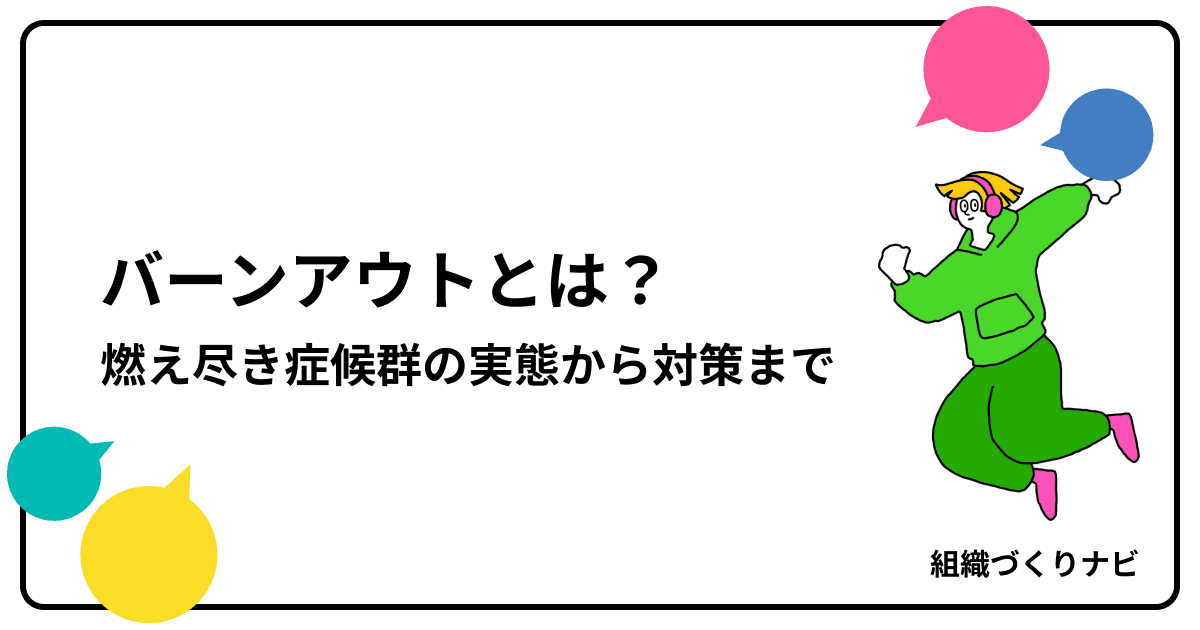


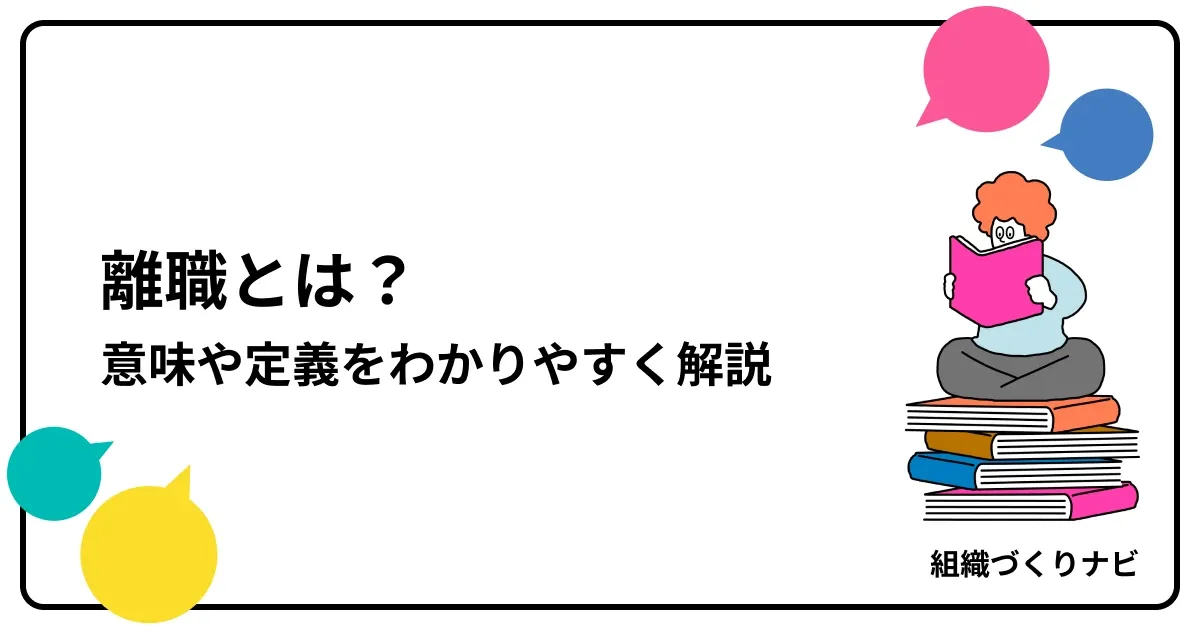




 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


