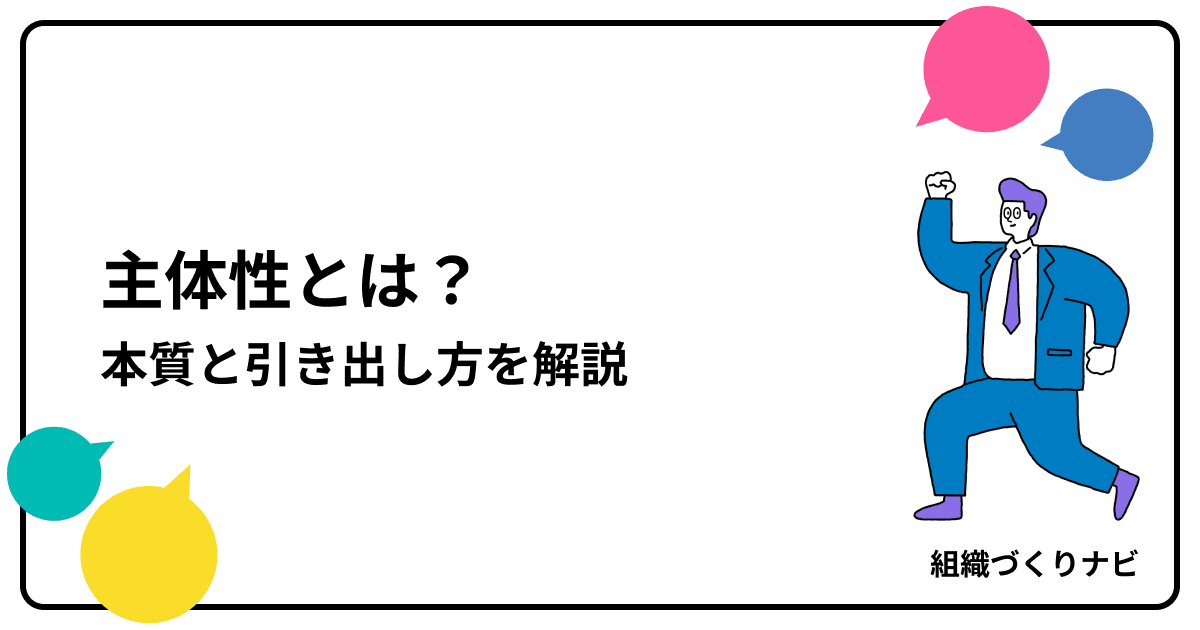
「主体性」とは?組織成長の鍵を握る本質と引き出し方を徹底解説!
現代ビジネスで必須の「主体性」とは、指示待ちでなく自ら課題を発見・解決し行動する力。予測困難な時代に組織成長を促す鍵です。しかし、なぜ部下の主体性は失われるのでしょうか?その原因は、心理的な抵抗感を乗り越え、行動を起こすための精神的な原動力ともいえる「心のエネルギー」の消耗にあるかもしれません。リーダーの言動や組織風土が、無意識のうちにこのエネルギーを奪っている可能性があります。本記事では、この「心のエネルギー」に着目。個人が仕事の目的を理解し、小さな成功を積み重ね、意見を発信する力を育む方法を提案します。また、リーダーには心理的安全性の確保、適切な権限委譲、プロセス評価を通じて部下の心のエネルギーを満たし、自律的な行動を促すマネジメント戦略を詳述。主体性育成を単なる意識改革でなく、具体的な行動として捉え、変化に強いイノベーション組織を築くヒントを提供します。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
主体性とは?組織成長の鍵を握るその本質
「指示待ち」から脱却:自律的な行動の源泉
「主体性」とは、与えられた指示を待つだけでなく、自ら課題を発見し、深く考察し、判断を下して行動へと移していく力を指します。これは、単に「勝手な行動」とは一線を画します。組織の目標や方向性を正確に理解した上で、「今、自分に何ができるか」「どうすれば現状をより良くできるか」を常に問い、責任を持って実行に移す姿勢そのものです。特に、予測困難な現代のビジネス環境において、従業員一人ひとりが自ら考え、行動する力は、組織全体の持続的な成長に不可欠な要素となっています。
激変する時代に不可欠な「個の力」
現代ビジネスは、変化のスピードが極めて速く、既存のマニュアルや前例だけでは対応しきれない事態が頻発します。このような状況下で、従業員一人ひとりが課題を「自分ごと」として捉え、自律的に解決策を導き出す主体性は、組織の競争力を高める上で不可欠です。主体性を持つ人材は、既成概念にとらわれない新しいアイデアや改善提案を生み出し、予期せぬ問題発生時にも迅速かつ的確に対応できます。これは、組織全体の生産性向上やイノベーション創出に直結するため、人事担当者や管理職の皆様にとって、部下の主体性育成は喫緊の課題と言えるでしょう。
なぜ部下の主体性は失われるのか?見過ごされがちな「心のエネルギー」の消耗
行動を阻む見えない壁:「心のエネルギー」とは
部下に「主体性がない」と感じる際、その根底には「心のエネルギー」の消耗が潜んでいるケースが少なくありません。この「心のエネルギー」とは、心理的な抵抗感や困難さを乗り越え、自ら行動を起こすための精神的な原動力、いわば「行動意欲の燃料」と考えると分かりやすいでしょう。例えば、業務上の不備に気づいても「自分が指摘して波風を立てたくない」という懸念や、「既に他の業務で手一杯だ」という感情が芽生えると、このエネルギーは急速に枯渇していきます。エネルギーが不足すると、いくら「こうしたい」という内なる欲求があっても、最初の一歩を踏み出すことが困難になるのです。
リーダーや組織風土が主体性を奪うメカニズム
部下の心のエネルギーを無意識のうちに奪い、主体性を阻害しているのは、多くの場合、リーダー自身の言動や職場の環境に起因します。具体的な例を挙げると、部下のアイデアや提案に対し、熟考せずに否定的な意見を返したり、些細な失敗を過度に咎めたりする行為は、「発言しても無意味だ」「失敗すれば厳しく叱責される」といった萎縮する気持ちを生み出し、心のエネルギーを著しく消耗させます。さらに、指示が不明瞭で業務の目的が見えなかったり、常に監視されているような窮屈な職場環境も、自ら考え行動する意欲を根本から削いでしまいます。リーダーは、自身のリーダーシップスタイルやチームの風土が、部下の主体性発揮にどのように作用しているか、常に深く省察する必要があります。
部下の主体性を引き出す実践的アプローチ
個人が「自ら動く」力を育むステップ
個人の主体性を育むためには、まず「自身の仕事が持つ目的と意義」を深く理解することが重要です。単に指示された業務をこなすだけでなく、「なぜこの業務が必要なのか」「それが組織全体にどう貢献するのか」を把握することで、自律的な工夫や改善策を考案する土台が築かれます。次に、意図的に小さな成功体験を積み重ねることも極めて効果的です。例えば、一見些細なタスクでも、自分なりの創意工夫によって良い結果を得られた経験は、確かな自信となり、次の挑戦への強力な推進力となるでしょう。さらに、疑問点や気づきを臆することなく質問し、自身の意見を積極的に発信する習慣を身につけることが、主体性発揮への大きな一歩となります。
関連する参考記事
竹内: 一番の変化は、メンバーが能動的になったことです。 以前はどこか受け身で、言われたことだけをこなす雰囲気もあったのですが、今は皆が主体性を持って、自分で考えて動いてくれるようになりました。
三浦: 具体的なエピソードとしては、トラブル対応の仕方が変わりましたね。 これまでは不良の発生などトラブルが起きて担当チームが忙しくなっても、周りは手を出さない、という状況がありました。 でも、討論会で「本当は自分も意見を言いたいし、手伝いたい」という声がメンバーから挙がったんです。 その意見を踏まえて、今ではトラブルが発生したら追加メンバーを加えてチームとして対応する体制にしています。
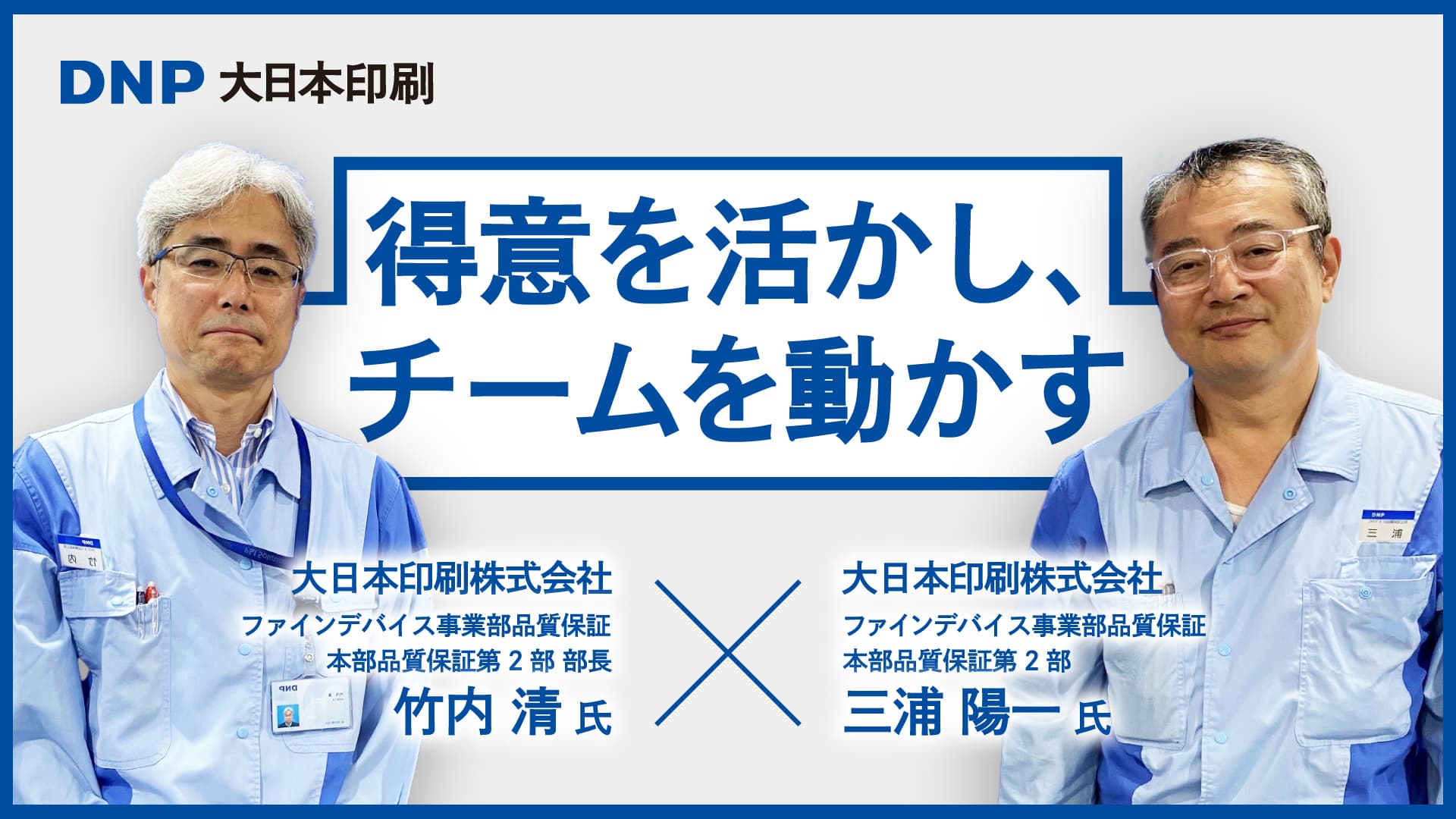
チーム全体の主体性を高めるマネジメント戦略
リーダーがチーム全体の主体性を最大限に引き出すためには、まず「心理的安全性」の確保が不可欠です。これは、失敗を過度に恐れることなく自由に意見を表明でき、新たな挑戦ができる、安心と信頼に満ちた環境を指します。部下には、達成すべき目標は明確に提示しつつ、その実現手段については本人に裁量を与えるなど、適切な範囲での権限委譲が極めて効果的です。さらに、単に結果だけでなく、自ら思考し、行動へと移そうとしたプロセス自体を正当に評価し、具体的なフィードバックと肯定的な承認を与えることで、部下の心のエネルギーは満たされ、次への意欲へとつながります。「なぜこの仕事をするのか」という「パーパス(目的・意義)」を深く共有することも、一人ひとりが当事者意識を醸成する上で欠かせない要素です。リーダーは、自身の言動が部下の心のエネルギーにどう作用するかを常に意識し、ポジティブな影響を与え続けるよう努めましょう。
まとめ
現代ビジネスにおいて「主体性」は、組織の成長とイノベーションを推進する上で不可欠な要素です。しかし、部下の主体性が不足していると感じる時、その背景には、見過ごされがちな「心のエネルギー」の消耗が潜んでいることがあります。リーダーの言動や職場の環境が、知らず知らずのうちに部下の行動意欲を奪い、このエネルギーを枯渇させている可能性があるのです。
主体性を育むためには、まず個々人が自身の仕事の目的と意義を理解し、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。そしてリーダーは、心理的安全性を確保し、適切な裁量を与え、プロセスを評価することで、部下の心のエネルギーを満たし、自律的な行動を促すことができます。
「心のエネルギー」という視点を持つことで、主体性育成は単なる「意識改革」ではなく、具体的なマネジメント行動として捉えることが可能なのです。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

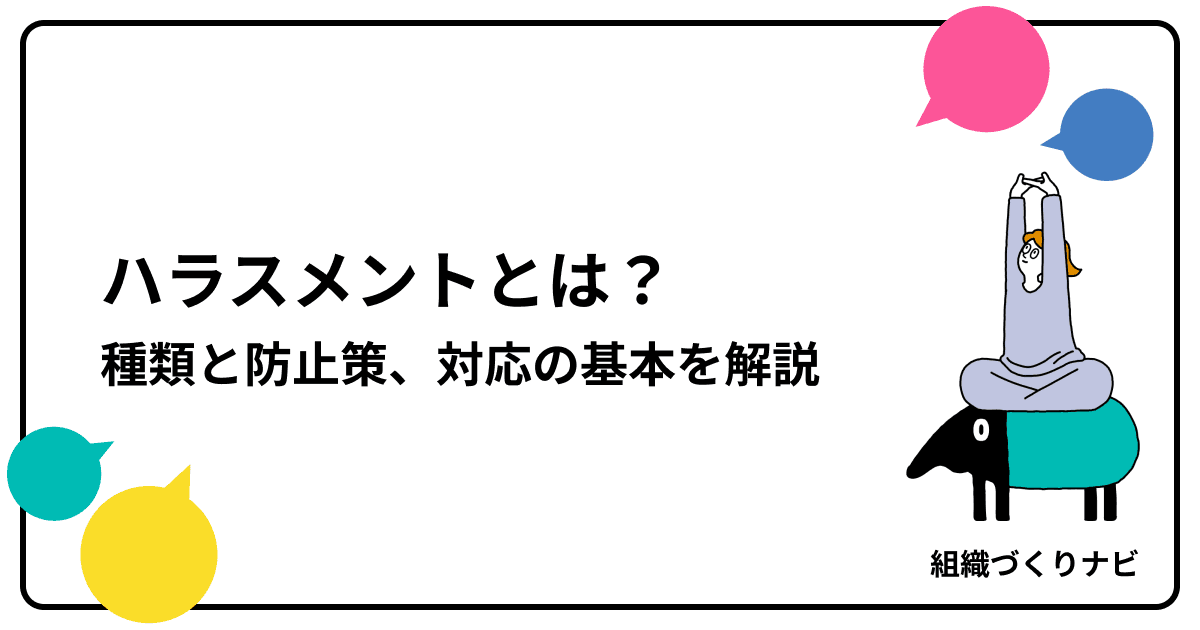
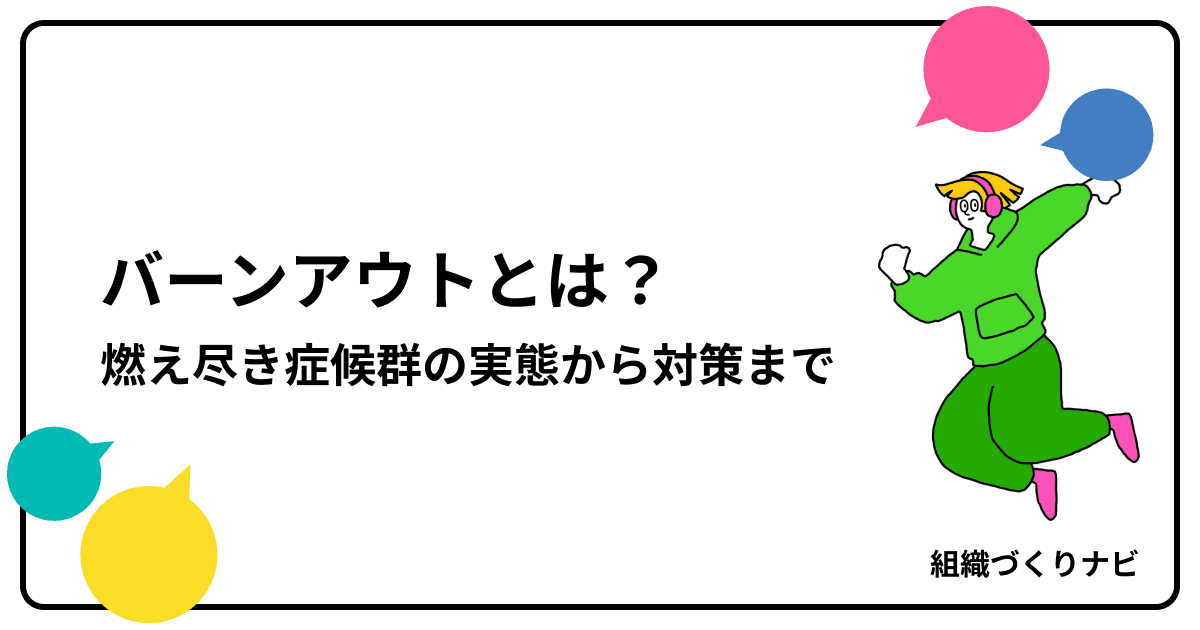


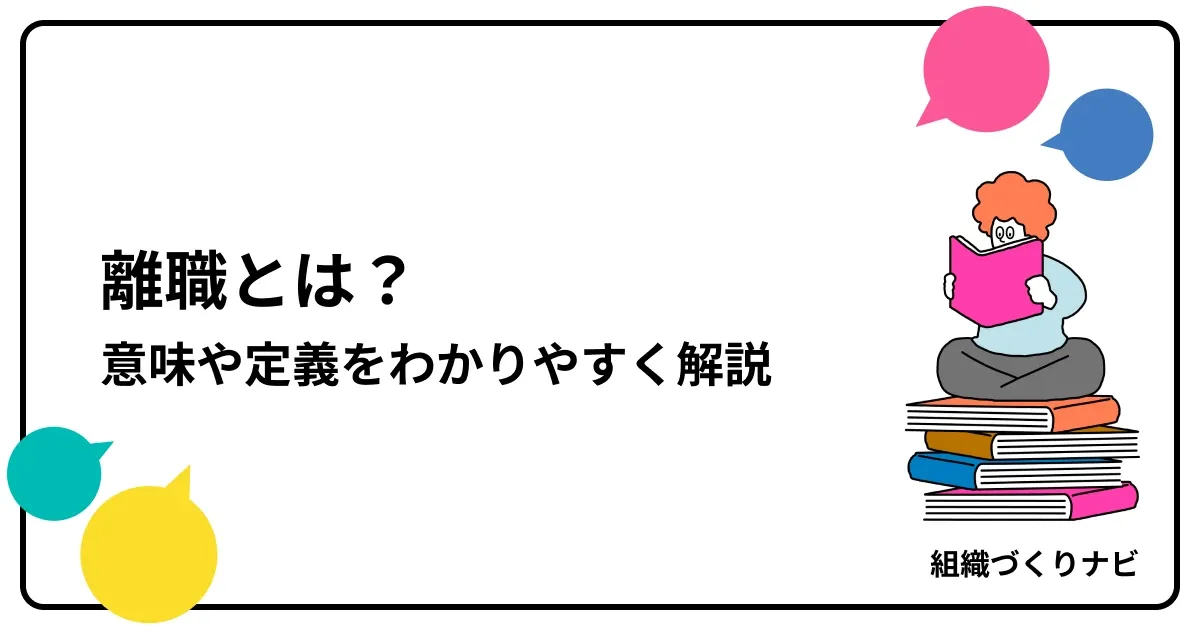




 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


