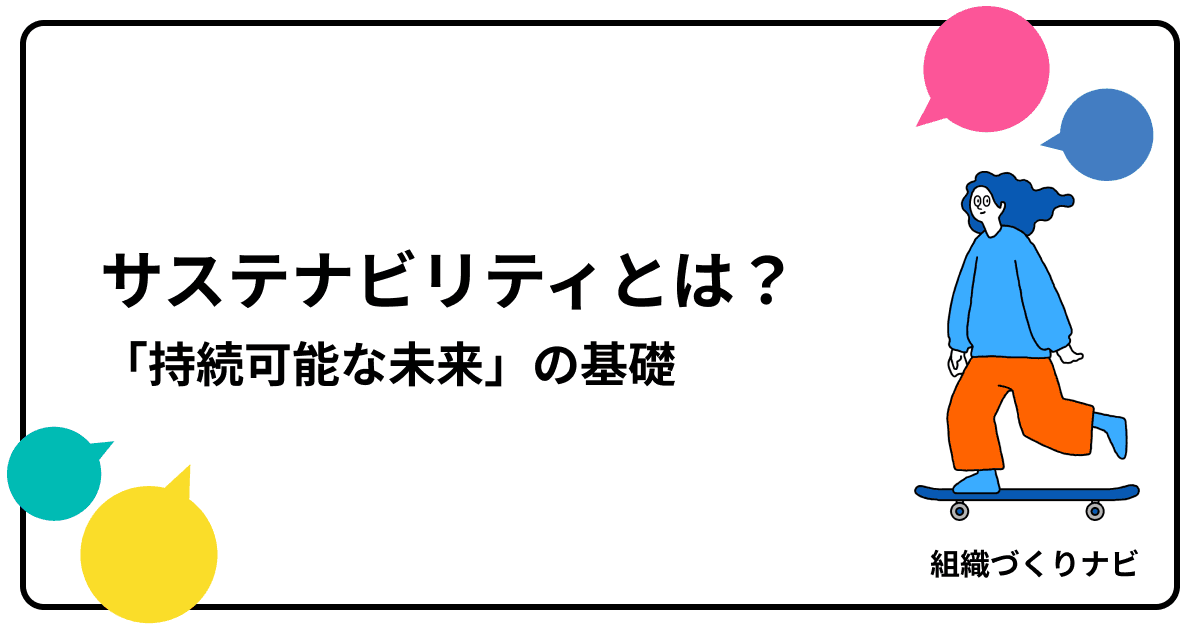
サステナビリティとは?企業も個人も知るべき「持続可能な未来」の基礎
サステナビリティとは、未来の世代が安心して豊かに暮らせる「持続可能な社会」を築くための壮大な考え方です。地球温暖化や海洋汚染、貧困といった地球規模の喫緊の課題が深刻化する今、私たちは、環境・社会・経済の3つの柱をバランス良く保ちながら、持続的な発展を目指す必要があります。 この概念は、SDGs(持続可能な開発目標)やESG投資、CSRといった関連用語を包含するもので、企業にとっては単なる義務ではなく、ブランド価値向上や人材獲得、イノベーション創出につながる中核的な経営戦略です。私たち一人ひとりも、環境に配慮した製品選びやリサイクルなど、日々の行動を通じてサステナブルな未来に貢献できます。未来を創る今の選択が、持続可能な地球へと繋がります。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。
サステナビリティとは?未来へつなぐ「持続可能な社会」を目指す考え方
サステナビリティの基本的な意味とは?「持続可能性」が意味するもの
サステナビリティとは、日本語で「持続可能性」と訳される、未来へ向けた壮大な概念です。これは、私たち現在の世代が地球の資源や環境を使い果たしたり、社会のバランスを崩したりすることなく、未来の世代が安心して、そして豊かに暮らせる地球を「今」から築き上げていくための考え方を指します。特に企業活動においては、目先の利益だけを追求するのではなく、地球環境や社会全体への責任を果たしながら、企業価値を長期的に高めていくための不可欠な戦略そのものと言えます。この考え方は、企業だけでなく、政府、そして私たち一人ひとりの日々の選択に深く根ざした、現代社会の羅針盤とも言えるでしょう。
なぜ今、サステナビリティが注目されるのでしょうか?未来を守る喫緊の課題
近年、サステナビリティがこれほどまでに重要視されるようになった背景には、地球規模で深刻化する課題があります。気候変動による異常気象、プラスチックごみによる海洋汚染、貧困や格差の拡大といった問題は、私たちの生活基盤や経済活動に、すでに深刻な影響を及ぼしています。また、国連が採択したSDGs(持続可能な開発目標)が広く認知されたことで、企業や個人の意識も大きく変化しました。環境や社会に配慮した製品やサービスを選ぶ消費者や、企業の取り組みを重視する投資家が増え、もはや、企業が事業を継続し、さらに成長を追求するためには、サステナビリティへの対応が不可欠な経営課題として認識されています。
関連する参考記事
次に、全員参加プロジェクトについてご紹介します。弊社がサステナビリティに関する活動をしていく中で、経営陣や一部の管理部門だけではなく、会社全体の様々な人が参加している状態を目指すようになりました。弊社では毎年サステナビリティに関するテーマを定め、様々な部門からリーダー、メンバーが集まって全員参加プロジェクトとして活動しています。
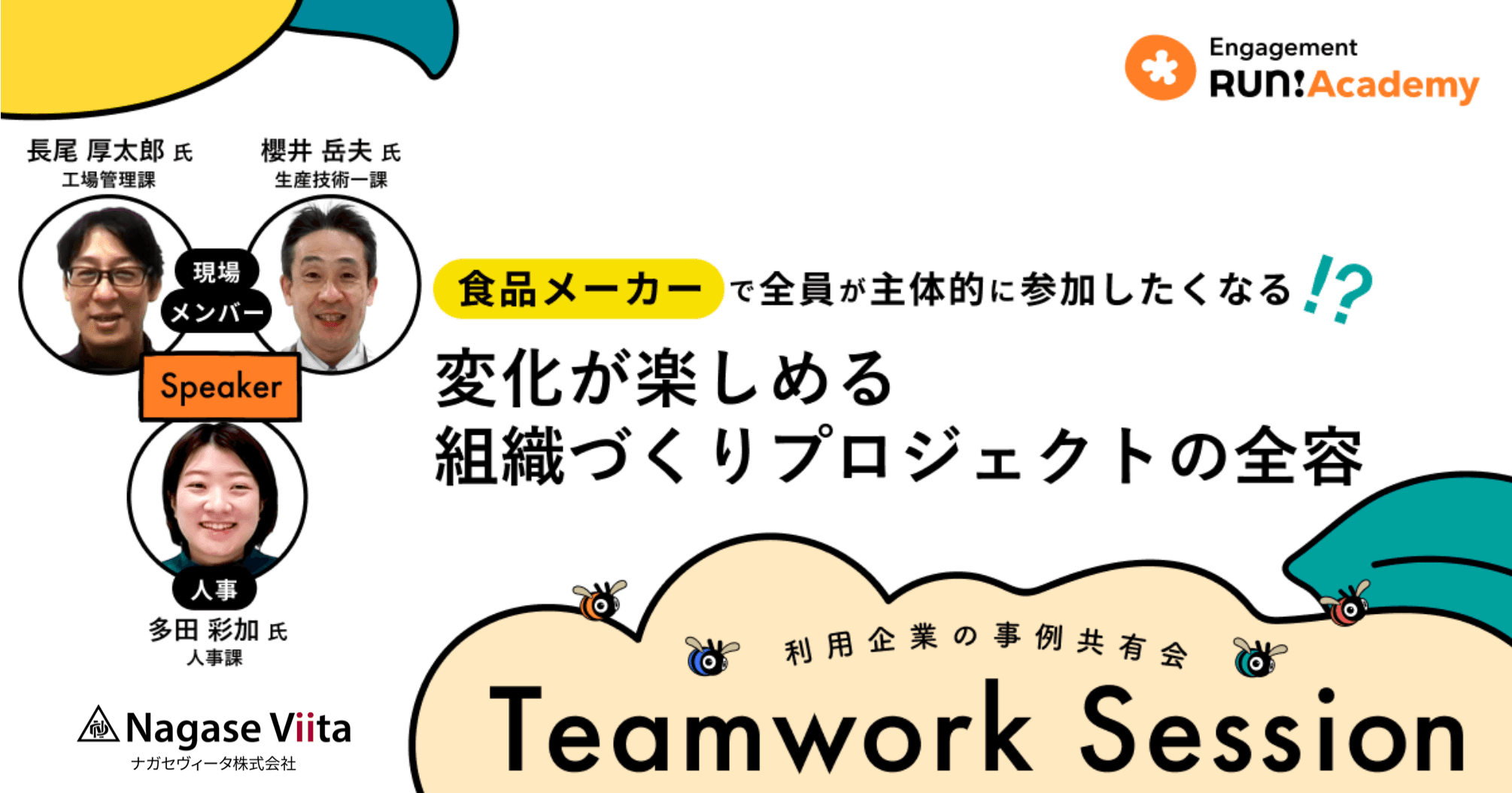
サステナビリティを支える3つの柱:環境・社会・経済
サステナビリティの概念は、主に「環境」「社会」「経済」の3つの要素がバランス良く保たれることで成り立っています。
環境(Environmental Protection)
: 地球温暖化対策、森林保護、海洋汚染対策、水資源の節約、生物多様性の保全など、地球の自然を守り、健全な状態を維持する活動を指します。持続可能な地球の恵みを、未来へつなぐための基盤です。
社会(Social Development)
: 人権の尊重、労働環境の改善、貧困や格差の是正、教育機会の均等、ジェンダー平等など、すべての人々が豊かで安心して生活できる公平な社会を築くための取り組みです。
経済(Economic Development)
: 単なる利益追求に留まらず、環境・社会への配慮と両立させながら、企業が長期的に成長し続けるための経済活動です。持続可能なビジネスモデルの構築こそが、現代企業に求められています。
これら三つの柱が相互に作用し、どれか一つが欠けても「持続可能な社会」は実現できません。
混同しやすい関連用語との違いをクリアに解説
サステナビリティと似ているように見える言葉に、SDGs、CSR、ESGなどがあります。それぞれの違いを理解しておくと、サステナビリティへの理解を一層深めることができます。
SDGs(持続可能な開発目標)
: サステナビリティが「持続可能な社会を目指す」という大きな目標そのものであるのに対し、SDGsはその目標を達成するために国連が定めた「具体的な17の目標と169の行動計画」を指します。
CSR(企業の社会的責任)
: 企業が事業活動を通じて、経済的成長だけでなく社会や環境に対する責任を果たすという考え方です。以前は寄付やボランティアなど
本業とは切り離された活動
と見られがちでしたが、サステナビリティにおいては、本業のプロセスそのものに社会課題解決を組み込み、価値創造へと昇華させる視点が重視されます。
ESG(環境・社会・ガバナンス)
: 主に投資家が企業の長期的な成長可能性を評価する際に用いる「環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance=企業統治)」の3つの視点です。サステナビリティが目指す社会を実現するための、企業の持続可能性を測る重要な評価指標であり、投資判断の根拠となる「羅針盤」の一つと言えるでしょう。
企業におけるサステナビリティ経営の重要性と具体的な取り組み
現代の企業経営において、サステナビリティは単なるコストや義務ではなく、企業価値向上の中核をなす、攻めの経営戦略となっています。これを「サステナビリティ経営」と呼びます。環境・社会・経済の3つの柱を経営に組み込むことで、企業は様々なメリットを享受し、持続的な成長を実現できます。
企業イメージ・ブランドイメージの向上
: 社会貢献に積極的な姿勢は、顧客や取引先からの信頼を深め、企業やブランドの価値を飛躍的に向上させます。
投資と資金調達の優位性
: ESG投資の拡大に伴い、環境・社会に配慮した企業は、長期的な成長性やリスク耐性が高く評価され、多様な資金調達機会を得やすくなります。
優秀な人材の獲得と定着
: サステナビリティに真摯に取り組む企業は、従業員の誇りや帰属意識を高め、生産性向上に繋がります。特に若い世代にとって、働く企業の理念は重要な選択基準となり、優秀な人材を引きつけ、定着させる力となります。
イノベーションと競争力の強化
: 環境・社会課題の解決は、時に未開拓の市場や画期的な技術開発へと繋がり、企業のイノベーションを加速させます。これは、他社との差別化を図り、持続的な競争優位性を確立する源泉となるでしょう。
多くの企業が、自社の事業特性に合わせてサステナビリティへの取り組みを強化しています。例えば、CO2排出量の削減のために再生可能エネルギーの導入や省エネ設備の活用を進めること、資源の有効活用を目指して製品のリサイクルを推進するなどが挙げられます。また、従業員の多様性を尊重し、働きがいのある職場環境を整備することも、企業の持続性を高める重要な取り組みです。さらに、サプライチェーン全体における人権尊重や環境負荷低減の徹底も、グローバル企業としての責任として、強く求められる時代です。
私たち一人ひとりができるサステナブルな未来への貢献
サステナブルな社会の実現は、企業や政府だけが担うものではありません。私たち一人ひとりの日々の行動も、未来を大きく変える力となります。例えば、買い物の際に環境ラベルの付いた製品を選ぶ、不要なものを減らしリサイクルを徹底する、節電・節水に努めるなど、日々の選択一つひとつが、地球と社会への貢献へと繋がります。また、社会課題解決に取り組むNPOやNGOを支援することも、有効な手段の一つです。私たち一人ひとりがサステナビリティを意識し、日々の行動に落とし込むことで、より豊かで、持続可能な未来を築き上げていくことが可能です。未来を創るのは「今」の私たちの選択です。
まとめ
サステナビリティは、私たち現在の世代が未来の世代のために築く「持続可能な社会」を目指す、不可欠な考え方です。環境、社会、経済の三つの柱が均衡を保つことで、初めてその実現が可能となります。気候変動や格差の拡大といった地球規模の課題が深刻化する今、サステナビリティは単なる概念ではなく、私たち全員が未来のために取り組むべき喫緊の課題であり、同時に無限の可能性を秘めた希望でもあります。企業は経営戦略として、個人は日々の行動として、この大きな潮流に参画することで、誰もが安心して暮らせる地球を、次の世代へと繋いでいくことができるでしょう。
記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

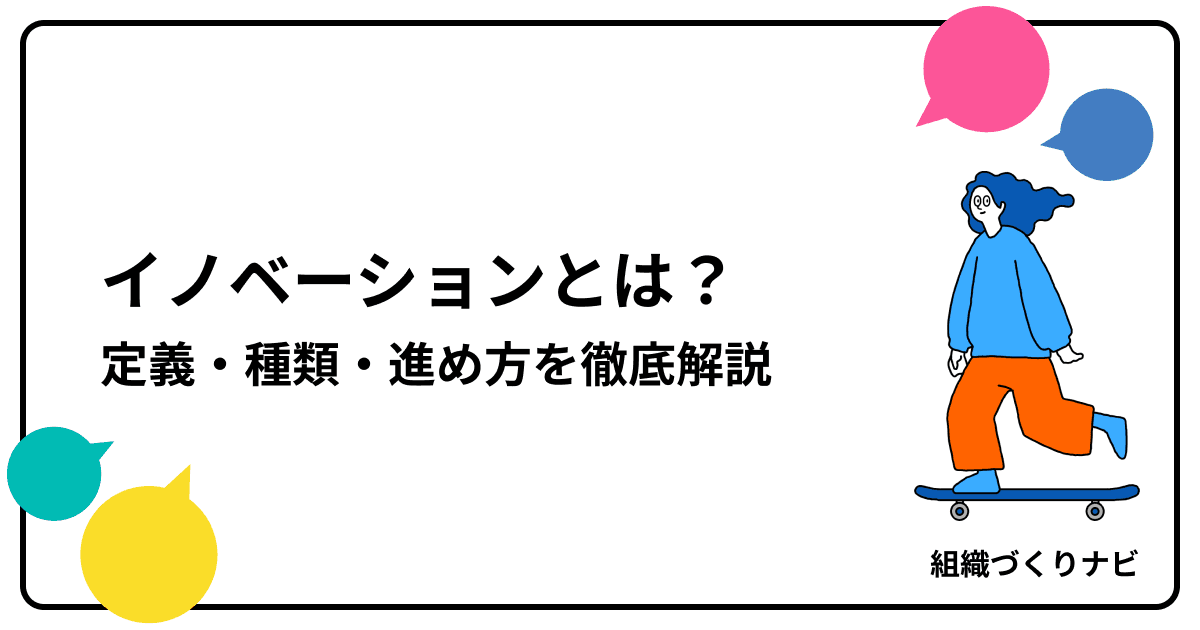
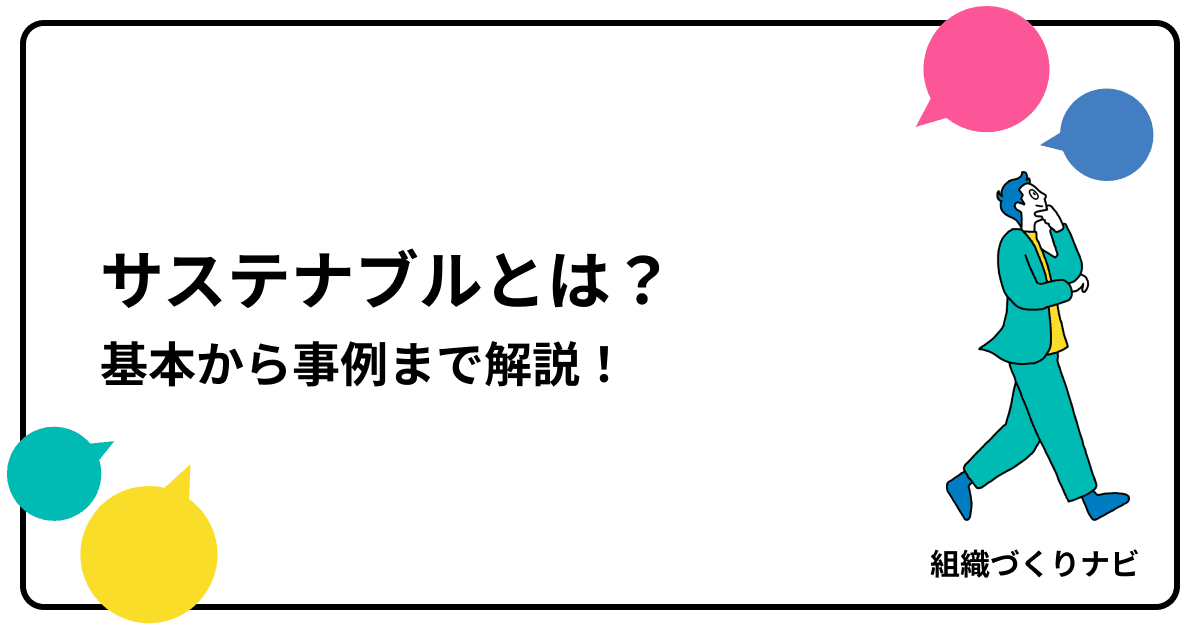
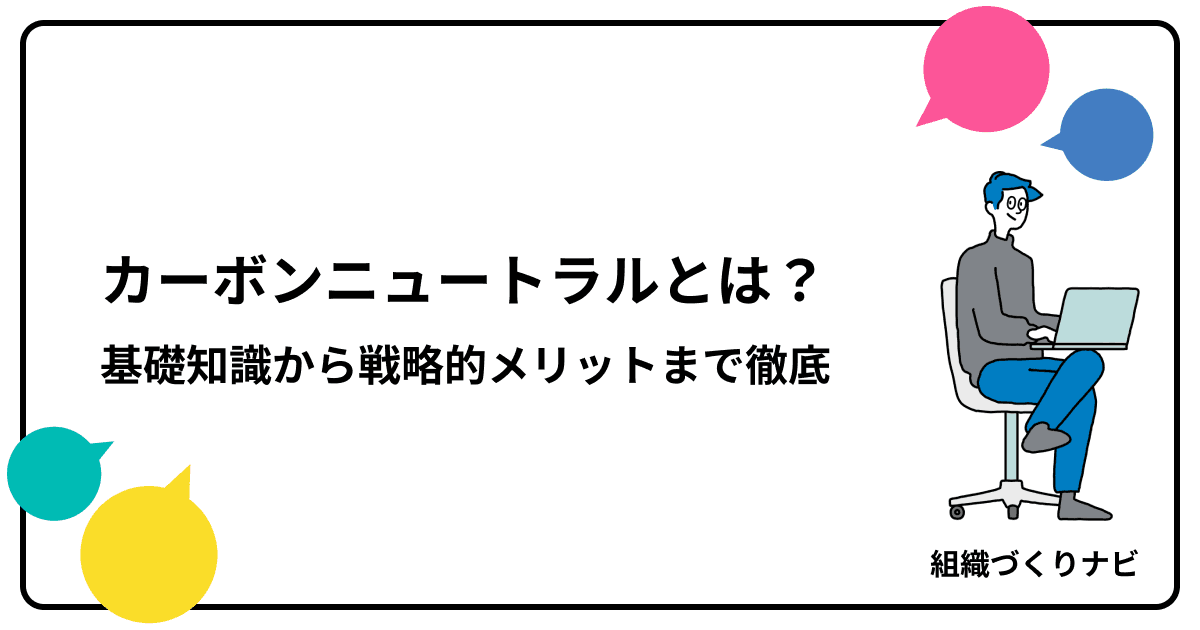
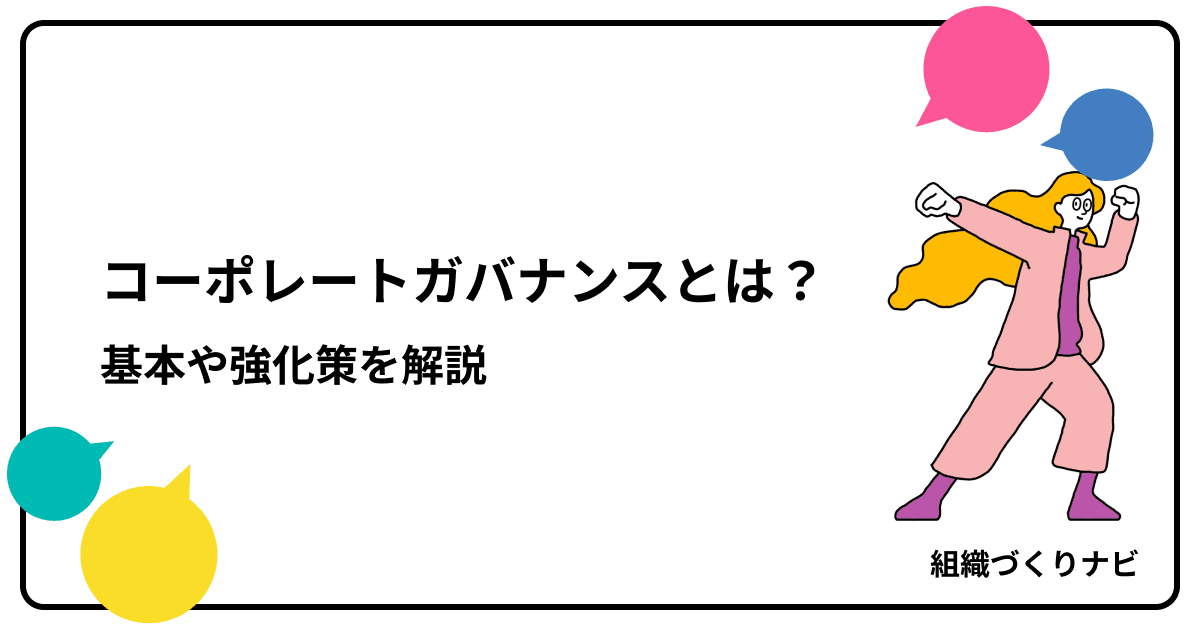
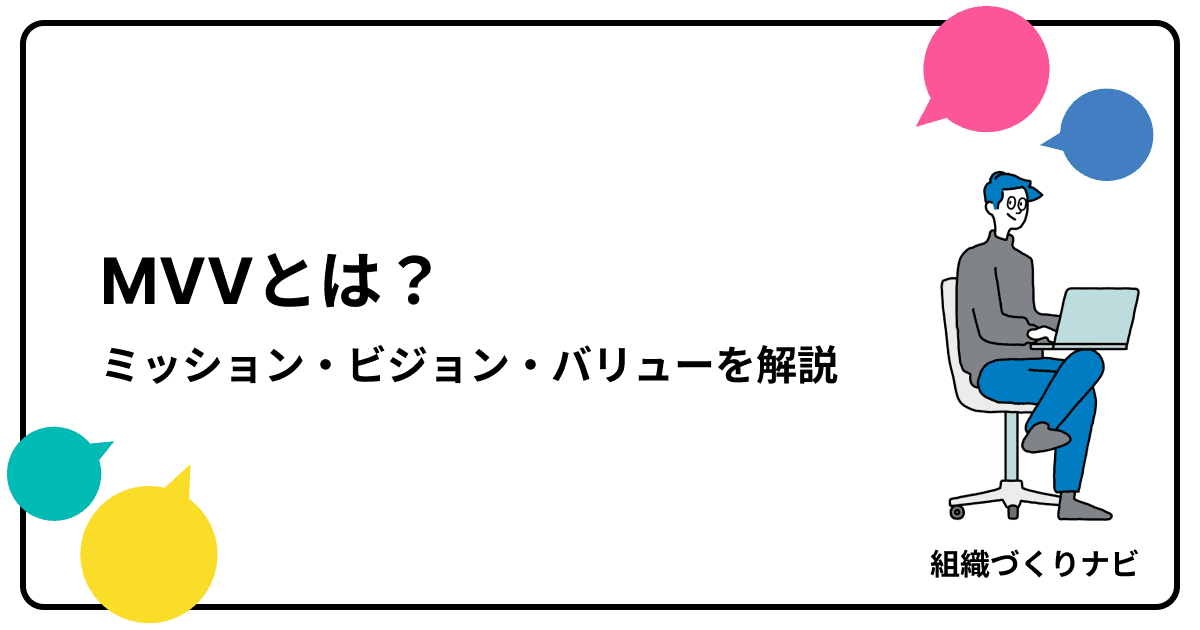




 組織を超えた学びの場
組織を超えた学びの場 動画を通した学び
動画を通した学び
 エンゲージメント可視化・分析
エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析
組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ
きづきのきっかけを遊んで学ぶ


